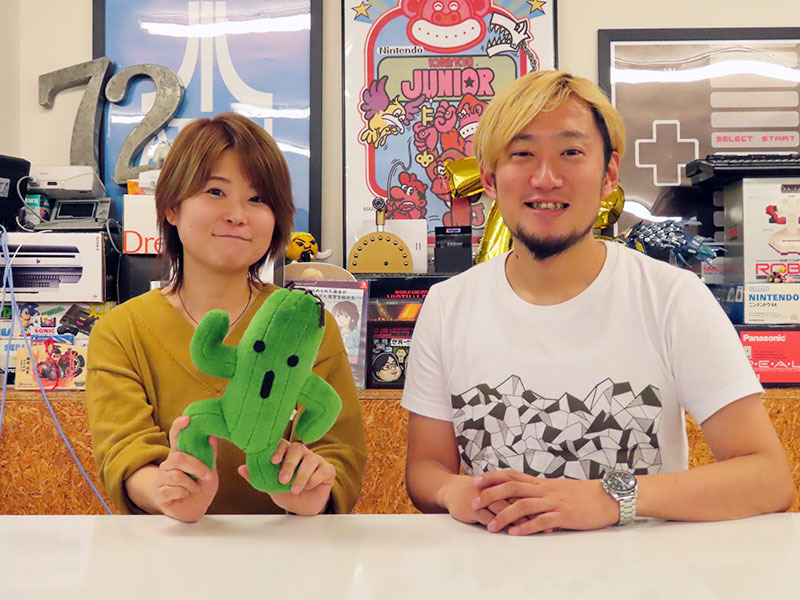ビジョンさえあればコンシューマゲームは半年で作れる! 河上聖治×アオキヒロシ×安藤武博クリエイター濃密鼎談
PSPで発売され、アクションとパズルが融合した斬新なゲーム性やスタイリッシュなグラフィックで話題を呼んだ『EXIT』。じつは、本作は制作期間がたった半年で作られたゲームだという。はたしてどのような経緯でこのゲームの企画が生まれ、完成していったのだろうか? この作品のキーマンである元TAITOのプロデューサー・河上聖治氏と、同じく元TAITOのディレクター・アオキヒロシ氏を迎え、その軌跡にゲームDJの安藤武博が深く切り込んでいく。

▲写真左から河上聖治氏、アオキヒロシ氏、安藤武博。
■PSPで『EXIT』が作られることになったきっかけ
安藤武博(以下、安藤):『EXIT』という作品は、2017年にシシララTVで実況もさせていただいたタイトルですが、納期や予算といった制約のあるなかでこれだけ独創的でチャレンジング、それでいてゲームバランスもしっかり取れたゲームを作り上げたことに改めて感銘を受けます。これはゲームのプロダクションを極めた人たちのチームワークだからこそ成し遂げた成果なのかなと思いました。当時、すでにおふたりは15年から20年ぐらいのキャリアはお持ちだったのでしょうか?
アオキヒロシさん(以下、アオキ):そうですね。業界入りしてから、確実に15年は過ぎていました。
河上聖治さん(以下、河上):わたしは高校を卒業してすぐタイトーに入ったので、もう30年以上ゲーム業界にいます(苦笑)。
安藤:すごい。レジェンドクリエイターですね。
アオキ:二人合わせると約60年(笑)。
安藤:合わせ技で還暦(笑)。おふたりは第一世代の家庭用ゲーム機から、ずっとゲームを作り続けてこられたわけですか。
河上:いえ、じつは僕もアオキも家庭用ゲーム機ではなく、アーケードゲームあがりのクリエイターなんです。
アオキ:じつはプレイステーション以前の家庭用ハードのゲームは作ったことがないんですよね。
安藤:最初は業務用のゲームを作られていたんですね。アオキさんのデビュー作はどんな作品になるのでしょうか?
アオキ:『パワーホイールズ(※1)』です。河上さんがリーダーで、わたしはプログラマーとして携わっていました。
(※1)1991年にTAITOからリリースされたアーケード用レースゲーム。ふたり分の座席がくっ付いた筐体が特徴で、豪快なレースが楽しめる。
河上:わたしは『ラスタンサーガ(※2)』です。モンスターや背景のドットを描いていました。もともとプログラムがやりたくてタイトーに入ったのですが、企画職が足りないということで企画になったんです。当時は企画とデザイナーに区別がなかったので、ドットを描いていたわけです(苦笑)。
(※2)1987年にTAITOからリリースされたアクションゲーム。蛮人の戦士ラスタンを操り、敵の城に乗り込みドラゴンを倒すために戦っていく。
安藤:経歴を見ると河上さんはプロデューサーとしてクレジットされているタイトルも多いですね。
河上:そうですね。『ドンドコドン(※3)』あたりからかな。
(※3)1989年にTAITOからリリースされたアクションゲーム。『フェアリーランドストーリー』や『バブルボブル』シリーズの流れを汲む名作。
アオキ:当時はプロデューサーという概念があまりなかったと思います。よくプロジェクトリーダーと呼ばれてましたね。
安藤武博(以下、安藤):『EXIT』という作品は、2017年にシシララTVで実況もさせていただいたタイトルですが、納期や予算といった制約のあるなかでこれだけ独創的でチャレンジング、それでいてゲームバランスもしっかり取れたゲームを作り上げたことに改めて感銘を受けます。これはゲームのプロダクションを極めた人たちのチームワークだからこそ成し遂げた成果なのかなと思いました。当時、すでにおふたりは15年から20年ぐらいのキャリアはお持ちだったのでしょうか?
アオキヒロシさん(以下、アオキ):そうですね。業界入りしてから、確実に15年は過ぎていました。
河上聖治さん(以下、河上):わたしは高校を卒業してすぐタイトーに入ったので、もう30年以上ゲーム業界にいます(苦笑)。
安藤:すごい。レジェンドクリエイターですね。
アオキ:二人合わせると約60年(笑)。
安藤:合わせ技で還暦(笑)。おふたりは第一世代の家庭用ゲーム機から、ずっとゲームを作り続けてこられたわけですか。
河上:いえ、じつは僕もアオキも家庭用ゲーム機ではなく、アーケードゲームあがりのクリエイターなんです。
アオキ:じつはプレイステーション以前の家庭用ハードのゲームは作ったことがないんですよね。
安藤:最初は業務用のゲームを作られていたんですね。アオキさんのデビュー作はどんな作品になるのでしょうか?
アオキ:『パワーホイールズ(※1)』です。河上さんがリーダーで、わたしはプログラマーとして携わっていました。
(※1)1991年にTAITOからリリースされたアーケード用レースゲーム。ふたり分の座席がくっ付いた筐体が特徴で、豪快なレースが楽しめる。
河上:わたしは『ラスタンサーガ(※2)』です。モンスターや背景のドットを描いていました。もともとプログラムがやりたくてタイトーに入ったのですが、企画職が足りないということで企画になったんです。当時は企画とデザイナーに区別がなかったので、ドットを描いていたわけです(苦笑)。
(※2)1987年にTAITOからリリースされたアクションゲーム。蛮人の戦士ラスタンを操り、敵の城に乗り込みドラゴンを倒すために戦っていく。
安藤:経歴を見ると河上さんはプロデューサーとしてクレジットされているタイトルも多いですね。
河上:そうですね。『ドンドコドン(※3)』あたりからかな。
(※3)1989年にTAITOからリリースされたアクションゲーム。『フェアリーランドストーリー』や『バブルボブル』シリーズの流れを汲む名作。
アオキ:当時はプロデューサーという概念があまりなかったと思います。よくプロジェクトリーダーと呼ばれてましたね。

河上:ゲームを作るチームの人数も少なかったですからね。『ドンドコドン』は企画とドットを自分でもやっていました。制作時間も短く、3カ月か4カ月で作った作品なんです。
安藤:そんなおふたりが家庭用ゲーム機を作るようになったのは、いつからなのでしょうか?
アオキ:シシララTVさんともなじみが深い『サイキックフォース(※5)』からですね。このタイトルは家庭用と業務用の両方を作っていました。ちなみに続編の『サイキックフォース2012』は、自分がアーケードで関わった最後の作品になりました。それ以降は家庭用開発にシフトしたため、キャリアとしては今の家庭用の方が業務用より長くなっています。
(※5)1996年にTAITOからリリースされた対戦格闘ゲーム。「サイキッカー」と呼ばれる者たちの戦いを描くストーリー性とキャラクターの魅力で人気に。
河上:わたしが最後に自分で手掛けたのは『きらめきスターロード♪イントロ倶楽部♪(※6)』でした。その後は進行管理の仕事が増えてきて。
(※6)1997年にTAITOからリリースされたクイズゲーム。イントロとともに出題されるクイズに挑むゲーム性で話題に。
アオキ:河上さんは、徐々に制作進行に近い立ち位置になっていきましたよね。
安藤:そんなおふたりがタッグを組み、2005年に『EXIT』を発売するわけですが、当時はどういった時代だったのでしょう?
アオキ:据え置き機が市場の中心の頃は、TAITO社内に「他社の大型タイトルに追いつこう」という意識が強かったように思うのですが、PSPやニンテンドーDSの台頭による携帯ゲーム市場の活性化により、もっと小回りの利くタイトルを作る方向に考えが変わった時期だったように思います。そんなときに部署の再編やプロジェクトの解体などがありまして、これまでの仕事にリセットをかけ、企画をイチから練り直すことになったんです。
その混沌期を経て生まれたタイトルが『EXIT』、そして『ロストマジック(※7)』でした。それまでは『武刃街(※8)』のようなミドル級のタイトルを手掛けることが多かったのですが、このタイミングでガラリとブランドのイメージが変わりましたね。
(※7)2006年にTAITOからリリースされたニンテンドーDSのアクションRPG。
(※8)2003年にTAITOからリリースされたPS2のアクションゲーム。アーティストのGACKTさんがキャラクターに起用されて話題となった。
安藤:わたしは2005年に『ヘビーメタルサンダー』をリリースしましたが、このタイトルは制作に3年以上の時間がかかりました。商業的に成功できなかったこともあり、今後はもっと小回りがきくタイトルを作らねばダメだと身をもって実感しましたね。
河上:当時はTAITOも厳しかったですよ。『電車でGO(※9)』と『武刃街』しか看板となるタイトルが出ていなかったので、早く次の結果を出さなければならなかったですから。
(※9)1997年にTAITOからリリースされた鉄道運転シミュレーション。アーケードからPSへの移植版は100万本以上を売り上げ、その後アーケードや家庭用ゲーム機で続編が次々に作られた。
アオキ:確かにそういう雰囲気はありましたよね。ただ、当時のマネージャーが部署を再編してくれたのは良かったことだったと思います。心機一転して頑張れましたから。
安藤:リフレッシュした環境のなかで『EXIT』の企画が動き出した、と。そもそもこの作品が生まれたきっかけはなんだったのでしょう?
アオキ:「2005年内に発売できるアクションゲームをPSPで作れ」という命題が、会社から下されたことがきっかけですね。
安藤:そんなおふたりが家庭用ゲーム機を作るようになったのは、いつからなのでしょうか?
アオキ:シシララTVさんともなじみが深い『サイキックフォース(※5)』からですね。このタイトルは家庭用と業務用の両方を作っていました。ちなみに続編の『サイキックフォース2012』は、自分がアーケードで関わった最後の作品になりました。それ以降は家庭用開発にシフトしたため、キャリアとしては今の家庭用の方が業務用より長くなっています。
(※5)1996年にTAITOからリリースされた対戦格闘ゲーム。「サイキッカー」と呼ばれる者たちの戦いを描くストーリー性とキャラクターの魅力で人気に。
河上:わたしが最後に自分で手掛けたのは『きらめきスターロード♪イントロ倶楽部♪(※6)』でした。その後は進行管理の仕事が増えてきて。
(※6)1997年にTAITOからリリースされたクイズゲーム。イントロとともに出題されるクイズに挑むゲーム性で話題に。
アオキ:河上さんは、徐々に制作進行に近い立ち位置になっていきましたよね。
安藤:そんなおふたりがタッグを組み、2005年に『EXIT』を発売するわけですが、当時はどういった時代だったのでしょう?
アオキ:据え置き機が市場の中心の頃は、TAITO社内に「他社の大型タイトルに追いつこう」という意識が強かったように思うのですが、PSPやニンテンドーDSの台頭による携帯ゲーム市場の活性化により、もっと小回りの利くタイトルを作る方向に考えが変わった時期だったように思います。そんなときに部署の再編やプロジェクトの解体などがありまして、これまでの仕事にリセットをかけ、企画をイチから練り直すことになったんです。
その混沌期を経て生まれたタイトルが『EXIT』、そして『ロストマジック(※7)』でした。それまでは『武刃街(※8)』のようなミドル級のタイトルを手掛けることが多かったのですが、このタイミングでガラリとブランドのイメージが変わりましたね。
(※7)2006年にTAITOからリリースされたニンテンドーDSのアクションRPG。
(※8)2003年にTAITOからリリースされたPS2のアクションゲーム。アーティストのGACKTさんがキャラクターに起用されて話題となった。
安藤:わたしは2005年に『ヘビーメタルサンダー』をリリースしましたが、このタイトルは制作に3年以上の時間がかかりました。商業的に成功できなかったこともあり、今後はもっと小回りがきくタイトルを作らねばダメだと身をもって実感しましたね。
河上:当時はTAITOも厳しかったですよ。『電車でGO(※9)』と『武刃街』しか看板となるタイトルが出ていなかったので、早く次の結果を出さなければならなかったですから。
(※9)1997年にTAITOからリリースされた鉄道運転シミュレーション。アーケードからPSへの移植版は100万本以上を売り上げ、その後アーケードや家庭用ゲーム機で続編が次々に作られた。
アオキ:確かにそういう雰囲気はありましたよね。ただ、当時のマネージャーが部署を再編してくれたのは良かったことだったと思います。心機一転して頑張れましたから。
安藤:リフレッシュした環境のなかで『EXIT』の企画が動き出した、と。そもそもこの作品が生まれたきっかけはなんだったのでしょう?
アオキ:「2005年内に発売できるアクションゲームをPSPで作れ」という命題が、会社から下されたことがきっかけですね。

安藤:すでにゴールラインが決められたうえでのキックオフだったわけですか。
アオキ:わたしたちが『武刃街』を開発したチームだったこともあり、『武刃街』のエンジンを上手に使え、というお題も出ていました。ただ、PSPのスペックで『武刃街』のような作品を作れるかはまったく未知数だったので、チーム内でアンケートをとってみたんです。PSPで『武刃街』を作るか、それとも新しいものを作るか。結果は、僅差でしたが“『武刃街』ような作品”のほうが多かったんですよね。
安藤:会社からそのようなお題が出されていたわけですから、当然と言えば当然ですね。
アオキ:ええ。その一方で新しいものに挑戦しようという意見も決して少なくなかったので、私の独断で完全新規の方向でいくと決めました。なぜなら半年という短い制作期間で『武刃街』のようなアクションゲームを仕上げられるイメージが頭の中に描けなかったのと、私自身がPSPを手に取ったときに、「このハードで遊びたいのは『武刃街』よりもっとコンパクトなゲームだ」と思ったからです。
あとは、当時のPSP市場が他機種からの移植モノやミニゲーム集といった作品ばかりだったので、このタイミングでオリジナルを発表することに意味があるとも考えました。ユーザーさんがPSP本体を買いたくなるような作品を我々で作りたいという反骨精神があったんですよね。
■どうすればコンシューマーゲームを半年間で形にできるのか?
安藤:『EXIT』の製作期間は半年しかなかったんですよね? 改めて驚きました。
アオキ:4月に企画がスタートして10月にはマスターアップしていましたから、本当に半年間ですね。
河上:お題が出されたのが2月で、実際に動き出したのが4月でしたからね。
安藤:しかし『武刃街』のエンジンも使わずにゼロから企画をスタートさせ、それを半年で完成させるというのは、想像以上に大変だったのではないでしょうか。
アオキ:最初はいろいろありましたね……(苦笑)。チーム全員でアイデアを出し合ってはみたものの思うように進捗しなかったので、途中から少人数チームでコンペをやる方法に切り替えたんです。まずコンセプトとなりそうなキーワードを全員で挙げていって、その中から「このキーワードとこのキーワードを組み合わせると面白そうだ」というものを5つぐらいに絞り込み、その組み合わせに引っかかったメンバー同士を小チームに振り分けました。そして各チームで練った企画を互いにプレゼンし、投票で決を採りました。
河上:すごく広い和室で会議をしていたことを覚えています(笑)。
アオキ:確か、その時通常の会議室の予約が取れなかったんですよ(笑)。
安藤:刺激的ですね。タイトルごとに毎回やっているものなんですか?
アオキ:いいえ、はじめての試みでした。残りの期間を考えると後がなかったので、やるしかないという状況でした(苦笑)。
アオキ:わたしたちが『武刃街』を開発したチームだったこともあり、『武刃街』のエンジンを上手に使え、というお題も出ていました。ただ、PSPのスペックで『武刃街』のような作品を作れるかはまったく未知数だったので、チーム内でアンケートをとってみたんです。PSPで『武刃街』を作るか、それとも新しいものを作るか。結果は、僅差でしたが“『武刃街』ような作品”のほうが多かったんですよね。
安藤:会社からそのようなお題が出されていたわけですから、当然と言えば当然ですね。
アオキ:ええ。その一方で新しいものに挑戦しようという意見も決して少なくなかったので、私の独断で完全新規の方向でいくと決めました。なぜなら半年という短い制作期間で『武刃街』のようなアクションゲームを仕上げられるイメージが頭の中に描けなかったのと、私自身がPSPを手に取ったときに、「このハードで遊びたいのは『武刃街』よりもっとコンパクトなゲームだ」と思ったからです。
あとは、当時のPSP市場が他機種からの移植モノやミニゲーム集といった作品ばかりだったので、このタイミングでオリジナルを発表することに意味があるとも考えました。ユーザーさんがPSP本体を買いたくなるような作品を我々で作りたいという反骨精神があったんですよね。
■どうすればコンシューマーゲームを半年間で形にできるのか?
安藤:『EXIT』の製作期間は半年しかなかったんですよね? 改めて驚きました。
アオキ:4月に企画がスタートして10月にはマスターアップしていましたから、本当に半年間ですね。
河上:お題が出されたのが2月で、実際に動き出したのが4月でしたからね。
安藤:しかし『武刃街』のエンジンも使わずにゼロから企画をスタートさせ、それを半年で完成させるというのは、想像以上に大変だったのではないでしょうか。
アオキ:最初はいろいろありましたね……(苦笑)。チーム全員でアイデアを出し合ってはみたものの思うように進捗しなかったので、途中から少人数チームでコンペをやる方法に切り替えたんです。まずコンセプトとなりそうなキーワードを全員で挙げていって、その中から「このキーワードとこのキーワードを組み合わせると面白そうだ」というものを5つぐらいに絞り込み、その組み合わせに引っかかったメンバー同士を小チームに振り分けました。そして各チームで練った企画を互いにプレゼンし、投票で決を採りました。
河上:すごく広い和室で会議をしていたことを覚えています(笑)。
アオキ:確か、その時通常の会議室の予約が取れなかったんですよ(笑)。
安藤:刺激的ですね。タイトルごとに毎回やっているものなんですか?
アオキ:いいえ、はじめての試みでした。残りの期間を考えると後がなかったので、やるしかないという状況でした(苦笑)。
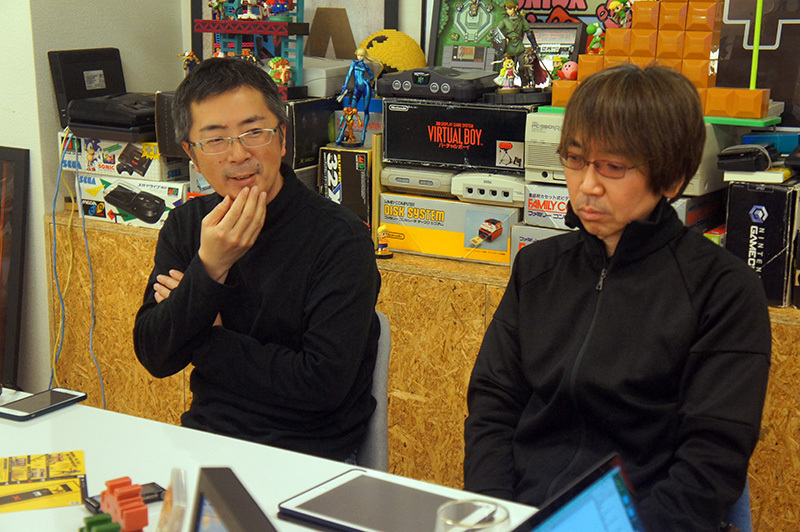
安藤:そのコンペから、どのようにして『EXIT』が立ちあがったのでしょう。
アオキ:『EXIT』はわたしがいた3人のチームで作った企画で、それがコンペで一番多くの票を獲得したんです。そのときのキーワードは“アクション”と“集団”という組み合わせで、そこから「集団で災害現場から脱出するアクションゲーム」というコンセプトを導き出しました。当初わたしが抱いたイメージは『レミングス』や『ピクミン』のようなものでしたが、ほかのメンバーから『セプテントリオン』じゃないかという声が挙がったので、そのビジョンを参考に内容を構築していきました。
安藤:『セプテントリオン』……嵐で沈没しそうになっている船から脱出するアクションゲームですね。たしかに、『EXIT』のゲーム性はあれに近いものを感じます。
アオキ:ただ、当時わたしが『セプテントリオン』をよく知らなかったので、あまりそこに縛られず純粋に「要救助者をどうやって脱出させるのか」そして「脱出にあたって、どうやって同行者と協力するのか」という部分に焦点を当てて、企画を練り込んでいく感じでした。
安藤:生放送の際、初期のコンセプトアートやプロモーションビデオも見せていただきましたが、そのときからかなりイメージは出来上がっていたように思います。
アオキ:そうですね。あれはプロジェクトが動き出してから1~2カ月くらいで作ったもので、そのおかげでゲームのイメージが早期に固まりました。
安藤:なるほど。半年で制作するとなると、逆にそのぐらいのタイミングではイメージがしっかり固まっていないといけないでしょうね。ちなみに、半年でゲームを完成させる秘訣のようなものはありますか?
アオキ:ノウハウやテクニックのようなものはとくにありませんでしたが、『EXIT』の場合、方向性を早めに示せたことがやはり大きかったんだと思います。シルエット調のキャラクターを採用した時点でモーションキャプチャーを使うことは決めてましたし、グラフィックデザインもすんなりアメコミ風に落ちつきました。モーションキャプチャーに関しても、アクターを開発スタッフに担当してもらったことが、スタッフ内でのイメージ共有に一役買ったと思います。
安藤:なるほど。箱をよじ登ったり女の子を持ち上げるといったアクションが身体的にどういうことになるのか、モーションキャプチャーを体験したことでわかるわけですね。
アオキ:はい。アクター費用も安く付きましたので、正に一石二鳥でした。
安藤:現在も過去も、納期内に間に合わせるというのは本当に難易度が高いことです。
アオキ:ええ。とくに新規タイトルの場合、ディレクターの中に完成系のビジョンがしっかり出来上がっていることが大事だと思います。これさえできていれば短期の開発が可能であることを、よくも悪くも『EXIT』で証明してしまったという感じですね(苦笑)。
河上:そうですね。ディレクターさんがしっかりビジョンを持っているタイトルは失敗しません。逆に、完成系が見えていないと途中でブレちゃうんですよね。いろいろな要素を追加しようとして、結果的に納期に間に合わなくなってしまったり。
安藤:逆に強固なビジョンを持って試作したのに、面白いものにならなかった場合、ディレクターはどうやって持ち直していくのでしょうか。わたしもクオリティを重視して納期を遅らせた経験があるので、ぜひお聞かせ願えればと。
アオキ:ちゃんと答えになっているかわかりませんが、“邪魔をしない”ことが重要だと思います。
安藤:それは横から何も口を出さないほうがいいということですか?
アオキ:いえ、横からより上からの意見の影響力の方が危険だと思います。自分より上の立場の人間から「これ、こうした方がよくない?」と異なる価値観で言われてしまうと、とくに若いディレクターは自分の考えや判断に迷いを生みかねませんので。
アオキ:『EXIT』はわたしがいた3人のチームで作った企画で、それがコンペで一番多くの票を獲得したんです。そのときのキーワードは“アクション”と“集団”という組み合わせで、そこから「集団で災害現場から脱出するアクションゲーム」というコンセプトを導き出しました。当初わたしが抱いたイメージは『レミングス』や『ピクミン』のようなものでしたが、ほかのメンバーから『セプテントリオン』じゃないかという声が挙がったので、そのビジョンを参考に内容を構築していきました。
安藤:『セプテントリオン』……嵐で沈没しそうになっている船から脱出するアクションゲームですね。たしかに、『EXIT』のゲーム性はあれに近いものを感じます。
アオキ:ただ、当時わたしが『セプテントリオン』をよく知らなかったので、あまりそこに縛られず純粋に「要救助者をどうやって脱出させるのか」そして「脱出にあたって、どうやって同行者と協力するのか」という部分に焦点を当てて、企画を練り込んでいく感じでした。
安藤:生放送の際、初期のコンセプトアートやプロモーションビデオも見せていただきましたが、そのときからかなりイメージは出来上がっていたように思います。
アオキ:そうですね。あれはプロジェクトが動き出してから1~2カ月くらいで作ったもので、そのおかげでゲームのイメージが早期に固まりました。
安藤:なるほど。半年で制作するとなると、逆にそのぐらいのタイミングではイメージがしっかり固まっていないといけないでしょうね。ちなみに、半年でゲームを完成させる秘訣のようなものはありますか?
アオキ:ノウハウやテクニックのようなものはとくにありませんでしたが、『EXIT』の場合、方向性を早めに示せたことがやはり大きかったんだと思います。シルエット調のキャラクターを採用した時点でモーションキャプチャーを使うことは決めてましたし、グラフィックデザインもすんなりアメコミ風に落ちつきました。モーションキャプチャーに関しても、アクターを開発スタッフに担当してもらったことが、スタッフ内でのイメージ共有に一役買ったと思います。
安藤:なるほど。箱をよじ登ったり女の子を持ち上げるといったアクションが身体的にどういうことになるのか、モーションキャプチャーを体験したことでわかるわけですね。
アオキ:はい。アクター費用も安く付きましたので、正に一石二鳥でした。
安藤:現在も過去も、納期内に間に合わせるというのは本当に難易度が高いことです。
アオキ:ええ。とくに新規タイトルの場合、ディレクターの中に完成系のビジョンがしっかり出来上がっていることが大事だと思います。これさえできていれば短期の開発が可能であることを、よくも悪くも『EXIT』で証明してしまったという感じですね(苦笑)。
河上:そうですね。ディレクターさんがしっかりビジョンを持っているタイトルは失敗しません。逆に、完成系が見えていないと途中でブレちゃうんですよね。いろいろな要素を追加しようとして、結果的に納期に間に合わなくなってしまったり。
安藤:逆に強固なビジョンを持って試作したのに、面白いものにならなかった場合、ディレクターはどうやって持ち直していくのでしょうか。わたしもクオリティを重視して納期を遅らせた経験があるので、ぜひお聞かせ願えればと。
アオキ:ちゃんと答えになっているかわかりませんが、“邪魔をしない”ことが重要だと思います。
安藤:それは横から何も口を出さないほうがいいということですか?
アオキ:いえ、横からより上からの意見の影響力の方が危険だと思います。自分より上の立場の人間から「これ、こうした方がよくない?」と異なる価値観で言われてしまうと、とくに若いディレクターは自分の考えや判断に迷いを生みかねませんので。

河上:そうですね。そういう側面はあると思います。
アオキ:『EXIT』では河上さんがゲームに対して大きな要求をしてくることは一度もありませんでした。その寛容さには助けられた思いです。もし自己主張の強いプロデューサーとの仕事だったら意見のぶつかりが度々発生して、半年で完成させるのは難しかったと思いますね。
安藤:そうなると、上長やプロデューサーといった人間は、途中経過で面白くないと感じても、グッとこらえる必要が出てきます。
アオキ:もちろん意見を一切言わない方がよいというわけではありません。ただプロジェクト開始当初から、プロデューサーとディレクターの間で方向性のすり合わせを十分にしておかないと、結局「誰の意見でこうなったんだっけ?」となってしまうケースがよくあります。
安藤:難しいですね(苦笑)。プロデューサーである河上さんは、この点に関してどうお考えですか?
河上:難しいです(苦笑)。そこがまた、ゲーム作りの面白さでもあると思いますけどね。
安藤:プロデューサー目線で見て、短期間でクオリティの高い作品を生み出すためのコツなどあれば教えて欲しいのですが。
河上:基本的にはディレクターを尊重しますが、若いディレクターは「あとでこんな仕様を入れます」とか「ここは抜けていますけどあとで修正します」といった、その場しのぎの発言をしてしまうことが多いように思いますね。あれはとても良くない。実装したあとにうまくいかないことがわかることも多いので、それを見越して早めにやっておくべきではないかと。そこらへんを徹底できるかどうかで、作品の納期やクオリティに差が出てくると思います。
安藤:参考になります。では、おふたりはどんな人がディレクターに向いていると思いますか?
河上:わたしは制作の能力以前に、人をまとめる力があるかどうかを重視しますね。ディレクターにリーダーシップがなければ、プロジェクトはうまく進みませんから。
アオキ:河上さんの意見に賛成です。それ以外で考えるなら、強烈なビジョンを持っている人ですね。僕なんかは、もしそういう若い人がいたらぜひ引っ張り上げてあげたいなと思ってしまいます。
安藤:「俺はこういうものが作りたいんだ」という情熱を持っている人ですね。
アオキ:ただ、その情熱というか自分のビジョンをプロジェクトメンバーに共有できない人だと困りますけど(笑)。
安藤:ビジョンを明確に持つためにはどういったことをすればいいのでしょう?
アオキ:どこが面白いのか論理的に説明できる能力を磨くことでしょうね。最初の発想はとくにロジカルである必要はありませんが、それを理屈に変換できればチームメンバーへの説得力が増すと思うんですよ。「なんとなくイイ」とか「俺はこれが好き」というレベルのままだと伝わらないので、考えをロジックに落とし込むことが重要だと思います。
安藤:自分なりにおもしろさのロジックを紐解いて、他人に説明するというのは必須能力だと感じます。
アオキ:例えば映画でもゲームでも良いのですが、「ここが好きだな」とか「ここが面白いな」と気付いたら、どうしてそう思ったのかを分析するクセを付けると良いと思います。
アオキ:『EXIT』では河上さんがゲームに対して大きな要求をしてくることは一度もありませんでした。その寛容さには助けられた思いです。もし自己主張の強いプロデューサーとの仕事だったら意見のぶつかりが度々発生して、半年で完成させるのは難しかったと思いますね。
安藤:そうなると、上長やプロデューサーといった人間は、途中経過で面白くないと感じても、グッとこらえる必要が出てきます。
アオキ:もちろん意見を一切言わない方がよいというわけではありません。ただプロジェクト開始当初から、プロデューサーとディレクターの間で方向性のすり合わせを十分にしておかないと、結局「誰の意見でこうなったんだっけ?」となってしまうケースがよくあります。
安藤:難しいですね(苦笑)。プロデューサーである河上さんは、この点に関してどうお考えですか?
河上:難しいです(苦笑)。そこがまた、ゲーム作りの面白さでもあると思いますけどね。
安藤:プロデューサー目線で見て、短期間でクオリティの高い作品を生み出すためのコツなどあれば教えて欲しいのですが。
河上:基本的にはディレクターを尊重しますが、若いディレクターは「あとでこんな仕様を入れます」とか「ここは抜けていますけどあとで修正します」といった、その場しのぎの発言をしてしまうことが多いように思いますね。あれはとても良くない。実装したあとにうまくいかないことがわかることも多いので、それを見越して早めにやっておくべきではないかと。そこらへんを徹底できるかどうかで、作品の納期やクオリティに差が出てくると思います。
安藤:参考になります。では、おふたりはどんな人がディレクターに向いていると思いますか?
河上:わたしは制作の能力以前に、人をまとめる力があるかどうかを重視しますね。ディレクターにリーダーシップがなければ、プロジェクトはうまく進みませんから。
アオキ:河上さんの意見に賛成です。それ以外で考えるなら、強烈なビジョンを持っている人ですね。僕なんかは、もしそういう若い人がいたらぜひ引っ張り上げてあげたいなと思ってしまいます。
安藤:「俺はこういうものが作りたいんだ」という情熱を持っている人ですね。
アオキ:ただ、その情熱というか自分のビジョンをプロジェクトメンバーに共有できない人だと困りますけど(笑)。
安藤:ビジョンを明確に持つためにはどういったことをすればいいのでしょう?
アオキ:どこが面白いのか論理的に説明できる能力を磨くことでしょうね。最初の発想はとくにロジカルである必要はありませんが、それを理屈に変換できればチームメンバーへの説得力が増すと思うんですよ。「なんとなくイイ」とか「俺はこれが好き」というレベルのままだと伝わらないので、考えをロジックに落とし込むことが重要だと思います。
安藤:自分なりにおもしろさのロジックを紐解いて、他人に説明するというのは必須能力だと感じます。
アオキ:例えば映画でもゲームでも良いのですが、「ここが好きだな」とか「ここが面白いな」と気付いたら、どうしてそう思ったのかを分析するクセを付けると良いと思います。

安藤:河上さんにはリーダーシップについてお聞きしたいのですが、人をまとめる力というのはどうすれば磨かれると思いますか?
河上:わたしが最初にタイトーに入ったときは、何もわからない状態で年上の外注さんと組むことになりました。そのときはがむしゃらに対応していましたが、そういったことを繰り返していくなかで「こういうことを言うと人は傷つくんだな」といったことを学べたと思います。だから、やはり経験を積むことも重要だと思います。
安藤:若いかたはディレクターになる前に、ほかの法人の方と組んで仕事をすることもあるでしょうし、そこでしっかりコミュニケーションを学ぶべきですね。
河上:問題はどうしたって起きますし、問題が発生したときにどうやって対応したかが重要なのでやはり経験を積むしかないと思います。いろいろな無茶を乗り越えてきた人間でないとリーダーは務まらないです。
安藤:そんなしっかりとしたビジョンを持つおふたりが中心となって作られた『EXIT』ですが、ほかにはどういったメンバーが参加されていたのでしょうか?
アオキ:『武刃街』の制作で一緒だったメンバーが中心で、ある程度キャリアを積んだ人間が多かったです。誰がどの能力に長けているのかがすでにわかっていたので、とてもやりやすかったですね。逆に新規で組むメンバーばかりだったら半年で制作するのは難しかったかもしれません(苦笑)。人間関係が最初から出来ていると、互いに意見を言いやすいですし。
■『EXIT』に詰め込まれたさまざまなアイデアが生まれたきっかけ
安藤:ここからは『EXIT』の中身についてお聞きしていきたいと思います。プレイして気付いたのは、じつに多様なギミックがあるということ。半年のプロジェクトでここまで出来るんだと感動しました。だんだんギミックが開放されていき、最終的に宇宙人とやり取りできる流れも単純にすごい。あれらのギミックはどのように思いついたアイデアなのでしょうか?
アオキ:“こういうアイテムやギミックがあればこういうアクションができる”という観点から組み立てていきました。まずはどんどんアイデアを出して、あとから無駄なものを削って仕様に落として込んでいきました。あと、『EXIT』を半年で開発するという点で、猿楽庁さんの参加は大きかったと思います。
安藤:猿楽庁は、本作にどのような形で関わっておられたのでしょう?
アオキ:猿楽庁さんはデバッグ業務のみならず、ゲームのクオリティアップのためにチューニングを施してくださる会社さんです。事実、この『EXIT』では社内の企画スタッフの不足もあり、殆どのマップのデザインやチューニングを猿楽庁さんにお願いしました。また、『EXIT』のマップエディタはマウスで操作できるPCアプリだったのですが、それも最初から猿楽庁さんありきで開発を進めるために準備したものだったんです。
安藤:デバッグやゲームバランスの調整を行っている会社だと思っていましたが、そんなことまでやられているんですね。勉強不足でした。
河上:『1』も『2』もDS版も、チューニングはすべて猿楽庁さんにお願いしました。とても信頼できる会社さんですよ。
河上:わたしが最初にタイトーに入ったときは、何もわからない状態で年上の外注さんと組むことになりました。そのときはがむしゃらに対応していましたが、そういったことを繰り返していくなかで「こういうことを言うと人は傷つくんだな」といったことを学べたと思います。だから、やはり経験を積むことも重要だと思います。
安藤:若いかたはディレクターになる前に、ほかの法人の方と組んで仕事をすることもあるでしょうし、そこでしっかりコミュニケーションを学ぶべきですね。
河上:問題はどうしたって起きますし、問題が発生したときにどうやって対応したかが重要なのでやはり経験を積むしかないと思います。いろいろな無茶を乗り越えてきた人間でないとリーダーは務まらないです。
安藤:そんなしっかりとしたビジョンを持つおふたりが中心となって作られた『EXIT』ですが、ほかにはどういったメンバーが参加されていたのでしょうか?
アオキ:『武刃街』の制作で一緒だったメンバーが中心で、ある程度キャリアを積んだ人間が多かったです。誰がどの能力に長けているのかがすでにわかっていたので、とてもやりやすかったですね。逆に新規で組むメンバーばかりだったら半年で制作するのは難しかったかもしれません(苦笑)。人間関係が最初から出来ていると、互いに意見を言いやすいですし。
■『EXIT』に詰め込まれたさまざまなアイデアが生まれたきっかけ
安藤:ここからは『EXIT』の中身についてお聞きしていきたいと思います。プレイして気付いたのは、じつに多様なギミックがあるということ。半年のプロジェクトでここまで出来るんだと感動しました。だんだんギミックが開放されていき、最終的に宇宙人とやり取りできる流れも単純にすごい。あれらのギミックはどのように思いついたアイデアなのでしょうか?
アオキ:“こういうアイテムやギミックがあればこういうアクションができる”という観点から組み立てていきました。まずはどんどんアイデアを出して、あとから無駄なものを削って仕様に落として込んでいきました。あと、『EXIT』を半年で開発するという点で、猿楽庁さんの参加は大きかったと思います。
安藤:猿楽庁は、本作にどのような形で関わっておられたのでしょう?
アオキ:猿楽庁さんはデバッグ業務のみならず、ゲームのクオリティアップのためにチューニングを施してくださる会社さんです。事実、この『EXIT』では社内の企画スタッフの不足もあり、殆どのマップのデザインやチューニングを猿楽庁さんにお願いしました。また、『EXIT』のマップエディタはマウスで操作できるPCアプリだったのですが、それも最初から猿楽庁さんありきで開発を進めるために準備したものだったんです。
安藤:デバッグやゲームバランスの調整を行っている会社だと思っていましたが、そんなことまでやられているんですね。勉強不足でした。
河上:『1』も『2』もDS版も、チューニングはすべて猿楽庁さんにお願いしました。とても信頼できる会社さんですよ。

アオキ:今はむしろデバック業務はやっておらず、チューニングをメインに仕事をされていますね。
安藤:ではここで、今だからこそ話せる苦労話なども教えていただければと。
アオキ:うーん、短期間ということもあって、苦労があまりなく割りとスムーズに開発が進行したんですよね。あえて自分で反省点をあげるならジャンプのタイミングがシビアだったことでしょうか。
河上:ああ、確かにそれは当時も営業から言われていました(笑)。ただ、あのクセさえもゲームの味だと思ったので、わざと直しませんでしたけど。
アオキ:私が『プリンス・オブ・ペルシャ』のような操作にちょっとクセがあるゲームが好きなこともあり、慣れが必要な要素をどこかに入れたかったんです。慣れていくことでプレイスキルの成長を感じさせたかったというのがありました。
安藤:運転の難しい車やバイクを、少しずつ乗りこなしていくような楽しさですよね。
アオキ:でも、ジャンプという基本動作にアクセントを持たせてしまったので、アクション的に妙な難しさを印象付けてしまったかもしれないですね。
安藤:ギミック部分がドライブした結果、アクションよりもパズルが難しくなる側面が出た。
アオキ:それは猿楽庁さんが本気を出した結果でもありますね(苦笑)。猿楽庁さんの作るマップが本当によく練られていて面白かったんですよ。
安藤:先ほど営業のほうからクレームが来たとお話されていましたが、現在はクリエイターとプレイヤーの距離感も近くなって直に評価が届くような時代になりましたよね。それについてはどうお考えですか?
河上:最近、ちょっと近すぎるかなとは思っているんですよね(苦笑)。
アオキ:言いたい放題言われちゃいますもんね(苦笑)。
安藤:クリエイターとプレイヤーの距離の取りかたは難しいですよね。意見を取り入れるのか、己を貫き通すのか。現在は炎上してアップデートで対応することも多い。
河上:わたしは現在ソーシャル系のアプリも手掛けていますが、不具合に関してはすぐに対応するようにしています。ただ内容に関しては、ユーザーさんでも意見が割れるので難しいですね。変えすぎるとゲームのコンセプトもブレてしまいますから。
安藤:そこは昔のゲーム作りと変わらないですよね。アオキさんはいかがですか?
安藤:ではここで、今だからこそ話せる苦労話なども教えていただければと。
アオキ:うーん、短期間ということもあって、苦労があまりなく割りとスムーズに開発が進行したんですよね。あえて自分で反省点をあげるならジャンプのタイミングがシビアだったことでしょうか。
河上:ああ、確かにそれは当時も営業から言われていました(笑)。ただ、あのクセさえもゲームの味だと思ったので、わざと直しませんでしたけど。
アオキ:私が『プリンス・オブ・ペルシャ』のような操作にちょっとクセがあるゲームが好きなこともあり、慣れが必要な要素をどこかに入れたかったんです。慣れていくことでプレイスキルの成長を感じさせたかったというのがありました。
安藤:運転の難しい車やバイクを、少しずつ乗りこなしていくような楽しさですよね。
アオキ:でも、ジャンプという基本動作にアクセントを持たせてしまったので、アクション的に妙な難しさを印象付けてしまったかもしれないですね。
安藤:ギミック部分がドライブした結果、アクションよりもパズルが難しくなる側面が出た。
アオキ:それは猿楽庁さんが本気を出した結果でもありますね(苦笑)。猿楽庁さんの作るマップが本当によく練られていて面白かったんですよ。
安藤:先ほど営業のほうからクレームが来たとお話されていましたが、現在はクリエイターとプレイヤーの距離感も近くなって直に評価が届くような時代になりましたよね。それについてはどうお考えですか?
河上:最近、ちょっと近すぎるかなとは思っているんですよね(苦笑)。
アオキ:言いたい放題言われちゃいますもんね(苦笑)。
安藤:クリエイターとプレイヤーの距離の取りかたは難しいですよね。意見を取り入れるのか、己を貫き通すのか。現在は炎上してアップデートで対応することも多い。
河上:わたしは現在ソーシャル系のアプリも手掛けていますが、不具合に関してはすぐに対応するようにしています。ただ内容に関しては、ユーザーさんでも意見が割れるので難しいですね。変えすぎるとゲームのコンセプトもブレてしまいますから。
安藤:そこは昔のゲーム作りと変わらないですよね。アオキさんはいかがですか?

アオキ:わたしはどちらかというとユーザーさんとコミュニケーションを取ってしまうほうですね。お客さんの意見で開発者が右往左往してしまうのはよくないですが、プロデューサーやディレクターがビジョンをしっかり持っていて作っている物に自信があれば、ユーザーさんの声を聞くこと自体決してマイナスではないと思いますね。
安藤:若い世代のクリエイターたちに向けて、おふたりからアドバイスはありますか?
河上:いいえ、みなさん優秀ですから。とくにありませんね(笑)。
アオキ:私もとくにありません(笑)。
安藤:そうなんですか? この前、若いクリエイターさんとお話する機会があったのですが、横井軍平さんを知らなくてビックリしたんですよ。映画を作りたいと言っているのにチャップリンやヒッチコックを知らないのと同じだと思ったんですよね。
アオキ:なるほど……。ただ、ゲームは映画よりも歴史が浅いですし、今時PC一台あれば個人でゲームを作れる時代です。そうなると知識として横井軍平さんを知っていることがメリットだとしても、知らないことが絶対的なデメリットとも言えない気がします。
安藤:確かに横井さんの“枯れた技術の水平思考”はゲーム制作の大事なヒントになりますが、制作の限りにおいては横井さん自身のお名前を知っている必要はないかもしれません。
河上:むしろ、若い人よりも自分が成長しなければと考えることのほうが多いくらいですよ。最近はソーシャルアプリに携わらせていただいていることもあり、ゲームの製作は変わったなと気付かされます。
安藤:ゲームという概念自体が広がって多様化していますね。もしもみなさんが2017年に『EXIT』をリバイバルするのであればどのように作りたいですか?
アオキ:タッチパネル操作のゲームにしたいですね。わたしは『EXIT』はアクションとパズルが半々ぐらいのゲームだと思っているのですが、世間ではパズルと認識されています。それだったら、完全にパズルに特化した『EXIT』を作りたいですね。あと『EXIT』ではAIのナビゲーションを実装できなかったので、それをサポートした上で新しい遊びを作ってみたいです。
河上:わたしはいっそVR作品でリメイクしたいです。緊迫感があって面白いゲームに仕上がるのではないかと思います。
安藤:ぶら下がるとか落ちるといったアクションはVRで見てみたいですね。
河上:もしくはリアルにアトラクションを作りたいですね。
安藤:リアル脱出ゲームなども流行しているので面白いかもしれませんね。では最後にこれだけ長い間ゲーム制作を続けているおふたりから、「これがあるからゲーム作りがやめられない」と思うポイントをお聞きしてもよろしいでしょうか。
アオキ:わたしは2つあります。1つは自分が面白いと思ったものがユーザーさんに認められたとき、もう1つはユーザーさんからの意見が聞けたときです。ユーザーさんにゲームを面白いと言っていただけるのはもちろんうれしいことですが、逆に「ここはこうしてほしかった」とか自分になかった意見をもらえた時は、新しい発想に繋がったりするので、とてもありがたいです。
安藤:河上さんはいかがですか?
河上:やはり作っている作品がイメージ通りの形になっていくときがいちばんです。あとはメディアさんにプロモーションをして、反応が良かったときもすごくうれしいですね。
安藤:若い世代のクリエイターたちに向けて、おふたりからアドバイスはありますか?
河上:いいえ、みなさん優秀ですから。とくにありませんね(笑)。
アオキ:私もとくにありません(笑)。
安藤:そうなんですか? この前、若いクリエイターさんとお話する機会があったのですが、横井軍平さんを知らなくてビックリしたんですよ。映画を作りたいと言っているのにチャップリンやヒッチコックを知らないのと同じだと思ったんですよね。
アオキ:なるほど……。ただ、ゲームは映画よりも歴史が浅いですし、今時PC一台あれば個人でゲームを作れる時代です。そうなると知識として横井軍平さんを知っていることがメリットだとしても、知らないことが絶対的なデメリットとも言えない気がします。
安藤:確かに横井さんの“枯れた技術の水平思考”はゲーム制作の大事なヒントになりますが、制作の限りにおいては横井さん自身のお名前を知っている必要はないかもしれません。
河上:むしろ、若い人よりも自分が成長しなければと考えることのほうが多いくらいですよ。最近はソーシャルアプリに携わらせていただいていることもあり、ゲームの製作は変わったなと気付かされます。
安藤:ゲームという概念自体が広がって多様化していますね。もしもみなさんが2017年に『EXIT』をリバイバルするのであればどのように作りたいですか?
アオキ:タッチパネル操作のゲームにしたいですね。わたしは『EXIT』はアクションとパズルが半々ぐらいのゲームだと思っているのですが、世間ではパズルと認識されています。それだったら、完全にパズルに特化した『EXIT』を作りたいですね。あと『EXIT』ではAIのナビゲーションを実装できなかったので、それをサポートした上で新しい遊びを作ってみたいです。
河上:わたしはいっそVR作品でリメイクしたいです。緊迫感があって面白いゲームに仕上がるのではないかと思います。
安藤:ぶら下がるとか落ちるといったアクションはVRで見てみたいですね。
河上:もしくはリアルにアトラクションを作りたいですね。
安藤:リアル脱出ゲームなども流行しているので面白いかもしれませんね。では最後にこれだけ長い間ゲーム制作を続けているおふたりから、「これがあるからゲーム作りがやめられない」と思うポイントをお聞きしてもよろしいでしょうか。
アオキ:わたしは2つあります。1つは自分が面白いと思ったものがユーザーさんに認められたとき、もう1つはユーザーさんからの意見が聞けたときです。ユーザーさんにゲームを面白いと言っていただけるのはもちろんうれしいことですが、逆に「ここはこうしてほしかった」とか自分になかった意見をもらえた時は、新しい発想に繋がったりするので、とてもありがたいです。
安藤:河上さんはいかがですか?
河上:やはり作っている作品がイメージ通りの形になっていくときがいちばんです。あとはメディアさんにプロモーションをして、反応が良かったときもすごくうれしいですね。

安藤:先ほど最後の質問とお聞きしましたが、もうひとつだけお聞かせください。おふたりにとって、ゲームとはなんでしょうか?
河上:わたしはこの仕事に就く前からゲームセンターでずっとゲームをやって遊んでいましたから、ライフワークですね。
アオキ:ゲーム開発って「面白い」とか「楽しい」という人間の曖昧な感情に訴えるという、正解がないモノ作りなんですよね。
安藤:確かに人それぞれですよね。
アオキ:音楽や映像など全てのエンタテインメント作品にヒット作はありますが、逆にヒットしなかったマイナーな作品にも「良い」とか「好き」と言ってくれるファンがいるんですよね。そういうところにゲーム作りのやりがいと難しさを感じたりしてます。河上さんと同様に一生を掛けることができる仕事だなと、わたしも思います。
安藤:わたしも同意見です。お互いにゲームを作り続けていきましょう。今日はおふたりにとても活力をもらえました。きっとこの鼎談を読んでいる若いクリエイターさんたちにも届いていると思います。本日はありがとうございました。
河上:わたしはこの仕事に就く前からゲームセンターでずっとゲームをやって遊んでいましたから、ライフワークですね。
アオキ:ゲーム開発って「面白い」とか「楽しい」という人間の曖昧な感情に訴えるという、正解がないモノ作りなんですよね。
安藤:確かに人それぞれですよね。
アオキ:音楽や映像など全てのエンタテインメント作品にヒット作はありますが、逆にヒットしなかったマイナーな作品にも「良い」とか「好き」と言ってくれるファンがいるんですよね。そういうところにゲーム作りのやりがいと難しさを感じたりしてます。河上さんと同様に一生を掛けることができる仕事だなと、わたしも思います。
安藤:わたしも同意見です。お互いにゲームを作り続けていきましょう。今日はおふたりにとても活力をもらえました。きっとこの鼎談を読んでいる若いクリエイターさんたちにも届いていると思います。本日はありがとうございました。
シシララTV オリジナル記事