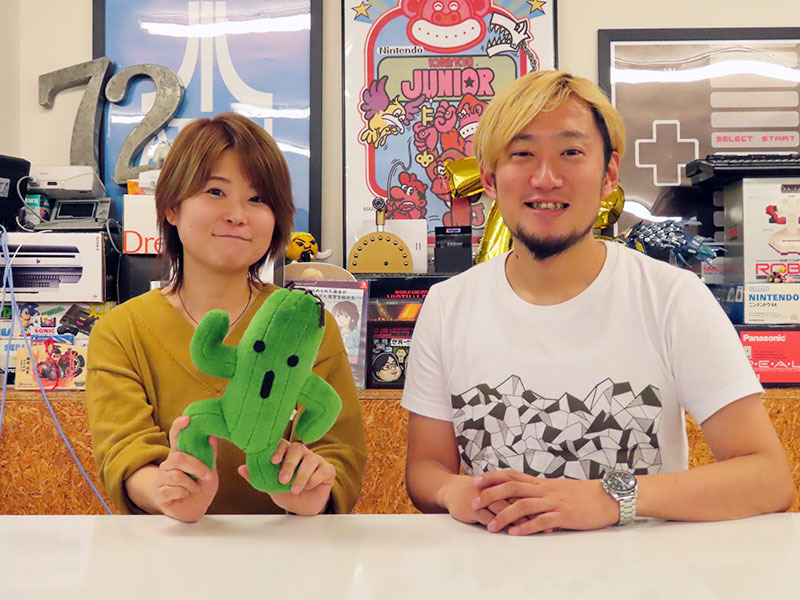「僕たちがKADOKAWAとスクエニを辞めた理由。」三木一馬VS安藤武博 濃密対談(前編)
KADOKAWA/電撃文庫編集部の編集長を務め、今年の春に独立してクリエイターマネジメント企業「ストレートエッジ」を立ち上げたエンタメ業界の仕掛け人・三木一馬氏。エージェントとして『とある魔術の禁書目録』の鎌池和馬氏や『ソードアート・オンライン』の川原 礫氏などの作家陣をプロデュースする三木氏が、出版業界の最大手を辞してまで叶えたかったこととはなんなのか? 同じくゲーム業界最大手のスクウェア・エニックスを辞してシシララTVを立ち上げたゲームDJ・安藤武博がインタビューする。
今回は企画の前編として、三木氏や安藤が考える「コンテンツを生み出す力」にスポットを当てたクロストークが展開!

▲左から安藤武博、三木一馬氏。
■第一印象が最悪なほど作家性が高い? 三木&安藤が語る「デキるクリエイター」
安藤武博(以下、安藤):三木さんとは『拡散性ミリオンアーサー』の時からのお付き合いですが、ともに大手の会社を辞めて事業を立ち上げたという共通項もあってシンパシーを感じています。今日はよろしくお願いいたします。いろいろとざっくばらんにお話をお聞きできれば。
三木一馬氏(以下、三木):よろしくお願いいたします。
安藤:わたしがスクウェア・エニックスを辞めてシシララTVを、三木さんはKADOKAWAを辞めてストレートエッジ(※1)を立ち上げることになったわけですが、今、エンタメ業界がそういう風向きになりつつあるのかなと感じています。じつは、以前シシララTVにも出演してもらったこともあるDeNAの渡部さん(※2)も、近々会社を辞められるそうなんですよ。
(※1)ストレートエッジ:三木一馬氏が代表を務める株式会社ストレートエッジ。業務内容はクリエイターマネジメント、出版物の編集・企画・制作・製造・販売、キャラクターコンテンツの企画・制作・販売など多岐に渡り、『とある魔術の禁書目録』の鎌池和馬氏や『ソードアート・オンライン』の川原 礫氏など、多くの作家陣と契約を結んでいる。
(※2)渡部さん:DeNAで執行役員を務めている渡部辰城氏。同社では『ファイナルファンタジー レコードキーパー』などに関わったほか、スクウェア・エニックス在籍時には『ドラゴンクエスト』シリーズにも携わっていた。
安藤:渡部さんはわたしのスクエニ時代からの盟友で、スクエニ時代には『ドラゴンクエスト』シリーズ、DeNA時代には『ファイナルファンタジー』シリーズと、人気RPGの両方に携わったことがある稀有な存在です。彼はエニックス時代の1年後輩なのですが、わたしは超絶仕事ができる会社員という意味を込めて「スーパーサラリーマン」と呼んでいました。出会った初日になぜか「お前はいつか社長になる男や!」と口にしたんですよね。大卒すぐの時点で謎の「社長オーラ」が出ていた(笑)。
三木:そんな渡部さんほどの人も、大手企業を辞めて独立される時代ってことですか……。しかし、先輩である安藤さんが次期社長と認めるというのは、なかなか面白いエピソードですね。

安藤:第一印象から何かピンときたんです。どん底時代のわたしを助けてくれた恩人ですしね。実際、いつか「渡部をスクエニの社長にしてやろう」というのが、わたしがスクエニで働き続けていた理由でした。先に彼が転職しちゃいましたけど(笑)。のちに、見事に社長(DeNA Osaka)になりましたよね。
三木:面白い(笑)。やはり、第一印象でピンとくる瞬間ってありますよね。じつは僕も、最初に会ったときに「ちょっとムカッとくる」作家さんほど売れるというジンクスがあります。
安藤:「第一印象が最悪=売れ筋作家になるという法則」ですか。
三木:悪い意味ではないんですよ。作品の内容について話しているときに「この人、跳ねっ返りだなぁ」とか、「ワガママな人だなぁ」と感じた作家ほど、結果個性的なものを書いてくださっているということだと思うんですけど。
安藤:つまり、鎌池和馬さん(※3)なんかも第一印象は最悪だったと?(笑)
三木:その誘導尋問やめてください!(苦笑) あくまで作品の「我が強い」ということですよ!
(※3)鎌池和馬さん:電撃文庫で『とある魔術の禁書目録』や『へヴィーオブジェクト』などの作品を手掛ける人気作家。安藤とは100万人のアーサー王の物語を描くカードバトルRPG『拡散性ミリオンアーサー』で仕事をともにした。
安藤:たしかに、鎌池さんと『ミリオンアーサー』で仕事をご一緒したときは、物腰はすごく柔らかいものの一本筋が通っているというか、こだわりがとても強い人だと感じました。
三木:打ち合わせの際、お互いに曲げられない考えがぶつかり合って、とてもイライラしながら話している時もありますね。それだけ剥き出しの感性をぶつけ合っているってことなんですけど、今、読者に求められているのはまさにそういうコンテンツなんだと思っています。やはり「作者が遠慮している作品」って読者にバレてしまうんですよね。
安藤:バレますね。「いい子ちゃんなコンテンツ」はバレますし、飽きられるのも早い。
三木:だから僕は、作家さんにはいつも「もっとドヤ顔をしよう」と伝えています。ご本人にドヤ顔をしてほしいという意味ではなく(笑)、作品でドヤ顔をみせてほしいという意味です。読者としては、まさに今からその世界観にのめり込もうとしている時に、作品が遠慮がちな顔をしていたら躊躇しちゃうじゃないですか。売れる作品というのは、遠慮がちな読者をがしっと受け止められるだけのドヤ顔をしているべきなんです。
安藤:それは小説に限らず、ゲームにも同じことが言えますね。
三木:そういう意味では、鎌池さんの作品は限界ギリギリまでドヤ顔をしていて、そこが彼の作品のいいところなんです。

安藤:わたしも同様の経験がありまして、一緒に仕事をしていて腹が立つディレクターほど優秀な方が多いですね。これは編集者もゲームプロデューサーも同様だと思うのですが、そういった「きかんぼう」なクリエイターの作品に、どこまで関与できるかというのかは難しい側面がありませんか? 「ここまでは関与する」って明確に線引きできないというか、数値化できない。ゲームでたとえれば、極端な話、プロデューサーが何もしなくてもゲームシステムやキャラクター性が魅力的であれば、それだけでその作品が売れてしまう可能性はあります。優秀なディレクターはそこをしっかりと認識していて、「オレは面白い作品であることを担保するけど、プロデューサーは何を担保してくれるの?」と大上段で打ち込んでくるんですよね。まずはそこに、いい意味で腹が立つのかなと。
三木:なるほど。
安藤:「ディレクターとして面白い作品を作ったんだから、売れなかったらプロデューサーの責任でしょ?」といった“圧”みたいなものをにじませてくる方もいる。もちろんプレッシャーなのですが、それだけ自分が手がけたゲームに真摯に向き合い、一生懸命に面白いものに仕上げているということでもありますから、プロデューサーとしてはものすごく刺激を受けます。
三木:スクウェア・エニックスさんって、そういう個性的なクリエイターを受け入れる度量があるなと感じます。「オリジナルコンテンツを作る」という老舗ゲームメーカーのパワーというか、生き様ですよね。自分たちで面白いものを作って売るという魂がプロデューサーにもディレクターにもあるように思います。僕はキャラクターコンテンツ事業で、バンダイナムコエンターテインメントさんとお仕事をする機会が多いのですが、同じゲーム会社なのに社風がまったく違いますよね。バンナムさんはゲームのみならず、小説やアニメといったほかのコンテンツに寄り添う美学がとにかく徹底している。
安藤:対して、スクウェア・エニックスは?
三木:スクエニはゲームコンテンツの「週刊少年ジャンプ」ですよ(笑)。オリジナルコンテンツをバリバリの王道で作っていってやる、という気概を感じます。

安藤:わたしから見れば、KADOKAWAもスクエニと似ているように思えるのですが。……これは「角川映画」のイメージがあるからなのかな。子どもの頃に「天と地と(※4)」を見て、どうしてこんなにお金をかけた作品を生み出せるんだと衝撃を受けました。あれだけの規模の邦画を作り出せるのは、当時の角川書店だからこそでしょう。
(※4)天と地と:1990年に公開された大作映画。越後の名将・上杉謙信とその宿敵・武田信玄との間に繰り広げられた川中島の戦いを描く。50億円という当時としては破格の製作費を投入して撮影され、プロデューサーである角川春樹氏が自ら監督も務めた。
安藤:ちなみに、スクウェアはまだエニックスと合併する前にフルCG映画『ファイナルファンタジー』を制作しました。こちらは興業的には厳しいものだったわけですが、このときの培ったCG制作の技術は、その後の日本のゲームやCG業界の礎になりました。あの作品があったからこそ、『ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン』につながったとも言えますからね。
三木:「この会社じゃないとできない」と思わせる力、それこそがコンテンツホルダーに求められるものですよね。
安藤:あの映像を見て、スクウェアのCG技術力の高さをあらためて実感した人も多いはず。事実、わたしもエニックス時代は「スクウェア、超カッコいい」と思っていました。辞めた今だからわかるのですが、スクエニは「絵の会社」。ビジュアルや世界観を作り込む技術に長けている会社なんですよ。これはスクウェアがファミコン、スーパーファミコンの時代から培ってきたところが大きくて。PS時代に入っても『ファイナルファンタジーVII』や『デュープリズム』、『ゼノギアス』に『聖剣伝説 LEGEND OF MANA』、そして『サガ フロンティア』と、ものすごい作品が立て続けに発売されていた時期もあって、現在でいうところのGoogleやAppleのようなカッコよさがありました。
三木:僕としても、スクウェアとエニックスが合併するというお話を聞いたときは衝撃を受けましたからね……。中の人だった安藤さんたちも、かなり印象に残っていることも多いのでは?
安藤:それはもう(苦笑)。当然ですが、社内で合併のことを知っている人間は経営陣だけだったため、我々はニュースになる直前に、電撃的に社長から伝えられたわけです。あの時はさすがに衝撃が大きくてみんなの仕事が止まってましたよ。合併後の会社名を社内で公募するなど、独特のお祭り騒ぎもあったのですが、今でも印象的なのは、当時のエニックスのプロデューサー陣の肩書きが「アシスタントプロデューサー」になったことです。
三木:それはどういう意味でしょう? 降格になったということですか?
安藤:そう単純なものでもなくて。スクウェアは、言ってみれば作家やディレクターの集まりだったんですよ。『ファイナルファンタジー』シリーズの北瀬佳範さん、『サガシリーズ』の河津秋敏さんや『半熟英雄』の時田貴司さんがいて、『聖剣伝説』の石井浩一さんがいて、コンポーザーの植松伸夫さんがいて、松野泰己さんもおられました。つまり、高レベルでディレクションができる生粋のクリエイター集団だったわけです。対して、エニックスサイドは自分で作品をディレクションするわけではなく、プロデューサーの集まりだったので、変な遠慮のようなものが働いたのかな。名刺を作る際に「アシスタントプロデューサー」という、個人的にはワケのわからない肩書きになると聞かされました。わたしは当時『疾走、ヤンキー魂。』をプロデュースしていたのですが、名刺はアシスタント。「じゃあこの作品のプロデューサーは誰なんだよ」と。「プロデューサーもいないのに、アシスタントもクソもないだろう」と暴れていたら、いつの間にかそんな変な肩書きの話はなくなっていたんですけどね(笑)。

三木:なるほど。当時は超大手同士の合併に驚いたものですが、お話を聞いてみると、まったく違う側面を持った会社同士がくっついたわけですから、むしろ相性は良かった、ということはないですか?
安藤:そのとおりですね。まさに作家と編集者が手を取り合うという感覚に近かったと思います。ものすごくバランスがよかった。合併当初はお互いの間に壁のようなものを感じていた時期もあったかもしれませんが、それは初対面で気を遣ったり探りあったりしていただけのこと。5年もすれば元スクウェアだの元エニックスだのといった空気はなくなっていましたね。最終的にはスクウェアでもなければエニックスでもなくて、スクウェア・エニックスという会社になったなと感じていました。
三木:ちなみに、お話を聞いていると安藤さんはエニックス側の人だったんですね。僕はなぜか、スクウェアっぽいなと思っていたんですけど。
安藤:え、本当ですか? それははじめて言われましたね。スマホのゲームを作る前は爆弾解体ものとか、プロレスとか、ヤンキーものとか、どちらかというと奇抜なエニックス気質の作品ばかり作っていましたし。ただ、先ほどお話ししたとおり、最終的にはスクウェアとエニックスに垣根も何もない環境で仕事をしていましたので、混ざりあった部分はあったかもしれません。
三木:僕の中では、野球にたとえるとエニックスが西武の中村剛也選手(おかわり君)で、スクウェアが日本ハムの中田翔選手のイメージなんです。……安藤さんは中田翔選手サイドのオーラを感じたんですよね。
安藤:ここで野球、それもパ・リーグの長距離ヒッターをたとえに持ち出してくる三木さんの発想。独特で面白いですね。でもわかりにくいです(笑)。
三木:今から説明します(笑)。中田選手は有言実行で結果を残すタイプで、スクウェアにはそういうイメージが強いんです。対して中村選手は、不言実行で結果を残すタイプ。気づけばホームラン王を取っている……みたいなところがエニックスに近いのかな、と。
安藤:エニックスはピッチャーにたとえると北別府かな。制球命で、気づいたら200勝しちゃっている……みたいな感じ(笑)。ちなみに、合併話といえばKADOKAWAも今の形になるまでには、いくつかの変遷がありましたよね。そうはいっても、ずっと電撃文庫編集部にいた三木さんには関係ないのかもしれませんが……。
三木:KADOKAWAというか、もともと電撃文庫編集部があったメディアワークスとしては、計2回の合併、1回の経営統合を経験しているんですが、たしかにモチベーションの維持をするのは大変だったかもしれません。

安藤:そうでした。もともとはアスキーとメディアワークスが合併してアスキー・メディアワークスになり、そのあと角川グループが1つになって今の「KADOKAWA」という会社になったんですよね。
三木:アスキーと合併したときも、やっぱりビックリしたんですよね。あちらがPCやらITやらといった情報が中心なのに対して、当時の我々の売り上げの中心は『シスター・プリンセス(※5)』から始まる、いわゆるオタク系コンテンツでしたから。
安藤:『シスプリ』! なつかしいですね!!
(※5)シスター・プリンセス:当時のメディアワークス(現:KADOKAWA)刊の『電撃G'sマガジン』の読者参加企画に端を発し、ゲームやアニメ、ラジオ番組など、さまざまなメディアミックス化が図られた人気コンテンツ。「12人の妹」が登場することで話題を集めた。
三木:正直、シナジーってどうすればいいんだろうと思いました(笑)。そこからまたいろいろあって、カンパニー制を経て角川グループが統合されてKADOKAWAになったときは、よりいっそう複雑です。これまで電撃文庫編集部の人間として、角川スニーカー文庫や富士見ファンタジア文庫、メディアファクトリー文庫やファミ通文庫はライバル的な存在だったわけですが、それが一気に仲間同士になるわけですから。そういわれても、いったいどうすればいいんだ……なんて思っていた時期はありましたね。
■三木一馬が電撃文庫編集部で培ってきたもの
安藤:そもそも、三木さんはいつから電撃文庫編集部に?
三木:2001年からですね。じつは僕、最初から電撃文庫編集部を望んでいたわけではなく、最初は電撃PlayStation編集部など、別の部署を志望していたんですよ。
安藤:えっ、そうなんですか? 三木さんが作る電プレ、ちょっと見てみたかったですね。
三木:少年時代はたくさんゲームをプレイして過ごしたこともあり、ゲーム業界にあこがれていたんですよ。だから、ゲーム情報を手掛ける媒体の編集者もいいなと思っていたんですけど、メディアワークスに入ったら電撃文庫編集部に配属されまして。いわゆる「ライトノベル」というジャンルの小説は、電撃文庫編集部に入ってからはじめて読みました。東京に来るまではオタクの流儀も知らなければ、コミックマーケットの存在すら知りませんでしたからね。
安藤:三木さんが後天的に、ライトノベルのことを学ばれたというのは不思議な感じですね。

三木:僕は週刊少年ジャンプのバトルマンガで育った世代で、萌えや美少女人気というのはさっぱりわからなかったので、本当に異世界でした。
安藤:ジャンプのバトルマンガですか。どうやら、編集者三木一馬のルーツはそこらへんにありそうですね。
三木:ルーツというか、せっかく編集者として作品に携わるわけですから、自分が好きなジャンプマンガ……少年マンガが持つ「熱」を入れ込みたかったんですよ。「1人の少女を助けるためにがむしゃらになっていたら、いつの間にか世界を救っていた」的な、我々世代の人間なら誰もが通った王道の展開。それが『灼眼のシャナ』や『とある魔術の禁書目録』ではいい形に作用したのかな、と。
安藤:三木さんがこれまでに関わってこられた作家さんって、どのような方々になるのでしょうか? 先ほどのお話しにあったように、個性的な方が多いわけですよね?
三木:そうですね。作家さんはやはり尖った方が多いです。ゲームが好きといっても、ビデオゲームだけではなく、T・RPGとかも大好きな生粋のタイプですね。
安藤:ただゲームを遊ぶだけではなく、自分で世界観まで構築してしまうような方が多いってことですか。そこに三木さんが少年マンガの体裁を入れ込んだわけですね。

三木:そこは作家さんとお話しながらですけど。そもそも、ライトノベルにセオリーなんてないと思っています。おもしろい作品であることこそが大事なわけですから。
安藤:そもそも「小説とライトノベルの違い」ってなんだ……って部分はありますよね。日本人はなんでも体系化したがるから便宜上ジャンル分けされていますけど、そこにどれだけの違いがあるのか。音楽に関してもそうなんですけど、「ロック」「メタル」「J-POP」など、カテゴライズしておいたほうが入りやすいから、わざとそうしているって側面があります。実際のところは、ほとんどのリスナーが音楽のジャンルなんて気にせず聴いているはずなのに、これはメディアの罪かもしれません。話が逸れましたが、『とある魔術の禁書目録』は、いわれてみればたしかに少年マンガのセオリーをおさえているように思えます。
三木:あの作品は、イラストを担当してくれているはいむらさん(※6)が、読んですぐに「これは少年マンガですね」と、僕をハッとさせる言葉を伝えてくれたので、自分としても、鎌池さんにはとことんこの方向性を貫いてもらおうと考えました。ですので、メディアミックスとしてマンガ化する際も、絶対に少年マンガ誌でやりたかったんです。
(※6)はいむらさん:イラストレーターのはいむらきよたか氏。『とある魔術の禁書目録』のイラストやキャラデザインのほか、『ミリオンアーサー』シリーズのイラストも手掛けている。
安藤:なるほど。なぜメディアワークスの小説がスクウェア・エニックスのマンガ誌に掲載されているのか疑問だったのですが、そういうこだわりがあったんですね。
三木:ええ。メディアワークスは、少年誌系バトルアクションマンガを掲載する媒体としては少しだけ方向が違うかも、と思っていました。もちろん、これは自分の好みだけで決めたわけではなく、それらの雑誌を読んでいる読者層に向けて作品を届けることが、戦略として理にかなっているという考えが大前提としてありました。引いては、それが作家さんや作品と寄り添っていくというスタンスでもありますね。
安藤:三木さんのそういったこだわりが、作品のメディアミックスの成功へとつながっているわけですね。では、そんな三木さんのお仕事に対する流儀について聞かせていただけますか?(後編へ続く)
今回の記事はここまで。後編では、三木氏と安藤が図らずも意識を共有させた「編集者/ゲームプロデューサー絶滅論」が語られますのでお楽しみに!
●作家/コンテンツに寄り添う“エージェント”としての仕事で業界改革を進める「ストレートエッジ」でお仕事をしてみたい方はコチラ
シシララTV オリジナル記事