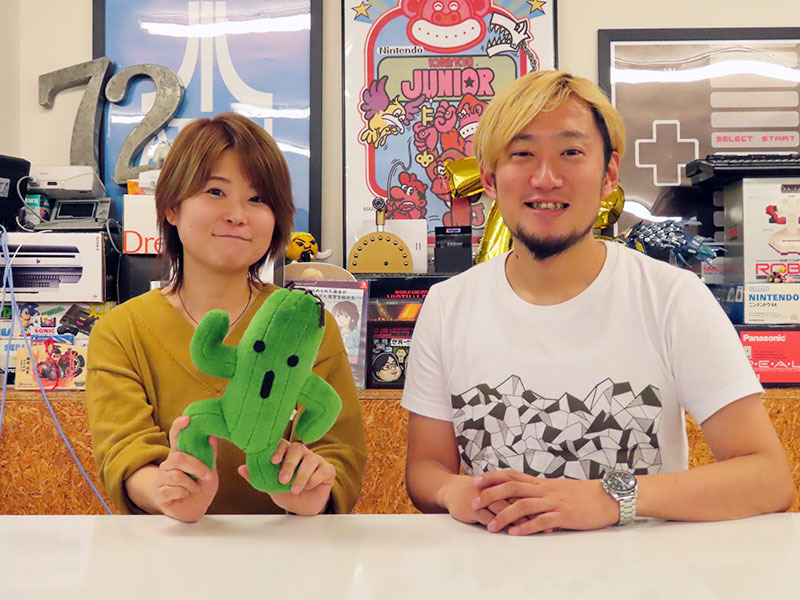クリエイターは満足したら死ぬ……“無意識の渇き”に秘められた一流の魂/高木謙一郎vs安藤武博ロング対談【後編】
爆乳の女の子たちが忍の世界で命がけの戦いを繰り広げる『閃乱カグラ』シリーズを世に送り出し、爆乳プロデューサーを自称する高木謙一郎氏。そして、『鈴木爆発』や『疾走、ヤンキー魂。』『ヘビーメタルサンダー』などの前衛的なゲームをプロデュースし、ゲームDJを名乗る安藤武博。そんな異色のクリエイター対談がここに実現した。はたして、2人の自由で柔軟な発想はどこから生まれているのか? 原点となるゲーム体験を振り返ってもらいつつ、普段はあまり表で語ることのない仕事論や現状のゲーム業界への進言を包み隠さずに語ってもらった。
後編となるとなる今回は、趣味であったゲームを仕事にすることにした理由や、クリエイティブに携わり続けるモチベーションについてのトークが展開。普段はエンターテイナーに徹している2人が静かに語る仕事論は、未来のゲームクリエイターだけでなくすべてのゲームユーザー必見の内容だ。
前編→名作ゲームに触れ続けることで培われるクリエイター魂
前編→名作ゲームに触れ続けることで培われるクリエイター魂

■ゲームクリエイターは「なろうと思ってなる」ものではない!?
安藤武博(以下、安藤):高木さんがゲームを作るほうに意識が向いたのはいつごろですか?
高木謙一郎さん(以下、高木):小学生のときですね。最初はマンガを描いていたのですが、1人だとなかなかストーリーが進まないのでみんなで作るものがやりたくなったんです。
安藤:わたしも小学生の頃はマンガを描いていました。高木さんのおっしゃるとおりで、1人だとなかなか進まないので、2人組の「なまたまご」というユニットを作って活動していました(笑)。
高木:なるほど、ゆでてはいないんですね(笑)。
安藤:パクりですね(笑)。描いていたマンガも「超人マン」とか、どこかで見たことがあるようなものばかりだった気がします。ちなみに、ゲームはどういうものを作ったんでしょう? やはりボードゲームとかですか?
高木:ええ。最初は紙とえんぴつでボードゲームを作りました。敵を倒して進んでいくRPG要素を含んでいましたね。自分の頭の中で複数のAIを作って、1人マルチプレイで遊んでいました(笑)。そのときはモンスターを考えるのが楽しかったので、将来はモンスターデザイナーになりたいと考えていました。
安藤:モンスターデザイナー。響きからしてカッコいいですね!
高木:『ドラゴンクエスト』をプレイしたときに「モンスターデザイン:鳥山明」と書いてあって「世の中にはこんな仕事があるのか!」と衝撃を受けたんですよ。結果的に、絵のスキルが足りなくてやめましたけど(笑)。
高木謙一郎さん(以下、高木):小学生のときですね。最初はマンガを描いていたのですが、1人だとなかなかストーリーが進まないのでみんなで作るものがやりたくなったんです。
安藤:わたしも小学生の頃はマンガを描いていました。高木さんのおっしゃるとおりで、1人だとなかなか進まないので、2人組の「なまたまご」というユニットを作って活動していました(笑)。
高木:なるほど、ゆでてはいないんですね(笑)。
安藤:パクりですね(笑)。描いていたマンガも「超人マン」とか、どこかで見たことがあるようなものばかりだった気がします。ちなみに、ゲームはどういうものを作ったんでしょう? やはりボードゲームとかですか?
高木:ええ。最初は紙とえんぴつでボードゲームを作りました。敵を倒して進んでいくRPG要素を含んでいましたね。自分の頭の中で複数のAIを作って、1人マルチプレイで遊んでいました(笑)。そのときはモンスターを考えるのが楽しかったので、将来はモンスターデザイナーになりたいと考えていました。
安藤:モンスターデザイナー。響きからしてカッコいいですね!
高木:『ドラゴンクエスト』をプレイしたときに「モンスターデザイン:鳥山明」と書いてあって「世の中にはこんな仕事があるのか!」と衝撃を受けたんですよ。結果的に、絵のスキルが足りなくてやめましたけど(笑)。

安藤:ゲームクリエイターになろうと思ったターニングポイントは?
高木:自分の場合、特定のゲームやクリエイターに影響を受けてクリエイターを目指したというよりは、「俺のほうがもっとおもしろいゲームが作れる!」という謎の自信というか、中2病的な考えがずっと頭から離れなかった結果……という感じです。
安藤:それはわたしも同じです。というか、モノを作ることを生業にするほどの人は、少なからずそういった側面があると思いますよ。中2病は最強ですよね。自分は中2のときに『美味しんぼ』のキャラクターが野球をする『美味しんぼーる』という漫画描いたのですが、「今の自分にこのときの俺を超えられるのか」ということはよく自問自答します。
高木:当時は現代のように、作品を世の中に簡単に発表できなかったことも大きいと思います。自分の頭の中だけで世界を作るから、よくも悪くもとんでもないものが生まれやすかった。
安藤:作り手も遊び手も自分しかいないですからね。でも、それがいい感じに煮詰まって奇跡の作品を生むことがある。
高木:自分は岡山の田舎に住んでいたこともあって、発表の場は本当にありませんでした。
安藤:わたしもアニメイトにイラストを貼ってもらったり、アニメ系のラジオ番組に投稿したりはしましたが、基本的には悶々と過ごしていましたね。
高木:だから一刻も早くゲームクリエイターになりたかったんですよ。早く世の中に自分の作品を出したくて出したくてたまらなかった。
安藤:めちゃくちゃ煮詰まっていたわけですね。高木さんはいつからゲームクリエイターへの道を意識したんでしょう?
高木:じつは、気付いたらもうクリエイターになっていたんですよね。よく広告などで「ゲームクリエイターになろう!」というキャッチコピーを目にするのですが、あれにはものすごい違和感があるんです。ゲームクリエイターって「何かを世に出したい」という衝動があふれ出した結果、「いつの間にかなっているもの」であって、「なろう!」と思ってなるものではないんですよ。
安藤:わかります。我々にとっては、作ることが日常なんですよね。むしろ作っていないと精神が安定しないというか、作ることで血液が流れ、手足が生えて人間として安定する(笑)。
高木:自分の場合、特定のゲームやクリエイターに影響を受けてクリエイターを目指したというよりは、「俺のほうがもっとおもしろいゲームが作れる!」という謎の自信というか、中2病的な考えがずっと頭から離れなかった結果……という感じです。
安藤:それはわたしも同じです。というか、モノを作ることを生業にするほどの人は、少なからずそういった側面があると思いますよ。中2病は最強ですよね。自分は中2のときに『美味しんぼ』のキャラクターが野球をする『美味しんぼーる』という漫画描いたのですが、「今の自分にこのときの俺を超えられるのか」ということはよく自問自答します。
高木:当時は現代のように、作品を世の中に簡単に発表できなかったことも大きいと思います。自分の頭の中だけで世界を作るから、よくも悪くもとんでもないものが生まれやすかった。
安藤:作り手も遊び手も自分しかいないですからね。でも、それがいい感じに煮詰まって奇跡の作品を生むことがある。
高木:自分は岡山の田舎に住んでいたこともあって、発表の場は本当にありませんでした。
安藤:わたしもアニメイトにイラストを貼ってもらったり、アニメ系のラジオ番組に投稿したりはしましたが、基本的には悶々と過ごしていましたね。
高木:だから一刻も早くゲームクリエイターになりたかったんですよ。早く世の中に自分の作品を出したくて出したくてたまらなかった。
安藤:めちゃくちゃ煮詰まっていたわけですね。高木さんはいつからゲームクリエイターへの道を意識したんでしょう?
高木:じつは、気付いたらもうクリエイターになっていたんですよね。よく広告などで「ゲームクリエイターになろう!」というキャッチコピーを目にするのですが、あれにはものすごい違和感があるんです。ゲームクリエイターって「何かを世に出したい」という衝動があふれ出した結果、「いつの間にかなっているもの」であって、「なろう!」と思ってなるものではないんですよ。
安藤:わかります。我々にとっては、作ることが日常なんですよね。むしろ作っていないと精神が安定しないというか、作ることで血液が流れ、手足が生えて人間として安定する(笑)。

高木:安藤さんはゲーム業界に入ろうと思った大きなきっかけとかあるんですか?
安藤:最初はゲーム会社ではなく、玩具会社を受けていたんですが、勉強をほとんどしていなかったので筆記試験があるところは全部落ちてしまいまして(笑)。そのあと、いろいろと会社説明会などを調べてゲーム会社に行き着き、柴さんといっしょにエニックスを受けました。
高木:エニックスに受かるのがすごいですよね。僕は当時広島に住んでいたのですが、まったくゲーム会社に受からなかったので、とりあえず身一つで上京したんです。
安藤:仕事も決まらないなか、ひとまず上京だけはしてしまおうと? また随分思い切ったことをなさいましたね。
高木:職もなかったのですが不動産屋に行って家を借り、派遣会社に登録したり、テレビのADの仕事をしたりしながらゲームの企画書を作っていました。でもそのうちに、テレビの仕事のほうで出世してしまいそうになっちゃいまして……。それはそれでありたがたいお話しだったですが、僕はゲームを作りたかったので、その話はきっぱりとお断りして、お仕事自体も辞めました。そうしてまたゲームの開発会社を受けて、株式会社オーパスという会社に入ったんです。
安藤:のちに『勇者30』の開発を手掛けることになる会社ですね。
高木:そうですね。このとき自分は25歳でしたが、26歳までにゲーム会社に就職できなければ田舎に帰ろうと思っていました。まさに背水の陣です。
安藤:そんな高木さんも現在はスタジオ長として部下を率いる立場になり、1人のクリエイターという立場ではいられなくなったのではないでしょうか?
高木:……うーん、立場は変わりましたが、これまでと特には変わりませんね。きちんと作品で結果を出せば、会社も自分の考えを優遇してくれますし。それに僕はリーダーをやろうと思ったわけではありませんし、極端な話、出世にもあまり興味がないんですよ。僕が唯一欲しいものは“作品に対する決定権”だけで、ほかのことにはさほど執着がない。まぁ、こんなことを言うと、会社には怒られてしまいそうですが(笑)。
安藤:偉くなるためにゲームを作っているわけではないという部分には、わたしも強く共感します。プロデューサーは手がけた作品が売れないと、自分が好きなものを作れないというのもわかります。ただ、会社に所属するゲームクリエイターは、サラリーマンであるがゆえに、作品が売れてしまうと立場的に偉くなってしまって、管理職に変わってしまうことも多い。わたしもスクウェア・エニックスで部長になり、最初は予算が増えたり執行権限が使えたりすることがうれしかったのですが、つくることが生きがいですので現場に戻りたくてたまりませんでした。1人であれば、もし何か失敗しても自分の給料が下がるだけいいのですが、部下を引っ張っていく立場になると、そうはいかなくなるんですよね。
高木:わかります。
安藤:最初はゲーム会社ではなく、玩具会社を受けていたんですが、勉強をほとんどしていなかったので筆記試験があるところは全部落ちてしまいまして(笑)。そのあと、いろいろと会社説明会などを調べてゲーム会社に行き着き、柴さんといっしょにエニックスを受けました。
高木:エニックスに受かるのがすごいですよね。僕は当時広島に住んでいたのですが、まったくゲーム会社に受からなかったので、とりあえず身一つで上京したんです。
安藤:仕事も決まらないなか、ひとまず上京だけはしてしまおうと? また随分思い切ったことをなさいましたね。
高木:職もなかったのですが不動産屋に行って家を借り、派遣会社に登録したり、テレビのADの仕事をしたりしながらゲームの企画書を作っていました。でもそのうちに、テレビの仕事のほうで出世してしまいそうになっちゃいまして……。それはそれでありたがたいお話しだったですが、僕はゲームを作りたかったので、その話はきっぱりとお断りして、お仕事自体も辞めました。そうしてまたゲームの開発会社を受けて、株式会社オーパスという会社に入ったんです。
安藤:のちに『勇者30』の開発を手掛けることになる会社ですね。
高木:そうですね。このとき自分は25歳でしたが、26歳までにゲーム会社に就職できなければ田舎に帰ろうと思っていました。まさに背水の陣です。
安藤:そんな高木さんも現在はスタジオ長として部下を率いる立場になり、1人のクリエイターという立場ではいられなくなったのではないでしょうか?
高木:……うーん、立場は変わりましたが、これまでと特には変わりませんね。きちんと作品で結果を出せば、会社も自分の考えを優遇してくれますし。それに僕はリーダーをやろうと思ったわけではありませんし、極端な話、出世にもあまり興味がないんですよ。僕が唯一欲しいものは“作品に対する決定権”だけで、ほかのことにはさほど執着がない。まぁ、こんなことを言うと、会社には怒られてしまいそうですが(笑)。
安藤:偉くなるためにゲームを作っているわけではないという部分には、わたしも強く共感します。プロデューサーは手がけた作品が売れないと、自分が好きなものを作れないというのもわかります。ただ、会社に所属するゲームクリエイターは、サラリーマンであるがゆえに、作品が売れてしまうと立場的に偉くなってしまって、管理職に変わってしまうことも多い。わたしもスクウェア・エニックスで部長になり、最初は予算が増えたり執行権限が使えたりすることがうれしかったのですが、つくることが生きがいですので現場に戻りたくてたまりませんでした。1人であれば、もし何か失敗しても自分の給料が下がるだけいいのですが、部下を引っ張っていく立場になると、そうはいかなくなるんですよね。
高木:わかります。

安藤:もちろん、作りながら管理職をしている人もいます。自分の尊敬する先輩である齊藤陽介さん(※1)もその1人ですが、彼が部長でありながら現場にも関わり続けていた頃がとても大変そうでしたね。一緒に飲みに行くと冗談で「ゲームだけ作っていたい!」「安藤、立場変わってくれ!」とこぼしていましたから(笑)。超絶に仕事が出来る齊藤さんですらこんなにツラいのであれば、自分はどちらかに専念しないとダメだと痛感しました。
(※1)齊藤陽介さん……スクウェア・エニックス所属のゲームクリエイター。ゲームDJ安藤武博が尊敬してやまない先輩の1人。最近は「2人目のゲームDJ」を自称するなど、安藤との関係は深い。相性は「よーすぴ」。おもな代表作は『アストロノーカ』、『ニーア』シリーズなど。7月29日に『ドラゴンクエスト』シリーズの最新作『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』もリリース予定。
高木:なるほど。
安藤:ちょうどその頃、周囲に引っ張ってあげたらおもしろいことをやってくれそうな岩野さん(※2)のような人たちがいたので、わたしは彼ら自身をプロデュースする立場に回ることにしたんです。ただ、ずっとその立場にいるのもおもしろくないので、後任を早く見つけて、自分はまた現場に戻ろうと思っていました。そうこうしている間に、とくにスマートフォンのゲーム市場は大きく様変わりしていて、かつてと同じやり方でおもしろいものが作れるかどうかはわからなくなったんです。ならばいっそスクウェア・エニックスを辞め、新しくイチから始めることにしようと。そういう考えで立ち上げたのが、このシシララTVという会社になります。
(※2)岩野さん……スクウェア・エニックス所属のゲームクリエイターである岩野弘明さんのこと。ゲームDJとともに『拡散性ミリオンアーサー』をプロデュースした。最新作である『ましろウィッチ』は2017年に配信予定。
高木:リスクを背負う覚悟で新しいことをはじめるため、会社を辞める必要があったんですね。超大手を辞めて独立されたことは、本当にすごいと思います。
安藤:ありがとうございます。わたしは、クリエイターが管理職になるのは日本のゲーム業界にとってよくない部分だと思っています。たとえば映画監督は、ずっと映画監督であって、プロデューサーになったりはしない。作る能力がある人は、ずっと作り続けるべきだと思うんです。偉くなってしまうと、本来であればその人が出なくていいような会議にも出なければならなくなったりしますし、そういう部分は改善の余地があると思っています。
(※1)齊藤陽介さん……スクウェア・エニックス所属のゲームクリエイター。ゲームDJ安藤武博が尊敬してやまない先輩の1人。最近は「2人目のゲームDJ」を自称するなど、安藤との関係は深い。相性は「よーすぴ」。おもな代表作は『アストロノーカ』、『ニーア』シリーズなど。7月29日に『ドラゴンクエスト』シリーズの最新作『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』もリリース予定。
高木:なるほど。
安藤:ちょうどその頃、周囲に引っ張ってあげたらおもしろいことをやってくれそうな岩野さん(※2)のような人たちがいたので、わたしは彼ら自身をプロデュースする立場に回ることにしたんです。ただ、ずっとその立場にいるのもおもしろくないので、後任を早く見つけて、自分はまた現場に戻ろうと思っていました。そうこうしている間に、とくにスマートフォンのゲーム市場は大きく様変わりしていて、かつてと同じやり方でおもしろいものが作れるかどうかはわからなくなったんです。ならばいっそスクウェア・エニックスを辞め、新しくイチから始めることにしようと。そういう考えで立ち上げたのが、このシシララTVという会社になります。
(※2)岩野さん……スクウェア・エニックス所属のゲームクリエイターである岩野弘明さんのこと。ゲームDJとともに『拡散性ミリオンアーサー』をプロデュースした。最新作である『ましろウィッチ』は2017年に配信予定。
高木:リスクを背負う覚悟で新しいことをはじめるため、会社を辞める必要があったんですね。超大手を辞めて独立されたことは、本当にすごいと思います。
安藤:ありがとうございます。わたしは、クリエイターが管理職になるのは日本のゲーム業界にとってよくない部分だと思っています。たとえば映画監督は、ずっと映画監督であって、プロデューサーになったりはしない。作る能力がある人は、ずっと作り続けるべきだと思うんです。偉くなってしまうと、本来であればその人が出なくていいような会議にも出なければならなくなったりしますし、そういう部分は改善の余地があると思っています。

高木:ディレクターの上にプロデューサーがいるという考えは、本来は間違っているんですよね。僕はディレクターとプロデューサーは同格だと考えています。お互いにやるべきことが違いますし、必要となる能力も違う。なかには両方の才覚を持った人もいるかもしれませんけど、それは稀有な例だと思います。ただ、僕は会社の重役会議に出ることはそれほど苦ではありません。会議で自分のタイトルに使える予算を増やせますからね。今、まさに現場で働いている若いプロデューサーたちのためにも、ゲーム事業全体に使える予算を増やしたいんですよ。たまに勘違いをされている人もいますが、お金って重要なんですよね。むしろ、その資金繰りがゲームを作るうえでいちばんハードルが高かったりする。
安藤:プロデューサーの仕事というのは、極端なことを言えば会社のお金を増やすことですからね。そのためにはマーケティングを読んで、市場にあった作品を出すことも重要だと思います。ただ、それだけだとお客さまへの刺激が足りなくなって、ゲーム自体が飽きられてしまうかもしれない。だから自分や高木さんのような方が、尖った内容のゲームを出すこともまた必要。
高木:自分としてもみなさんに愛してもらっている『閃乱カグラ』シリーズを続けていきたい一方で、やってみたい新作のアイディアがたくさんあります。自分は今年で40歳になったのですが、最近になって“これは敵だな”と思うのは「満足しそうになっている自分」なんです。20代のときは、自分よりも上の世代にいるクリエイターは“恵まれていた時代にいたから評価されただけだし、すぐに全員追い抜いてやる!”ぐらいのことを思っていたんですよ。ただ、自分もこの年齢になって落ち着いてきたり、おかげさまで評価されることも増えてきたりしたこともあって、現状に満足してしまいそうになることがあるんです。これは作り手としてはとても危険なんですよね。
安藤:クリエイターは、満足してはいけない。常に先、その先を見て、ひたすらおもしろいものを作り続けれなければいけませんよね。
高木:その通りです。だから僕は、若かりし頃に持っていた“渇き”を絶対になくしたくないんです。安藤さんは独立という道を進みましたが、自分はマーベラスという会社に所属したうえで、その椅子に満足して座り続けることなく、いつまでもおもしろいものを作り続けたいと思っています。
安藤:プロデューサーの仕事というのは、極端なことを言えば会社のお金を増やすことですからね。そのためにはマーケティングを読んで、市場にあった作品を出すことも重要だと思います。ただ、それだけだとお客さまへの刺激が足りなくなって、ゲーム自体が飽きられてしまうかもしれない。だから自分や高木さんのような方が、尖った内容のゲームを出すこともまた必要。
高木:自分としてもみなさんに愛してもらっている『閃乱カグラ』シリーズを続けていきたい一方で、やってみたい新作のアイディアがたくさんあります。自分は今年で40歳になったのですが、最近になって“これは敵だな”と思うのは「満足しそうになっている自分」なんです。20代のときは、自分よりも上の世代にいるクリエイターは“恵まれていた時代にいたから評価されただけだし、すぐに全員追い抜いてやる!”ぐらいのことを思っていたんですよ。ただ、自分もこの年齢になって落ち着いてきたり、おかげさまで評価されることも増えてきたりしたこともあって、現状に満足してしまいそうになることがあるんです。これは作り手としてはとても危険なんですよね。
安藤:クリエイターは、満足してはいけない。常に先、その先を見て、ひたすらおもしろいものを作り続けれなければいけませんよね。
高木:その通りです。だから僕は、若かりし頃に持っていた“渇き”を絶対になくしたくないんです。安藤さんは独立という道を進みましたが、自分はマーベラスという会社に所属したうえで、その椅子に満足して座り続けることなく、いつまでもおもしろいものを作り続けたいと思っています。

安藤:極端な話ですが、高木さんぐらいに作りたいものがある人でなければ、ゲームクリエイターになるべきではないなとさえ思います。高木さんは自分がやりたいことをやるために、しっかり売り上げで結果を出している一流のプロデューサー。コンシューマーで結果を出し続けるということはわたしには出来なかったことなので、とても尊敬しています。しかも格好をつけたりせず、とても楽しそうにしているところがいい。
高木:いやいやいや。面と向かって言われると照れますね(苦笑)。
安藤:「爆乳プロデューサー」を自称して自身の活動スタンスを明確化したり、ゲーム制作をより円滑にできるよう「HONEY∞PARADE GAMES」というスタジオを立ち上げたりしたのも、じつに高木さんらしい試みだと思います。規模は違いますけど、ゲームDJを自称したり、シシララTVを発足したりしている自分としては、強烈なシンパシーを感じます。今後ともお互いに、楽しいことを世の中に仕掛けていきましょう。またゲーム実況にもぜひ遊びに来てください!
高木:もちろんです。こちらとしても、ものすごくいい刺激を受けました。安藤さんの今後の活動も楽しみにしています。
高木:いやいやいや。面と向かって言われると照れますね(苦笑)。
安藤:「爆乳プロデューサー」を自称して自身の活動スタンスを明確化したり、ゲーム制作をより円滑にできるよう「HONEY∞PARADE GAMES」というスタジオを立ち上げたりしたのも、じつに高木さんらしい試みだと思います。規模は違いますけど、ゲームDJを自称したり、シシララTVを発足したりしている自分としては、強烈なシンパシーを感じます。今後ともお互いに、楽しいことを世の中に仕掛けていきましょう。またゲーム実況にもぜひ遊びに来てください!
高木:もちろんです。こちらとしても、ものすごくいい刺激を受けました。安藤さんの今後の活動も楽しみにしています。
テキスト:カワチ(Makoto Kawachi) 1981年生まれ。ライター。ビジュアルノベルに目がないと公言するが、本当は肌色が多けれななんでもいい系のビンビン♂ライター。女性声優とセクシー女優が大好き。
ツイッターアカウント→カワチ@kawapi
シシララTV オリジナル記事