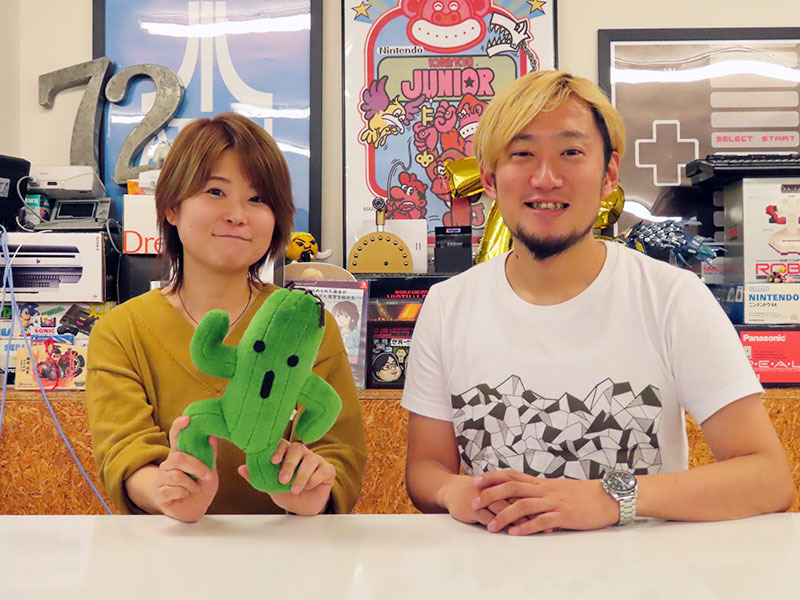20年の時を超え『サイキックフォース』の続編は実現するか!? アオキヒロシ×石川勝久×安藤武博クリエイター鼎談【後編】
1996年に登場し、独特なゲームシステムやアニメチックなキャラクター、悲劇的な世界観のストーリーなどが注目を集めた格闘ゲーム『サイキックフォース』。昨年には、誕生20周年記念としてイベントも開催され、たくさんのファンが集まりました。そのファンの多くが、じつは女性。当時開発ディレクターを務めたアオキヒロシさんと、サウンドクリエイターの石川勝久さんを迎えて送る鼎談。後編は格闘ゲームとしてはめずらしく女性人気が出た理由に迫ります。

アオキヒロシさん(写真左)
現・マーベラス所属のゲームクリエイター。『サイキックフォース』シリーズのディレクターを担当。代表作に『ダライアスバースト』や『スペースインベーダーエクストリーム』などがある。なお、シシララTVの生放送への最多出演回数を誇る。
石川勝久さん(写真中央)
TAITOのサウンドチーム「ZUNTATA」所属のサウンドクリエイター。『サイキックフォース』では効果音制作に加えてサウンドディレクションを手掛けた。おもな代表作品は『メタルブラック』、『武刃街』、『ダライアスバースト』など。現在、ZUNTATAの5代目リーダーとして精力的に活動中。愛称は「ばび~」。
現・マーベラス所属のゲームクリエイター。『サイキックフォース』シリーズのディレクターを担当。代表作に『ダライアスバースト』や『スペースインベーダーエクストリーム』などがある。なお、シシララTVの生放送への最多出演回数を誇る。
石川勝久さん(写真中央)
TAITOのサウンドチーム「ZUNTATA」所属のサウンドクリエイター。『サイキックフォース』では効果音制作に加えてサウンドディレクションを手掛けた。おもな代表作品は『メタルブラック』、『武刃街』、『ダライアスバースト』など。現在、ZUNTATAの5代目リーダーとして精力的に活動中。愛称は「ばび~」。
■バレンタインには、会社にチョコがどっさり届いた
安藤武博(以下、安藤):格闘ゲームって普通は、勝ったほうが「10年早いんだよ!」などのセリフを言うものですが、『サイキックフォース』は負けたほうが、「負け口上」を述べるんですよね。これはどうしてなんですか?
アオキヒロシさん(以下、アオキ):お客さんとキャラクターに近づいてほしかったんですよね。負けて悔しがるところに共感してほしいというか。弱いところを見せたほうがドラマが生まれますし。
安藤:そういった工夫が女性に人気が出た秘訣なのでしょうか。『サイキックフォース』は、アーケードの格闘ゲームとしてはめずらしく、女性人気が高い作品になったんですよね。
石川勝久さん(以下、石川):当時からよく開発陣で話してたんですけど、女性がこんなに支持してくれるなんて我々は思いもしなかったんですよ。『サイキックフォース』でゲームセンターデビューした、という女性もかなりいるそうです。ありがたいことですね。
アオキヒロシさん(以下、アオキ):お客さんとキャラクターに近づいてほしかったんですよね。負けて悔しがるところに共感してほしいというか。弱いところを見せたほうがドラマが生まれますし。
安藤:そういった工夫が女性に人気が出た秘訣なのでしょうか。『サイキックフォース』は、アーケードの格闘ゲームとしてはめずらしく、女性人気が高い作品になったんですよね。
石川勝久さん(以下、石川):当時からよく開発陣で話してたんですけど、女性がこんなに支持してくれるなんて我々は思いもしなかったんですよ。『サイキックフォース』でゲームセンターデビューした、という女性もかなりいるそうです。ありがたいことですね。

アオキ:当時の思い出として、東京ゲームショウのタイトーブースで『サイキックフォース』を展示していたら、そのブースのまわりがコスプレイヤーさんで埋め尽くされていたことがあったんです。あれはびっくりしましたね。ほぼ女性で、ソニアやウェンディーなどの女性キャラはもちろん、エミリオやウォンといった男性キャラのコスプレをしてくれている人もいました。
安藤:ほかに、当時の人気を物語るエピソードはありますか?
石川:バレンタインですかね。『サイキックフォース』のキャラクターあてのチョコレートが、どさっとタイトーに届いたんです。そんなこと、これまでありませんでした(笑)。
アオキ:ダンボール数箱分は来ましたね。到底チームメンバーだけでは食べきれないので、「バレンタインのチョコを食べたい人は、『サイキックフォース』チームのところに来てください」という社内一斉メールを送りました。そうしたら、みんなニコニコしながら集まってくれて。
安藤:ほかに、当時の人気を物語るエピソードはありますか?
石川:バレンタインですかね。『サイキックフォース』のキャラクターあてのチョコレートが、どさっとタイトーに届いたんです。そんなこと、これまでありませんでした(笑)。
アオキ:ダンボール数箱分は来ましたね。到底チームメンバーだけでは食べきれないので、「バレンタインのチョコを食べたい人は、『サイキックフォース』チームのところに来てください」という社内一斉メールを送りました。そうしたら、みんなニコニコしながら集まってくれて。

安藤:愛されているのが形になって見えるのは、うれしいことですね。
アオキ:チョコが送られてきたのには一応理由があって、主要キャラであるキースの誕生日が2月14日なんです。しかもこれ、最初は決めてなかったんですよ。『サイキックフォース』がリリースされたあと、同人誌関係の雑誌から取材が来て、その質問のなかに「誕生日はいつですか」というものがあったんです。で、キースはモテそうな美形キャラだし、2月14日がいいかなと思ってとりあえず設定しました。そうしたら、まさかあんなにチョコが届くとは(笑)。キース以外のキャラクターに送ってくれたチョコもありました。主人公のバーンにバラの花束を送ってくれた人もいたなあ。
安藤:ファンがキャラを好きすぎて、設定を知りたがるってすばらしいですね。たしか二次創作も盛んで、世界最大規模の同人誌即売会であるところのコミケで、『サイキックフォース』の同人サークルだけが集まった“島”(机を組み合わせたエリア)ができたとか。
アオキ:そうなんですよ。僕、買いに行ったんですけど、女性向けだからと売ってもらえなくて。まあ、そりゃ気まずいか(笑)。
石川:同人誌即売会と言えば、『サイキックフォース』オンリーの即売会も開催されて、そこに僕らが呼ばれていったんですよ。おもしろかったのが、お昼くらいまで即売会をやったら、そのあとはお茶会をやるんです。片付けて、お茶を出して、みんなで『サイキックフォース』のトークをしたり、コスプレを見せあったりする。その文化に激しく驚きました(笑)。
アオキ:チョコが送られてきたのには一応理由があって、主要キャラであるキースの誕生日が2月14日なんです。しかもこれ、最初は決めてなかったんですよ。『サイキックフォース』がリリースされたあと、同人誌関係の雑誌から取材が来て、その質問のなかに「誕生日はいつですか」というものがあったんです。で、キースはモテそうな美形キャラだし、2月14日がいいかなと思ってとりあえず設定しました。そうしたら、まさかあんなにチョコが届くとは(笑)。キース以外のキャラクターに送ってくれたチョコもありました。主人公のバーンにバラの花束を送ってくれた人もいたなあ。
安藤:ファンがキャラを好きすぎて、設定を知りたがるってすばらしいですね。たしか二次創作も盛んで、世界最大規模の同人誌即売会であるところのコミケで、『サイキックフォース』の同人サークルだけが集まった“島”(机を組み合わせたエリア)ができたとか。
アオキ:そうなんですよ。僕、買いに行ったんですけど、女性向けだからと売ってもらえなくて。まあ、そりゃ気まずいか(笑)。
石川:同人誌即売会と言えば、『サイキックフォース』オンリーの即売会も開催されて、そこに僕らが呼ばれていったんですよ。おもしろかったのが、お昼くらいまで即売会をやったら、そのあとはお茶会をやるんです。片付けて、お茶を出して、みんなで『サイキックフォース』のトークをしたり、コスプレを見せあったりする。その文化に激しく驚きました(笑)。

■悲劇の超能力者は、技名を叫ばない
安藤:ファンミーティングをお茶会と呼ぶのは、宝塚歌劇もそうなんですよ。女性特有の文化なのかな。おもしろいですねえ。なぜ、そこまで二次創作が盛り上がったのか。ご自身ではどう分析していますか?

アオキ:当時からファンの皆さんに言われていたのは『サイキックフォース』は行間があるところがいいと。そこを埋めようとして、みんながいろいろ考えてくれたのかなと思います。行間は狙ってつくったのではなく、最低限キャラクターを立たせるための設定だけ考えればいいと思ってたからなんですよね。キャラクターのバックボーン、エンディング、あとは戦っているときのセリフくらいあればいい、と。でも、好きになってもらうためには世界観がそれなりに練られていないとダメだろう、とは思っていました。
安藤:例えば、どういうところにこだわったんですか?
アオキ:ひとつは、技名を言わないこと。
安藤:たしかに『サイキックフォース』は「昇龍拳!」みたいに、技の名前を言いませんね。
アオキ:それはなぜかというと、彼らは技だと思って超能力を使ってるわけじゃないんですよ。炎を操る超能力者である主人公のバーンは、防衛本能から火の鳥を創り出しているだけなんです。あの技には、一応「ゴッドフェニックス」という名前がありますが、便宜上名付けているだけで、本人が「ゴッドフェニックスだー!」と出してるわけじゃない(笑)。そこはすごく大事にしました。
安藤:例えば、どういうところにこだわったんですか?
アオキ:ひとつは、技名を言わないこと。
安藤:たしかに『サイキックフォース』は「昇龍拳!」みたいに、技の名前を言いませんね。
アオキ:それはなぜかというと、彼らは技だと思って超能力を使ってるわけじゃないんですよ。炎を操る超能力者である主人公のバーンは、防衛本能から火の鳥を創り出しているだけなんです。あの技には、一応「ゴッドフェニックス」という名前がありますが、便宜上名付けているだけで、本人が「ゴッドフェニックスだー!」と出してるわけじゃない(笑)。そこはすごく大事にしました。

安藤:そもそも彼らは、戦いたくて戦っているわけではない、という世界設定ですもんね。そこで確かにノリノリで技名叫んでたらおかしい(笑)。
アオキ:で、時間を操る超能力者のウォンは分身技を使えるんですけど、分身に攻撃が来ると「はずれですよ」とわざわざ言う。これは、ウォンが戦いを楽しんでいるキャラクターだからです。このように、キャラクターとしての一貫性は持たせるようにしました。
安藤:すごく細かく考えられていますね。『サイキックフォース』は、声優陣が豪華なのも特徴でした。そこも、女性に人気が出た秘訣なのかと思ったのですが、どうでしょう。
石川:声優さんの声は、すごくこのゲームの魅力を増してくれましたね。僕、実は開発中の『サイキックフォース』の画像を見たとき、ちょっとがっかりしたんです。アオキさんは、このゲームをアニメっぽくしたいと言っていて、企画書にもそう書いてあったのに、プレイステーションの性能が低スペックで、アニメーションの世界を表現するまでには至らなかった。
アオキ:で、時間を操る超能力者のウォンは分身技を使えるんですけど、分身に攻撃が来ると「はずれですよ」とわざわざ言う。これは、ウォンが戦いを楽しんでいるキャラクターだからです。このように、キャラクターとしての一貫性は持たせるようにしました。
安藤:すごく細かく考えられていますね。『サイキックフォース』は、声優陣が豪華なのも特徴でした。そこも、女性に人気が出た秘訣なのかと思ったのですが、どうでしょう。
石川:声優さんの声は、すごくこのゲームの魅力を増してくれましたね。僕、実は開発中の『サイキックフォース』の画像を見たとき、ちょっとがっかりしたんです。アオキさんは、このゲームをアニメっぽくしたいと言っていて、企画書にもそう書いてあったのに、プレイステーションの性能が低スペックで、アニメーションの世界を表現するまでには至らなかった。

安藤:私も含めて初代プレイステーションのゲームを作ったことがあるクリエイターは、よくそのことに言及しますね。プレイステーションは前評判やイメージがすごすぎて、思い描いたことがなんでもできる気がしましたが、実際はそこまでではなかったですもんね。
石川:だから最初に画面を見た時は、「これ、ぜんぜんアニメじゃないじゃん……」と思ったんですよ。でも、アニメで活躍されている声優さんが参加されて、音が入ったら、一気にキャラクターに命が吹き込まれて、「これはいける」と思いました。
石川:だから最初に画面を見た時は、「これ、ぜんぜんアニメじゃないじゃん……」と思ったんですよ。でも、アニメで活躍されている声優さんが参加されて、音が入ったら、一気にキャラクターに命が吹き込まれて、「これはいける」と思いました。

安藤:真殿光昭さん、高山みなみさん、中尾隆聖さんなどそうそうたる声優さんが参加されていて、キース役の津久井教生さんは、昨年の『サイキックフォース』20周年イベントでMCをしてくださったとか。出演された方にも愛されるゲームになっているというのは、すごいことですよね。
石川:津久井さん自体が、キースのファンにとても愛されていたんですよね。それもあって、津久井さんにとっても『サイキックフォース』が特別な作品になったようです。津久井さんはファンを大切にされる方なので、結果的にキースを津久井さんに演じていただけて本当に良かった。これは狙ったからではなく、偶然、幸せなキャスティングができました。
石川:津久井さん自体が、キースのファンにとても愛されていたんですよね。それもあって、津久井さんにとっても『サイキックフォース』が特別な作品になったようです。津久井さんはファンを大切にされる方なので、結果的にキースを津久井さんに演じていただけて本当に良かった。これは狙ったからではなく、偶然、幸せなキャスティングができました。
■同業者はみんな、等しく妬ましい
安藤:『サイキックフォース』について、今だから言える裏話などはありますか?
アオキ:ラスボスとして出てくるキースが、ボスキャラとして作られたわけではなかったこと、ですかね。
安藤:えー、そうだったんですか!
アオキ:彼は、単なる登場人物の一人だったんです。ボスキャラは別につくろうとしていたんですけど、制作スケジュールの都合上、そこまで何人もつくれないということが判明して。このキャラはつくらなくてもいいか、と削除していったなかにボスもいたんです。そして、じゃあキースがボスかな、というかたちで繰り上がったんですよ。でも最初から主人公のバーンと親友だという設定だったので、そこは活かしました。
安藤:なるほど。1996年に『サイキックフォース』を作っている自分に、何かメッセージを残せるとしたらなんて言いますか?
アオキ:ラスボスとして出てくるキースが、ボスキャラとして作られたわけではなかったこと、ですかね。
安藤:えー、そうだったんですか!
アオキ:彼は、単なる登場人物の一人だったんです。ボスキャラは別につくろうとしていたんですけど、制作スケジュールの都合上、そこまで何人もつくれないということが判明して。このキャラはつくらなくてもいいか、と削除していったなかにボスもいたんです。そして、じゃあキースがボスかな、というかたちで繰り上がったんですよ。でも最初から主人公のバーンと親友だという設定だったので、そこは活かしました。
安藤:なるほど。1996年に『サイキックフォース』を作っている自分に、何かメッセージを残せるとしたらなんて言いますか?

アオキ:当時の自分はまだ若くて、失敗を恐れず突き進めたんですよね。今の自分は、プロデューサーなども経験して、もっといろいろなことを考えてしまう。やりたいことを貫き通す、推進力みたいなものがこのゲームを創り出したと思っているので、「そのままでいいよ」と言いたいです。
石川:僕も、音楽や音声は今聞いてもいいと思うので、そのままでと伝えたいですが、効果音だけはちょっとなあ。やっぱりこれまで20年以上やってきた積み重ねが今の自分にはあるので、「効果音は俺にやらせろ」と言いたいですかね(笑)。
安藤:サウンドエフェクトはノウハウが物を言う世界なんですね。
石川:効果音は経験があればあるほどいいものができますね。
安藤:石川さんは、同じ業界の中でライバルだと思ってる人などいるんですか?
石川:全員ライバルだと思ってますよ。音屋はみんな平等に妬ましい(笑)。僕より経験がある上の世代の方はもちろん、下の若い世代もすごいやつはたくさんいるので、すごいという気持ちを超えて「ちきしょう」みたいな気持ちになります。僕は昔から「妬みの石川」なんですよ。
アオキ:それ、初めて聞いたよ(笑)。
石川:だから、この仕事についてからゲームを素直に楽しめないんです。すごくいい音だと、「おもしろいけど、くやしいー!」ってなっちゃうので(笑)。アオキさんは?
石川:僕も、音楽や音声は今聞いてもいいと思うので、そのままでと伝えたいですが、効果音だけはちょっとなあ。やっぱりこれまで20年以上やってきた積み重ねが今の自分にはあるので、「効果音は俺にやらせろ」と言いたいですかね(笑)。
安藤:サウンドエフェクトはノウハウが物を言う世界なんですね。
石川:効果音は経験があればあるほどいいものができますね。
安藤:石川さんは、同じ業界の中でライバルだと思ってる人などいるんですか?
石川:全員ライバルだと思ってますよ。音屋はみんな平等に妬ましい(笑)。僕より経験がある上の世代の方はもちろん、下の若い世代もすごいやつはたくさんいるので、すごいという気持ちを超えて「ちきしょう」みたいな気持ちになります。僕は昔から「妬みの石川」なんですよ。
アオキ:それ、初めて聞いたよ(笑)。
石川:だから、この仕事についてからゲームを素直に楽しめないんです。すごくいい音だと、「おもしろいけど、くやしいー!」ってなっちゃうので(笑)。アオキさんは?

アオキ:僕は、あんまりライバル意識は強くないかなあ。どちらかというと、自分で満足できる作品が作れるかということが重要。自己満足で終わってしまってはいけないけど、自分で納得できる作品を作るというのは最低ラインだなと思っています。そこに達しないものは、売ってはいけないと思っているので。
■当時の弱点を克服して、また『サイキックフォース』をつくりたい
安藤:お二人はもう30年近くゲームのお仕事をされてきているわけですが、スキル、アイデア、資金など、なんでも手に入るとしたら、今何が欲しいですか? というのも、僕はプロデューサーとしてやっぱり資金が欲しいんです。資金があれば、優秀なスタッフも集められるし、その優秀なスタッフが秀逸なアイデアを持っているので、結局全部手に入るから。最初に物事を動かすのは、開発資金かなと思っています。
アオキ:それ、まさにプロデューサー目線ですよね。今のお話を聞いていて、自分はプロデュースワークもやるんだけど、プロデューサーではないと思いました(笑)。僕は、やっぱりすばらしいアイデアが欲しいんですよ。アイデアがすべての原動力になる。お金があってもアイデアがなければ無駄になっちゃうのではないでしょうか。優秀なスタッフがいても同様。逆に、アイデアがあれば、お金もスタッフも集まると思っているんですよね。
アオキ:それ、まさにプロデューサー目線ですよね。今のお話を聞いていて、自分はプロデュースワークもやるんだけど、プロデューサーではないと思いました(笑)。僕は、やっぱりすばらしいアイデアが欲しいんですよ。アイデアがすべての原動力になる。お金があってもアイデアがなければ無駄になっちゃうのではないでしょうか。優秀なスタッフがいても同様。逆に、アイデアがあれば、お金もスタッフも集まると思っているんですよね。

石川:僕は、クリエイターとしてのスキルですね。サウンドエンジニアとしてのスキルがもっと欲しい。僕はずっとサウンドエンジニア、サウンドエフェクトクリエイターとしてやってきましたが、じつは通信カラオケの音源を作ったり、レーベルを立ち上げたり、イベントをやったり、いろいろなことをしているんです。あと最近では、サウンドディレクターというかたちで、ほかのサウンドメンバーに音を作ってもらうこともある。ずっとスキルを磨き続けてきたわけではありません。だから、ずっとやり続けている人に比べるとスキルが低いなと思っているんですよね。目指す姿としては、クリエイターとしてドーンと成長したいので、スキルだなと思います。
安藤:きれいに三者三様の答えが出ましたね。ここで最後に、なぜ『サイキックフォース』の盛り上がりは3年ほどで収束してしまい、今までブランドが続いてこなかったのかという、答えにくい質問をしてみましょう(笑)。
アオキ:いやー……(笑)。一応僕は、『サイキックフォース』シリーズの企画をこの20年のなかで何度も出したんです。でも、企業として作れない事情があったんですよね。正直に言うと、続編の『サイキックフォース2012』があまり売れなかったことも一つの要因だと思います。
安藤:でも、アオキさんとしては、機会があったらまたチャレンジしてみたい?
アオキ:今だったら3D空間を生かした新しいシステムをいくらでも作れますけど、あえてこの『サイキックフォース』独特のスタイルにこだわりたいです。他社さんがあまり類似のゲームを出さなかったので、このポジションがぽっかり空いてるんですよね。今なら、当時のゲームシステムの弱点もわかっているから、改良の仕方も考えられる。ぜひチャレンジしたいです。このまま失われていくのは、もったいないゲームだと最近とくに思っているんです。
安藤:では、この記事をきっかけに復活するかもしれませんね。タイトーやスクウェア・エニックスにいる『サイキックフォース』が好きな方はアオキさんに連絡をください(笑)。
安藤:きれいに三者三様の答えが出ましたね。ここで最後に、なぜ『サイキックフォース』の盛り上がりは3年ほどで収束してしまい、今までブランドが続いてこなかったのかという、答えにくい質問をしてみましょう(笑)。
アオキ:いやー……(笑)。一応僕は、『サイキックフォース』シリーズの企画をこの20年のなかで何度も出したんです。でも、企業として作れない事情があったんですよね。正直に言うと、続編の『サイキックフォース2012』があまり売れなかったことも一つの要因だと思います。
安藤:でも、アオキさんとしては、機会があったらまたチャレンジしてみたい?
アオキ:今だったら3D空間を生かした新しいシステムをいくらでも作れますけど、あえてこの『サイキックフォース』独特のスタイルにこだわりたいです。他社さんがあまり類似のゲームを出さなかったので、このポジションがぽっかり空いてるんですよね。今なら、当時のゲームシステムの弱点もわかっているから、改良の仕方も考えられる。ぜひチャレンジしたいです。このまま失われていくのは、もったいないゲームだと最近とくに思っているんです。
安藤:では、この記事をきっかけに復活するかもしれませんね。タイトーやスクウェア・エニックスにいる『サイキックフォース』が好きな方はアオキさんに連絡をください(笑)。

テキスト:崎谷 実穂(Sakiya Miho)
新卒で入社した人材系企業でコピーライティングを、転職先の広告制作会社で著名人・タレントなどの取材記事を担当し、2012年に独立。ビジネス系の記事、書籍のライティングを中心に活動。趣味は将棋で、アニメ・マンガ(BL含む)もわりとよく観る&読む中途半端なオタク。
崎谷実穂 サイト→『sakiyamiho.com』
ツイッターアカウント→sakiya@yaiask
シシララTV オリジナル記事