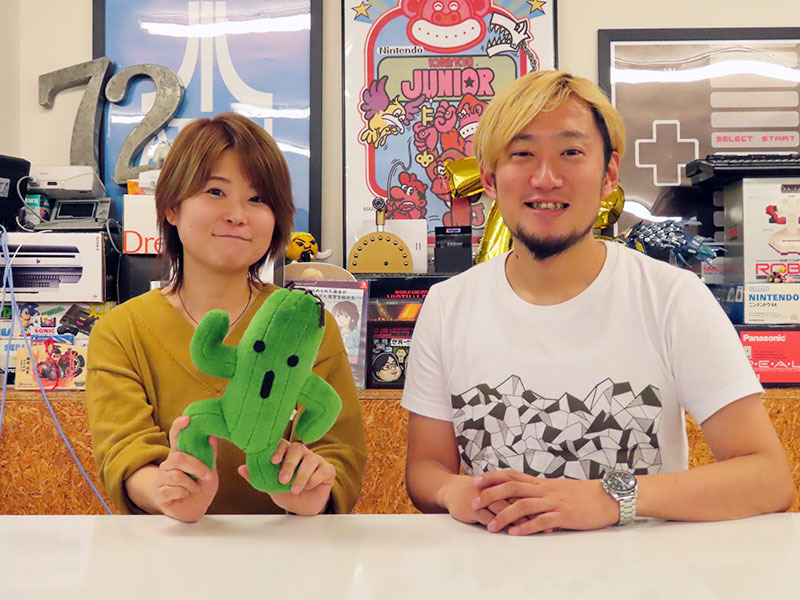大切なのは“シーン”に身を置くこと──行動に移すことがプロゲーマーへの道/ふ~どVS安藤武博 濃密対談
「ゲームをプレイすること」を生業にして生活している“プロゲーマー”。ゲーマーにとっては夢のような職業にも思えるが、実際にどのような経緯でプロになり、どうやってお金を稼いでいくのか、漠然としたイメージしか抱くことができない人も多いだろう。
そこで今回、『RAGE vol.4 ストリートファイターV GRAND FINALS』での活躍も記憶に新しいTeam Grapht所属のプロゲーマー・ふ~ど氏をゲストに迎え、ゲームDJの安藤武博がプロゲーマーと“e-Sportsの今”に鋭く切り込んでいく対談企画をお届け。ふ~ど氏の人となりを紐解きつつ、プロゲーマーという職業の現実にも踏み込んでいく。

■“プロゲーマー”とはどのような職業なのか?
安藤武博(以下、安藤):本日はよろしくお願いします。ふ~どさんはさまざまなゲーム大会で活躍されていますが、なかでも今年の「RAGE(※)」の優勝はすごかったですね。
(※)RAGE……さまざまなジャンルのゲーム大会を開催する次世代型e-Sportsイベント。ふ~どさんが優勝した大会は「RAGE vol.4 ストリートファイターV GRAND FINALS」。
ふ~どさん(以下、敬称略):ありがとうございます。
安藤:今日は「プロゲーマー」という職業がいったいどのようなお仕事なのか……そしてどんな形で生活していくためのお金を稼いでいるのかなど、かなり踏み込んで聞いてみたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。さっそくですが、「RAGE」のような賞金が出るゲーム大会というのは、日本国内ではどれぐらい行われているのでしょうか?
ふ~ど:高額賞金のものとなると、数はとても少ないです。それこそ『ストリートファイター』シリーズという括りならば、「RAGE」ぐらいしかないですね。
安藤:日本のプロゲーマー界隈では、高額賞金が出るタイトルを見定めて練習するスタイルと、得意なタイトルの技術を磨いたあとで出場できる賞金大会を探すスタイル、どちらがスタンダードなのでしょう?
ふ~ど:後者ですね。自分の得意ジャンルで勝負する人が多いと思います。そもそも、複数のタイトルをプレイしている人、そのうえで上位を狙える実力があるという人は、とても数が少ないんですよ。スポーツでたとえると、ラグビーが上手い人がいたとして、その人がサッカーも上手いとは限らないじゃないですか。これはプロゲーマーにも同じことがいえます。
安藤武博(以下、安藤):本日はよろしくお願いします。ふ~どさんはさまざまなゲーム大会で活躍されていますが、なかでも今年の「RAGE(※)」の優勝はすごかったですね。
(※)RAGE……さまざまなジャンルのゲーム大会を開催する次世代型e-Sportsイベント。ふ~どさんが優勝した大会は「RAGE vol.4 ストリートファイターV GRAND FINALS」。
ふ~どさん(以下、敬称略):ありがとうございます。
安藤:今日は「プロゲーマー」という職業がいったいどのようなお仕事なのか……そしてどんな形で生活していくためのお金を稼いでいるのかなど、かなり踏み込んで聞いてみたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。さっそくですが、「RAGE」のような賞金が出るゲーム大会というのは、日本国内ではどれぐらい行われているのでしょうか?
ふ~ど:高額賞金のものとなると、数はとても少ないです。それこそ『ストリートファイター』シリーズという括りならば、「RAGE」ぐらいしかないですね。
安藤:日本のプロゲーマー界隈では、高額賞金が出るタイトルを見定めて練習するスタイルと、得意なタイトルの技術を磨いたあとで出場できる賞金大会を探すスタイル、どちらがスタンダードなのでしょう?
ふ~ど:後者ですね。自分の得意ジャンルで勝負する人が多いと思います。そもそも、複数のタイトルをプレイしている人、そのうえで上位を狙える実力があるという人は、とても数が少ないんですよ。スポーツでたとえると、ラグビーが上手い人がいたとして、その人がサッカーも上手いとは限らないじゃないですか。これはプロゲーマーにも同じことがいえます。

安藤:一口にゲームといっても、その実、ジャンルの幅は広いですからね。それこそラグビーとサッカーの比ではないぐらい。
ふ~ど:はい。そのためプロゲーマーと呼ばれる人は自分の得意なジャンルのみをプレイしている人が多いです。なかでも格闘ゲームは『ストリートファイター』のような2Dゲームと、『鉄拳』のような3Dゲームでまた大きく違いますからね。じつはプロゲーマーという言葉自体はとても曖昧で、スポーツならばラグビーやサッカーなどの種目ごとで括っているのに、ゲームはゲームという括りにされてしまっているんですよ。
安藤:たしかに。「プロゲーマー」という括り方って「プロスポーツ選手」って括りと同じであると考えると、曖昧というか幅が広すぎる。実際は、各々に専門としているものや、得意ジャンルがあるというわけですね。では、ふ~どさんが専門にしているタイトルはやはり『ストリートファイターV』になるんですか?
ふ~ど:そうですね。あとは『ガンスリンガー ストラトス』(※)ですかね。この『ガンスト』も高額の賞金が出る大会が開催されたタイトルなのですが、5回開催されたなかで3回優勝することができました。
(※)ガンスリンガーストラトス……スクウェア・エニックスよりリリースされたアーケード用対戦ゲーム。オンラインマルチ対戦型のダブルガンアクションで、現在は『ガンスリンガー ストラトス3』が稼働中。
安藤:それはすごい! でも『ストV』と『ガンスト』は、ぜんぜん違うタイプのゲームですよね。『ガンスト』はどういった経緯でプレイすることになったんですか?
ふ~ど:もともとはプロゲーマーとしてイベントに呼ばれたことがきっかけです。遊んでみたらゲームとしてとてもおもしろかったので、そのまま趣味で遊び続けていました。ただ、あくまで自分は『ストV』のプロゲーマーなので、『ガンスト』を遊ぶことはプロ意識に欠けると言われてしまうと、返す言葉がないんですけど。
ふ~ど:はい。そのためプロゲーマーと呼ばれる人は自分の得意なジャンルのみをプレイしている人が多いです。なかでも格闘ゲームは『ストリートファイター』のような2Dゲームと、『鉄拳』のような3Dゲームでまた大きく違いますからね。じつはプロゲーマーという言葉自体はとても曖昧で、スポーツならばラグビーやサッカーなどの種目ごとで括っているのに、ゲームはゲームという括りにされてしまっているんですよ。
安藤:たしかに。「プロゲーマー」という括り方って「プロスポーツ選手」って括りと同じであると考えると、曖昧というか幅が広すぎる。実際は、各々に専門としているものや、得意ジャンルがあるというわけですね。では、ふ~どさんが専門にしているタイトルはやはり『ストリートファイターV』になるんですか?
ふ~ど:そうですね。あとは『ガンスリンガー ストラトス』(※)ですかね。この『ガンスト』も高額の賞金が出る大会が開催されたタイトルなのですが、5回開催されたなかで3回優勝することができました。
(※)ガンスリンガーストラトス……スクウェア・エニックスよりリリースされたアーケード用対戦ゲーム。オンラインマルチ対戦型のダブルガンアクションで、現在は『ガンスリンガー ストラトス3』が稼働中。
安藤:それはすごい! でも『ストV』と『ガンスト』は、ぜんぜん違うタイプのゲームですよね。『ガンスト』はどういった経緯でプレイすることになったんですか?
ふ~ど:もともとはプロゲーマーとしてイベントに呼ばれたことがきっかけです。遊んでみたらゲームとしてとてもおもしろかったので、そのまま趣味で遊び続けていました。ただ、あくまで自分は『ストV』のプロゲーマーなので、『ガンスト』を遊ぶことはプロ意識に欠けると言われてしまうと、返す言葉がないんですけど。

安藤:それはいったいどうしてでしょう。
ふ~ど:『ガンスト』のプレイを始めた時点では、賞金大会が開催されることなんて決まってもいなかったわけですから。結果的に大会が開催され、そこで賞金を稼ぐことが出来たからよかったものの、本来は「無駄な時間を使っている」と言われても仕方がないところなんですよ。
安藤:プロゲーマーは、ほかのゲームを遊んでいる時間すら無駄と言われてしまうぐらいシビアな世界ってことですか。
ふ~ど:「娯楽の範疇を越える遊び方」をするのがマズいって意味です。正直なところ、自分は『ストV』よりも『ガンスト』を遊んでいた時期があって、そのときは完全に娯楽の範疇を越えていたと思います。これはプロゲーマーとして考えると非常にマズい。
安藤:ふ~どさんは『シャドウバース』をプレイしていたり、シシララTVの番組でも『デュエル エクス マキナ』を一緒にプレイしてくれたりと、TCGにも精通している印象なのですが、ご自身としてはどういうタイプのゲームが好きなんですか?
ふ~ど:『ストV』しかり、『ガンスト』や『シャドバ』しかりなんですけど、総じて対人戦が楽しいゲームが好きです。なので、1人用のRPGなんかはほとんどプレイしませんね。「レベルを上げれば確実に敵に勝てる」という明確な答えが出てしまっているのが嫌なので。そのため、自分がRPGを遊ぶときは縛りを作ってプレイしたりします。
安藤:なるほど。
ふ~ど:『ガンスト』のプレイを始めた時点では、賞金大会が開催されることなんて決まってもいなかったわけですから。結果的に大会が開催され、そこで賞金を稼ぐことが出来たからよかったものの、本来は「無駄な時間を使っている」と言われても仕方がないところなんですよ。
安藤:プロゲーマーは、ほかのゲームを遊んでいる時間すら無駄と言われてしまうぐらいシビアな世界ってことですか。
ふ~ど:「娯楽の範疇を越える遊び方」をするのがマズいって意味です。正直なところ、自分は『ストV』よりも『ガンスト』を遊んでいた時期があって、そのときは完全に娯楽の範疇を越えていたと思います。これはプロゲーマーとして考えると非常にマズい。
安藤:ふ~どさんは『シャドウバース』をプレイしていたり、シシララTVの番組でも『デュエル エクス マキナ』を一緒にプレイしてくれたりと、TCGにも精通している印象なのですが、ご自身としてはどういうタイプのゲームが好きなんですか?
ふ~ど:『ストV』しかり、『ガンスト』や『シャドバ』しかりなんですけど、総じて対人戦が楽しいゲームが好きです。なので、1人用のRPGなんかはほとんどプレイしませんね。「レベルを上げれば確実に敵に勝てる」という明確な答えが出てしまっているのが嫌なので。そのため、自分がRPGを遊ぶときは縛りを作ってプレイしたりします。
安藤:なるほど。

■人間vs人間の戦いだからこそ生まれるドラマ──若さ=強さの方程式は成り立つのか?
ふ~ど:一時期、ファミコンの難しいゲームをクリアするのがマイブームだったりしたんですけど、やはり生身の人間と戦うほうがエキサイティングで楽しいです。1人用のゲームは何日かあればクリアできてしまいますが、『ストリートファイターII』は30年経った今でも、まだ研究され続けていますよね。自分としては、そちらのほうがゲームとしての深みがあると思うんです。
安藤:対戦相手が人間であるからこそ、研究に終わりがないと。
ふ~ど:「対戦がしたいならゲームじゃなくてもいいんじゃないか?」と思われてしまうかもしれませんが、ゲームなら身体的なハンデもほとんどありませんし、ジャッジするのも人間ではないので曖昧さがないため、限りなく公平な戦いができるんですよ。そこらへんも、対戦ゲームが好きな理由です。
安藤:しかし、一方で『LORD of VERMILION』(※)などの大会を見ていると、マルチタスクや動体視力などの能力は勝利のために必要なスキルに思えます。ゲームプレイヤーにとって、若さは有利に働くのではないでしょうか?
(※)LORD of VERMILION……スクウェア・エニックスのアーケード用オンラインカードゲーム。現在、最新作の『LORD of VERMILION IV』が稼働中。
ふ~ど:「若さ=強さ」というのは、プロゲーマーのあいだでもよく話題になるテーマですね。正直なところ、毎回人によって意見が分かれるので結論は出ていません。ちなみに、僕は「若者至上主義」なので、若い人のほうが強いと思っています。なぜかというと、アーケードの格闘ゲームは、昔から若い人が年上の強者を倒していくという歴史があったからです。
安藤:若者が年長者を越えていく。まさに下剋上の歴史ですね。
ふ~ど:僕が10代の頃なんて、「24~25歳なんておっさんでしょ? 負けるわけないじゃん」と思っていました(笑)。ただ、それは社会人になってゲームをやる時間が少なくなっていたから……という理由もあると思います。
ふ~ど:一時期、ファミコンの難しいゲームをクリアするのがマイブームだったりしたんですけど、やはり生身の人間と戦うほうがエキサイティングで楽しいです。1人用のゲームは何日かあればクリアできてしまいますが、『ストリートファイターII』は30年経った今でも、まだ研究され続けていますよね。自分としては、そちらのほうがゲームとしての深みがあると思うんです。
安藤:対戦相手が人間であるからこそ、研究に終わりがないと。
ふ~ど:「対戦がしたいならゲームじゃなくてもいいんじゃないか?」と思われてしまうかもしれませんが、ゲームなら身体的なハンデもほとんどありませんし、ジャッジするのも人間ではないので曖昧さがないため、限りなく公平な戦いができるんですよ。そこらへんも、対戦ゲームが好きな理由です。
安藤:しかし、一方で『LORD of VERMILION』(※)などの大会を見ていると、マルチタスクや動体視力などの能力は勝利のために必要なスキルに思えます。ゲームプレイヤーにとって、若さは有利に働くのではないでしょうか?
(※)LORD of VERMILION……スクウェア・エニックスのアーケード用オンラインカードゲーム。現在、最新作の『LORD of VERMILION IV』が稼働中。
ふ~ど:「若さ=強さ」というのは、プロゲーマーのあいだでもよく話題になるテーマですね。正直なところ、毎回人によって意見が分かれるので結論は出ていません。ちなみに、僕は「若者至上主義」なので、若い人のほうが強いと思っています。なぜかというと、アーケードの格闘ゲームは、昔から若い人が年上の強者を倒していくという歴史があったからです。
安藤:若者が年長者を越えていく。まさに下剋上の歴史ですね。
ふ~ど:僕が10代の頃なんて、「24~25歳なんておっさんでしょ? 負けるわけないじゃん」と思っていました(笑)。ただ、それは社会人になってゲームをやる時間が少なくなっていたから……という理由もあると思います。

安藤:でも、最近はふ~どさんのように大人になってもずっとゲームを続けているプロゲーマーもいるので、状況は変わってきていますよね?
ふ~ど:そうですね。大人になってもゲームをやめない人が増えたため、相対的に、経験豊富なプレイヤーが増えました。しかし、それがすべて「強さ」に結びつくかというと、それも違うと思っています。
安藤:言いきりますね。その心は?
ふ~ど:ゲームの上達には経験が大事になる一方で、“考え方”や“気付くこと”のほうが大切だと思っているからです。たとえば、今の自分が20代の頃の自分とゲームで戦ったら、最初は確実に今の自分が勝つと思います。ただ、そのノウハウやテクニックは半年で教えることができるので、そのあとに再戦したらもう勝てないと思うんですよね。だから、自分は若者のほうが強いと結論付けています。
安藤:若者のほうが反応速度などに優れているし、考え方や発想も柔軟だから……ってことでしょうか。だから最近では、プロゲーマーの養成学校が成立しはじめているんですね。
ふ~ど:そうですね。
ふ~ど:そうですね。大人になってもゲームをやめない人が増えたため、相対的に、経験豊富なプレイヤーが増えました。しかし、それがすべて「強さ」に結びつくかというと、それも違うと思っています。
安藤:言いきりますね。その心は?
ふ~ど:ゲームの上達には経験が大事になる一方で、“考え方”や“気付くこと”のほうが大切だと思っているからです。たとえば、今の自分が20代の頃の自分とゲームで戦ったら、最初は確実に今の自分が勝つと思います。ただ、そのノウハウやテクニックは半年で教えることができるので、そのあとに再戦したらもう勝てないと思うんですよね。だから、自分は若者のほうが強いと結論付けています。
安藤:若者のほうが反応速度などに優れているし、考え方や発想も柔軟だから……ってことでしょうか。だから最近では、プロゲーマーの養成学校が成立しはじめているんですね。
ふ~ど:そうですね。

安藤:その手の学校ではどういうことを教えるんでしょうか? テクニックなのか、それとも心理的な駆け引きなのか……。
ふ~ど:両方ですね。たとえば『ストリートファイター』の起き攻め。相手をダウンさせたあと、飛び込んで攻撃するかどうかを瞬時に判断する必要がありますが、そこでどう動くべきかはある程度セオリーがあるんです。「昇龍拳などで迎撃されてもこちらはやられない」、「相手の体力的に飛び込んで攻撃を重ねたら倒せる」、「相手が中~遠距離を得意とするので近距離での多戦いのほうが有利になる」など、いくつかの要素を照らし合わせれば、そこに正解が生まれます。
安藤:定石のようなシチュエーションがある、と。
ふ~ど:はい。その正解を、自分たちのような熟練プレイヤーは経験で導き出せますし、そのノウハウはロジックとして若い人たちに教えることができるんです。
安藤:緊張に関してはいかがでしょうか? 「RAGE」や「EVO」のような大規模な大会で試合をするときはどんな気持ちなんでしょう?
ふ~ど:なるべく緊張はしないようにしています。もちろん完全にしないなんてことは無理ですが、そこは対戦相手も緊張していると思うので、そこまで対戦するうえでマイナスになることは思いません。ただマンダレイ・ベイでやった「EVO」の決勝トーナメントは、音響が下から突き上げてくるように流れてくるため、強制的に動悸を促されるような昂揚感がありました。あれははじめての経験でしたね。
安藤:まるで『ダライアス』の筐体みたいですね(笑)。
ふ~ど:まさにそれですね、それの化け物ヴァージョンです(笑)。ただ、その環境こそ特殊ではありましたけど、ゲームのプレイ中にまで緊張することはないです。自分はなにも考えていない時間が緊張を生むと考えているので、次に自分が取る行動を考えたり、相手の行動を読んでいたりすれば、緊張が入り込む余地はないと思っていますから。逆に緊張してしまっているときは、ゲームに集中できていないんだなと反省しますね。
ふ~ど:両方ですね。たとえば『ストリートファイター』の起き攻め。相手をダウンさせたあと、飛び込んで攻撃するかどうかを瞬時に判断する必要がありますが、そこでどう動くべきかはある程度セオリーがあるんです。「昇龍拳などで迎撃されてもこちらはやられない」、「相手の体力的に飛び込んで攻撃を重ねたら倒せる」、「相手が中~遠距離を得意とするので近距離での多戦いのほうが有利になる」など、いくつかの要素を照らし合わせれば、そこに正解が生まれます。
安藤:定石のようなシチュエーションがある、と。
ふ~ど:はい。その正解を、自分たちのような熟練プレイヤーは経験で導き出せますし、そのノウハウはロジックとして若い人たちに教えることができるんです。
安藤:緊張に関してはいかがでしょうか? 「RAGE」や「EVO」のような大規模な大会で試合をするときはどんな気持ちなんでしょう?
ふ~ど:なるべく緊張はしないようにしています。もちろん完全にしないなんてことは無理ですが、そこは対戦相手も緊張していると思うので、そこまで対戦するうえでマイナスになることは思いません。ただマンダレイ・ベイでやった「EVO」の決勝トーナメントは、音響が下から突き上げてくるように流れてくるため、強制的に動悸を促されるような昂揚感がありました。あれははじめての経験でしたね。
安藤:まるで『ダライアス』の筐体みたいですね(笑)。
ふ~ど:まさにそれですね、それの化け物ヴァージョンです(笑)。ただ、その環境こそ特殊ではありましたけど、ゲームのプレイ中にまで緊張することはないです。自分はなにも考えていない時間が緊張を生むと考えているので、次に自分が取る行動を考えたり、相手の行動を読んでいたりすれば、緊張が入り込む余地はないと思っていますから。逆に緊張してしまっているときは、ゲームに集中できていないんだなと反省しますね。

安藤:余計なことを考える余地がないぐらいゲームと相手のことで脳を支配してしまうんですね。ちなみに、アスリートは練習にルーティーンがあったり、食事のメニューが決まっていたりしますが、プロゲーマーにもそういった類のものはありますか?
ふ~ど:人によりけりだとは思いますが、少なくとも自分は、毎日の生活に規則や習慣性があるとはいえませんね。そもそもプロゲーマーという言葉の定義からして難しいんですよ。プロ野球選手やプロサッカー選手の場合は、「試合に出ること」が明確な仕事になると思いますが、現在の自分たちプロゲーマーは、試合に出ることはもちろん、シシララTVさんをはじめとしたメディアに出演することも大切な仕事だと考えています。そうなると、ただひたすらゲームをプレイするだけの生活って、ちょっと違うんじゃないかなと。ゲームをプレイすることはもちろんなのですが、自分はそれ以外にも、ゲームの体験会に足を運んだりゲーム実況の配信に出演したりといった、人との交流も大事にしています。
安藤:ゲームのプレイ以外にも、相応の時間を当てるということですね。これは正直、意外な答えが聞けました。世間一般的には、プロゲーマーはひたすらゲームだけを遊んでいると誤解している人も少なくなさそうですからね。では、メインで活躍されている『ストV』にかんしては、いったいどのような練習をされているのでしょうか?
ふ~ど:このご時世、家庭用ハードでオンラインプレイをして練習している人が多いと思いますが、自分は家に環境が整っていないので、ゲームセンターや知り合いの家でプレイすることが多いです。週4から週5でプレイしていますね。ただ、自分はゲームをやっている時間の長さと、プレイヤーの実力が必ずしも比例するとは思っていません。
安藤:そうなんですか? いったいなぜでしょう?
ふ~ど:少なくとも自分は、対戦してテクニックを磨くというよりは、戦略を考えている時間のほうが長いんです。ひたすらプレイを積み重ねるだけではなく、お酒を飲みながらほかのプレイヤーたちから情報を聞くといった、「シーン」にいることのほうがとても大事だと思っています。操作すること自体は誰でも出来るので、それよりも人から話を聞いたり、動画を見て研究したりしたほうが、結果的に有意義かなと考えています。
ふ~ど:人によりけりだとは思いますが、少なくとも自分は、毎日の生活に規則や習慣性があるとはいえませんね。そもそもプロゲーマーという言葉の定義からして難しいんですよ。プロ野球選手やプロサッカー選手の場合は、「試合に出ること」が明確な仕事になると思いますが、現在の自分たちプロゲーマーは、試合に出ることはもちろん、シシララTVさんをはじめとしたメディアに出演することも大切な仕事だと考えています。そうなると、ただひたすらゲームをプレイするだけの生活って、ちょっと違うんじゃないかなと。ゲームをプレイすることはもちろんなのですが、自分はそれ以外にも、ゲームの体験会に足を運んだりゲーム実況の配信に出演したりといった、人との交流も大事にしています。
安藤:ゲームのプレイ以外にも、相応の時間を当てるということですね。これは正直、意外な答えが聞けました。世間一般的には、プロゲーマーはひたすらゲームだけを遊んでいると誤解している人も少なくなさそうですからね。では、メインで活躍されている『ストV』にかんしては、いったいどのような練習をされているのでしょうか?
ふ~ど:このご時世、家庭用ハードでオンラインプレイをして練習している人が多いと思いますが、自分は家に環境が整っていないので、ゲームセンターや知り合いの家でプレイすることが多いです。週4から週5でプレイしていますね。ただ、自分はゲームをやっている時間の長さと、プレイヤーの実力が必ずしも比例するとは思っていません。
安藤:そうなんですか? いったいなぜでしょう?
ふ~ど:少なくとも自分は、対戦してテクニックを磨くというよりは、戦略を考えている時間のほうが長いんです。ひたすらプレイを積み重ねるだけではなく、お酒を飲みながらほかのプレイヤーたちから情報を聞くといった、「シーン」にいることのほうがとても大事だと思っています。操作すること自体は誰でも出来るので、それよりも人から話を聞いたり、動画を見て研究したりしたほうが、結果的に有意義かなと考えています。

■大切なのは“シーン”に身を置くこと──その理由とは
安藤:「操作することは誰でも出来る」というのは、とても力強い言葉ですね。今の話で気になったのは「シーン」という単語です。これからふ~どくんのようにプロを目指すプレイヤーも多いと思うので聞きたいのですが、この「シーン」というのはどこにあり、どのように飛び込んでいけばいいのでしょうか?
ふ~ど:明確に説明することは難しいのですが、「人の多い環境にいること」が「シーン」に身を置く大前提だと思います。たとえば自分は、池袋のサントロペというゲーセンをホームにしているのですが、『ガンスト』にハマッているときは朝から晩までそこでプレイしていました。結果、そこに人がどんどん集まるようになり、僕と対戦したい人など、腕に覚えがある人もどんどん来るようになったんです。
安藤:なるほど。そういった環境に身を置くことこそが「シーン」に身を置くということですね。納得しました。
ふ~ど:あのときは、最高の「シーン」を自分で作り上げることができたなと思いましたよ。
安藤:そうなると、人の集まる都市部のほうが有利でしょうね。
ふ~ど:そのとおりです。なので、もし本気で「シーンに身を置きたい」と考えている人がいるのなら、そこはなんとかして上京してきてほしいと思います。とにかく、自分で考えて行動に移すことが大事なんですよ。たとえば、プロゲーマーになりたいのに「EVO」に行かないと言う人もいたりするじゃないですか。個人的には、そういう人って「絶対にプロゲーマーになりたいわけではないんだろうな」と思ってしまいます。だって「EVO」で勝つことができれば、それだけでプロゲーマーになれるんですよ? ラスベガスという街自体も楽しいわけですし、参加しない理由がないじゃないですか。
安藤:「操作することは誰でも出来る」というのは、とても力強い言葉ですね。今の話で気になったのは「シーン」という単語です。これからふ~どくんのようにプロを目指すプレイヤーも多いと思うので聞きたいのですが、この「シーン」というのはどこにあり、どのように飛び込んでいけばいいのでしょうか?
ふ~ど:明確に説明することは難しいのですが、「人の多い環境にいること」が「シーン」に身を置く大前提だと思います。たとえば自分は、池袋のサントロペというゲーセンをホームにしているのですが、『ガンスト』にハマッているときは朝から晩までそこでプレイしていました。結果、そこに人がどんどん集まるようになり、僕と対戦したい人など、腕に覚えがある人もどんどん来るようになったんです。
安藤:なるほど。そういった環境に身を置くことこそが「シーン」に身を置くということですね。納得しました。
ふ~ど:あのときは、最高の「シーン」を自分で作り上げることができたなと思いましたよ。
安藤:そうなると、人の集まる都市部のほうが有利でしょうね。
ふ~ど:そのとおりです。なので、もし本気で「シーンに身を置きたい」と考えている人がいるのなら、そこはなんとかして上京してきてほしいと思います。とにかく、自分で考えて行動に移すことが大事なんですよ。たとえば、プロゲーマーになりたいのに「EVO」に行かないと言う人もいたりするじゃないですか。個人的には、そういう人って「絶対にプロゲーマーになりたいわけではないんだろうな」と思ってしまいます。だって「EVO」で勝つことができれば、それだけでプロゲーマーになれるんですよ? ラスベガスという街自体も楽しいわけですし、参加しない理由がないじゃないですか。

安藤:言っていることはよくわかります。プロゲーマーになるためには、行動力や決断力も必要ってことですよね。ちなみにふ~どさんは、遊びに行く感覚で「EVO」に出場して優勝しちゃったってことなんですか?
ふ~ど:もちろん勝てる算段もありましたけど、遊びの延長で参加したという感覚のほうが強いかもしれませんね。「遊び」と言っちゃうと少しムッとされてしまうかもしれませんが、物事を楽しむということは、自分のなかでは悪いことではないんですよ。歯を食いしばって努力している人と楽しみながら学んでいる人では、どうしても前者のほうが評価されがちなんですが、そんな世の中が嫌いですね。やることが同じなら、楽しんでやったほうがいいじゃないですか。
安藤:ふ~どさんは独自の意見をしっかりと持っていて面白いですね。後半では、そんなふ~どさんの人となりについても、もっとお話を聞かせてもらいたいと思います。
(後編へ続く)
後編はコチラ→縄文時代は終わり弥生時代が始まる──今、プロゲーマーに起きている変革とは!?
テキスト:カワチ(Makoto Kawachi) 1981年生まれ。ライター。ビジュアルノベルに目がないと公言するが、本当は肌色が多けれななんでもいい系のビンビン♂ライター。女性声優とセクシー女優が大好き。
ツイッターアカウント→カワチ@kawapi
ふ~ど:もちろん勝てる算段もありましたけど、遊びの延長で参加したという感覚のほうが強いかもしれませんね。「遊び」と言っちゃうと少しムッとされてしまうかもしれませんが、物事を楽しむということは、自分のなかでは悪いことではないんですよ。歯を食いしばって努力している人と楽しみながら学んでいる人では、どうしても前者のほうが評価されがちなんですが、そんな世の中が嫌いですね。やることが同じなら、楽しんでやったほうがいいじゃないですか。
安藤:ふ~どさんは独自の意見をしっかりと持っていて面白いですね。後半では、そんなふ~どさんの人となりについても、もっとお話を聞かせてもらいたいと思います。
(後編へ続く)
後編はコチラ→縄文時代は終わり弥生時代が始まる──今、プロゲーマーに起きている変革とは!?
テキスト:カワチ(Makoto Kawachi) 1981年生まれ。ライター。ビジュアルノベルに目がないと公言するが、本当は肌色が多けれななんでもいい系のビンビン♂ライター。女性声優とセクシー女優が大好き。
ツイッターアカウント→カワチ@kawapi
シシララTV オリジナル記事