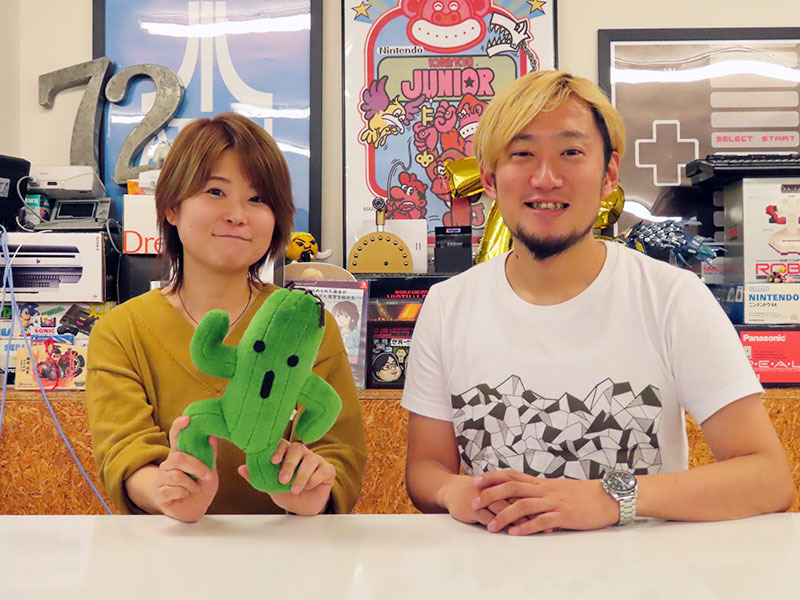音楽とプログラム、2つのスキルを生かすために選んだゲーム業界の道──濱田誠一×安藤武博 対談【サウンドコンポーザーに訊く!/連載第3回・前編】
ミュージシャン活動をする傍ら、会社員としてプログラマーの道を歩み始め、その2つのスキルを手に1989年にデータイーストに入社した濱田誠一氏。アーケードにコンシューマにと多数のデコゲーのサウンドを制作し、更にデータイースト公式バンド・ゲーマデリックにもベーシストとして参加。データイースト退社後はセガに所属、多数のタイトル制作に携わる。また『探偵 神宮寺三郎』シリーズのサウンドも引き続き手掛けるなど、30年近く精力的にゲーム音楽作曲家として活動を続けている。前編の今回は、濱田氏の知られざるアマチュアミュージシャン時代の話から、データイースト時代の話に切り込んでいく!
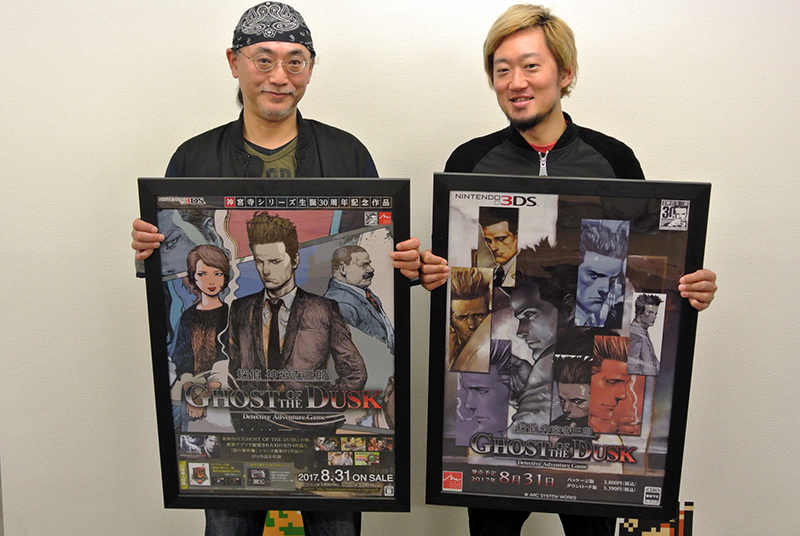
濱田誠一氏(写真左)
データイースト、セガを経て現在はフリーランスで活動するゲーム音楽作曲家兼ベーシスト。データイーストのゲームミュージックバンド、ゲーマデリックではベースを担当。代表作は『フライングパワーディスク』、『ヘラクレスの栄光』シリーズなど。特に『探偵 神宮寺三郎』シリーズはファミコン版4作目の『時の過ぎゆくままに』以降、『灯火が消えぬ間に』を除く全タイトルのサウンド制作に携わっている。
■キャリアスタートはキャバレーの箱バン? 濱田誠一の青春時代
安藤武博(以下、安藤):濱田さん、今日はよろしくお願いいたします。ご自身はデータイーストでのお仕事が、ゲーム業界でのキャリアスタートになるのでしょうか?
濱田誠一さん(以下、濱田):社会に出てからという意味では、データイースト以前にも別の仕事をしていましたが、ゲーム業界ということであればそうなります。じつは僕、この業界に入るのは遅かったんですよ。27歳の時でしたからね。
安藤:それまではどんな活動をされていたのでしょうか?
濱田:仕事って意味でいうと、まず音楽学校に行きながらキャバレーの箱バンをやっていたんですよ。
安藤:差し支えなければ、キャバレーの箱バンとは一体なんなのか、具体的にお聞きしたいです!
濱田:『ブルース・ブラザーズ』っていう映画をご覧になったことがある方ならわかると思うんですけど、バンドが地方のクラブとかに行って、金網の貼ってあるステージの中で演奏するシーンあるんですね。要は、お客さんのリクエストに応えて曲を演奏するっていうお仕事です。演奏するお店のことを箱って読んでいて、そこについているレギュラーのバンドのことを箱バンって言っていたんです。
安藤:今でも赤羽や銀座にキャバレーがありますよね。わたしも何度か行ったことがありますが、その時出演していたバンドも箱バンの人だったのかな。ちなみに東京のキャバレーでやられていたんですか?
濱田:池袋の北口にあった店でやっていたんですけど、自分はレギュラーではなく、学校の先輩たちが休みの時の代役でした。代役のことをトラって言うんですよ。トラに入るっていう。
安藤:なんでトラって言うんでしょう? 面白いですね。
濱田:「エキストラ」のトラですね。
安藤:なるほど!
濱田:当時まだ19歳ぐらいでしたけど、その時に初めて人前で楽器を弾いて、ギャラをいただくという経験をしました。
安藤:その時からベースをやられていたのでしょうか?
濱田:そうですね。学校がベース課だったんで、先輩から頼まれてって感じで。
安藤:わたしもベーシストなんですけど、そもそも濱田さんがベースを選んだきっかけはなんですか? 「ヘビメタさん」というヘビーメタルの番組を手掛けたことがあるんですが、その時にESPの学生からベーシストを30人くらい集めて「なんでベースを始めたんですか?」というアンケートを取ったことがあります。そのときの答えは9割が同じ理由だったんですよ。
濱田:「俺よりギターがうまいやつがいたから」ですか?(笑)
安藤:あとは「俺しか残っていなかったから」とか(笑)。濱田さんの場合はどうでしたか?
濱田:これは過去に何度か聞かれていて、その都度思い付きで答えてるんだけど(笑)。でも、よくよく考えてみたらちゃんとした理由がありまして。自分の子供の頃って、テレビが白黒からようやくカラーになるくらいの時代だったんだけど、スピーカーがモノラルだったんですよ。
安藤:私が子どもの時もまだまだモノラルでしたね。
濱田:つまるところ、音響特性がよくないわけですよね。例えばそのスピーカーで歌番組とかを観ていると、聴こえてくるのは歌とベースの音ばかりなんです。なので、昔聴いた歌謡曲とかって、ベースラインを鮮烈に覚えているんですよね。
安藤:当時の歌番組を観ると、ベースが走っていますよね。メロディもリズムも引っ張っている。
濱田:時代にもよりますが、60年代後半から80年代初頭ぐらいまでは、例えば戦隊モノや歌モノのスタジオミュージシャンで、「知られざる名プレイヤー」が数多くいらっしゃったんですよ。これは僕もつい最近、セガの後輩に教えてもらった名前なんですが、例えば寺川正興さん。「仮面ライダー」とか、尾崎紀世彦さんの「また逢う日まで」とか、歌謡曲から特撮の曲までをいっぱい担当されていますし、劇伴もいっぱい手掛けています。その寺川さんが、元々はジャズプレイヤーなんですよね。
データイースト、セガを経て現在はフリーランスで活動するゲーム音楽作曲家兼ベーシスト。データイーストのゲームミュージックバンド、ゲーマデリックではベースを担当。代表作は『フライングパワーディスク』、『ヘラクレスの栄光』シリーズなど。特に『探偵 神宮寺三郎』シリーズはファミコン版4作目の『時の過ぎゆくままに』以降、『灯火が消えぬ間に』を除く全タイトルのサウンド制作に携わっている。
■キャリアスタートはキャバレーの箱バン? 濱田誠一の青春時代
安藤武博(以下、安藤):濱田さん、今日はよろしくお願いいたします。ご自身はデータイーストでのお仕事が、ゲーム業界でのキャリアスタートになるのでしょうか?
濱田誠一さん(以下、濱田):社会に出てからという意味では、データイースト以前にも別の仕事をしていましたが、ゲーム業界ということであればそうなります。じつは僕、この業界に入るのは遅かったんですよ。27歳の時でしたからね。
安藤:それまではどんな活動をされていたのでしょうか?
濱田:仕事って意味でいうと、まず音楽学校に行きながらキャバレーの箱バンをやっていたんですよ。
安藤:差し支えなければ、キャバレーの箱バンとは一体なんなのか、具体的にお聞きしたいです!
濱田:『ブルース・ブラザーズ』っていう映画をご覧になったことがある方ならわかると思うんですけど、バンドが地方のクラブとかに行って、金網の貼ってあるステージの中で演奏するシーンあるんですね。要は、お客さんのリクエストに応えて曲を演奏するっていうお仕事です。演奏するお店のことを箱って読んでいて、そこについているレギュラーのバンドのことを箱バンって言っていたんです。
安藤:今でも赤羽や銀座にキャバレーがありますよね。わたしも何度か行ったことがありますが、その時出演していたバンドも箱バンの人だったのかな。ちなみに東京のキャバレーでやられていたんですか?
濱田:池袋の北口にあった店でやっていたんですけど、自分はレギュラーではなく、学校の先輩たちが休みの時の代役でした。代役のことをトラって言うんですよ。トラに入るっていう。
安藤:なんでトラって言うんでしょう? 面白いですね。
濱田:「エキストラ」のトラですね。
安藤:なるほど!
濱田:当時まだ19歳ぐらいでしたけど、その時に初めて人前で楽器を弾いて、ギャラをいただくという経験をしました。
安藤:その時からベースをやられていたのでしょうか?
濱田:そうですね。学校がベース課だったんで、先輩から頼まれてって感じで。
安藤:わたしもベーシストなんですけど、そもそも濱田さんがベースを選んだきっかけはなんですか? 「ヘビメタさん」というヘビーメタルの番組を手掛けたことがあるんですが、その時にESPの学生からベーシストを30人くらい集めて「なんでベースを始めたんですか?」というアンケートを取ったことがあります。そのときの答えは9割が同じ理由だったんですよ。
濱田:「俺よりギターがうまいやつがいたから」ですか?(笑)
安藤:あとは「俺しか残っていなかったから」とか(笑)。濱田さんの場合はどうでしたか?
濱田:これは過去に何度か聞かれていて、その都度思い付きで答えてるんだけど(笑)。でも、よくよく考えてみたらちゃんとした理由がありまして。自分の子供の頃って、テレビが白黒からようやくカラーになるくらいの時代だったんだけど、スピーカーがモノラルだったんですよ。
安藤:私が子どもの時もまだまだモノラルでしたね。
濱田:つまるところ、音響特性がよくないわけですよね。例えばそのスピーカーで歌番組とかを観ていると、聴こえてくるのは歌とベースの音ばかりなんです。なので、昔聴いた歌謡曲とかって、ベースラインを鮮烈に覚えているんですよね。
安藤:当時の歌番組を観ると、ベースが走っていますよね。メロディもリズムも引っ張っている。
濱田:時代にもよりますが、60年代後半から80年代初頭ぐらいまでは、例えば戦隊モノや歌モノのスタジオミュージシャンで、「知られざる名プレイヤー」が数多くいらっしゃったんですよ。これは僕もつい最近、セガの後輩に教えてもらった名前なんですが、例えば寺川正興さん。「仮面ライダー」とか、尾崎紀世彦さんの「また逢う日まで」とか、歌謡曲から特撮の曲までをいっぱい担当されていますし、劇伴もいっぱい手掛けています。その寺川さんが、元々はジャズプレイヤーなんですよね。

安藤:寺川さんのことをPCでリサーチしてみました。『海のトリトン』に『天才バカボン』、『電人ザボーガー』に『鋼鉄ジーグ』……なるほど。このあたりの楽曲を手がけられている方なんですね。
濱田:バンドではウッドベース担当なんだけど、スタジオではエレキベースを弾いていて、音がすごいんですよ。でもこの人の名前が知られるようになったのはごく最近だと思います。それは、いわゆるノンクレジットのスタジオ仕事がほとんどだったから。だけど、よくよく聴いてみると「あ、この曲も寺川さんの担当だったんだ」みたいな。恐らく子供のころに聴いたベースは、この人の音がかなりのウェイトを占めているんです。
安藤:聴いてみた印象としては、結構ダイナミックにフレットを移動する印象ですね。
濱田:そうです。通常のバッキングで2オクターブ近く動き続ける「エレベーターベース」って言われているくらいですからね。
安藤:特撮は当然ですけど、昭和の頃はベースの音がすごく動くものがたくさんありますよね。
濱田:あの動くベースっていうのはモータウン(※1)から来ているんですよね。ジェームス・ジェマーソン(※2)とか。
(※1)モータウン……ソウルミュージックやブラックミュージックを中心としたアメリカのレコードレーベル。
(※2)ジェームス・ジェマーソン……1960年代から70年代初頭にかけて、モータウン黄金期に活動したアメリカのベーシスト。
安藤:濱田さん自身のルーツは寺川さんの音であり、その寺川さんのルーツはモータウンであり、ジャズに近いところもあるので、後々の『探偵 神宮寺三郎』シリーズの音楽に生きているという部分もあるのでしょうか?
濱田:それも一つのラインとしてありますね。ジャズとソウル、R&Bって近い部分があるじゃないですか。どっちにしろブラックミュージックなんですけど。その辺は子供のころから、意識せずに刷り込まれているので。
安藤:好きなベーシストっていますか?
濱田:ああ~、これがね(笑)。今の自分のスタイルとは全く違うんですけど、今言ったジェームス・ジェマーソンや、キャロル・ケイ(※3)も自分の中で語らなきゃいけない一人ですし、あと外せないのはジャコ・パストリアス(※4)。僕が高校時代にデビューしたベーシストです。
(※3)キャロル・ケイ……1960~70年代に活躍したプロのジャズ・ギタリスト、ロサンゼルスのセッション・ミュージシャンとして、1万曲以上のレコーディングに参加した。
(※4)ジャコ・パストリアス……1970年代に活躍したジャズ、フュージョンのベーシスト&アレンジャー。
安藤:濱田さんの雰囲気、ジャコ・パストリアスを彷彿とさせます(笑)。
濱田:いやいやいや、ああいう死に方(※5)はしたくない(笑)。
(※5)(ジャコ・パストリアスの)ああいう死に方……泥酔状態でクラブに入店しようとしたところでガードマンと乱闘になり、コンクリートに頭部を強打。脳挫傷による意識不明の重体に陥る。植物状態になった後、父親のジャックの判断で人工呼吸器が外され、1987年9月21日に永眠した。
安藤:今回の対談、ものすごくマニアックになりそうです(笑)。普段はフレットレスベース(※6)も使われていますか?
(※6)フレットレスベース……指版にフレット(突起部分)がないタイプのベース。
濱田:使いますよ。ライブではなかなか出番がありませんけど、レコーディングでは使いますね。フレットレスのチューンの5弦と、あとはアップライト(※7)。主に『探偵 神宮寺三郎』のレコーディングで使っています。
濱田:バンドではウッドベース担当なんだけど、スタジオではエレキベースを弾いていて、音がすごいんですよ。でもこの人の名前が知られるようになったのはごく最近だと思います。それは、いわゆるノンクレジットのスタジオ仕事がほとんどだったから。だけど、よくよく聴いてみると「あ、この曲も寺川さんの担当だったんだ」みたいな。恐らく子供のころに聴いたベースは、この人の音がかなりのウェイトを占めているんです。
安藤:聴いてみた印象としては、結構ダイナミックにフレットを移動する印象ですね。
濱田:そうです。通常のバッキングで2オクターブ近く動き続ける「エレベーターベース」って言われているくらいですからね。
安藤:特撮は当然ですけど、昭和の頃はベースの音がすごく動くものがたくさんありますよね。
濱田:あの動くベースっていうのはモータウン(※1)から来ているんですよね。ジェームス・ジェマーソン(※2)とか。
(※1)モータウン……ソウルミュージックやブラックミュージックを中心としたアメリカのレコードレーベル。
(※2)ジェームス・ジェマーソン……1960年代から70年代初頭にかけて、モータウン黄金期に活動したアメリカのベーシスト。
安藤:濱田さん自身のルーツは寺川さんの音であり、その寺川さんのルーツはモータウンであり、ジャズに近いところもあるので、後々の『探偵 神宮寺三郎』シリーズの音楽に生きているという部分もあるのでしょうか?
濱田:それも一つのラインとしてありますね。ジャズとソウル、R&Bって近い部分があるじゃないですか。どっちにしろブラックミュージックなんですけど。その辺は子供のころから、意識せずに刷り込まれているので。
安藤:好きなベーシストっていますか?
濱田:ああ~、これがね(笑)。今の自分のスタイルとは全く違うんですけど、今言ったジェームス・ジェマーソンや、キャロル・ケイ(※3)も自分の中で語らなきゃいけない一人ですし、あと外せないのはジャコ・パストリアス(※4)。僕が高校時代にデビューしたベーシストです。
(※3)キャロル・ケイ……1960~70年代に活躍したプロのジャズ・ギタリスト、ロサンゼルスのセッション・ミュージシャンとして、1万曲以上のレコーディングに参加した。
(※4)ジャコ・パストリアス……1970年代に活躍したジャズ、フュージョンのベーシスト&アレンジャー。
安藤:濱田さんの雰囲気、ジャコ・パストリアスを彷彿とさせます(笑)。
濱田:いやいやいや、ああいう死に方(※5)はしたくない(笑)。
(※5)(ジャコ・パストリアスの)ああいう死に方……泥酔状態でクラブに入店しようとしたところでガードマンと乱闘になり、コンクリートに頭部を強打。脳挫傷による意識不明の重体に陥る。植物状態になった後、父親のジャックの判断で人工呼吸器が外され、1987年9月21日に永眠した。
安藤:今回の対談、ものすごくマニアックになりそうです(笑)。普段はフレットレスベース(※6)も使われていますか?
(※6)フレットレスベース……指版にフレット(突起部分)がないタイプのベース。
濱田:使いますよ。ライブではなかなか出番がありませんけど、レコーディングでは使いますね。フレットレスのチューンの5弦と、あとはアップライト(※7)。主に『探偵 神宮寺三郎』のレコーディングで使っています。
(※7)アップライト……楽器を下に立てて演奏する、直立型のベース。

安藤:箱バンの時からアップライトを使用される機会ってありましたか?
濱田:箱バンの時はジャズではなくて歌謡曲が多かったので、ほとんど使っていなかったです。
安藤:お客さんのリクエストに応えていくって感じですか?
濱田:そうですね。昔は赤本(※8)っていうのがありまして、歌謡曲のワンコーラスだけ全部コード譜面が書いてあるっていう。
(※8)赤本……正式名称は「歌謡曲のすべて」。昭和初期からの歌謡曲が掲載されている。
安藤:お客さんのリクエスト曲は、だいたいその赤本の中に入っているんですね。
濱田:有名な曲はだいたい入っていますね。お客さんからリクエストが来ると、バンマスが「何ページ」って指定してくるんです。
安藤:ボーカルのコードとメロディだけは書かれているから、付けていくベースラインは雰囲気とか、記憶の中にあるものをアドリブで当てはめていく感じでしょうか?
濱田:そうですねそれでオッケーがもらえれば、また次の仕事がもらえるって感じでした。
安藤:ベースラインの開発とか、「このタッチだとこういう感じでいけるな」って手ごたえやノウハウがたまっていきそうな環境ですね。
濱田:結果的にはそうなりますね。自分は箱バンのメンツの中では最後のほうなんで、ヒエラルキーで言うと最下層なわけですよ。つまるところ、怒られる役なわけです。キャリアもペーペーなのでしょっちゅうダメ出しばかりされていて、おかげさまでいい勉強になりました。
安藤:プレイヤーとして叩き上げで鍛えられたわけですか。
濱田:そうですね。箱バンってほんとタテ社会なんで。ちなみにキャバレーって裏階段から上がるじゃないですか。そうすると、いきなり目に入るのはベビーベッドなんですよ(笑)。
安藤:ホステスさんのお子さんたちが寝ているベッドですか?(笑)
濱田:そうそう。箱バンだと一晩で4ステージとかやるんですけど、出番のない間は裏で子守りをしていました(笑)。
安藤:いいですね! いかにも昭和の風景というか。
濱田:ほんとに。でも「俺こんなとこで何やってるんだろう」って思うこともありましたよ(笑)。あと経緯は忘れちゃったんだけど、バンド仲間のコネクションで「ジャニーズがバックバンドを募集しているからやってみないか?」って話が来たことがあって。当時、たのきんトリオがバックバンドを付けていましてね。そのバンドが「ANKH(アンク)」(※9)って名前でデビューして。その後、ANKHがバラけたことでまたデビューさせようとしてたんでしょうけど、そこのボーカリストのバックバンド募集をしていたんです。
(※9)ANKH(アンク)……1980年代前半にジャニーズ事務所に所属していたバンド。
安藤:当時ありましたよね。YAMATOとか、シブ楽器隊とか。
濱田:そうです。当時、新宿ルイ―ドってライブハウスがあったんですけど、そこでジャニーズはデビュー前のショウケース的なライブをよくやってたんですね。ライブをやりながらテレビ出演のプロモーションもしつつ、デビューする流れになるんですけど、その辺でバックバンドをやってました。なので当時、TBSの夕方5時の生番組とかにもずっと出ていましたよ。バックバンドとして、当て振り(※10)でね(笑)。
安藤:当時から当て振りだったんですね(笑)。
(※10)当て振り……音源を流し、それに合わせて楽器を弾いている演技をすること。
安藤:箱バンやジャニーズのバックバンド時代の経験が、ゲームのコンポーズに生きた部分はあるのでは?
濱田:コンポーザーとしてはないですけど、ゲーマデリックの活動をするうえではありましたね。バンドをどう運営していくかってことに関してのノウハウとか。ほら、バンドって基本的に人間関係だから。
安藤:わかります。
濱田:徒弟制度を通って、なおかつジャニーズのバックバンド時代に“ザ・芸能界的”なことをわかったうえでバンド活動するというのは、ものすごく役に立ったと思いますね。バンドの中だけではなく、外部の制作側の人たちとのコンタクトの仕方とか、そういうコミュニケーション部分でもかなり勉強になりました。
■27歳で自分の人生を振り返って棚卸し……音楽とプログラムのスキルを持ってデータイーストへ
安藤:その後、濱田さんはデータイーストに入られるわけですけど、バンド時代からゲームサウンドに関わる機会はあったのでしょうか?
濱田:当時は箱バンだけじゃ食えないんで、土木設計事務所の電算室でプログラムを組む仕事をしていました。パソコンが導入され始めたばかりの時期で、まだアプリケーションも少なくて、各社で必要なソフトを開発していた時期です。当時所属していた会社は、たまたまそういうソフトをパッケージ化する、割と新しいことをしていた会社で。その会社に採用されてプログラマーとして働きを始めたのが、ゲームやコンピュータに関わるキャリアのスタートですね。
濱田:箱バンの時はジャズではなくて歌謡曲が多かったので、ほとんど使っていなかったです。
安藤:お客さんのリクエストに応えていくって感じですか?
濱田:そうですね。昔は赤本(※8)っていうのがありまして、歌謡曲のワンコーラスだけ全部コード譜面が書いてあるっていう。
(※8)赤本……正式名称は「歌謡曲のすべて」。昭和初期からの歌謡曲が掲載されている。
安藤:お客さんのリクエスト曲は、だいたいその赤本の中に入っているんですね。
濱田:有名な曲はだいたい入っていますね。お客さんからリクエストが来ると、バンマスが「何ページ」って指定してくるんです。
安藤:ボーカルのコードとメロディだけは書かれているから、付けていくベースラインは雰囲気とか、記憶の中にあるものをアドリブで当てはめていく感じでしょうか?
濱田:そうですねそれでオッケーがもらえれば、また次の仕事がもらえるって感じでした。
安藤:ベースラインの開発とか、「このタッチだとこういう感じでいけるな」って手ごたえやノウハウがたまっていきそうな環境ですね。
濱田:結果的にはそうなりますね。自分は箱バンのメンツの中では最後のほうなんで、ヒエラルキーで言うと最下層なわけですよ。つまるところ、怒られる役なわけです。キャリアもペーペーなのでしょっちゅうダメ出しばかりされていて、おかげさまでいい勉強になりました。
安藤:プレイヤーとして叩き上げで鍛えられたわけですか。
濱田:そうですね。箱バンってほんとタテ社会なんで。ちなみにキャバレーって裏階段から上がるじゃないですか。そうすると、いきなり目に入るのはベビーベッドなんですよ(笑)。
安藤:ホステスさんのお子さんたちが寝ているベッドですか?(笑)
濱田:そうそう。箱バンだと一晩で4ステージとかやるんですけど、出番のない間は裏で子守りをしていました(笑)。
安藤:いいですね! いかにも昭和の風景というか。
濱田:ほんとに。でも「俺こんなとこで何やってるんだろう」って思うこともありましたよ(笑)。あと経緯は忘れちゃったんだけど、バンド仲間のコネクションで「ジャニーズがバックバンドを募集しているからやってみないか?」って話が来たことがあって。当時、たのきんトリオがバックバンドを付けていましてね。そのバンドが「ANKH(アンク)」(※9)って名前でデビューして。その後、ANKHがバラけたことでまたデビューさせようとしてたんでしょうけど、そこのボーカリストのバックバンド募集をしていたんです。
(※9)ANKH(アンク)……1980年代前半にジャニーズ事務所に所属していたバンド。
安藤:当時ありましたよね。YAMATOとか、シブ楽器隊とか。
濱田:そうです。当時、新宿ルイ―ドってライブハウスがあったんですけど、そこでジャニーズはデビュー前のショウケース的なライブをよくやってたんですね。ライブをやりながらテレビ出演のプロモーションもしつつ、デビューする流れになるんですけど、その辺でバックバンドをやってました。なので当時、TBSの夕方5時の生番組とかにもずっと出ていましたよ。バックバンドとして、当て振り(※10)でね(笑)。
安藤:当時から当て振りだったんですね(笑)。
(※10)当て振り……音源を流し、それに合わせて楽器を弾いている演技をすること。
安藤:箱バンやジャニーズのバックバンド時代の経験が、ゲームのコンポーズに生きた部分はあるのでは?
濱田:コンポーザーとしてはないですけど、ゲーマデリックの活動をするうえではありましたね。バンドをどう運営していくかってことに関してのノウハウとか。ほら、バンドって基本的に人間関係だから。
安藤:わかります。
濱田:徒弟制度を通って、なおかつジャニーズのバックバンド時代に“ザ・芸能界的”なことをわかったうえでバンド活動するというのは、ものすごく役に立ったと思いますね。バンドの中だけではなく、外部の制作側の人たちとのコンタクトの仕方とか、そういうコミュニケーション部分でもかなり勉強になりました。
■27歳で自分の人生を振り返って棚卸し……音楽とプログラムのスキルを持ってデータイーストへ
安藤:その後、濱田さんはデータイーストに入られるわけですけど、バンド時代からゲームサウンドに関わる機会はあったのでしょうか?
濱田:当時は箱バンだけじゃ食えないんで、土木設計事務所の電算室でプログラムを組む仕事をしていました。パソコンが導入され始めたばかりの時期で、まだアプリケーションも少なくて、各社で必要なソフトを開発していた時期です。当時所属していた会社は、たまたまそういうソフトをパッケージ化する、割と新しいことをしていた会社で。その会社に採用されてプログラマーとして働きを始めたのが、ゲームやコンピュータに関わるキャリアのスタートですね。

安藤:元々はプログラマーだったんですね。そこから転じてDTMというか、MIDIのようなな打ち込みもやられていたんですか?
濱田:MIDIが出てきた頃っていうのはすごく衝撃的で、先輩ミュージシャンたちにとってもMIDIの出現っていうのはすごい脅威だったわけですよ。とくに一番脅威を感じていたのはドラマーでしょうね。しかも、その心配はものすごく的を射ていた(笑)。最初に仕事が減ったところがドラマーでしたからね。
安藤:ドラムは今となっては、機械か人かわからない部分もありますからね。
濱田:一番機械化しにくいと言われていたシンバルができるようになりましたから。そういう中で、自分も元々コンピュータが好きだっていうのもあって、これはチャンスかもしれないな、と。ちょっと話がさかのぼっちゃうんですけど、親父がOA機器のディーラーの会社をやっていまして、そこで東芝と付き合いがあったんです。当時は東芝も8ビットパソコンを販売し始めていて。やっぱりアプリケーションがないと「ハードはあるのにソフトがない」状態になるわけですよね。それで高校生の頃、親父に「ちょっと研修に行ってきてくれ」とお願いされて行ったのが、BASICでプログラミングをする講習会。そこにずっと通って勉強させてくれてたんですよ。
安藤:お父さんの指示でBASICを学ぶことになったんですね。
濱田:今思えば、そこが起点なんですよね。プログラミングの何たるかをそこで学んで「これは今後、何か使えるんじゃないか?」と感じました。
安藤:BASICでの作曲も、その頃からいわゆるPLAY文を使っていたんですか?
濱田:「マイコンBASICマガジン」に載っているプログラムをガーッと打ち込んだりしていました。
安藤:僕も打ち込んでいました! 今となると、すごい時代ですよね。小学生から大学生くらいの人までが自分でプログラムを打ち込んでゲーム作ったり、アプリケーションを作る時代。普通に趣味として面白かった。ところで、濱田さんはゲームはお好きだったんですか?
濱田:ええ。一番やり込んだのは『スペースインベーダー』かな。あと、すごくハマったのがアーケードの野球ゲーム。『ファミスタ』よりもっと前のゲームで、あれはやり込みました。
安藤:どっちかというとずっとアーケードゲームなんでしょうか?
濱田:ファミコンが出る前だったんでね。ファミコンが出てからは「あ、これで100円使わなくて済むな」と思って、ファミコンばっかりやっていました。『沙羅曼蛇』とかすごいカッコよくて。でも1面すらクリアできないっていう(笑)。
安藤:『沙羅曼蛇』は難しいですもんね(笑)。そんな経歴で、なぜ入ったのがデータイーストだったんですか? そもそも、どうしてゲーム業界を選んだのでしょう?
濱田:当時の僕は、紆余曲折を経て父の会社を手伝うことになったんですけど。あるとき会社の経営が厳しくなってきたからから、もう会社を畳むぞってことになって。さて今後どうしようということになった時、はたと自分のキャリアの棚卸しをしたわけですよ。27歳のころかな。そうしたときに、二本の柱としてコンピュータと音楽があった。じゃあ、この2つの接点がある業界は何かないだろうかと考えた時に、ゲーム業界が思いつきまして。
安藤:当時のゲーム音楽の制作環境って今と比べてどうだったんですか? 今はもうゲーム音楽って言うと……。
濱田:一つのジャンルとして定着してますよね。でも、当時の特にコンシューマなんかは、とりあえず音が出ているってレベルのものも少なくなかったと思うんです。まだまともに音楽になってない状況。ハードウェアの制限も多かったんで、任天堂さんが出してるゲームでもオープニングのジングルが終わったらあとはBGMなしとか、そういうゲームが多かった。そんな時に出てきたのが『ドラゴンクエスト』だったんですよ。これがすごく衝撃的で。すぎやまこういちさんって、自分は音楽業界の人として認知してたんで、「夜のヒットパレードの人がゲーム音楽を作ってる! すごい!!」って。
安藤:すぎやま先生はユニークですよね、『夜のヒットパレード』はプロデューサーですからね。
濱田:テレビ局員だったわけですよね。『ドラゴンクエスト』の曲を聴いた時に一番印象的だったのは、ファミコンという音数の少ないハードを一つの楽器として使っていたこと。楽器をあれだけコントロールする形で、ほんとに他のゲームはとレベル差のある音楽を作ってたんですよ。こういうことができるんだっていう可能性を見せつけてくれましたね。
安藤:そして『ヘラクレスの栄光』が生まれるわけですね!
濱田:ははは(笑)。そうなりますね。
安藤:持論ですが『ドラゴンクエスト』を純粋にフォローしたゲームって、あとにも先にも『ヘラクレスの栄光』だけだと思っているんです。『ファイナルファンタジー』は『ドラゴンクエスト』とは違った、恐竜的な進化を果たしたゲームですし、『桃太郎伝説』はパロディ。『ドラゴンクエスト』はメガヒット作なのに、じつはそれをフォローしたゲームがないのは不思議だな……と考えたことがあったんですけど、『ヘラクレスの栄光』が一番近いように思えたんです。ファンに受け止められて、続編もリリースされていますしね。濱田さんがデータイーストに入られて、最初に手がけられたゲームはどの作品だったんでしょうか?
濱田:たしか、ファミコン版『ロボコップ』です。アーケードのほうも同時に作ってたんだけど、それのファミコン移植版のほうを担当しました。開発途中で入ったんですが、サウンドのサブルーチンを作ったりしていましたね。
安藤:プログラマー寄りのことをされていたんですね。
濱田:そうですね、アセンブラで。あと、効果音もちょこっと作ってましたし、BGMも1曲くらい作ったものが入っています。
濱田:MIDIが出てきた頃っていうのはすごく衝撃的で、先輩ミュージシャンたちにとってもMIDIの出現っていうのはすごい脅威だったわけですよ。とくに一番脅威を感じていたのはドラマーでしょうね。しかも、その心配はものすごく的を射ていた(笑)。最初に仕事が減ったところがドラマーでしたからね。
安藤:ドラムは今となっては、機械か人かわからない部分もありますからね。
濱田:一番機械化しにくいと言われていたシンバルができるようになりましたから。そういう中で、自分も元々コンピュータが好きだっていうのもあって、これはチャンスかもしれないな、と。ちょっと話がさかのぼっちゃうんですけど、親父がOA機器のディーラーの会社をやっていまして、そこで東芝と付き合いがあったんです。当時は東芝も8ビットパソコンを販売し始めていて。やっぱりアプリケーションがないと「ハードはあるのにソフトがない」状態になるわけですよね。それで高校生の頃、親父に「ちょっと研修に行ってきてくれ」とお願いされて行ったのが、BASICでプログラミングをする講習会。そこにずっと通って勉強させてくれてたんですよ。
安藤:お父さんの指示でBASICを学ぶことになったんですね。
濱田:今思えば、そこが起点なんですよね。プログラミングの何たるかをそこで学んで「これは今後、何か使えるんじゃないか?」と感じました。
安藤:BASICでの作曲も、その頃からいわゆるPLAY文を使っていたんですか?
濱田:「マイコンBASICマガジン」に載っているプログラムをガーッと打ち込んだりしていました。
安藤:僕も打ち込んでいました! 今となると、すごい時代ですよね。小学生から大学生くらいの人までが自分でプログラムを打ち込んでゲーム作ったり、アプリケーションを作る時代。普通に趣味として面白かった。ところで、濱田さんはゲームはお好きだったんですか?
濱田:ええ。一番やり込んだのは『スペースインベーダー』かな。あと、すごくハマったのがアーケードの野球ゲーム。『ファミスタ』よりもっと前のゲームで、あれはやり込みました。
安藤:どっちかというとずっとアーケードゲームなんでしょうか?
濱田:ファミコンが出る前だったんでね。ファミコンが出てからは「あ、これで100円使わなくて済むな」と思って、ファミコンばっかりやっていました。『沙羅曼蛇』とかすごいカッコよくて。でも1面すらクリアできないっていう(笑)。
安藤:『沙羅曼蛇』は難しいですもんね(笑)。そんな経歴で、なぜ入ったのがデータイーストだったんですか? そもそも、どうしてゲーム業界を選んだのでしょう?
濱田:当時の僕は、紆余曲折を経て父の会社を手伝うことになったんですけど。あるとき会社の経営が厳しくなってきたからから、もう会社を畳むぞってことになって。さて今後どうしようということになった時、はたと自分のキャリアの棚卸しをしたわけですよ。27歳のころかな。そうしたときに、二本の柱としてコンピュータと音楽があった。じゃあ、この2つの接点がある業界は何かないだろうかと考えた時に、ゲーム業界が思いつきまして。
安藤:当時のゲーム音楽の制作環境って今と比べてどうだったんですか? 今はもうゲーム音楽って言うと……。
濱田:一つのジャンルとして定着してますよね。でも、当時の特にコンシューマなんかは、とりあえず音が出ているってレベルのものも少なくなかったと思うんです。まだまともに音楽になってない状況。ハードウェアの制限も多かったんで、任天堂さんが出してるゲームでもオープニングのジングルが終わったらあとはBGMなしとか、そういうゲームが多かった。そんな時に出てきたのが『ドラゴンクエスト』だったんですよ。これがすごく衝撃的で。すぎやまこういちさんって、自分は音楽業界の人として認知してたんで、「夜のヒットパレードの人がゲーム音楽を作ってる! すごい!!」って。
安藤:すぎやま先生はユニークですよね、『夜のヒットパレード』はプロデューサーですからね。
濱田:テレビ局員だったわけですよね。『ドラゴンクエスト』の曲を聴いた時に一番印象的だったのは、ファミコンという音数の少ないハードを一つの楽器として使っていたこと。楽器をあれだけコントロールする形で、ほんとに他のゲームはとレベル差のある音楽を作ってたんですよ。こういうことができるんだっていう可能性を見せつけてくれましたね。
安藤:そして『ヘラクレスの栄光』が生まれるわけですね!
濱田:ははは(笑)。そうなりますね。
安藤:持論ですが『ドラゴンクエスト』を純粋にフォローしたゲームって、あとにも先にも『ヘラクレスの栄光』だけだと思っているんです。『ファイナルファンタジー』は『ドラゴンクエスト』とは違った、恐竜的な進化を果たしたゲームですし、『桃太郎伝説』はパロディ。『ドラゴンクエスト』はメガヒット作なのに、じつはそれをフォローしたゲームがないのは不思議だな……と考えたことがあったんですけど、『ヘラクレスの栄光』が一番近いように思えたんです。ファンに受け止められて、続編もリリースされていますしね。濱田さんがデータイーストに入られて、最初に手がけられたゲームはどの作品だったんでしょうか?
濱田:たしか、ファミコン版『ロボコップ』です。アーケードのほうも同時に作ってたんだけど、それのファミコン移植版のほうを担当しました。開発途中で入ったんですが、サウンドのサブルーチンを作ったりしていましたね。
安藤:プログラマー寄りのことをされていたんですね。
濱田:そうですね、アセンブラで。あと、効果音もちょこっと作ってましたし、BGMも1曲くらい作ったものが入っています。

安藤:データイーストではコンポーザーでありながらもプログラマーっていう関わり方からスタートしているんですね。
濱田:採用としてはサウンドプログラムのサポート的なウェイトが大きかったんですよね。でも結局……まあ、正直言ってまともに音程が取れるテーブルもないプログラムだったので、これではダメだなってところからのスタートでした。
安藤:それを作り直して、きちんと音が鳴る楽器として仕上げていったのが一番最初の仕事だったわけですか。今からコンポーザーになる人にはまず経験のできないことですよね。
濱田:ええ。だって必要ないですからね(笑)。
安藤:まずちゃんと音を鳴らさなきゃって。これは前回対談させていただいた細江慎司さんの時にも、同じエピソードが出てきました。
濱田:細江さんも大体同世代ですからね。
安藤:ゲーム音楽は繰り返し聴くから、ローテクな時代からすごかったんですけど、実はそもそも鳴るか鳴らないかってところに立ち向かう戦いでもあったんですね。
濱田:そうです。当時ファミコンなんか矩形波と三角波とノイズだけで、しかも内蔵してるアンプがあまり高級じゃなくて、かなりノイジー。開発機械のICE(※11)からヘッドホン端子でモニターしていると耳をやられるんですよ。周波数特性がピーキーで、しかも暴走すると爆音が出る(笑)。あの音に耐えられた人間だけが曲を作っていたっていうね。
(※11)ICE……インサーキット・エミュレータ(in-circuit emulator)の略で、CPUをエミュレートする装置のこと。
安藤:今となってはああいうノイジーな音楽って増えていますけど、当時は凶暴だったでしょうね。
濱田:こっちはそれが好きで出しているわけじゃないんだけど、それしかできなかったから。
安藤:そういう制限に立ち向かわれていたのってファミコンの時までですか?
濱田:いや、スーパーファミコン時代も制限はかなりありましたよ。スーファミはサンプリング音源を使えるようになったんですが、任天堂から出されているツールとシーケンスソフトって、本当に基本的な部分だけなんですよ。社内ではすごくいいの作ってるのに(笑)。
安藤:任天堂も、外にライブラリの公開はしないってことですね。
濱田:しないですね。だから自分たちで工夫をしないといけない。曲を作る前に、まずはそこから始まったんですよね。
安藤:どれだけ艶っぽくするか、かっこ良くするかっていう競争が、作曲の前に試行錯誤があったわけですか。
濱田:ありましたね。あとその前に社内でメモリの取り合いという戦いもありました(笑)。
安藤:同じ開発部門での綱引きみたいなものもあるわけですね。
濱田:どっちの発言権が大きいかで、メモリのサイズが決まるっていう(笑)。
安藤:ファミコン時代にサウンドメイクとして「これはすごい!」って思ったゲームはありますか?
濱田:パッと思い出すのは、『燃えろ!!プロ野球』ですね。ジャレコやるなあって。初めてファミコンにしゃべらせたゲームじゃないですかね。
安藤:電源を入れたら「プレイボール!」ですからね。
濱田:採用としてはサウンドプログラムのサポート的なウェイトが大きかったんですよね。でも結局……まあ、正直言ってまともに音程が取れるテーブルもないプログラムだったので、これではダメだなってところからのスタートでした。
安藤:それを作り直して、きちんと音が鳴る楽器として仕上げていったのが一番最初の仕事だったわけですか。今からコンポーザーになる人にはまず経験のできないことですよね。
濱田:ええ。だって必要ないですからね(笑)。
安藤:まずちゃんと音を鳴らさなきゃって。これは前回対談させていただいた細江慎司さんの時にも、同じエピソードが出てきました。
濱田:細江さんも大体同世代ですからね。
安藤:ゲーム音楽は繰り返し聴くから、ローテクな時代からすごかったんですけど、実はそもそも鳴るか鳴らないかってところに立ち向かう戦いでもあったんですね。
濱田:そうです。当時ファミコンなんか矩形波と三角波とノイズだけで、しかも内蔵してるアンプがあまり高級じゃなくて、かなりノイジー。開発機械のICE(※11)からヘッドホン端子でモニターしていると耳をやられるんですよ。周波数特性がピーキーで、しかも暴走すると爆音が出る(笑)。あの音に耐えられた人間だけが曲を作っていたっていうね。
(※11)ICE……インサーキット・エミュレータ(in-circuit emulator)の略で、CPUをエミュレートする装置のこと。
安藤:今となってはああいうノイジーな音楽って増えていますけど、当時は凶暴だったでしょうね。
濱田:こっちはそれが好きで出しているわけじゃないんだけど、それしかできなかったから。
安藤:そういう制限に立ち向かわれていたのってファミコンの時までですか?
濱田:いや、スーパーファミコン時代も制限はかなりありましたよ。スーファミはサンプリング音源を使えるようになったんですが、任天堂から出されているツールとシーケンスソフトって、本当に基本的な部分だけなんですよ。社内ではすごくいいの作ってるのに(笑)。
安藤:任天堂も、外にライブラリの公開はしないってことですね。
濱田:しないですね。だから自分たちで工夫をしないといけない。曲を作る前に、まずはそこから始まったんですよね。
安藤:どれだけ艶っぽくするか、かっこ良くするかっていう競争が、作曲の前に試行錯誤があったわけですか。
濱田:ありましたね。あとその前に社内でメモリの取り合いという戦いもありました(笑)。
安藤:同じ開発部門での綱引きみたいなものもあるわけですね。
濱田:どっちの発言権が大きいかで、メモリのサイズが決まるっていう(笑)。
安藤:ファミコン時代にサウンドメイクとして「これはすごい!」って思ったゲームはありますか?
濱田:パッと思い出すのは、『燃えろ!!プロ野球』ですね。ジャレコやるなあって。初めてファミコンにしゃべらせたゲームじゃないですかね。
安藤:電源を入れたら「プレイボール!」ですからね。

濱田:結局、ボイスをどう使うかっていうのがファミコン時代は課題になっていて、やってるとこはやってるんだけど、でもそれってそっちにメモリを持っていかれて他はお留守になるっていうことなので。で、プロジェクトの中で「これにどれだけコストかけますか?」みたいな引き合いの中で、ボイスを使うとサウンドが割を食うという、悲しいことになるっていうのが理由にありました。
安藤:スーパーファミコンですごいと思った音楽は?
濱田:『アクトレイザー』かなあ。
安藤:『アクトレイザー』はすごかったですよね。あのサウンドを聴いて、『ファイナルファンタジーIV』のチームがサウンドを作り直したというエピソードを聞いたことがあります。それくらい、当時のゲームサウンドとしてずば抜けていました。
濱田:あれはエポックでしたね。古代さんは僕と同じプログラマー上がりの人なんで、自分でドライバを作って自分で曲も書く人なんです。同じ土俵だとその辺の差がはっきり出るので、その辺の勝負はしていましたね。でもプログラマーは専業で精進しないといけない域があるわけですよ。自分はそこまでは無理だなと思ったので、スーファミ以降はサウンド専任のプログラマーを付けました。自分は仕様書だけを書く形です。
安藤:『アクトレイザー』のどこがすごかったんでしょうか。
濱田:楽曲の素晴らしさはもちろんなんですが、そもそも出音のコントロールを、どうやっていたんだろうって。RAMのメモリが8メガとか16メガしかないなかで、どれだけメモリがあればこの音が出せるんだろうと思っていましたよ。それくらい音質が良かった。あとはやっぱりDSP(※12)かな。DSPがディレイだけなんですけど、ディレイのアルゴリズムをいじってるんじゃないかな。いわゆる残響の付け方が全然違ってたから。
(※12)DSP……デジタルシグナルプロセッサの略。アナログ信号をデジタルに変換するチップ。
安藤:音の響き方や残り方が特徴的だった、と。
濱田:メモリ共有型だったんで、DSP用にメモリをいっぱい割けばいい音にはなるんだけど、このゲームでそんなにメモリがもらえるわけないよなって。どういうメモリマッピングしてるんだろうって思ってました。
安藤:いろんな要素が詰まっていますから。古代さんに今度聞いてみたいですね。以前、一緒に『アクトレイザー』の実況をしたことがあるんですよ。20年以上経つと難しくて、誰もクリアできませんでしたが(笑)。面白かったのは神様の「ハッ!」っていうかけ声が、古代さん自身の声だとわかったこと。あれは収穫でした。「これ、俺の声を加工しているんですよ」って言われたときは衝撃でしたから。
濱田:その手のことは僕もやったなあ(笑)。スーファミってサンプリングが使えるので、それがはっきりわかるのは音声じゃないですか。だから『燃えプロ』の悔しさをスーファミ時代に雪辱するっていうね。
安藤:ファミコンの頃は結局ボイスにメモリを割けなかったんですね。
濱田:データイーストではそこまでメモリもらえなかったですからね。でも実験だけはしましたよ。DMA(※13)でメモリ全部使って「こんにちは、渡辺満里奈です」ってしゃべらせてみたりね(笑)。
(※13)DMA ……Direct Memory Accessの略。メモリとメモリ間でデータの転送を行うシステム。
安藤:濱田さんの声で「渡辺満里奈です」ってしゃべるわけですか?(笑)
安藤:スーパーファミコンですごいと思った音楽は?
濱田:『アクトレイザー』かなあ。
安藤:『アクトレイザー』はすごかったですよね。あのサウンドを聴いて、『ファイナルファンタジーIV』のチームがサウンドを作り直したというエピソードを聞いたことがあります。それくらい、当時のゲームサウンドとしてずば抜けていました。
濱田:あれはエポックでしたね。古代さんは僕と同じプログラマー上がりの人なんで、自分でドライバを作って自分で曲も書く人なんです。同じ土俵だとその辺の差がはっきり出るので、その辺の勝負はしていましたね。でもプログラマーは専業で精進しないといけない域があるわけですよ。自分はそこまでは無理だなと思ったので、スーファミ以降はサウンド専任のプログラマーを付けました。自分は仕様書だけを書く形です。
安藤:『アクトレイザー』のどこがすごかったんでしょうか。
濱田:楽曲の素晴らしさはもちろんなんですが、そもそも出音のコントロールを、どうやっていたんだろうって。RAMのメモリが8メガとか16メガしかないなかで、どれだけメモリがあればこの音が出せるんだろうと思っていましたよ。それくらい音質が良かった。あとはやっぱりDSP(※12)かな。DSPがディレイだけなんですけど、ディレイのアルゴリズムをいじってるんじゃないかな。いわゆる残響の付け方が全然違ってたから。
(※12)DSP……デジタルシグナルプロセッサの略。アナログ信号をデジタルに変換するチップ。
安藤:音の響き方や残り方が特徴的だった、と。
濱田:メモリ共有型だったんで、DSP用にメモリをいっぱい割けばいい音にはなるんだけど、このゲームでそんなにメモリがもらえるわけないよなって。どういうメモリマッピングしてるんだろうって思ってました。
安藤:いろんな要素が詰まっていますから。古代さんに今度聞いてみたいですね。以前、一緒に『アクトレイザー』の実況をしたことがあるんですよ。20年以上経つと難しくて、誰もクリアできませんでしたが(笑)。面白かったのは神様の「ハッ!」っていうかけ声が、古代さん自身の声だとわかったこと。あれは収穫でした。「これ、俺の声を加工しているんですよ」って言われたときは衝撃でしたから。
濱田:その手のことは僕もやったなあ(笑)。スーファミってサンプリングが使えるので、それがはっきりわかるのは音声じゃないですか。だから『燃えプロ』の悔しさをスーファミ時代に雪辱するっていうね。
安藤:ファミコンの頃は結局ボイスにメモリを割けなかったんですね。
濱田:データイーストではそこまでメモリもらえなかったですからね。でも実験だけはしましたよ。DMA(※13)でメモリ全部使って「こんにちは、渡辺満里奈です」ってしゃべらせてみたりね(笑)。
(※13)DMA ……Direct Memory Accessの略。メモリとメモリ間でデータの転送を行うシステム。
安藤:濱田さんの声で「渡辺満里奈です」ってしゃべるわけですか?(笑)

濱田:いや、渡辺満里奈のファンCDを持ってる社員がいて、それを借りてサンプリングして。まぁ、それだけにすべてのメモリを割くことになるので、全然現実的ではありませんでしたけど。実験後に他の社員たちに「で?」って言われちゃいましたし(苦笑)。
■元祖ボカロ? 『ヘラクレスの栄光IV』の歌にはメモリを節約する、ある工夫がされていた!
濱田:サンプリング音声の話なんだけど『ヘラクレスの栄光IV』で、町の中の子供に話しかけると、その子が「ぜんぶ好き」っていう歌を歌う演出があるんですよ。あの曲は僕が作ったんですけど、町シーンのメモリはこれだけしかないって制限のなかで、サンプリングボイスを入れなきゃいけませんでした。ドカンとメモリを取るわけにはいかないっていう状況で、母音と子音をちょん切って、子音をループさせる手法を思いつきました。
安藤:ものすごい工夫ですね! それでかなりのメモリが削減できるわけですか。
濱田:ゲーム中は歌詞を字幕で出してあげれば、プレイヤー側にはそう聴こえるな、みたいなところもありまして。
安藤:ボーカロイドみたいな感じになるってことですよね?
濱田:なるなる。実際に聴くとボカロみたいですよ。ちなみに「ぜんぶ好き」の歌詞を書いたのは『ファイナルファンタジー VII』でディレクターをやった野島一成氏です。
安藤:プレイヤーもビックリしたでしょうね。
濱田:そうそう、そういうビックリさせるネタが欲しかったんですよ。野島もね「歌わせたいんだけど、なんとかならない?」って言ってきてね。
安藤:そこは濱田さんのプログラマーとしての考え方が生きる結果になったのでは。
濱田:そうですね。ちなみに歌の元音源は『マジカルドロップ』のハイプリエステスや『ファイターズヒストリー』の加納亮子の声を担当した子で、データイーストの庶務だった女性なんです(笑)。その子をスタジオに缶詰めにして収録しました。歌詞で使う分全部「あ~か~さ~た~な~」って言わせてね(笑)。
安藤:なるほど(笑)。ファミコン版『ロボコップ』の次に関わったゲームは何になりますか?
濱田:次が『探偵 神宮寺三郎 時の過ぎゆくままに』だったと思います。『探偵 神宮寺三郎』シリーズで初めてサウンドを担当したタイトル。
安藤:いきなりハードボイルドな世界になりましたね。
濱田:自分がラッキーだったなと思うのは、キャリアの最初から『探偵 神宮寺三郎』に関われたことだと思うんです。当然ファミコンなので、ハードボイルドといっても音楽で表現できることに限界はあったんですけど、やりたいことは割とはっきりしてましたね。「渋い大人」がモチーフっていう。
安藤:芯がしっかりとあったことが、このシリーズがいまだに続いている理由だと思います。なかなか30年って続かないですからね。
濱田:ほんとにね。タイトルのキャリアだけを見れば『ドラゴンクエスト』に匹敵するんで。当時もね、こんなおっさんキャラ……と言っても神宮寺三郎は20代なんですけど、ファミコンユーザーからすればおっさんですよね。ファミコンのゲームでおっさんが主人公っていうのはなかなかないじゃないですか。
安藤:プロジェクトの話を最初に聞いたときの印象は?
濱田:元々劇伴が好きだったので、そういうことをやるのに『探偵 神宮寺三郎』は向いてるなと。サスペンス物とか、スリラーとか、映像と音で演出するっていう。火曜サスペンスじゃないですけど、ああいうのが大好きだったのでやりたいことができるかなって思いはありましたね。
安藤:コンセプトを聞いたときにインスピレーションが……『探偵 神宮寺三郎』と言えばバーで酒を飲む、タバコを吸うっていう、そこで流れてる音楽っていうイメージがありますから。ジャズだったりとか、そういうイメージみたいなものはスッと降りてきた感じですか。
濱田:ありましたね。フィリップ・マーロウ(※14)とかアメリカのハードボイルドものも下敷きにありますし。こういう世界観だよねっていうのが、割と明確にみんなの中でイメージが共有されてましたね。
■元祖ボカロ? 『ヘラクレスの栄光IV』の歌にはメモリを節約する、ある工夫がされていた!
濱田:サンプリング音声の話なんだけど『ヘラクレスの栄光IV』で、町の中の子供に話しかけると、その子が「ぜんぶ好き」っていう歌を歌う演出があるんですよ。あの曲は僕が作ったんですけど、町シーンのメモリはこれだけしかないって制限のなかで、サンプリングボイスを入れなきゃいけませんでした。ドカンとメモリを取るわけにはいかないっていう状況で、母音と子音をちょん切って、子音をループさせる手法を思いつきました。
安藤:ものすごい工夫ですね! それでかなりのメモリが削減できるわけですか。
濱田:ゲーム中は歌詞を字幕で出してあげれば、プレイヤー側にはそう聴こえるな、みたいなところもありまして。
安藤:ボーカロイドみたいな感じになるってことですよね?
濱田:なるなる。実際に聴くとボカロみたいですよ。ちなみに「ぜんぶ好き」の歌詞を書いたのは『ファイナルファンタジー VII』でディレクターをやった野島一成氏です。
安藤:プレイヤーもビックリしたでしょうね。
濱田:そうそう、そういうビックリさせるネタが欲しかったんですよ。野島もね「歌わせたいんだけど、なんとかならない?」って言ってきてね。
安藤:そこは濱田さんのプログラマーとしての考え方が生きる結果になったのでは。
濱田:そうですね。ちなみに歌の元音源は『マジカルドロップ』のハイプリエステスや『ファイターズヒストリー』の加納亮子の声を担当した子で、データイーストの庶務だった女性なんです(笑)。その子をスタジオに缶詰めにして収録しました。歌詞で使う分全部「あ~か~さ~た~な~」って言わせてね(笑)。
安藤:なるほど(笑)。ファミコン版『ロボコップ』の次に関わったゲームは何になりますか?
濱田:次が『探偵 神宮寺三郎 時の過ぎゆくままに』だったと思います。『探偵 神宮寺三郎』シリーズで初めてサウンドを担当したタイトル。
安藤:いきなりハードボイルドな世界になりましたね。
濱田:自分がラッキーだったなと思うのは、キャリアの最初から『探偵 神宮寺三郎』に関われたことだと思うんです。当然ファミコンなので、ハードボイルドといっても音楽で表現できることに限界はあったんですけど、やりたいことは割とはっきりしてましたね。「渋い大人」がモチーフっていう。
安藤:芯がしっかりとあったことが、このシリーズがいまだに続いている理由だと思います。なかなか30年って続かないですからね。
濱田:ほんとにね。タイトルのキャリアだけを見れば『ドラゴンクエスト』に匹敵するんで。当時もね、こんなおっさんキャラ……と言っても神宮寺三郎は20代なんですけど、ファミコンユーザーからすればおっさんですよね。ファミコンのゲームでおっさんが主人公っていうのはなかなかないじゃないですか。
安藤:プロジェクトの話を最初に聞いたときの印象は?
濱田:元々劇伴が好きだったので、そういうことをやるのに『探偵 神宮寺三郎』は向いてるなと。サスペンス物とか、スリラーとか、映像と音で演出するっていう。火曜サスペンスじゃないですけど、ああいうのが大好きだったのでやりたいことができるかなって思いはありましたね。
安藤:コンセプトを聞いたときにインスピレーションが……『探偵 神宮寺三郎』と言えばバーで酒を飲む、タバコを吸うっていう、そこで流れてる音楽っていうイメージがありますから。ジャズだったりとか、そういうイメージみたいなものはスッと降りてきた感じですか。
濱田:ありましたね。フィリップ・マーロウ(※14)とかアメリカのハードボイルドものも下敷きにありますし。こういう世界観だよねっていうのが、割と明確にみんなの中でイメージが共有されてましたね。

(※14)フィリップ・マーロウ……作家・レイモンド・チャンドラーによるハードボイルド小説に登場する探偵。
安藤:ファミコンの制限の中でジャズミュージックを作っていくときに、大変だったことや面白かったことはなんですか?
濱田:ジャズをファミコンでっていう話なんですが、実は1作目の『新宿中央公園殺人事件』から3作目の『危険な二人』までは、サウンドが外注なんですよ。
安藤:そうだったんですね!
濱田:とある会社がサウンドドライバと合わせて楽曲を納品してくれていたんです。あと、DX-7というシンセサイザーのデモンストレーター用の音色プログラムなどを作っていた二人組がいるんですけど、そのうちのお一人が初期3作で『探偵 神宮寺三郎』の曲を書いていたんです。『探偵 神宮寺三郎』の企画者とその会社が昔から親交があってそういう流れになったらしく、4作目以降に社内でサウンドを引き継いだ形なんですよね。みなさんは最初から『探偵 神宮寺三郎』はジャズだったと思っているかもしれませんが、じつはよく聴くと、当時の音楽はそんなにジャズ的要素はないんですよ。
安藤:劇伴のほうが近いってことですか?
濱田:ジャズって言ったら例えば4ビートとかトリオ編成のコンボジャズ系とかだと思うんですけど、さすがにファミコンで4ビートはできなかったんです。一つだけ言えるのは、コードの取り方がテンションコードを結構使ってるんです。9th(ナインス)以上で。これをサウンドで流すには技がいるんですよ。ファミコンなのにそれをちゃんとやってたんですよね。後から全曲コピーして、コードをアナライズしてみたら「あ、ちゃんとしてるな」って。
安藤:和音が2つ以上使えないのにテンションコードを鳴らすのって、いったいどうやっているのでしょうか?
濱田:例えばルート音を三角波で出します。で、コードはCメジャーナインスだとするとまずドが鳴っていますよね。そこにミを鳴らしてシとレでメロディ作るんですよ。
安藤:つまりメロディとベースが重なった時にコード感が出るんですね。マニアックな話だなあ(笑)。めちゃめちゃ面白い。
濱田:これ、じつはすごい工夫なんですよ。例えばソの音(5th)なんて鳴らしてないんですよ。
安藤:ソの音は鳴らないんですね。レが上で鳴ってないと。それがないとただのCメジャーになっちゃいますもんね。結局その瞬間のタイムラインで、鳴っている響きでコードを感じるからそれでいいってことですね、面白いです!
濱田:あとはアルペジオですよね。やっぱりコード進行は洒落てましたからね。そこは内部でサウンドをやるようになっても踏襲しました。
安藤:PS時代の『探偵 神宮寺三郎』サウンドへのアプローチってどうだったんですか。PSになると、ファミコンとは違って結構本格的なジャズ音楽を作るってことに取り組まないといけなかったと思うんですが。濱田さんにはジャズ音楽を作る土台みたいなものって元々あったんでしょうか?
濱田:そういう意味で言うと、僕の一番最初の音楽の原風景の中にボサノバがあるんですよ。ボサノバってジャズとサンバが融合したブラジル音楽なんですけど、子どもの頃にあのコード感がボサノバだと仕込まれているんです。そして、自分が中学~高校生の頃にクロスオーバーからフュージョンのブームがありまして。ジャズ音楽から派生したクロスオーバー・フュージョンをよく聴いていました。あと、若い頃はコレクター魂が働くので、そこから60年代ジャズに遡っていくという流れもあったんです。自分ではプレイヤーとしてジャズを演奏していないけれども、自分の素養の中にジャズは刷り込まれています。あとはイージーリスニングもかな。
安藤:環境音楽みたいな静かな音楽ですよね。
濱田:軽音楽と呼ばれるものですね。ポール・モーリア(※15)とかミシェル・ルグラン(※16)とか。映画音楽なんかをやっている、ポップスオーケストラと呼ばれている。
(※15)ポール・モーリア……フランスの作曲家、編曲家、指揮者、ピアニスト、チェンバロ奏者。
(※16)ミシェル・ルグラン……フランスの作曲家、ピアニスト、映画監督、俳優。
安藤:リチャード・クレイダーマン(※17)なんかもそうですか?
(※17)リチャード・クレイダーマン……フランスのピアニスト。
濱田:そうですね。リチャード・クレイダーマンもピアノに対してオケをつけていますよね。
安藤:ロイヤルホストに行ったら、BGMでかかっているような音楽ですよね。
濱田:まさにそういった感じの環境音楽です。BGMとしてそういう音楽を刷り込まれています。でも、ジャズって幅が広くて、いわゆるモダンジャズと言われるのは聴くための音楽として特殊な発展をした音楽です。テーマがちょっとあってあとはアドリブをバリバリやるっていう。でもあのスタイルはジャズのごく一部。それ以外のスウィングやポップなものもたくさんあるので、何をジャズって言うかってなっちゃう。だから『探偵 神宮寺三郎』の音楽イメージとしては、バーなんだよね。バーで一杯酒を飲んで、ジュークボックスで音楽をかける時に何をかけましょうかっていう。
安藤:バーで流れている音楽というのが一番しっくりきますね。そこにタバコもお酒も紐づいてきて、登場人物も紐づいてくる。
濱田:「ジャズ的な雰囲気」、これが重要なんですよ。音楽的なジャズのエッジというよりも、全体のテクスチャ。ジャズは歴史のある音楽なんで、深掘りしようと思ったらいくらでもできるんだけど、そうではなくてこのテクスチャをどうするかっていうことに注力して作っています。邪魔にならない音楽ってのがすごく大事なことで特にモダンジャズは主張の強い音楽だから。そういう意味では作家としての主張は弱いかもしれない。でもそれが『探偵 神宮寺三郎』にとって……。
安藤:ピッタリということですね。
濱田:そういうことですね!
安藤:ファミコンの制限の中でジャズミュージックを作っていくときに、大変だったことや面白かったことはなんですか?
濱田:ジャズをファミコンでっていう話なんですが、実は1作目の『新宿中央公園殺人事件』から3作目の『危険な二人』までは、サウンドが外注なんですよ。
安藤:そうだったんですね!
濱田:とある会社がサウンドドライバと合わせて楽曲を納品してくれていたんです。あと、DX-7というシンセサイザーのデモンストレーター用の音色プログラムなどを作っていた二人組がいるんですけど、そのうちのお一人が初期3作で『探偵 神宮寺三郎』の曲を書いていたんです。『探偵 神宮寺三郎』の企画者とその会社が昔から親交があってそういう流れになったらしく、4作目以降に社内でサウンドを引き継いだ形なんですよね。みなさんは最初から『探偵 神宮寺三郎』はジャズだったと思っているかもしれませんが、じつはよく聴くと、当時の音楽はそんなにジャズ的要素はないんですよ。
安藤:劇伴のほうが近いってことですか?
濱田:ジャズって言ったら例えば4ビートとかトリオ編成のコンボジャズ系とかだと思うんですけど、さすがにファミコンで4ビートはできなかったんです。一つだけ言えるのは、コードの取り方がテンションコードを結構使ってるんです。9th(ナインス)以上で。これをサウンドで流すには技がいるんですよ。ファミコンなのにそれをちゃんとやってたんですよね。後から全曲コピーして、コードをアナライズしてみたら「あ、ちゃんとしてるな」って。
安藤:和音が2つ以上使えないのにテンションコードを鳴らすのって、いったいどうやっているのでしょうか?
濱田:例えばルート音を三角波で出します。で、コードはCメジャーナインスだとするとまずドが鳴っていますよね。そこにミを鳴らしてシとレでメロディ作るんですよ。
安藤:つまりメロディとベースが重なった時にコード感が出るんですね。マニアックな話だなあ(笑)。めちゃめちゃ面白い。
濱田:これ、じつはすごい工夫なんですよ。例えばソの音(5th)なんて鳴らしてないんですよ。
安藤:ソの音は鳴らないんですね。レが上で鳴ってないと。それがないとただのCメジャーになっちゃいますもんね。結局その瞬間のタイムラインで、鳴っている響きでコードを感じるからそれでいいってことですね、面白いです!
濱田:あとはアルペジオですよね。やっぱりコード進行は洒落てましたからね。そこは内部でサウンドをやるようになっても踏襲しました。
安藤:PS時代の『探偵 神宮寺三郎』サウンドへのアプローチってどうだったんですか。PSになると、ファミコンとは違って結構本格的なジャズ音楽を作るってことに取り組まないといけなかったと思うんですが。濱田さんにはジャズ音楽を作る土台みたいなものって元々あったんでしょうか?
濱田:そういう意味で言うと、僕の一番最初の音楽の原風景の中にボサノバがあるんですよ。ボサノバってジャズとサンバが融合したブラジル音楽なんですけど、子どもの頃にあのコード感がボサノバだと仕込まれているんです。そして、自分が中学~高校生の頃にクロスオーバーからフュージョンのブームがありまして。ジャズ音楽から派生したクロスオーバー・フュージョンをよく聴いていました。あと、若い頃はコレクター魂が働くので、そこから60年代ジャズに遡っていくという流れもあったんです。自分ではプレイヤーとしてジャズを演奏していないけれども、自分の素養の中にジャズは刷り込まれています。あとはイージーリスニングもかな。
安藤:環境音楽みたいな静かな音楽ですよね。
濱田:軽音楽と呼ばれるものですね。ポール・モーリア(※15)とかミシェル・ルグラン(※16)とか。映画音楽なんかをやっている、ポップスオーケストラと呼ばれている。
(※15)ポール・モーリア……フランスの作曲家、編曲家、指揮者、ピアニスト、チェンバロ奏者。
(※16)ミシェル・ルグラン……フランスの作曲家、ピアニスト、映画監督、俳優。
安藤:リチャード・クレイダーマン(※17)なんかもそうですか?
(※17)リチャード・クレイダーマン……フランスのピアニスト。
濱田:そうですね。リチャード・クレイダーマンもピアノに対してオケをつけていますよね。
安藤:ロイヤルホストに行ったら、BGMでかかっているような音楽ですよね。
濱田:まさにそういった感じの環境音楽です。BGMとしてそういう音楽を刷り込まれています。でも、ジャズって幅が広くて、いわゆるモダンジャズと言われるのは聴くための音楽として特殊な発展をした音楽です。テーマがちょっとあってあとはアドリブをバリバリやるっていう。でもあのスタイルはジャズのごく一部。それ以外のスウィングやポップなものもたくさんあるので、何をジャズって言うかってなっちゃう。だから『探偵 神宮寺三郎』の音楽イメージとしては、バーなんだよね。バーで一杯酒を飲んで、ジュークボックスで音楽をかける時に何をかけましょうかっていう。
安藤:バーで流れている音楽というのが一番しっくりきますね。そこにタバコもお酒も紐づいてきて、登場人物も紐づいてくる。
濱田:「ジャズ的な雰囲気」、これが重要なんですよ。音楽的なジャズのエッジというよりも、全体のテクスチャ。ジャズは歴史のある音楽なんで、深掘りしようと思ったらいくらでもできるんだけど、そうではなくてこのテクスチャをどうするかっていうことに注力して作っています。邪魔にならない音楽ってのがすごく大事なことで特にモダンジャズは主張の強い音楽だから。そういう意味では作家としての主張は弱いかもしれない。でもそれが『探偵 神宮寺三郎』にとって……。
安藤:ピッタリということですね。
濱田:そういうことですね!
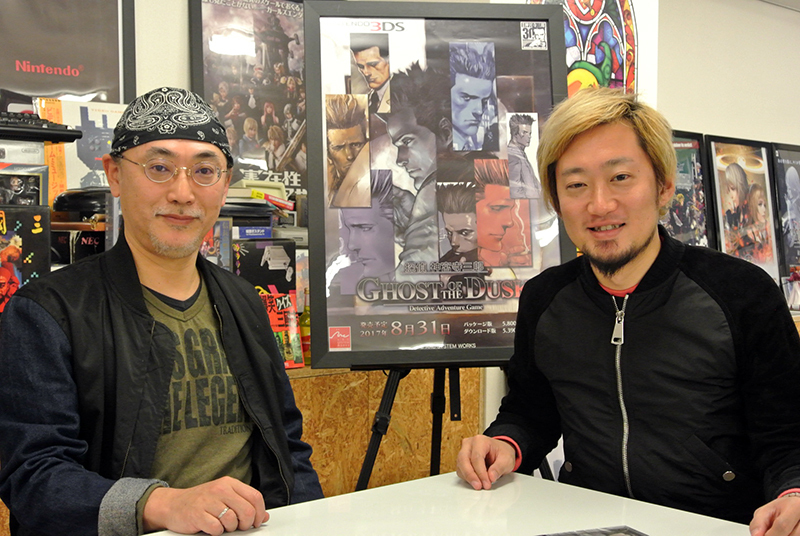
(後編に続く)
後編はコチラ→寝るひまもなかったセガ在籍時代、それでもやりたかった『探偵 神宮寺三郎』のサウンド制作
CHECK!
ゲーマデリックライブ情報
濱田氏がベースを担当する、データイーストのゲームミュージックバンドであるゲーマデリックが、16SHOT主催ライブ“どんどんぼっち まってます2017”への出演が決定! ゲーマデリックの2017年最後のライブを見逃すな!
日時:2017年12月23日(土)
開場:19:30(予定)
場所:新宿御苑スタジオ
チケット:前売り2,800円 当日3,800円
テキスト:風のイオナ(FLOOR25) ゲームと音楽と旅と自転車が好きな東京在住フリーライター&エディター。最近は地下アイドルグループDORCAのプロデューサー業もやってます。
ツイッターアカウント→風のイオナ@ハイパーいおなぴ@ionadisco
後編はコチラ→寝るひまもなかったセガ在籍時代、それでもやりたかった『探偵 神宮寺三郎』のサウンド制作
CHECK!
ゲーマデリックライブ情報
濱田氏がベースを担当する、データイーストのゲームミュージックバンドであるゲーマデリックが、16SHOT主催ライブ“どんどんぼっち まってます2017”への出演が決定! ゲーマデリックの2017年最後のライブを見逃すな!
日時:2017年12月23日(土)
開場:19:30(予定)
場所:新宿御苑スタジオ
チケット:前売り2,800円 当日3,800円
テキスト:風のイオナ(FLOOR25) ゲームと音楽と旅と自転車が好きな東京在住フリーライター&エディター。最近は地下アイドルグループDORCAのプロデューサー業もやってます。
ツイッターアカウント→風のイオナ@ハイパーいおなぴ@ionadisco
シシララTV オリジナル記事