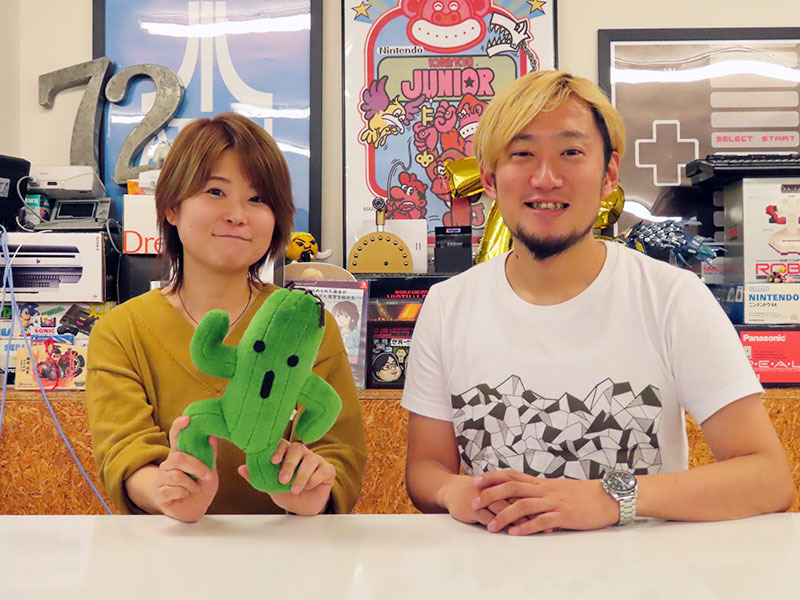寝るひまもなかったセガ在籍時代、それでもやりたかった『探偵 神宮寺三郎』のサウンド制作──濱田誠一×安藤武博 対談【サウンドコンポーザーに訊く!/連載第3回・後編】
ミュージシャン活動をする傍ら、会社員としてプログラマーの道を歩み始め、その2つのスキルを手に1989年にデータイーストに入社した濱田誠一氏。アーケードにコンシューマにと多数のデコゲーのサウンドを制作し、更にデータイースト公式バンド・ゲーマデリックにもベーシストとして参加。データイースト退社後はセガに所属、多数のタイトル制作に携わる。また『探偵 神宮寺三郎』シリーズのサウンドも引き続き手掛けるなど、30年近く精力的にゲーム音楽作曲家として活動を続けている。
後編の今回は、濱田氏のバンド「ゲーマデリック」の誕生秘話から、今なお関わり続けている『探偵 神宮寺三郎』シリーズへの想いまでをおうかがいしていく。

濱田誠一氏(写真左)
データイースト、セガを経て現在はフリーランスで活動するゲーム音楽作曲家兼ベーシスト。データイーストのゲームミュージックバンド、ゲーマデリックではベースを担当。代表作は『フライングパワーディスク』、『ヘラクレスの栄光』シリーズなど。特に『探偵 神宮寺三郎』シリーズはファミコン版4作目の『時の過ぎゆくままに』以降、『灯火が消えぬ間に』を除く全タイトルのサウンド制作に携わっている。
前編はコチラ→音楽とプログラム、2つのスキルを生かすために選んだゲーム業界の道
■「ゲーマデリック」が生まれるまで
安藤武博(以下、安藤):今回はゲーマデリックの誕生秘話からお聞きしたいんですけど、一時期、ゲームメーカー公式でゲームミュージックバンドを立ち上げるっていう流行がありましたよね。
濱田誠一さん(以下、濱田):そうですね。セガから「S.S.T.BAND」が出てきたりして。それは、社内でも「セガさんがカッコいいことやってるじゃないすか!」ってなりますよね(笑)。当時、MZA有明でのデビューライブもみんなで観に行って「カッコいいね」と。1990年には日本青年館で“ゲームミュージック フェスティバル'90”が開催されて、そこにTAITOのZUNTATAとS.S.T.BANDが出たんです。
そして翌年1991年にサイトロンさんから「データイーストさんも出ませんか」っていう話をいただきまして。社内で俄然「やるやる!」と盛り上がりました。ラッキーだったのは、たまたまサウンドにギターやドラム、ベースなど全パートの奏者がいたってことです(笑)。
安藤:全パートがそろい踏みだったんですね。当時、サウンドチームは何人ぐらいいたんですか? 濱田:アーケードとコンシューマ、合わせて12~13名はいましたね。常に新作の開発が走っていましたし、アーケードは毎月何かをリリースしてるような状況で、この人数でもてんてこまいでした。で、ゲーマデリックの話なんですけど。せっかく全パートのメンバーがいるので「じゃあやるか!」ってなって初出演したのが1991年に中野サンプラザで開催された“ゲームミュージック フェスティバル'91”ですね。
安藤:社内サウンドチームにプレイヤーが多いのも、当時は当たり前だったんですか? DTM全盛以降の今、プレイヤーじゃなくてもコンポーザーをやっている方も多いと思うんですけど。
濱田:鍵盤が弾ける人は多かったですね。その次に多いのがギター。結局、制作ツールが非常にチープだから、まず最初に曲をアナログの状態で作って、それをツールに落とし込む作業になるんですよ。なので、自分で曲を表現できないとどうしようもなかった。当時はDTMのような便利ツールはほとんどないので、曲を表現して人に聴かせるためにどうするかっていったら、自分で楽器を弾くしかないんですよ。あとは譜面を理解できるかどうか、そのどっちかですよね。
安藤:濱田さんはどちらだったんですか?
濱田:僕はどっちもやりましたね。
安藤:バンドのみなさんも譜面を書けるのが当たり前の人たちということですよね。
濱田:そうですね。自分は出身が箱バンだから、譜面がないと話にならなかったので。とは言っても、そんなにバリバリ読み書きできる程でもなかったけど(苦笑)。一応、ひととおりの読み書きはできますし、ゲーマデリックでは基本的に全部書き譜でやっていました。理由はリハの時間がそんなに取れないので、まずアレンジャーが欲しいものを全部譜面に書くっていう。
安藤:譜面は五線譜ですか、TAB譜ですか?
濱田:五線譜ですね。16段譜(※1)の形式で書いてました。だから4リズムを一覧で書いてくる感じ。コードも必要だったらトップの音は書くっていう。ベースラインもリフはこう、みたいに伝えて。
(※1)16段譜……一枚の譜面に五線譜が16段ある形式の楽譜。
安藤:ミュージシャンですね。完全に。
濱田:そうですね。ギターのMAROはハードロックギタリストなんですけど、彼は大学のジャズ研出身なんですよ。だから、譜面を書くのは彼が一番早かったな。
データイースト、セガを経て現在はフリーランスで活動するゲーム音楽作曲家兼ベーシスト。データイーストのゲームミュージックバンド、ゲーマデリックではベースを担当。代表作は『フライングパワーディスク』、『ヘラクレスの栄光』シリーズなど。特に『探偵 神宮寺三郎』シリーズはファミコン版4作目の『時の過ぎゆくままに』以降、『灯火が消えぬ間に』を除く全タイトルのサウンド制作に携わっている。
前編はコチラ→音楽とプログラム、2つのスキルを生かすために選んだゲーム業界の道
■「ゲーマデリック」が生まれるまで
安藤武博(以下、安藤):今回はゲーマデリックの誕生秘話からお聞きしたいんですけど、一時期、ゲームメーカー公式でゲームミュージックバンドを立ち上げるっていう流行がありましたよね。
濱田誠一さん(以下、濱田):そうですね。セガから「S.S.T.BAND」が出てきたりして。それは、社内でも「セガさんがカッコいいことやってるじゃないすか!」ってなりますよね(笑)。当時、MZA有明でのデビューライブもみんなで観に行って「カッコいいね」と。1990年には日本青年館で“ゲームミュージック フェスティバル'90”が開催されて、そこにTAITOのZUNTATAとS.S.T.BANDが出たんです。
そして翌年1991年にサイトロンさんから「データイーストさんも出ませんか」っていう話をいただきまして。社内で俄然「やるやる!」と盛り上がりました。ラッキーだったのは、たまたまサウンドにギターやドラム、ベースなど全パートの奏者がいたってことです(笑)。
安藤:全パートがそろい踏みだったんですね。当時、サウンドチームは何人ぐらいいたんですか? 濱田:アーケードとコンシューマ、合わせて12~13名はいましたね。常に新作の開発が走っていましたし、アーケードは毎月何かをリリースしてるような状況で、この人数でもてんてこまいでした。で、ゲーマデリックの話なんですけど。せっかく全パートのメンバーがいるので「じゃあやるか!」ってなって初出演したのが1991年に中野サンプラザで開催された“ゲームミュージック フェスティバル'91”ですね。
安藤:社内サウンドチームにプレイヤーが多いのも、当時は当たり前だったんですか? DTM全盛以降の今、プレイヤーじゃなくてもコンポーザーをやっている方も多いと思うんですけど。
濱田:鍵盤が弾ける人は多かったですね。その次に多いのがギター。結局、制作ツールが非常にチープだから、まず最初に曲をアナログの状態で作って、それをツールに落とし込む作業になるんですよ。なので、自分で曲を表現できないとどうしようもなかった。当時はDTMのような便利ツールはほとんどないので、曲を表現して人に聴かせるためにどうするかっていったら、自分で楽器を弾くしかないんですよ。あとは譜面を理解できるかどうか、そのどっちかですよね。
安藤:濱田さんはどちらだったんですか?
濱田:僕はどっちもやりましたね。
安藤:バンドのみなさんも譜面を書けるのが当たり前の人たちということですよね。
濱田:そうですね。自分は出身が箱バンだから、譜面がないと話にならなかったので。とは言っても、そんなにバリバリ読み書きできる程でもなかったけど(苦笑)。一応、ひととおりの読み書きはできますし、ゲーマデリックでは基本的に全部書き譜でやっていました。理由はリハの時間がそんなに取れないので、まずアレンジャーが欲しいものを全部譜面に書くっていう。
安藤:譜面は五線譜ですか、TAB譜ですか?
濱田:五線譜ですね。16段譜(※1)の形式で書いてました。だから4リズムを一覧で書いてくる感じ。コードも必要だったらトップの音は書くっていう。ベースラインもリフはこう、みたいに伝えて。
(※1)16段譜……一枚の譜面に五線譜が16段ある形式の楽譜。
安藤:ミュージシャンですね。完全に。
濱田:そうですね。ギターのMAROはハードロックギタリストなんですけど、彼は大学のジャズ研出身なんですよ。だから、譜面を書くのは彼が一番早かったな。

安藤:楽器の演奏とか読み書きもできる人たちが集まっていたのがデコサウンドだったと。
濱田:日本語を使うのと同じ感覚で、会話用メモの言語として譜面を使うっていうのはありましたね。そうそう、その頃MSXで音符を置いていく音楽系ソフトがあって、それも仕事に使っていました。そのソフトが3~4和音ぐらいまで出せるんですよ。それをデータ保存してからファイルに抜き出して、MMLにコンバートするんです。
安藤:コンバートツールも作られていたんですか? 濱田:作りましたね。カモンミュージックから出ていたPC-98の「レコンポーザ」ってソフト、あれのファイルを解析してコンバートツールを作ったりしていました。
安藤:MSXの音楽ソフトが仕事に使えるとは。ただのホビー系ソフトだと思っていました。
濱田:自分も最初はそう思っていました(笑)。
安藤:入力のインターフェースとしてはすごく使いやすいソフトだったってことなんでしょうね。
濱田:MMLを手打ちするのとどっちが早いかっていうレベルの話でした。慣れている人はMMLを直打ちしたほうが早かったと思います。例えば細江さんみたいなタイプの人は、たぶん直打ちのほうが早いでしょうね(笑)。僕はケースバイケースで使い分けてましたが、ベタ打ちでは無理な表現があることを経験則的にわかっていたので、ざっくりとツールで作ってからMMLで細かく作り込んでいく手法をとっていたんです。
安藤:濱田さんはアーケードの『フライングパワーディスク』などを手掛けられた一方で、『探偵 神宮寺三郎』シリーズをはじめとするコンシューマのサウンドも手掛けられていましたが、これはコンシューマとアーケードを行き来されていたということですか?
濱田:最初はコンシューマ担当で入社したんですが、NEO-GEOが登場して以降、データイーストではそこの境目がほとんどなくなったんですよね。
安藤:手掛けてきた中で印象的なタイトルはなんですか?
濱田:サウンドというよりは業務として、『ABCマンデーナイトフットボール』がおもしろかったです。これはスポーツゲームなのですが、デイブ・ギフォードっていうアメリカのアナウンサーがずっと実況でしゃべっていて、ほかに「ワーッ」っていう歓声や「ドカンドカン」、「ガチャン」といった、いかにもなSEも鳴らさなきゃいけなかったんですけど、それは社内で作れなかったんです。それでプログラムの制作を外注に出し、担当だった僕が外注先の会社があった浦和にずっと通ってサウンドを入れ込んでいたという……。
あと、あのゲームに関わってよかったのは、フットボールのルールを覚えたこと(笑)。あれでフットボールのおもしろさを知りました。あとは『サイドポケット』かな。ファミコンの頃から続いていた定番タイトルだったから。そうそう、実は『探偵 神宮寺三郎』よりも『サイドポケット』のほうが音楽は断然ジャズなんですよ。
安藤:確かに。ストーリーがないゲームですからさらっと鳴っていましたけど、『サイドポケット』の音楽の雰囲気は今でも思い出せますね。
濱田:当時、ゲーマデリックで1~2曲、『サイドポケット』のサウンドを演奏したことがあります。完全に4ビートで。あと、BGMではないんですけど、PCエンジンの『サイレントデバッガーズ』も印象的です。これは「早すぎた3Dサウンドゲーム」と言われていたんですよ。あの『エネミー・ゼロ』より先んじてね(笑)。
安藤:『エネミー・ゼロ』ですか。濱田さんは飯野さんと絡みってあったんですか?
濱田:意外とあったんですよね。じつは僕、飯野さんに初めて会ったのって飯野さんが雑誌の企画でインタビュアーとして、データイーストに来られた時なんですよ。
安藤:飯野さん、インタビュアーをやられていたんですね。飯野さんはすごくトークがうまくて、しゃべり出すと止まらないというのは聞いたことがあります。
濱田:その時も、インタビュー時間の半分は自分のゲーム観を語って帰っていきましたね(笑)。
濱田:日本語を使うのと同じ感覚で、会話用メモの言語として譜面を使うっていうのはありましたね。そうそう、その頃MSXで音符を置いていく音楽系ソフトがあって、それも仕事に使っていました。そのソフトが3~4和音ぐらいまで出せるんですよ。それをデータ保存してからファイルに抜き出して、MMLにコンバートするんです。
安藤:コンバートツールも作られていたんですか? 濱田:作りましたね。カモンミュージックから出ていたPC-98の「レコンポーザ」ってソフト、あれのファイルを解析してコンバートツールを作ったりしていました。
安藤:MSXの音楽ソフトが仕事に使えるとは。ただのホビー系ソフトだと思っていました。
濱田:自分も最初はそう思っていました(笑)。
安藤:入力のインターフェースとしてはすごく使いやすいソフトだったってことなんでしょうね。
濱田:MMLを手打ちするのとどっちが早いかっていうレベルの話でした。慣れている人はMMLを直打ちしたほうが早かったと思います。例えば細江さんみたいなタイプの人は、たぶん直打ちのほうが早いでしょうね(笑)。僕はケースバイケースで使い分けてましたが、ベタ打ちでは無理な表現があることを経験則的にわかっていたので、ざっくりとツールで作ってからMMLで細かく作り込んでいく手法をとっていたんです。
安藤:濱田さんはアーケードの『フライングパワーディスク』などを手掛けられた一方で、『探偵 神宮寺三郎』シリーズをはじめとするコンシューマのサウンドも手掛けられていましたが、これはコンシューマとアーケードを行き来されていたということですか?
濱田:最初はコンシューマ担当で入社したんですが、NEO-GEOが登場して以降、データイーストではそこの境目がほとんどなくなったんですよね。
安藤:手掛けてきた中で印象的なタイトルはなんですか?
濱田:サウンドというよりは業務として、『ABCマンデーナイトフットボール』がおもしろかったです。これはスポーツゲームなのですが、デイブ・ギフォードっていうアメリカのアナウンサーがずっと実況でしゃべっていて、ほかに「ワーッ」っていう歓声や「ドカンドカン」、「ガチャン」といった、いかにもなSEも鳴らさなきゃいけなかったんですけど、それは社内で作れなかったんです。それでプログラムの制作を外注に出し、担当だった僕が外注先の会社があった浦和にずっと通ってサウンドを入れ込んでいたという……。
あと、あのゲームに関わってよかったのは、フットボールのルールを覚えたこと(笑)。あれでフットボールのおもしろさを知りました。あとは『サイドポケット』かな。ファミコンの頃から続いていた定番タイトルだったから。そうそう、実は『探偵 神宮寺三郎』よりも『サイドポケット』のほうが音楽は断然ジャズなんですよ。
安藤:確かに。ストーリーがないゲームですからさらっと鳴っていましたけど、『サイドポケット』の音楽の雰囲気は今でも思い出せますね。
濱田:当時、ゲーマデリックで1~2曲、『サイドポケット』のサウンドを演奏したことがあります。完全に4ビートで。あと、BGMではないんですけど、PCエンジンの『サイレントデバッガーズ』も印象的です。これは「早すぎた3Dサウンドゲーム」と言われていたんですよ。あの『エネミー・ゼロ』より先んじてね(笑)。
安藤:『エネミー・ゼロ』ですか。濱田さんは飯野さんと絡みってあったんですか?
濱田:意外とあったんですよね。じつは僕、飯野さんに初めて会ったのって飯野さんが雑誌の企画でインタビュアーとして、データイーストに来られた時なんですよ。
安藤:飯野さん、インタビュアーをやられていたんですね。飯野さんはすごくトークがうまくて、しゃべり出すと止まらないというのは聞いたことがあります。
濱田:その時も、インタビュー時間の半分は自分のゲーム観を語って帰っていきましたね(笑)。

安藤:なんかわかる(笑)。濱田さんにとって一番最初のゲームメーカーであったデータイーストはどういう会社だったんでしょう? ファンからすると『チェルノブ』のようなデコゲーと言われる特徴的なゲームが多いですけど、それとは別に『探偵 神宮寺三郎』シリーズがあったりして、「好きなゲームを好きなように作っている」ってイメージがあります。中の人はどう思っていたのかが気になります。
濱田:中のスタッフは、非常に大真面目にゲームを作っていたんですよ。なので当時、「ヘンなゲーム」って言われていたのはすごく心外だったんです。
安藤:(笑)。
濱田:でも、変わったスタッフが多かったのは間違いないです。スタッフの採用基準ってどうなっていたのかなって気になりますよね。
安藤:社員はストレートにものを作っていたけど、そのアウトプットが独特だったわけですね。
濱田:大真面目に作った企画書が、外から見たらとんでもないものだったのかなって。でもそれを「とんでもない!」と評価できる、目の肥えた上層部がいなかったってことだと思いますけど(笑)。社長の福田さんも技術畑の人なんですよね。だから経営的な部分よりも技術的に面白いとか、こいつらやる気があるなとか、そういうところに予算をつけちゃう人でした。
だからデータイーストの社員からすれば、いい社長だったと思います。ただ会社としてとか、株主としては勘弁してくれよって部分が多かったんじゃないかな。まあ、そんなこんなでいつも予算にピーピー言っていました。やりたいことをいかに安くやるかってことばかり考えていましたね(笑)。
安藤:予算管理も考えながら立ち向かっていた。なんだかプログラマー的ですね。前編で濱田さん自身の棚卸しのお話がありました。音楽をやっている人はそういう部分が苦手な印象が強いんです。ゲームはインプットしないとアウトプットしないところからスタートしているので、案外ミュージシャンとしての熱い自分と、それを冷たく俯瞰で見ている人が多いなって思います。
濱田:そこが単なるミュージシャンでいられないところだと思うんですよ。ミュージシャンは「オレ最高!」って言ってないとダメじゃないですか。そこが大きな違いで、職業作家の適性な部分じゃないですかね。
■日本のほとんどの開発会社は、一時期ほとんどが『シェンムー』の開発をしていた!?
安藤:そして濱田さんはデータイーストのあとにセガに移るわけですが、その理由はデータイーストが縮小していったところでセガに移られたってことなんでしょうか。
濱田:元々、セガの中山社長と福田さんが親交があって、非常に密な付き合いをしていたんです。人材の交流もけっこう多かったし。セガサターンの頃はセガから出向社員も結構来ていましたから。今思えば、それは吸収の一環だったのかな。その辺からデータイーストの規模が縮小するにつれて、セガに移籍していくスタッフが増えてきました。データイーストって割と定着率が良かったので、スタッフが減らないんですよ。なのでところてん式かなと思います。
安藤:データイーストの社員のみなさんは、スムーズにセガに移られたパターンが多かったんですね。
濱田:そうですね。割と太いパイプがありましたし。ただ、その後で苦労した人もだいぶいたみたいですけど。
安藤:1999年頃ですよね。
濱田:そうですね、1999年です。ちょうどセガでは『シェンムー』を作っていました。
安藤:濱田さんは『シェンムー』では「効果音」でクレジットされていますよね。あの頃、日本の開発会社のほとんどが『シェンムー』を作っていたように記憶しています。私もその頃はゲームを作り始めていたので、各社を行脚したときに「みんな『シェンムー』を作っているぞ!?」と思っていました(笑)。
濱田:あれはねー(笑)。僕、『シェンムー』の話だけで2時間は語れますよ(笑)。
安藤:あの時期は本当にみんな『シェンムー』を作っていましたよね。「あれ、この人も『シェンムー』を作ってるぞ」みたいな状況(笑)。
濱田:でも、今あの当時のことを語りたがる人ってあまりいないでしょ?
安藤:そうですね(笑)。私は仕事柄「最近どうなっていますか」とか「開発のラインはどうなっていますか」って開発会社に確認するんですけど、「今、セガさんの案件をやっているんですよ」って返事がくると『シェンムー』なのかなって(笑)。
濱田:まぁ、巨大なタコ部屋でした(笑)。
安藤:今考えれば、ゲームの歴史に残るエポックメイキングな作品というか、オープンワールドを本気でやったら大変な規模になるというプロダクションを、日本のゲーム業界全体で経験した瞬間だと思います。効果音なんかもおびただしい数だったんじゃないでしょうか。ということで、『シェンムー』の効果音のお話もいろいろ聞かせてもらいたいです。
濱田:『シェンムー』では、効果音とサウンドシステムの設計を全部やっていました。全部3Dで距離と方向をコントロールするシステムを制作したんです。今となっては当たり前なんですけど、昔はCPUの処理能力がそんなに高くないので、省力化していかに音がついて来るか、システムに落とし込むのがたいへんでした。例えば街を歩いていると、ラジカセから音が出ているシーンをどう表現するか、ふすまの向こう側にいる人の足音をどうするかとか、そういうサウンドスケープの設計。そして、そこに乗せるための効果音の制作。地味だけど面白い仕事でした。何気にデータイーストに入った頃と同じような仕事をしていたんですよね。
安藤:もはやサウンドプログラム。ツールを作るところからスタートしているのがすごい。データイーストとセガで会社の色みたいな差を感じられるところはありましたか?
濱田:やっぱり、セガは上場企業だということですね。スタッフの資質は意外と近いところがあったと思いますが、各セクションの上にいる人間は、その前のアーケード時代の成功体験者なので、みなさんイケイケなわけですよ。なので、人使いの粗さはデータイーストの比ではない。
安藤:そうなんですね(笑)。
濱田:時代が時代でしたし、今では笑い話ですけどね(苦笑)。1週間のうち1回家に帰って、着るものを持ってまた出社という状況でした。音声収録もまたたいへんで、シナリオがコロコロ変わるから、その都度、音声を録るわけですよ。だけど録ったあとにそのシーンが丸々なくなったりして、すべてが無駄になる……そんなことすらありました。
安藤:お蔵入りになった効果音も相当あったということですか。
濱田:そうですね。とんでもなく経費がかかっています。最後のほうは、午前中に録って午後に録り終わってデータ化して、次の朝には持っていくんですよ。それがワード数にして4000とかあるんですよ。それを3交代制で延々やってました。
濱田:中のスタッフは、非常に大真面目にゲームを作っていたんですよ。なので当時、「ヘンなゲーム」って言われていたのはすごく心外だったんです。
安藤:(笑)。
濱田:でも、変わったスタッフが多かったのは間違いないです。スタッフの採用基準ってどうなっていたのかなって気になりますよね。
安藤:社員はストレートにものを作っていたけど、そのアウトプットが独特だったわけですね。
濱田:大真面目に作った企画書が、外から見たらとんでもないものだったのかなって。でもそれを「とんでもない!」と評価できる、目の肥えた上層部がいなかったってことだと思いますけど(笑)。社長の福田さんも技術畑の人なんですよね。だから経営的な部分よりも技術的に面白いとか、こいつらやる気があるなとか、そういうところに予算をつけちゃう人でした。
だからデータイーストの社員からすれば、いい社長だったと思います。ただ会社としてとか、株主としては勘弁してくれよって部分が多かったんじゃないかな。まあ、そんなこんなでいつも予算にピーピー言っていました。やりたいことをいかに安くやるかってことばかり考えていましたね(笑)。
安藤:予算管理も考えながら立ち向かっていた。なんだかプログラマー的ですね。前編で濱田さん自身の棚卸しのお話がありました。音楽をやっている人はそういう部分が苦手な印象が強いんです。ゲームはインプットしないとアウトプットしないところからスタートしているので、案外ミュージシャンとしての熱い自分と、それを冷たく俯瞰で見ている人が多いなって思います。
濱田:そこが単なるミュージシャンでいられないところだと思うんですよ。ミュージシャンは「オレ最高!」って言ってないとダメじゃないですか。そこが大きな違いで、職業作家の適性な部分じゃないですかね。
■日本のほとんどの開発会社は、一時期ほとんどが『シェンムー』の開発をしていた!?
安藤:そして濱田さんはデータイーストのあとにセガに移るわけですが、その理由はデータイーストが縮小していったところでセガに移られたってことなんでしょうか。
濱田:元々、セガの中山社長と福田さんが親交があって、非常に密な付き合いをしていたんです。人材の交流もけっこう多かったし。セガサターンの頃はセガから出向社員も結構来ていましたから。今思えば、それは吸収の一環だったのかな。その辺からデータイーストの規模が縮小するにつれて、セガに移籍していくスタッフが増えてきました。データイーストって割と定着率が良かったので、スタッフが減らないんですよ。なのでところてん式かなと思います。
安藤:データイーストの社員のみなさんは、スムーズにセガに移られたパターンが多かったんですね。
濱田:そうですね。割と太いパイプがありましたし。ただ、その後で苦労した人もだいぶいたみたいですけど。
安藤:1999年頃ですよね。
濱田:そうですね、1999年です。ちょうどセガでは『シェンムー』を作っていました。
安藤:濱田さんは『シェンムー』では「効果音」でクレジットされていますよね。あの頃、日本の開発会社のほとんどが『シェンムー』を作っていたように記憶しています。私もその頃はゲームを作り始めていたので、各社を行脚したときに「みんな『シェンムー』を作っているぞ!?」と思っていました(笑)。
濱田:あれはねー(笑)。僕、『シェンムー』の話だけで2時間は語れますよ(笑)。
安藤:あの時期は本当にみんな『シェンムー』を作っていましたよね。「あれ、この人も『シェンムー』を作ってるぞ」みたいな状況(笑)。
濱田:でも、今あの当時のことを語りたがる人ってあまりいないでしょ?
安藤:そうですね(笑)。私は仕事柄「最近どうなっていますか」とか「開発のラインはどうなっていますか」って開発会社に確認するんですけど、「今、セガさんの案件をやっているんですよ」って返事がくると『シェンムー』なのかなって(笑)。
濱田:まぁ、巨大なタコ部屋でした(笑)。
安藤:今考えれば、ゲームの歴史に残るエポックメイキングな作品というか、オープンワールドを本気でやったら大変な規模になるというプロダクションを、日本のゲーム業界全体で経験した瞬間だと思います。効果音なんかもおびただしい数だったんじゃないでしょうか。ということで、『シェンムー』の効果音のお話もいろいろ聞かせてもらいたいです。
濱田:『シェンムー』では、効果音とサウンドシステムの設計を全部やっていました。全部3Dで距離と方向をコントロールするシステムを制作したんです。今となっては当たり前なんですけど、昔はCPUの処理能力がそんなに高くないので、省力化していかに音がついて来るか、システムに落とし込むのがたいへんでした。例えば街を歩いていると、ラジカセから音が出ているシーンをどう表現するか、ふすまの向こう側にいる人の足音をどうするかとか、そういうサウンドスケープの設計。そして、そこに乗せるための効果音の制作。地味だけど面白い仕事でした。何気にデータイーストに入った頃と同じような仕事をしていたんですよね。
安藤:もはやサウンドプログラム。ツールを作るところからスタートしているのがすごい。データイーストとセガで会社の色みたいな差を感じられるところはありましたか?
濱田:やっぱり、セガは上場企業だということですね。スタッフの資質は意外と近いところがあったと思いますが、各セクションの上にいる人間は、その前のアーケード時代の成功体験者なので、みなさんイケイケなわけですよ。なので、人使いの粗さはデータイーストの比ではない。
安藤:そうなんですね(笑)。
濱田:時代が時代でしたし、今では笑い話ですけどね(苦笑)。1週間のうち1回家に帰って、着るものを持ってまた出社という状況でした。音声収録もまたたいへんで、シナリオがコロコロ変わるから、その都度、音声を録るわけですよ。だけど録ったあとにそのシーンが丸々なくなったりして、すべてが無駄になる……そんなことすらありました。
安藤:お蔵入りになった効果音も相当あったということですか。
濱田:そうですね。とんでもなく経費がかかっています。最後のほうは、午前中に録って午後に録り終わってデータ化して、次の朝には持っていくんですよ。それがワード数にして4000とかあるんですよ。それを3交代制で延々やってました。

安藤:そんな作り方をした大規模なゲームのプロジェクト、歴史上でほかにあるんですかね? ちょっと興味があります。まさに20世紀のゲームバブルならではの作り方。
濱田:そう、20世紀の作り方ですね。結局それは「見てみなければわからない」と「その場に出てみなければわからない」という鈴木裕さんのモットーを貫いたことになるわけです。鈴木さんは、本当にいろいろなことに気がつくすごい方でした。そんな人と一緒にあんなゲームの作り方に携われたことは、僕の人生のなかでしっかりとした意味があったと思います。
安藤:ちょっと羨ましいです。わたしにとっての『シェンムー』は、フォークリフトのレースなんですよ。あのミニゲームがすごくおもしろくて、ずっとタイムアタックをしていました。オンラインでタイムをシェアするという経験も初めてでしたし、とにかく夢中で。
濱田:もう香港行かなくていいやってなったんですね?(笑)
安藤:ずっと港湾で作業しているっていう(笑)。ただのミニゲームであの手の込みよう……純粋にすごいなと思いました。
濱田:あれも、フォークリフトの挙動にめちゃめちゃこだわっていたからね。
安藤:挙動が素晴らしくて本物のフォークリフトのようだったから、普通のレースゲームと違うおもしろさがありました。でも、フォークリフトレースだけでゲームとして発売したら、絶対に売れない。だからあのおもしろさって、『シェンムー』のあの港だけでしか経験できないものなんですよ。まさに唯一無二。
濱田:音にももちろんこだわっていますよ。「エンジン音はやっぱりディーゼルなんだよー!」ってね。
安藤:まさか、ディーゼルエンジンの音を収録しに行ったりしたんですか?
濱田:そりゃあ行きましたよ! 行きましたけど、そうやって録ったやつは大体使えないんですけどね。生々しさがイマイチ出ないというか。結局は「そういう風に聴こえるもの」を作るため、取材に行ったようなものですね。
安藤:ディーゼルエンジンとなると、どんな素材を収録されたんですか?
濱田:コマツとかのフォークリフトの音かな。重機を録りに行きました。でもあれだったらランクルとかでもよかったのかも(笑)。
安藤:ランドクルーザーの音のほうが「それっぽく聞こえる」とか、あるんですよね(笑)。
濱田:そうそう。ゲームはBGMが注目されるのもわかるんですけど、結局は音声と効果音があってこそなんです。
安藤:わかります。そうして濱田さんは、セガに10年以上在籍されていたわけですが……。
濱田:2014年までだから、15年も在籍していました。データイーストよりも長くなっちゃった。
安藤:『ボーダーブレイク』や『バーチャファイター5』など、最近のアーケードまで関わられていますけど、いわゆる90年代のアーケードゲームと、2000年代~2010年代のアーケードゲームで、サウンドメイクの変遷などはありますか。
濱田:昔と比べて筐体の再生環境が良くなってきていますから、そのぶんの変遷はありますよ。メーカーによってサウンドに対するアプローチとか、ウェイトのかけ方が違うのが印象的でしたね。アーケードだと筐体デザインを見れば、どれだけサウンドに重きを置いているかがよくわかるんです。
安藤:サウンドを重視しているメーカーは、おのずとそれに即した筐体デザインになっていたわけですね。
濱田:そういうことです。ハードウェア側の問題で、そこまでサウンドの部品に予算を割けなかったデーターイースト時代の筐体なんて、最近のものとは比べることさえおこがましいレベルでしたよ。実際、ステレオスピーカーが筐体に付けられること自体が贅沢なわけで。データイーストのアーケード基板や筐体ってモノラルが多いんですよね。
安藤:いつまでモノラルだったんでしょうか。
濱田:NEO-GEO手前までの自社基板は、ほぼモノラルでした。モノラルでなおかつADPCMチップも8ビット。でもこれが幸いしたのは、サウンドのほとんどがロックサウンドだったこと。そのおかげで、8ビットでもカッコいいサウンドが鳴らせたんですよ。
安藤:納得です。それでアーケードのデコサウンドは、ロックの方向性に行ったんですね。
濱田:例えば『空牙』は、コインを入れるとクレジット音で「クイーン!」といい音で鳴るんですが、あれは音としてはものすごいレベルで歪んでいるんですよ。でも、それがスピーカーの特性と相まって、すごくピーキーに聴こえる。
安藤:歪みまで利用してのカッコいい音ってことですね。
濱田:制約はあったけど、それを逆手に取ってどう作るかを工夫していた時代です。
■セガ移籍後も『探偵 神宮寺三郎』シリーズのサウンド制作に関わってきた理由
安藤:セガを辞めて独立されたきっかけはどういう流れなんですか?
濱田:自分のキャリアを考えて、プログラマーからスタートしてサウンドのコンポーズ、素材作成などを手掛けてきたんですけど、今や制作現場において、特殊スキルを得るためにゲーム業界に居続ける必要はなくなったんですよ。昔はゲームメーカーが、内部にあれだけの人材を抱えていたからこそできたものがありました。
でも今後は、どんどんコモディティ化していってその規模が必要なくなり、個人で同じレベルのものができるようになるはずです。そうなったら、アイデア次第でおもしろいものがたくさん出てくるだろうなと思った時に、大きな会社に所属していたら、逆にその面白いものに携わる機会がなくなるのではと危惧しまして。
安藤:会社という構造上、どうしても出てきてしまうジレンマですよね。
濱田:そういう意味で言うと、僕はサラリーマン失格だったのでしょう。企業戦士として持っているべき、企業へのロイヤリティを持ったことがないかもしれない。
安藤:セガに所属してからのお話しですか? それともデータイースト時代からでしょうか?
濱田:そう、20世紀の作り方ですね。結局それは「見てみなければわからない」と「その場に出てみなければわからない」という鈴木裕さんのモットーを貫いたことになるわけです。鈴木さんは、本当にいろいろなことに気がつくすごい方でした。そんな人と一緒にあんなゲームの作り方に携われたことは、僕の人生のなかでしっかりとした意味があったと思います。
安藤:ちょっと羨ましいです。わたしにとっての『シェンムー』は、フォークリフトのレースなんですよ。あのミニゲームがすごくおもしろくて、ずっとタイムアタックをしていました。オンラインでタイムをシェアするという経験も初めてでしたし、とにかく夢中で。
濱田:もう香港行かなくていいやってなったんですね?(笑)
安藤:ずっと港湾で作業しているっていう(笑)。ただのミニゲームであの手の込みよう……純粋にすごいなと思いました。
濱田:あれも、フォークリフトの挙動にめちゃめちゃこだわっていたからね。
安藤:挙動が素晴らしくて本物のフォークリフトのようだったから、普通のレースゲームと違うおもしろさがありました。でも、フォークリフトレースだけでゲームとして発売したら、絶対に売れない。だからあのおもしろさって、『シェンムー』のあの港だけでしか経験できないものなんですよ。まさに唯一無二。
濱田:音にももちろんこだわっていますよ。「エンジン音はやっぱりディーゼルなんだよー!」ってね。
安藤:まさか、ディーゼルエンジンの音を収録しに行ったりしたんですか?
濱田:そりゃあ行きましたよ! 行きましたけど、そうやって録ったやつは大体使えないんですけどね。生々しさがイマイチ出ないというか。結局は「そういう風に聴こえるもの」を作るため、取材に行ったようなものですね。
安藤:ディーゼルエンジンとなると、どんな素材を収録されたんですか?
濱田:コマツとかのフォークリフトの音かな。重機を録りに行きました。でもあれだったらランクルとかでもよかったのかも(笑)。
安藤:ランドクルーザーの音のほうが「それっぽく聞こえる」とか、あるんですよね(笑)。
濱田:そうそう。ゲームはBGMが注目されるのもわかるんですけど、結局は音声と効果音があってこそなんです。
安藤:わかります。そうして濱田さんは、セガに10年以上在籍されていたわけですが……。
濱田:2014年までだから、15年も在籍していました。データイーストよりも長くなっちゃった。
安藤:『ボーダーブレイク』や『バーチャファイター5』など、最近のアーケードまで関わられていますけど、いわゆる90年代のアーケードゲームと、2000年代~2010年代のアーケードゲームで、サウンドメイクの変遷などはありますか。
濱田:昔と比べて筐体の再生環境が良くなってきていますから、そのぶんの変遷はありますよ。メーカーによってサウンドに対するアプローチとか、ウェイトのかけ方が違うのが印象的でしたね。アーケードだと筐体デザインを見れば、どれだけサウンドに重きを置いているかがよくわかるんです。
安藤:サウンドを重視しているメーカーは、おのずとそれに即した筐体デザインになっていたわけですね。
濱田:そういうことです。ハードウェア側の問題で、そこまでサウンドの部品に予算を割けなかったデーターイースト時代の筐体なんて、最近のものとは比べることさえおこがましいレベルでしたよ。実際、ステレオスピーカーが筐体に付けられること自体が贅沢なわけで。データイーストのアーケード基板や筐体ってモノラルが多いんですよね。
安藤:いつまでモノラルだったんでしょうか。
濱田:NEO-GEO手前までの自社基板は、ほぼモノラルでした。モノラルでなおかつADPCMチップも8ビット。でもこれが幸いしたのは、サウンドのほとんどがロックサウンドだったこと。そのおかげで、8ビットでもカッコいいサウンドが鳴らせたんですよ。
安藤:納得です。それでアーケードのデコサウンドは、ロックの方向性に行ったんですね。
濱田:例えば『空牙』は、コインを入れるとクレジット音で「クイーン!」といい音で鳴るんですが、あれは音としてはものすごいレベルで歪んでいるんですよ。でも、それがスピーカーの特性と相まって、すごくピーキーに聴こえる。
安藤:歪みまで利用してのカッコいい音ってことですね。
濱田:制約はあったけど、それを逆手に取ってどう作るかを工夫していた時代です。
■セガ移籍後も『探偵 神宮寺三郎』シリーズのサウンド制作に関わってきた理由
安藤:セガを辞めて独立されたきっかけはどういう流れなんですか?
濱田:自分のキャリアを考えて、プログラマーからスタートしてサウンドのコンポーズ、素材作成などを手掛けてきたんですけど、今や制作現場において、特殊スキルを得るためにゲーム業界に居続ける必要はなくなったんですよ。昔はゲームメーカーが、内部にあれだけの人材を抱えていたからこそできたものがありました。
でも今後は、どんどんコモディティ化していってその規模が必要なくなり、個人で同じレベルのものができるようになるはずです。そうなったら、アイデア次第でおもしろいものがたくさん出てくるだろうなと思った時に、大きな会社に所属していたら、逆にその面白いものに携わる機会がなくなるのではと危惧しまして。
安藤:会社という構造上、どうしても出てきてしまうジレンマですよね。
濱田:そういう意味で言うと、僕はサラリーマン失格だったのでしょう。企業戦士として持っているべき、企業へのロイヤリティを持ったことがないかもしれない。
安藤:セガに所属してからのお話しですか? それともデータイースト時代からでしょうか?

濱田:どうだろう。データイーストって、チームとしてのこだわりというか、連帯感はすごかったんですけど、それが愛社精神だったかと言うと、またちょっと違うと思いますね。
安藤:いちユーザー視点で言わせていただくと、データイーストからはあまり「企業感」を感じなかったんです。濱田さんが話してくれた「セガは上場企業だと感じた」という部分は、ギャップがすごくておもしろかったです。
濱田:どちらかと言うと、データイーストは会社というより予備校みたいなところでしたね(笑)。おもしろいのは、データイーストがなくなったあともそのOBたちはいろんな所でいろんなことをやっていて、思ってもみなかったところで再会するんですよね。割と業界内でしぶとく生き残っている人間が多い。
安藤:それだけ職人肌な方が多かったということでしょうか。ところで、濱田さんがセガに在籍されてるときにも『探偵 神宮寺三郎』シリーズの音楽を手がけられているのが、とても不思議に思うんです。会社の枠組みを超えた仕事の受注って、どのようにして実現されたのでしょうか。
濱田:データイーストが倒産して『探偵 神宮寺三郎』のライセンスはワークジャムに移ったんです。その際、『探偵 神宮寺三郎』の開発チームもほぼそのままワークジャムに移籍しまして。当時、僕はもうセガにいたんですけど、『探偵 神宮寺三郎』のプロデューサーから直々に「誰か『探偵 神宮寺三郎』のサウンドを作れる人を紹介してくれないか」と連絡があったんですよ。
安藤:最初は濱田さんご自身にではなく、あくまでも「紹介してほしい」という依頼だったんですね。
濱田:そうです。『探偵 神宮寺三郎』のサウンドってコンポーザーも結構使っていましたし、プレイヤーもたくさん使っているんですよね。そのラインをそのまま渡すから使ってと言ったんですけど、結局サウンドを仕切れる人間がいないから「半分だけでもやってもらえない?」というお話になって。
それでデータイースト時代の『未完のルポ』と『夢の終わりに』で関わってもらった外注のプレイヤーを呼んで、僕から「こういう理由があるから手伝ってくれない?」とお願いしてみました。そうして仕上がったのが『Innocent Black』。ちなみに、今のお話に出てきたプロデューサーは『クロス探偵物語』を作った神長豊さんです。
安藤:ここで『クロス探偵物語』の血が入るんですよね。
濱田:正確に言えば、神長さんと元・データイーストで『探偵 神宮寺三郎』をプロデュースしていた西山英一さんが共同で作ったものなんですけど、それでうまく作れて「このやり方でいけるじゃん!」となってしまって(苦笑)。
安藤:ちなみに『Innocent Black』以降は、別の名前でクレジットされていますよね。
濱田:そうですね。「馳見“Ace”大地(※2)」っていうペンネームを作って、『探偵 神宮寺三郎』ではその名前でサウンド制作に関わってました。名前の由来は濱田誠一のアナグラムになっています。
(※2)馳見“Ace”大地……濱田誠一の氏の名前をローマ字(Seiichi Hamada)にし、文字を入れて変えてHasemi a daichiとアナグラム化したもの。余った「a」の字は「Ace」に置き換えている
安藤:結果的に「別会社の開発に携わった」わけですけど、こういうことってゲーム業界ではよくあることなのでしょうか?
濱田:自分と同世代だと結構ありましたよ。労働規約がわりと緩いというか(苦笑)。もちろん表向きはダメなんだけど、きちんと仕事していればうるさくいわなくてもいいや……みたいな、緩い時代があったんです。
安藤:大らかだったんですね。今は時代的に、正式に副業OKな会社も多いようですけど。
濱田:でも、そういう会社って「給料が少ない代わりに副業していいよ」みたいな感じじゃないですか。それもどうかなと思いますけどね。
安藤:最新作『GHOST OF THE DUSK』のサウンドクレジットは、濱田誠一に戻っていますが、これはどういう心境の変化が?
濱田:単純に、セガを辞めて表立って活動できるようになったので戻しただけなんですけど。体が二つないと無理! 的な状況ではあったんですがそれを押してでも『探偵 神宮寺三郎』のサウンド制作ってやりたい仕事だったんですよ。
安藤:『探偵 神宮寺三郎』では作曲を濱田さんがほぼ全部手掛けて、演奏をチームでやっていたということですよね。
安藤:いちユーザー視点で言わせていただくと、データイーストからはあまり「企業感」を感じなかったんです。濱田さんが話してくれた「セガは上場企業だと感じた」という部分は、ギャップがすごくておもしろかったです。
濱田:どちらかと言うと、データイーストは会社というより予備校みたいなところでしたね(笑)。おもしろいのは、データイーストがなくなったあともそのOBたちはいろんな所でいろんなことをやっていて、思ってもみなかったところで再会するんですよね。割と業界内でしぶとく生き残っている人間が多い。
安藤:それだけ職人肌な方が多かったということでしょうか。ところで、濱田さんがセガに在籍されてるときにも『探偵 神宮寺三郎』シリーズの音楽を手がけられているのが、とても不思議に思うんです。会社の枠組みを超えた仕事の受注って、どのようにして実現されたのでしょうか。
濱田:データイーストが倒産して『探偵 神宮寺三郎』のライセンスはワークジャムに移ったんです。その際、『探偵 神宮寺三郎』の開発チームもほぼそのままワークジャムに移籍しまして。当時、僕はもうセガにいたんですけど、『探偵 神宮寺三郎』のプロデューサーから直々に「誰か『探偵 神宮寺三郎』のサウンドを作れる人を紹介してくれないか」と連絡があったんですよ。
安藤:最初は濱田さんご自身にではなく、あくまでも「紹介してほしい」という依頼だったんですね。
濱田:そうです。『探偵 神宮寺三郎』のサウンドってコンポーザーも結構使っていましたし、プレイヤーもたくさん使っているんですよね。そのラインをそのまま渡すから使ってと言ったんですけど、結局サウンドを仕切れる人間がいないから「半分だけでもやってもらえない?」というお話になって。
それでデータイースト時代の『未完のルポ』と『夢の終わりに』で関わってもらった外注のプレイヤーを呼んで、僕から「こういう理由があるから手伝ってくれない?」とお願いしてみました。そうして仕上がったのが『Innocent Black』。ちなみに、今のお話に出てきたプロデューサーは『クロス探偵物語』を作った神長豊さんです。
安藤:ここで『クロス探偵物語』の血が入るんですよね。
濱田:正確に言えば、神長さんと元・データイーストで『探偵 神宮寺三郎』をプロデュースしていた西山英一さんが共同で作ったものなんですけど、それでうまく作れて「このやり方でいけるじゃん!」となってしまって(苦笑)。
安藤:ちなみに『Innocent Black』以降は、別の名前でクレジットされていますよね。
濱田:そうですね。「馳見“Ace”大地(※2)」っていうペンネームを作って、『探偵 神宮寺三郎』ではその名前でサウンド制作に関わってました。名前の由来は濱田誠一のアナグラムになっています。
(※2)馳見“Ace”大地……濱田誠一の氏の名前をローマ字(Seiichi Hamada)にし、文字を入れて変えてHasemi a daichiとアナグラム化したもの。余った「a」の字は「Ace」に置き換えている
安藤:結果的に「別会社の開発に携わった」わけですけど、こういうことってゲーム業界ではよくあることなのでしょうか?
濱田:自分と同世代だと結構ありましたよ。労働規約がわりと緩いというか(苦笑)。もちろん表向きはダメなんだけど、きちんと仕事していればうるさくいわなくてもいいや……みたいな、緩い時代があったんです。
安藤:大らかだったんですね。今は時代的に、正式に副業OKな会社も多いようですけど。
濱田:でも、そういう会社って「給料が少ない代わりに副業していいよ」みたいな感じじゃないですか。それもどうかなと思いますけどね。
安藤:最新作『GHOST OF THE DUSK』のサウンドクレジットは、濱田誠一に戻っていますが、これはどういう心境の変化が?
濱田:単純に、セガを辞めて表立って活動できるようになったので戻しただけなんですけど。体が二つないと無理! 的な状況ではあったんですがそれを押してでも『探偵 神宮寺三郎』のサウンド制作ってやりたい仕事だったんですよ。
安藤:『探偵 神宮寺三郎』では作曲を濱田さんがほぼ全部手掛けて、演奏をチームでやっていたということですよね。

濱田:作曲も、一部は別の方が書いてます。とくに、ずっと一緒にやってくれているピアニストの中道勝彦が、3分の1ぐらいは曲を手掛けてくれていますね。そうしてチームで作っていくことで自分も煮詰まらなくて済みますし、刺激を受け続けながら作ることができる。あと、『探偵 神宮寺三郎』のサウンド制作ってレコーディングが必須になるので、やっぱりそういった「現場仕事」をやり続けていたかった部分は大きいですね。
安藤:そして現在は、セガを辞められて引き続き『探偵 神宮寺三郎』シリーズに参加しつつ、『イヌワシ』にも関わられるなど、フリーランスで伸び伸びとたくさんのゲーム音楽を手がけられているわけですね。
濱田:そうですね。ありがたいことに今のところたくさんお仕事をいただけています。
安藤:先ほど『探偵 神宮寺三郎』のサウンドで「現場仕事」をやり続けていたかったというお話がありましたが、ベースのレコーディングは基本的に濱田さんが演奏されているのでしょうか?
濱田:もちろん。レコーディングではほとんどベースを弾いてますよ。でも自分のレコーディングぶんって制作スケジュールに入っていなくて(笑)。なので、全パートが上がってきてから最後にベースを入れているんです。打ち込みで入れてあった音も最終的に「これは生の音のほうがいいな」と思ったら、ちゃんと生で弾いて差し替えています。
安藤:一度活動を休止していたゲーマデリックが復活して、バンド活動を続けておられますよね。これはどういった心境の変化があったんですか?
濱田:きっかけは2013年の“ゲームミュージックトリビュートライブ”に出演することだったんです。ライブの1年前にスタッフさんから「こういう企画があるんだけど」って相談されたとき、「参加してみたいけどメンバーが集まらないだろうな……」って思っていたんですよ。ギターのMAROも、当時は元データイーストのスタッフで立ち上げたパオンでサウンドのトップを務めていましたし、そのほかのメンバーもみんな業界に散らばっていたので、できるとしても、1回だけのお祭りみたいな形になると考えていました。でも、MAROと話した時に「やるんだったらちゃんとやろうよ」となり、ギターのMAROとベースの自分、ドラムの三浦という3人が再結集しまして。
安藤:ゲーマデリックが復活したわけですね。
濱田:みんなまだプレイヤーとして現役でしたし、20代中盤から後半にかけて、同じ釜の飯を食いながらしゃにむにやっていたメンバーなので、気心が知れているんですよね。すぐに当時のバンドの音が出るようになりました。バンドを維持できるというのはすごくありがたいことなので、身体が動く限りやろうと思っています。聴いてくれるお客さんもいますし、そのためにやり続けるというのがモチベーションとして一番大きいですね。
■ゲームミュージックをきちんとやっているゲームを、今後作ってみたい
安藤:濱田さんはこれからもゲーム音楽を多数手がけていかれると思うのですが、今やってみたいこと、チャレンジしてみたいことってありますか?
濱田:ちょっと逆説的ですが、会社でなくても制作においてチームってすごく大事だと思うんですね。幸いにして、この業界に四半世紀以上所属していて、アドバンテージがあったのは人脈だと思うんです。若い人たちも含めて、いろんなところに知り合いがいて、その人脈やネットワークのなかでチームを作って何かを作りたいということは、常に意識しています。
安藤:具体的に、この人と組んでみたいという方はいますか?
濱田:人というよりはやりたいタイトル、やりたいコンセプトが第一ですかね。
安藤:では、挑戦してみたいタイトルやコンセプトはなんでしょう?
安藤:そして現在は、セガを辞められて引き続き『探偵 神宮寺三郎』シリーズに参加しつつ、『イヌワシ』にも関わられるなど、フリーランスで伸び伸びとたくさんのゲーム音楽を手がけられているわけですね。
濱田:そうですね。ありがたいことに今のところたくさんお仕事をいただけています。
安藤:先ほど『探偵 神宮寺三郎』のサウンドで「現場仕事」をやり続けていたかったというお話がありましたが、ベースのレコーディングは基本的に濱田さんが演奏されているのでしょうか?
濱田:もちろん。レコーディングではほとんどベースを弾いてますよ。でも自分のレコーディングぶんって制作スケジュールに入っていなくて(笑)。なので、全パートが上がってきてから最後にベースを入れているんです。打ち込みで入れてあった音も最終的に「これは生の音のほうがいいな」と思ったら、ちゃんと生で弾いて差し替えています。
安藤:一度活動を休止していたゲーマデリックが復活して、バンド活動を続けておられますよね。これはどういった心境の変化があったんですか?
濱田:きっかけは2013年の“ゲームミュージックトリビュートライブ”に出演することだったんです。ライブの1年前にスタッフさんから「こういう企画があるんだけど」って相談されたとき、「参加してみたいけどメンバーが集まらないだろうな……」って思っていたんですよ。ギターのMAROも、当時は元データイーストのスタッフで立ち上げたパオンでサウンドのトップを務めていましたし、そのほかのメンバーもみんな業界に散らばっていたので、できるとしても、1回だけのお祭りみたいな形になると考えていました。でも、MAROと話した時に「やるんだったらちゃんとやろうよ」となり、ギターのMAROとベースの自分、ドラムの三浦という3人が再結集しまして。
安藤:ゲーマデリックが復活したわけですね。
濱田:みんなまだプレイヤーとして現役でしたし、20代中盤から後半にかけて、同じ釜の飯を食いながらしゃにむにやっていたメンバーなので、気心が知れているんですよね。すぐに当時のバンドの音が出るようになりました。バンドを維持できるというのはすごくありがたいことなので、身体が動く限りやろうと思っています。聴いてくれるお客さんもいますし、そのためにやり続けるというのがモチベーションとして一番大きいですね。
■ゲームミュージックをきちんとやっているゲームを、今後作ってみたい
安藤:濱田さんはこれからもゲーム音楽を多数手がけていかれると思うのですが、今やってみたいこと、チャレンジしてみたいことってありますか?
濱田:ちょっと逆説的ですが、会社でなくても制作においてチームってすごく大事だと思うんですね。幸いにして、この業界に四半世紀以上所属していて、アドバンテージがあったのは人脈だと思うんです。若い人たちも含めて、いろんなところに知り合いがいて、その人脈やネットワークのなかでチームを作って何かを作りたいということは、常に意識しています。
安藤:具体的に、この人と組んでみたいという方はいますか?
濱田:人というよりはやりたいタイトル、やりたいコンセプトが第一ですかね。
安藤:では、挑戦してみたいタイトルやコンセプトはなんでしょう?

濱田:これは昔からどこで話しても首を縦に振られたことがないんだけど、今だったら意外といけるかもしれないと思っているのが、「ゲームミュージックをきちんとやっているゲーム」ですね。
安藤:「ゲームミュージックをきちんとやっているゲーム」……すぐにピンとこないんですけど、具体的にお聞きしてもよろしいですか?
濱田:一般的な音楽とゲームミュージックの決定的な違いは「インタラクティブ性」です。これをきちんと生かしつつ、音楽が効果的に鳴るゲームを作りたいって意味ですね。現状、それが出来ているのは、任天堂さんだけだと思っています。いろいろなタイトルでチャレンジはされているんだけど、ちゃんとした成功例はほとんどないんですよ。
安藤:インタラクティブ性となると、『Rez』とか『スペースチャンネル5』といったゲームのイメージが近いのでしょうか。
濱田:古くは『パラッパラッパー』とか、ああいう形のゲームでサウンドをメインにして作れないかなと。でもサウンドをやるだけでもダメだし、プログラマーのセンスもものすごく問われるんですよね。別に自分が主導権持たなくても構いませんが、究極のところでいえば『Rez』や『スペースチャンネル5』のさらに先を行くものを見たいという思いがあるんです。
安藤:いわゆる「音ゲー」と呼ばれるものは、『beatmania』シリーズを源流とした譜面叩きのゲーム性が今なお主流ですけど、そうではない新たな形のゲームをつくってみたいということですね?
濱田:そうそう! 安藤さんもベーシストならおわかりになると思いますが、今の音ゲーのシステムでは、グルーヴをつけたらアウトじゃないですか。
安藤:タイミングに合わせてコマンドを的確に入力していくゲーム性ですから、楽器の演奏とは似て非なるものですからね。楽器の演奏はゴーストノートと言われる裏リズム的なものを入れないとノリが出ませんが、そこは今までの音ゲーでは表現できない。
濱田:そういうことです。そこらへんの認識を変えるゲームをつくれないかな、と。
安藤:つんく♂さんが作った『リズム天国』は、日本人に「裏拍の概念」を叩き込むことをコンセプトにしているってお話を聞いたことがあるんですけど、あれはベーシストとして遊んでもおもしろかった。
安藤:「ゲームミュージックをきちんとやっているゲーム」……すぐにピンとこないんですけど、具体的にお聞きしてもよろしいですか?
濱田:一般的な音楽とゲームミュージックの決定的な違いは「インタラクティブ性」です。これをきちんと生かしつつ、音楽が効果的に鳴るゲームを作りたいって意味ですね。現状、それが出来ているのは、任天堂さんだけだと思っています。いろいろなタイトルでチャレンジはされているんだけど、ちゃんとした成功例はほとんどないんですよ。
安藤:インタラクティブ性となると、『Rez』とか『スペースチャンネル5』といったゲームのイメージが近いのでしょうか。
濱田:古くは『パラッパラッパー』とか、ああいう形のゲームでサウンドをメインにして作れないかなと。でもサウンドをやるだけでもダメだし、プログラマーのセンスもものすごく問われるんですよね。別に自分が主導権持たなくても構いませんが、究極のところでいえば『Rez』や『スペースチャンネル5』のさらに先を行くものを見たいという思いがあるんです。
安藤:いわゆる「音ゲー」と呼ばれるものは、『beatmania』シリーズを源流とした譜面叩きのゲーム性が今なお主流ですけど、そうではない新たな形のゲームをつくってみたいということですね?
濱田:そうそう! 安藤さんもベーシストならおわかりになると思いますが、今の音ゲーのシステムでは、グルーヴをつけたらアウトじゃないですか。
安藤:タイミングに合わせてコマンドを的確に入力していくゲーム性ですから、楽器の演奏とは似て非なるものですからね。楽器の演奏はゴーストノートと言われる裏リズム的なものを入れないとノリが出ませんが、そこは今までの音ゲーでは表現できない。
濱田:そういうことです。そこらへんの認識を変えるゲームをつくれないかな、と。
安藤:つんく♂さんが作った『リズム天国』は、日本人に「裏拍の概念」を叩き込むことをコンセプトにしているってお話を聞いたことがあるんですけど、あれはベーシストとして遊んでもおもしろかった。

濱田:うん。いけたよね?
安藤:いけましたね。
濱田:じつは『リズム天国』のアーケード移植やDS版は、セガのAM2研が手がけていたんですよ。なので僕もサウンド制作を手伝っていたんですけど、あのゲームは本当によく出来ていますよね。
安藤:すごいですよね。コマンド入力式の音ゲーが主流のなか、『リズム天国』はちょっと異色だと思います。一般のプレイヤーも楽しめるし、音楽をやっている人も楽しめる。濱田さんはそういうゲームを目指したいってことですね。
濱田:ゲームって基本的に子どもが遊ぶものじゃないですか。少年時代に遊んだゲームから、いろいろなものを学んで刷り込まれる側面ってありますよね。
安藤:ありますね。多感であるがゆえに受ける影響は大きい。
濱田:そんなものをつくるわけですから、僕はサウンドについての責任を背負わなければならないとずっと思っているんです。そこも含めて、『リズム天国』ほど大きいタイトルじゃなくても、何かこれまでとは違った形で、子どもたちにゲームミュージックの素晴らしさを刷り込んでいきたいんですよ。
安藤:濱田さんのようなレジェンドクリエイターが、今なおそういう気概を持ってゲームサウンドの一線で踏ん張っているというのは、ものすごくアツいですね。クリエイターとして刺激を受けます。
濱田:だからといってマニアックになっちゃうのもどうかと思うし、難しいところなんですけど。あと、昨今のゲームのメインターゲット層が持つセンスと、自分が持っているセンスはおそらくもう価値観がアジャストしないと思います。なので、そういうどちらの価値観も理解できるような若い世代の誰かとチームを組まないと、これからはやっていけないとも思うんですよね。そういう人たちと一緒にできる機会を、もっとたくさん持てればいいなと思っています。
安藤:おもしろいなと思ったのは、時代ごとの最新ガジェットに歩み寄っている音楽ゲームってじつはなくて、断絶しているんだなって部分。かつてはエニックスでもダンスのゲームを作っていましたし、『パラッパラッパー』や『ビブリボン』、『beatmania』などのゲームが出てきましたが、アーケードはさておき、コンシューマではほとんどが断絶しているんですよね。でも、今は単に枯れてしまっているだけで、また再び甦らせることはできるのではないかとも思えました。
濱田:現状のプラットフォームがスマホメインに移行しているのも、理由としてあるかもしれませんね。スマホで遊べる音ゲーやリズム系ゲームも増えてはいますが、コンシューマほど本格的なものに仕上げるにはデバイスの問題としてキツいと思うので。もしかしたら、外部デバイスを含めてのお話になってくるのかもしれないけど。
安藤:アーケードやスマホで『バンドリ!』が人気ですが、あれも基本的には上からノーツが落ちてきたり上がってきたりするのをタッチしていくゲームなんですよね。それだけじゃないゲーム性を生み出し、デバイスの問題をクリアできれば、幅広い層に受け入れられると思います。もしかすると、Nintendo Switchで何か革新的なものが出来るかもしれませんしね。
濱田:正直、そんなに大仰なプロジェクトじゃなくても出来ることはあると思っているんですよね。何かしらのアイデアひとつで音楽をもっと好きになって楽しめるゲームを生み出す。いつか実現したいなと思っています。
安藤:つまり、濱田さんは「音楽が主役になるゲーム」を実現したいってことですね。
濱田:そうですね。やっぱり自分が遊んで楽しいゲームを作りたいじゃないですか(笑)。
安藤:いちプロデューサーとして、そこをテーマにして考えるのはおもしろいと感じました。楽曲をプレイして、演奏がうまくなってきたらキャラもレベルアップしてカッコよくなって、楽曲もより複雑に、だけどよりカッコよくなっていく……そんなゲームってまだありませんからね。
濱田:それって現代のミュージカルだと思わない?
安藤:そんなゲームがあったらいいですよね。わたしもミュージカルはすごく好きなんですけど、ミュージカルには物語も音楽もないと成立しないという意味では、ゲームと方向性が似ている。つまり親和性は高いんですよね。ミュージカルの構図をベースにしつつRPGとして楽しめる……そんなゲームを手掛けてみたいと思いました。このアイデアを実現できる日が来たら、濱田さんと一緒にやりたいですね。
濱田:やりましょう! サウンド的にはバラエティに富んだものにしないといけないから、いろんな人の手を借りることになりそうですけどね。
安藤:このプロジェクトを実現するためには、構造がわかっているメンバーが集まることは必要不可欠ですよね。インタラクティブである以上、通常のコンポーザーにはないスキルを持った人が集まらないといけない。ハードルはなかなか高そうですが、いつか実現してみたいです。
濱田:この業界いるからには、いつかやってみたいことって感じですね。曲をパーツごとに分解し、そこから再構成していく……そんなインタラクティブ性もあると思います。
安藤:今日はものすごくおもしろかったです! 最後に、今後のゲーマデリックの活動の目標とかってあるんでしょうか?
濱田:ゲーマデリックの活動は今のところ昔の楽曲を再現するバンドになっていますけど、幸いなことに今も自分がゲーム音楽を作っているので、それをゲーマデリックに落とし込んでいくってことも今後は考えていきたいと思ってます。あとこれまではアーケードが中心でしたが、今後はコンシューマ関係、とくに『ヘラクレスの栄光』とか『メタルマックス』なんかの楽曲もカバーしていきたいですね。聴きたいっていうお客さんからの要望も多いので。
安藤:濱田さんが今後作るゲームサウンド、そして今後のゲーマデリックの活動も楽しみにしています。本日はありがとうございました!
安藤:いけましたね。
濱田:じつは『リズム天国』のアーケード移植やDS版は、セガのAM2研が手がけていたんですよ。なので僕もサウンド制作を手伝っていたんですけど、あのゲームは本当によく出来ていますよね。
安藤:すごいですよね。コマンド入力式の音ゲーが主流のなか、『リズム天国』はちょっと異色だと思います。一般のプレイヤーも楽しめるし、音楽をやっている人も楽しめる。濱田さんはそういうゲームを目指したいってことですね。
濱田:ゲームって基本的に子どもが遊ぶものじゃないですか。少年時代に遊んだゲームから、いろいろなものを学んで刷り込まれる側面ってありますよね。
安藤:ありますね。多感であるがゆえに受ける影響は大きい。
濱田:そんなものをつくるわけですから、僕はサウンドについての責任を背負わなければならないとずっと思っているんです。そこも含めて、『リズム天国』ほど大きいタイトルじゃなくても、何かこれまでとは違った形で、子どもたちにゲームミュージックの素晴らしさを刷り込んでいきたいんですよ。
安藤:濱田さんのようなレジェンドクリエイターが、今なおそういう気概を持ってゲームサウンドの一線で踏ん張っているというのは、ものすごくアツいですね。クリエイターとして刺激を受けます。
濱田:だからといってマニアックになっちゃうのもどうかと思うし、難しいところなんですけど。あと、昨今のゲームのメインターゲット層が持つセンスと、自分が持っているセンスはおそらくもう価値観がアジャストしないと思います。なので、そういうどちらの価値観も理解できるような若い世代の誰かとチームを組まないと、これからはやっていけないとも思うんですよね。そういう人たちと一緒にできる機会を、もっとたくさん持てればいいなと思っています。
安藤:おもしろいなと思ったのは、時代ごとの最新ガジェットに歩み寄っている音楽ゲームってじつはなくて、断絶しているんだなって部分。かつてはエニックスでもダンスのゲームを作っていましたし、『パラッパラッパー』や『ビブリボン』、『beatmania』などのゲームが出てきましたが、アーケードはさておき、コンシューマではほとんどが断絶しているんですよね。でも、今は単に枯れてしまっているだけで、また再び甦らせることはできるのではないかとも思えました。
濱田:現状のプラットフォームがスマホメインに移行しているのも、理由としてあるかもしれませんね。スマホで遊べる音ゲーやリズム系ゲームも増えてはいますが、コンシューマほど本格的なものに仕上げるにはデバイスの問題としてキツいと思うので。もしかしたら、外部デバイスを含めてのお話になってくるのかもしれないけど。
安藤:アーケードやスマホで『バンドリ!』が人気ですが、あれも基本的には上からノーツが落ちてきたり上がってきたりするのをタッチしていくゲームなんですよね。それだけじゃないゲーム性を生み出し、デバイスの問題をクリアできれば、幅広い層に受け入れられると思います。もしかすると、Nintendo Switchで何か革新的なものが出来るかもしれませんしね。
濱田:正直、そんなに大仰なプロジェクトじゃなくても出来ることはあると思っているんですよね。何かしらのアイデアひとつで音楽をもっと好きになって楽しめるゲームを生み出す。いつか実現したいなと思っています。
安藤:つまり、濱田さんは「音楽が主役になるゲーム」を実現したいってことですね。
濱田:そうですね。やっぱり自分が遊んで楽しいゲームを作りたいじゃないですか(笑)。
安藤:いちプロデューサーとして、そこをテーマにして考えるのはおもしろいと感じました。楽曲をプレイして、演奏がうまくなってきたらキャラもレベルアップしてカッコよくなって、楽曲もより複雑に、だけどよりカッコよくなっていく……そんなゲームってまだありませんからね。
濱田:それって現代のミュージカルだと思わない?
安藤:そんなゲームがあったらいいですよね。わたしもミュージカルはすごく好きなんですけど、ミュージカルには物語も音楽もないと成立しないという意味では、ゲームと方向性が似ている。つまり親和性は高いんですよね。ミュージカルの構図をベースにしつつRPGとして楽しめる……そんなゲームを手掛けてみたいと思いました。このアイデアを実現できる日が来たら、濱田さんと一緒にやりたいですね。
濱田:やりましょう! サウンド的にはバラエティに富んだものにしないといけないから、いろんな人の手を借りることになりそうですけどね。
安藤:このプロジェクトを実現するためには、構造がわかっているメンバーが集まることは必要不可欠ですよね。インタラクティブである以上、通常のコンポーザーにはないスキルを持った人が集まらないといけない。ハードルはなかなか高そうですが、いつか実現してみたいです。
濱田:この業界いるからには、いつかやってみたいことって感じですね。曲をパーツごとに分解し、そこから再構成していく……そんなインタラクティブ性もあると思います。
安藤:今日はものすごくおもしろかったです! 最後に、今後のゲーマデリックの活動の目標とかってあるんでしょうか?
濱田:ゲーマデリックの活動は今のところ昔の楽曲を再現するバンドになっていますけど、幸いなことに今も自分がゲーム音楽を作っているので、それをゲーマデリックに落とし込んでいくってことも今後は考えていきたいと思ってます。あとこれまではアーケードが中心でしたが、今後はコンシューマ関係、とくに『ヘラクレスの栄光』とか『メタルマックス』なんかの楽曲もカバーしていきたいですね。聴きたいっていうお客さんからの要望も多いので。
安藤:濱田さんが今後作るゲームサウンド、そして今後のゲーマデリックの活動も楽しみにしています。本日はありがとうございました!

テキスト:風のイオナ(FLOOR25) ゲームと音楽と旅と自転車が好きな東京在住フリーライター&エディター。最近は地下アイドルグループDORCAのプロデューサー業もやってます。
ツイッターアカウント→風のイオナ@ハイパーいおなぴ@ionadisco
シシララTV オリジナル記事