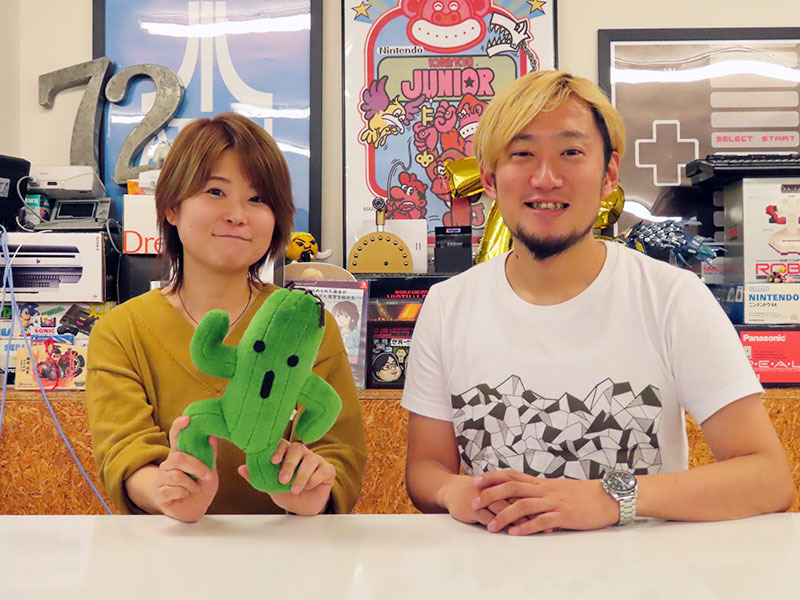制作の黒幕はクーロンズ・ゲートさん!? 『クーロンズ・ゲート』の開発を手掛けた木村央志×井上幸喜×蓜島邦明ロングインタビュー【前編】
ソニー・ミュージックエンタテインメントより、1997年にリリースされたPlayStation用ゲーム『クーロンズ・ゲート』。その唯一無二の世界観で、リリースから20年が経つ今でもなおファンを魅了し続けている。シシララTVではそのアニバーサリーイヤーを記念して、企画・脚本・監督の木村央志さん、キャラクターデザインの井上幸喜さん、音楽監督の蓜島邦明さんによる豪華鼎談を実施。ゲームDJ・安藤武博がインタビュアーとなり、制作秘話や今後の展望などをおうかがいしていく。

▲蓜島邦明さん(左)、井上幸喜さん(中央)、木村央志さん(右)。
■それぞれのアイデアの相乗効果で構築されていった『クーロンズ・ゲート』の世界
安藤武博(以下、安藤):『クーロンズ・ゲート』のリリースから20年目の節目にあたる2017年に木村さん、井上さん、蓜島さんにお集まりいただけたこと、本当に光栄です。今日は当時の開発秘話から、今後の展望までをお話しいただければと思います。
蓜島邦明さん(以下、蓜島):昨年、「クーロンズ・ゲート コンサート2016 九龍夜奏繪(※1)」を開催するにあたって、昔の曲を根こそぎ聴いたんだけど。「あのとき、こんなことまでやってたのか」と感心しました。正直、今までは『クーロンズ・ゲート』の曲をライブでやるのは無理だと思っていたけど、全部アナログに変えてストリングスにすれば面白くなると思って、ライブではその形になりました。
(※1)クーロンズ・ゲート コンサート2016 九龍夜奏繪……2016年5月22日に開催された『クーロンズ・ゲート』初のコンサートイベント。「繪」は「絵」の旧字であり、パーティを表す「会」の旧字は「會」であるため、本来は糸偏が不要である。木村さんいわく、ここが間違っているあたりが「陰界クオリティである」とのこと。
安藤:こうして3人がそろうのは、そのライブ以来になるのでしょうか?
井上幸喜さん(以下、井上):3人全員が集まるとなると、そうなりますね。
蓜島:井上さんとはこの前会ったよね? 井上さんが『クーロンズゲートVR Suzaku』を作ったでしょう。あれがとても悔しくて。自分の中にもまったく別次元の『クーロンズ・ゲート』があるんだけど、いつかその曲を作ってCDを出そうと思っていました。じつは、ソニーさんにも許諾の申請は出してOKをいただいているんですよね。
安藤:蓜島さんの中にも、また違った『クーロンズ・ゲート』があるんですね。ディレクターやキャラデザイナー、コンポーザーの方までみんなが世界観を完璧に共有しているのって、ゲーム開発の現場ではとても珍しいことだと思います。
蓜島:PSで世に出た『クーロンズ・ゲート』は井上さんのキャラクターと、木村さんのストーリーがあってこそ出来上がったもの。でも、それはそれとして、自分のなかにも妄想の『クーロンズ・ゲート』の世界があるわけです。いつか、それをやってみたい。井上さんがVRを出したから、次は僕の番かな……と(笑)。
井上:そもそもPSでの制作方法が、かなり特殊だったんですよね。みんながみんな「好きにやっていいよ」って状態でゲームを作っていた。
蓜島:だから、個人個人の心のなかにあの世界がある。
安藤:あの世界観はどうやって構築していかれたんですか?
木村央志さん(以下、木村):すべての根源にあるのは、コアメンバーみんなで香港を訪れたときの思い出です。「シリコングラフィクス社製のCG用ワークステーション(※2)を用いてゲームを作る」ということはすでに決まっていたので、このマシンをどう使おうかというところから始まりましたね。ハードはPlayStationでリリースすることも決まっていたので、制作にあたって「次世代機らしく」音楽とポリゴンとムービーが主軸になることもわかっていました。
(※2)シリコングラフィックス社製のCG用ワークステーション……コンピュータグラフィックスに特化した最先端の製品を開発し続け、コンピュータグラフィックスの進化に絶大な影響を与えた企業・シリコングラフィックス社。当時、木村さんは同社が開発したSGI Onyx(約8,000万円ほどで、小型冷蔵庫くらいのサイズのワークステーション)を用いていた。「Onyxがあったからこそあの魔窟が描けた」とのこと。
井上:シリコングラフィックスもPlayStationも、当時としては次世代ですよ(笑)。
安藤:そうですよね。シリコングラフィクスがあるというだけで、会社に人が集まる時代でした。
木村:当時私は、ソニーミュージックコミュニケーションズでコピーライターを担当していました。ある日、SMEニューメディア室で凄いコンピュータをお披露目すると案内があって見に行くことになったんです。帰りがけ、同僚と「何に使うんだろうね」と話をしていたんですが、その三ヵ月後、奇しくも当のニューメディア室に異動になって、CGでゲームを作るみたいな流れになりました。
それまでのCGは「歪みと汚れ」の表現を苦手としていたのですが、シリコングラフィックス、そしてPlayStationであればその表現も可能だろうと、あえてその方向で進むことになったんです。最初は、映画の「ブレードランナー」のようなスカした世界観を目指していたんですよ。デキる男が主人公となり、歪んだ世界で冒険を繰り広げていくみたいな。
蓜島:そんな内容になっていたら、音楽はまったく別物になっていたと思うな。
安藤武博(以下、安藤):『クーロンズ・ゲート』のリリースから20年目の節目にあたる2017年に木村さん、井上さん、蓜島さんにお集まりいただけたこと、本当に光栄です。今日は当時の開発秘話から、今後の展望までをお話しいただければと思います。
蓜島邦明さん(以下、蓜島):昨年、「クーロンズ・ゲート コンサート2016 九龍夜奏繪(※1)」を開催するにあたって、昔の曲を根こそぎ聴いたんだけど。「あのとき、こんなことまでやってたのか」と感心しました。正直、今までは『クーロンズ・ゲート』の曲をライブでやるのは無理だと思っていたけど、全部アナログに変えてストリングスにすれば面白くなると思って、ライブではその形になりました。
(※1)クーロンズ・ゲート コンサート2016 九龍夜奏繪……2016年5月22日に開催された『クーロンズ・ゲート』初のコンサートイベント。「繪」は「絵」の旧字であり、パーティを表す「会」の旧字は「會」であるため、本来は糸偏が不要である。木村さんいわく、ここが間違っているあたりが「陰界クオリティである」とのこと。
安藤:こうして3人がそろうのは、そのライブ以来になるのでしょうか?
井上幸喜さん(以下、井上):3人全員が集まるとなると、そうなりますね。
蓜島:井上さんとはこの前会ったよね? 井上さんが『クーロンズゲートVR Suzaku』を作ったでしょう。あれがとても悔しくて。自分の中にもまったく別次元の『クーロンズ・ゲート』があるんだけど、いつかその曲を作ってCDを出そうと思っていました。じつは、ソニーさんにも許諾の申請は出してOKをいただいているんですよね。
安藤:蓜島さんの中にも、また違った『クーロンズ・ゲート』があるんですね。ディレクターやキャラデザイナー、コンポーザーの方までみんなが世界観を完璧に共有しているのって、ゲーム開発の現場ではとても珍しいことだと思います。
蓜島:PSで世に出た『クーロンズ・ゲート』は井上さんのキャラクターと、木村さんのストーリーがあってこそ出来上がったもの。でも、それはそれとして、自分のなかにも妄想の『クーロンズ・ゲート』の世界があるわけです。いつか、それをやってみたい。井上さんがVRを出したから、次は僕の番かな……と(笑)。
井上:そもそもPSでの制作方法が、かなり特殊だったんですよね。みんながみんな「好きにやっていいよ」って状態でゲームを作っていた。
蓜島:だから、個人個人の心のなかにあの世界がある。
安藤:あの世界観はどうやって構築していかれたんですか?
木村央志さん(以下、木村):すべての根源にあるのは、コアメンバーみんなで香港を訪れたときの思い出です。「シリコングラフィクス社製のCG用ワークステーション(※2)を用いてゲームを作る」ということはすでに決まっていたので、このマシンをどう使おうかというところから始まりましたね。ハードはPlayStationでリリースすることも決まっていたので、制作にあたって「次世代機らしく」音楽とポリゴンとムービーが主軸になることもわかっていました。
(※2)シリコングラフィックス社製のCG用ワークステーション……コンピュータグラフィックスに特化した最先端の製品を開発し続け、コンピュータグラフィックスの進化に絶大な影響を与えた企業・シリコングラフィックス社。当時、木村さんは同社が開発したSGI Onyx(約8,000万円ほどで、小型冷蔵庫くらいのサイズのワークステーション)を用いていた。「Onyxがあったからこそあの魔窟が描けた」とのこと。
井上:シリコングラフィックスもPlayStationも、当時としては次世代ですよ(笑)。
安藤:そうですよね。シリコングラフィクスがあるというだけで、会社に人が集まる時代でした。
木村:当時私は、ソニーミュージックコミュニケーションズでコピーライターを担当していました。ある日、SMEニューメディア室で凄いコンピュータをお披露目すると案内があって見に行くことになったんです。帰りがけ、同僚と「何に使うんだろうね」と話をしていたんですが、その三ヵ月後、奇しくも当のニューメディア室に異動になって、CGでゲームを作るみたいな流れになりました。
それまでのCGは「歪みと汚れ」の表現を苦手としていたのですが、シリコングラフィックス、そしてPlayStationであればその表現も可能だろうと、あえてその方向で進むことになったんです。最初は、映画の「ブレードランナー」のようなスカした世界観を目指していたんですよ。デキる男が主人公となり、歪んだ世界で冒険を繰り広げていくみたいな。
蓜島:そんな内容になっていたら、音楽はまったく別物になっていたと思うな。

木村:世界観が固まったあと、蓜島さんも香港に行かれたんですよね。蓜島さんに音楽をお願いすることが決まった段階で、「ゲームの雰囲気は「香港」なんですけど、口で説明しても仕方がないので実際に見てもらった方がいい」とお伝えして。
蓜島:じつは、僕が木村さんや井上さんに遅れて香港に行ったときは、もう現実の九龍城砦(※3)はなかったんだよね。
(※3)九龍城砦……きゅうりゅうじょうさい。正式には九龍寨城、俗に九龍城(クーロンじょう)とも呼ばれる。元は宋代の要塞であったが、19世紀末、英国による新界租借後は飛び地として治外法権化し、中華人民共和国誕生後も香港政庁の手が及ばない無法地帯となる。1970年代頃から違法建築のビルが増殖しはじめ、2.6haの土地に十数階建てのビルが300棟以上も密集する一大スラム街となった。最盛期には5万人が暮らしたという九龍城砦は、複雑極まる迷宮の様相を呈したいたことから「九龍城には一回入ると出てこられない」とも言われていた。1993年から1994年にかけて取り壊し工事が行われ、現在は公園として整備されている。
井上:我々が行ったときも、公園内に記念として残されている最下層しかなかったしね。
木村:ホンモノは見られなかったけど、香港には似た雰囲気のヤバそうな場所がたくさんあったから、参考にはなったでしょう?
蓜島:たしかに。
安藤:本作はかなり独特の世界観が話題を呼びました。こういう作家性の強い作品は、たいていの場合、明確にその世界が見えている誰か1人が引っ張っていくことが多いと思うのですが、この『クーロンズ・ゲート』の場合は違いますよね。みなさんそれぞれの心の中に『クーロンズ・ゲート』があるというのは、かなり特殊なことではないでしょうか。
木村:みんな、何かのスイッチが入ったんだよね。
井上:そうそう。スイッチが入って、何かに引っ張られるかのようにお互いが競争していく感じ。木村さんがこんなシナリオを書いてきたけど、僕は言うことを聞かないでこんなデザインにしてみたら、結果的に喜ばれるとか、いろいろありましたよね。蓜島さんが作ってくれた音楽を聴いて、この楽曲を生かすならこんなムービーも必要だよね、とか。お互いの相乗効果がありましたよね。
安藤:王道の「剣と魔法の世界」なら、世界観の共有は比較的簡単だなあと思うのですが、本作は唯一無二。ライバルもいませんし、今後もこんな作品は出てこないと思うんです。それなのに、まさか3人のプラットフォームになっているとは。
井上:当時、こんなゲームは手本がなかったよね。
木村:なかったね。
蓜島:あれだけ独創性があるものを、あの時期に出したのは早すぎたんだと思うよ。でも、あれから20年が経過して、伝説になりつつあるというのはスゴい。歴史に残るものを作ったってことだからね。
■クリエイター陣に指示を出していた「クーロンズ・ゲートさん」の存在
安藤:本作は、PlayStation初期のリリース予定タイトルにラインナップされていましたね。それが難産の末、ハードの発売から3年後の1997年にリリースされて。本当に独創的でした。
蓜島:あの世界観は本物のアーティストじゃないと作れないと思うんですよ。自分で自分を本物っていうとおこがましいけど、これだけの年月が経過していたら誰かしら業界からいなくなっていてもおかしくないのに、誰もがこの世界にしがみついているんだから、「本物のアーティスト」って言ってもいいよね(笑)。
井上:開発当時、誰かに何かを指示された記憶がまったくないんですよね。まぁ、安藤さんのおっしゃるとおり、リリースは遅れに遅れたわけで、「急げ」とはよく言われましたけど(笑)。
安藤:納期については言われても、クリエイティブに関しては口出しされることはなかったわけですね。
木村:開発も後半まで進んでくると、「クーロンズ・ゲートさん」が指示を出していたんですよね。
井上:そうそう。それはみんな同じことを言うよね(笑)。
安藤:クーロンズ・ゲートさん!?
木村:「僕はこれじゃ嫌だ」とか、クーロンズ・ゲートさんが言ってくる。僕は彼が言っていることに従って、シナリオを書いているイメージがありました。
蓜島:じつは、僕が木村さんや井上さんに遅れて香港に行ったときは、もう現実の九龍城砦(※3)はなかったんだよね。
(※3)九龍城砦……きゅうりゅうじょうさい。正式には九龍寨城、俗に九龍城(クーロンじょう)とも呼ばれる。元は宋代の要塞であったが、19世紀末、英国による新界租借後は飛び地として治外法権化し、中華人民共和国誕生後も香港政庁の手が及ばない無法地帯となる。1970年代頃から違法建築のビルが増殖しはじめ、2.6haの土地に十数階建てのビルが300棟以上も密集する一大スラム街となった。最盛期には5万人が暮らしたという九龍城砦は、複雑極まる迷宮の様相を呈したいたことから「九龍城には一回入ると出てこられない」とも言われていた。1993年から1994年にかけて取り壊し工事が行われ、現在は公園として整備されている。
井上:我々が行ったときも、公園内に記念として残されている最下層しかなかったしね。
木村:ホンモノは見られなかったけど、香港には似た雰囲気のヤバそうな場所がたくさんあったから、参考にはなったでしょう?
蓜島:たしかに。
安藤:本作はかなり独特の世界観が話題を呼びました。こういう作家性の強い作品は、たいていの場合、明確にその世界が見えている誰か1人が引っ張っていくことが多いと思うのですが、この『クーロンズ・ゲート』の場合は違いますよね。みなさんそれぞれの心の中に『クーロンズ・ゲート』があるというのは、かなり特殊なことではないでしょうか。
木村:みんな、何かのスイッチが入ったんだよね。
井上:そうそう。スイッチが入って、何かに引っ張られるかのようにお互いが競争していく感じ。木村さんがこんなシナリオを書いてきたけど、僕は言うことを聞かないでこんなデザインにしてみたら、結果的に喜ばれるとか、いろいろありましたよね。蓜島さんが作ってくれた音楽を聴いて、この楽曲を生かすならこんなムービーも必要だよね、とか。お互いの相乗効果がありましたよね。
安藤:王道の「剣と魔法の世界」なら、世界観の共有は比較的簡単だなあと思うのですが、本作は唯一無二。ライバルもいませんし、今後もこんな作品は出てこないと思うんです。それなのに、まさか3人のプラットフォームになっているとは。
井上:当時、こんなゲームは手本がなかったよね。
木村:なかったね。
蓜島:あれだけ独創性があるものを、あの時期に出したのは早すぎたんだと思うよ。でも、あれから20年が経過して、伝説になりつつあるというのはスゴい。歴史に残るものを作ったってことだからね。
■クリエイター陣に指示を出していた「クーロンズ・ゲートさん」の存在
安藤:本作は、PlayStation初期のリリース予定タイトルにラインナップされていましたね。それが難産の末、ハードの発売から3年後の1997年にリリースされて。本当に独創的でした。
蓜島:あの世界観は本物のアーティストじゃないと作れないと思うんですよ。自分で自分を本物っていうとおこがましいけど、これだけの年月が経過していたら誰かしら業界からいなくなっていてもおかしくないのに、誰もがこの世界にしがみついているんだから、「本物のアーティスト」って言ってもいいよね(笑)。
井上:開発当時、誰かに何かを指示された記憶がまったくないんですよね。まぁ、安藤さんのおっしゃるとおり、リリースは遅れに遅れたわけで、「急げ」とはよく言われましたけど(笑)。
安藤:納期については言われても、クリエイティブに関しては口出しされることはなかったわけですね。
木村:開発も後半まで進んでくると、「クーロンズ・ゲートさん」が指示を出していたんですよね。
井上:そうそう。それはみんな同じことを言うよね(笑)。
安藤:クーロンズ・ゲートさん!?
木村:「僕はこれじゃ嫌だ」とか、クーロンズ・ゲートさんが言ってくる。僕は彼が言っていることに従って、シナリオを書いているイメージがありました。

井上:普通はシナリオライターが書いたシナリオに合わせて絵コンテを描き、それに沿って制作していきます。でも、『クーロンズ・ゲート』の現場では、誰も言うことを聞かなかった。
木村:会議で集まっても、話すことがないんですよ。みんな、クーロンズ・ゲートさんの言うことを聞いているだけだから。
安藤:「クーロンズ・ゲートさん」が概念となって存在し、みなさんに指示を出してこられたんですか。ほかの現場でも、そのような経験をしたことはありますか?
木村:いいえ。これが最初で最後。
井上:蓜島さんの曲を聴いた瞬間に、絵が浮かんできたこともあったよね。
木村:ありましたね。そもそも、音楽に関しても細かい注文は一切なかった。
安藤:音楽を蓜島さんにお願いすることになった経緯はなんなのでしょう?
井上:テレビドラマの「NIGHT HEAD」を見て、蓜島さんの作った曲がゲームの雰囲気にぴったりだということになり。僕とCGデザイナーの武富聖くんは、当時フジテレビでCGを作っていたこともあって、「世にも奇妙な物語」のスタッフ経由で蓜島さんとのラインを繋げてもらったんですよ。
蓜島:最初に『クーロンズ・ゲート』のスタッフに会ったときは、ストリートバスケットボールをやっているお兄ちゃんが来たかと思ったんだよね。「Yo! Yo!」ってやっているラッパーみたいな服装だったのを覚えてる。
井上:武富くんと、プロデューサーの須藤 朗さんですね。2人とも普通のサラリーマンではなかったから、Tシャツにだるだるのジーンズ姿でうかがったようで(笑)。2人に蓜島さんどうだったって聞いたら「即決でやってもらえることになりましたよ」って。そこから絵作りを始めました。
安藤:蓜島さんは楽曲を作るにあたって、世界観の説明などを受けたんですか?
蓜島:当時、絵コンテとかあったっけ?
井上:なかったですね。CGが数分程度あっただけ。武富くんが作ったパイプがうわーっと描かれたCGを見てもらったように思います。
木村:オープニングのムービーですね。路面を破壊してパイプ類が有機物のようにせり出してくる部分。
蓜島:そうだ。それを見て、テーマ曲を作りましたからね。
木村:みなさんご承知のとおり、開発にはとにかく時間がかかったんですよ。最初に発表した時は、全体の20分の1しか出来ていなかったくらい。それでも、「ハードのローンチ時期にリリースするんだ」と言ってしまったんですけど、まぁ、出るわけないですよね(苦笑)。
■お手本がない状態でのゲーム作りでこだわったこと
安藤:みなさんがゲーム開発に携わったのは『クーロンズ・ゲート』が初めてになるのでしょうか?
木村:そうですね。
木村:会議で集まっても、話すことがないんですよ。みんな、クーロンズ・ゲートさんの言うことを聞いているだけだから。
安藤:「クーロンズ・ゲートさん」が概念となって存在し、みなさんに指示を出してこられたんですか。ほかの現場でも、そのような経験をしたことはありますか?
木村:いいえ。これが最初で最後。
井上:蓜島さんの曲を聴いた瞬間に、絵が浮かんできたこともあったよね。
木村:ありましたね。そもそも、音楽に関しても細かい注文は一切なかった。
安藤:音楽を蓜島さんにお願いすることになった経緯はなんなのでしょう?
井上:テレビドラマの「NIGHT HEAD」を見て、蓜島さんの作った曲がゲームの雰囲気にぴったりだということになり。僕とCGデザイナーの武富聖くんは、当時フジテレビでCGを作っていたこともあって、「世にも奇妙な物語」のスタッフ経由で蓜島さんとのラインを繋げてもらったんですよ。
蓜島:最初に『クーロンズ・ゲート』のスタッフに会ったときは、ストリートバスケットボールをやっているお兄ちゃんが来たかと思ったんだよね。「Yo! Yo!」ってやっているラッパーみたいな服装だったのを覚えてる。
井上:武富くんと、プロデューサーの須藤 朗さんですね。2人とも普通のサラリーマンではなかったから、Tシャツにだるだるのジーンズ姿でうかがったようで(笑)。2人に蓜島さんどうだったって聞いたら「即決でやってもらえることになりましたよ」って。そこから絵作りを始めました。
安藤:蓜島さんは楽曲を作るにあたって、世界観の説明などを受けたんですか?
蓜島:当時、絵コンテとかあったっけ?
井上:なかったですね。CGが数分程度あっただけ。武富くんが作ったパイプがうわーっと描かれたCGを見てもらったように思います。
木村:オープニングのムービーですね。路面を破壊してパイプ類が有機物のようにせり出してくる部分。
蓜島:そうだ。それを見て、テーマ曲を作りましたからね。
木村:みなさんご承知のとおり、開発にはとにかく時間がかかったんですよ。最初に発表した時は、全体の20分の1しか出来ていなかったくらい。それでも、「ハードのローンチ時期にリリースするんだ」と言ってしまったんですけど、まぁ、出るわけないですよね(苦笑)。
■お手本がない状態でのゲーム作りでこだわったこと
安藤:みなさんがゲーム開発に携わったのは『クーロンズ・ゲート』が初めてになるのでしょうか?
木村:そうですね。

安藤:あの独特の雰囲気というか、独自の「不条理感」みたいなものは、どこから生まれたものなのでしょう。
木村:クーロンズ・ゲートさんとのやり取りで培われたものではあるのですが、Macintoshでリリースされた『マンホール』というゲームの影響は受けていますね。あんなテイストをやりたかったので。クリック&ムーブで歩き回るみたいな。
安藤:わたしは、プレイしていて『MYST』のテイストを感じていました。
木村:それもありますね。『MYST』のPCで最適化された操作性を、PSのコントローラで表現するとどうなるだろうと考えていました。それで、操作性がガラリと変わるダンジョンやイベントは、ムービーを挟むことで違和感なくつなげようと考えたんです。ある意味、一番難しい方向性でしたけどね。
井上:贅沢な方向に行きましたね。
安藤:プロデューサーの須藤さんが自ら、蓜島さんの説得に赴くなど、みんなで一緒にやろうという空気があったんですね。普通のゲーム会社であれば、「ちょっと濃すぎやしないか」と誰かにストップをかけられるほどに際立ったタイトルだと思うのですが、それがなかったのも僥倖ですね。
木村:ソニー・ミュージックエンターテインメントも、いろいろとおかしな会社でしたからね(笑)。まず最初に、シリコングラフィックスのコンピュータありき。会社での立場を護るうえで、いかにこのワークステーションを使い倒すかがミッションとして重要だったんです。
井上:SMEは当時ニューメディア本部でしたっけ?
木村:そう。PlayStationを作ったのはSCE(ソニー・コンピュータエンタテインメント。現ソニー・インタラクティブエンターテインメント)なんですけど、我々がいたのはソニーミュージックだから、基本的にはゲームを作る必要なんてなかったんです。でも、ワークステーションを買ってしまったんだから何かしなければいけないということで、成り行きに近い形からゲームを作ることになったんです。そういうチームオーダーを感じていました。
井上:SCEとは違うラインナップで、よりアーティスティックなものを求められていた一面もありました。
木村:音楽業界はサブカル系の人が多いから。そこに引っかかる作品を作っていくというのは命題でしたね。あのときの私たちには、ゲーム業界との接点はまったくなかったんですよ。マーケティングのスタッフが、ゲームやマルチメディア系の雑誌の奥付を見ながら編集部に電話して「こんなゲームがあるんですけど、記事掲載してもらえますか」ってお願いしていたレベルでしたから。もちろん、最初はほとんど相手にされなかったんですけどね(笑)。
安藤:今となってはみなさんともに、『クーロンズ・ゲート』をきっかけにゲームに関わり続けているわけですから、人生は面白いですね。
井上:私は映像を作っていたのに、ゲームを作れといきなり言われて。じつは最初、キャラクターデザインは大友克洋さん(※3)にお願いしに行こうという話になっていました。それでこんな風にお願いしようと下絵を描いていたら、須藤さんがそれでいこうとなって。
(※3)大友克洋……日本の漫画家・映画監督。氏が手掛けたアニメーション映画『AKIRA』は、「ジャパニメーション」と呼ばれる日本国外における日本アニメムーブメントのさきがけ的な作品となった。
木村:サイバーパンクの王道だったら、大友さんにお願いしたよね。でもそうじゃないところがあったから、自前で行こうということになった。
井上:当時の僕は、設定画の描き方なんてまるで知らないので、急いでアニメイトに走りましたよ。そこで買ってきたアニメの設定集を見ながら、「こんな角度で描くんだ」って勉強したりして(苦笑)。
安藤:蓜島さんも、「ゲーム音楽」の制作自体は本作が初めてですよね?
蓜島:そうですね。この『クーロンズ・ゲート』で、始めてループの方法を教えてもらいました。
安藤:ループを多用する楽曲作りって、ゲームサウンドならではのものですよね。
蓜島:資料として送られてきた画像は、すでに世界観がしっかり出来上がっていたので、それに合わせてアジア系や民族系の楽器を使って味付けしていきました。このゲームには、環境音楽とかSEに近いニュアンスの音楽が合うなって最初から考えていたんです。でも、当時はそういう機微がわからない人も多くて、「世の役に立たない」なんて言われたものですよ。
安藤:今となっては、ゲームサウンドは「環境音中心のもの」もたくさん存在します。そういう意味でも、時代の先を行っていたんですね。
木村:クーロンズ・ゲートさんとのやり取りで培われたものではあるのですが、Macintoshでリリースされた『マンホール』というゲームの影響は受けていますね。あんなテイストをやりたかったので。クリック&ムーブで歩き回るみたいな。
安藤:わたしは、プレイしていて『MYST』のテイストを感じていました。
木村:それもありますね。『MYST』のPCで最適化された操作性を、PSのコントローラで表現するとどうなるだろうと考えていました。それで、操作性がガラリと変わるダンジョンやイベントは、ムービーを挟むことで違和感なくつなげようと考えたんです。ある意味、一番難しい方向性でしたけどね。
井上:贅沢な方向に行きましたね。
安藤:プロデューサーの須藤さんが自ら、蓜島さんの説得に赴くなど、みんなで一緒にやろうという空気があったんですね。普通のゲーム会社であれば、「ちょっと濃すぎやしないか」と誰かにストップをかけられるほどに際立ったタイトルだと思うのですが、それがなかったのも僥倖ですね。
木村:ソニー・ミュージックエンターテインメントも、いろいろとおかしな会社でしたからね(笑)。まず最初に、シリコングラフィックスのコンピュータありき。会社での立場を護るうえで、いかにこのワークステーションを使い倒すかがミッションとして重要だったんです。
井上:SMEは当時ニューメディア本部でしたっけ?
木村:そう。PlayStationを作ったのはSCE(ソニー・コンピュータエンタテインメント。現ソニー・インタラクティブエンターテインメント)なんですけど、我々がいたのはソニーミュージックだから、基本的にはゲームを作る必要なんてなかったんです。でも、ワークステーションを買ってしまったんだから何かしなければいけないということで、成り行きに近い形からゲームを作ることになったんです。そういうチームオーダーを感じていました。
井上:SCEとは違うラインナップで、よりアーティスティックなものを求められていた一面もありました。
木村:音楽業界はサブカル系の人が多いから。そこに引っかかる作品を作っていくというのは命題でしたね。あのときの私たちには、ゲーム業界との接点はまったくなかったんですよ。マーケティングのスタッフが、ゲームやマルチメディア系の雑誌の奥付を見ながら編集部に電話して「こんなゲームがあるんですけど、記事掲載してもらえますか」ってお願いしていたレベルでしたから。もちろん、最初はほとんど相手にされなかったんですけどね(笑)。
安藤:今となってはみなさんともに、『クーロンズ・ゲート』をきっかけにゲームに関わり続けているわけですから、人生は面白いですね。
井上:私は映像を作っていたのに、ゲームを作れといきなり言われて。じつは最初、キャラクターデザインは大友克洋さん(※3)にお願いしに行こうという話になっていました。それでこんな風にお願いしようと下絵を描いていたら、須藤さんがそれでいこうとなって。
(※3)大友克洋……日本の漫画家・映画監督。氏が手掛けたアニメーション映画『AKIRA』は、「ジャパニメーション」と呼ばれる日本国外における日本アニメムーブメントのさきがけ的な作品となった。
木村:サイバーパンクの王道だったら、大友さんにお願いしたよね。でもそうじゃないところがあったから、自前で行こうということになった。
井上:当時の僕は、設定画の描き方なんてまるで知らないので、急いでアニメイトに走りましたよ。そこで買ってきたアニメの設定集を見ながら、「こんな角度で描くんだ」って勉強したりして(苦笑)。
安藤:蓜島さんも、「ゲーム音楽」の制作自体は本作が初めてですよね?
蓜島:そうですね。この『クーロンズ・ゲート』で、始めてループの方法を教えてもらいました。
安藤:ループを多用する楽曲作りって、ゲームサウンドならではのものですよね。
蓜島:資料として送られてきた画像は、すでに世界観がしっかり出来上がっていたので、それに合わせてアジア系や民族系の楽器を使って味付けしていきました。このゲームには、環境音楽とかSEに近いニュアンスの音楽が合うなって最初から考えていたんです。でも、当時はそういう機微がわからない人も多くて、「世の役に立たない」なんて言われたものですよ。
安藤:今となっては、ゲームサウンドは「環境音中心のもの」もたくさん存在します。そういう意味でも、時代の先を行っていたんですね。

■見えないものを表現しようとしたゲーム作り
安藤:独創的なキャラクターたちはどのようにして生み出されていったんでしょうか?
井上:いくつかパターンがありますが、おもに木村さんの発注によるものですね。「なんとか男」ってつくキャラは、ほとんど木村さんのオーダーです。
木村:窓男とか、鍵穴男とかね。
井上:木村さんの中にビジュアルイメージがあるものは、キャラ設定に挿し絵が描かれていたので問題なくイメージをつかめました。ただ、キーワードだけのものは、そこからデザインを膨らませなくてはならなかったんですよ。自分のなかで「CGで制作する時にめんどうなデザインにはしない」という不文律がありましたので、できるだけシンプルなデザインを心がけました。
今でこそデザイン、モデリング、CGは別々の人間が手がけることが多いですが、当時は全部自分で作っていたもので。めんどうなことは極力しない、でも作っていて楽しいものというのを、あえてバランスを壊しながら作っていきましたね。
安藤:バランスを考えることなく吹っ切って作ったからこそ、あのような際立ったキャラが生まれたわけですね。
井上:あと、住民には牙などの武器を持たせないことにも気を付けました。彼らは昔からそこにいただけで、プレイヤーの敵というわけではない。だから、当然武器を持って襲ってくることもないんです。
蓜島:たしかに。だからあの世界は、ただそこに居るだけで心地がいいんだな。
安藤:ゲーム中にはバトルもあります。いわゆる「ロールプレイングゲームの要素」もしっかり詰め込まれているんですよね。
木村:最初はなかった要素なんですよ、バトルは。ただ、どうしても「五行思想の属性(※4)」の相克関係を使いたかったんですよ。あとアイテムを手に入れたらうれしいので、それを使って何かがしたい。戦闘というよりも、交換に近いですね。
(※4)五行思想……「万物は木・火・土・金・水の5属性の元素からなる」という、古代中国に端を発する自然哲学の思想。
井上:「アイテムバトル」と「風水バトル」の2つがあるんですけど、時代がそうさせたんだと思います。
安藤:制作期間はかなり長くなったとのことでしたが、具体的にどれくらいかかったんでしょうか?
木村:最初の計画の2.5倍くらいでしょうか。常識的に考えるとありえない延期ぶりですが、きっと当時の上長がいろいろと守ってくれていたんだろうなと(苦笑)。
安藤:制作期間がかかったのは、ゲーム開発が初めてだからでしょうか?
木村:それも大きいとは思いますが、それだけではない何かがありましたよ。武富くんが、溝に落ちた自転車のスポークをちゃんと描き込んでいる。ゲーム中では見えるわけがないのに。窓も5、6枚のテクスチャを重ねて汚してあるんです。「やっぱり、香港の窓はこうでなきゃ」ってこだわって。
安藤:ただの汚れにそこまでのこだわりがあったとは。
井上:クーロンズ・ゲートさんの言葉に従って作り続け、そろそろここでいいよと言われたから終わった感じです。お尻がなかったら、永遠に作り続けていたと思います。作り続けることができるだけのものだったんです。
安藤:独創的なキャラクターたちはどのようにして生み出されていったんでしょうか?
井上:いくつかパターンがありますが、おもに木村さんの発注によるものですね。「なんとか男」ってつくキャラは、ほとんど木村さんのオーダーです。
木村:窓男とか、鍵穴男とかね。
井上:木村さんの中にビジュアルイメージがあるものは、キャラ設定に挿し絵が描かれていたので問題なくイメージをつかめました。ただ、キーワードだけのものは、そこからデザインを膨らませなくてはならなかったんですよ。自分のなかで「CGで制作する時にめんどうなデザインにはしない」という不文律がありましたので、できるだけシンプルなデザインを心がけました。
今でこそデザイン、モデリング、CGは別々の人間が手がけることが多いですが、当時は全部自分で作っていたもので。めんどうなことは極力しない、でも作っていて楽しいものというのを、あえてバランスを壊しながら作っていきましたね。
安藤:バランスを考えることなく吹っ切って作ったからこそ、あのような際立ったキャラが生まれたわけですね。
井上:あと、住民には牙などの武器を持たせないことにも気を付けました。彼らは昔からそこにいただけで、プレイヤーの敵というわけではない。だから、当然武器を持って襲ってくることもないんです。
蓜島:たしかに。だからあの世界は、ただそこに居るだけで心地がいいんだな。
安藤:ゲーム中にはバトルもあります。いわゆる「ロールプレイングゲームの要素」もしっかり詰め込まれているんですよね。
木村:最初はなかった要素なんですよ、バトルは。ただ、どうしても「五行思想の属性(※4)」の相克関係を使いたかったんですよ。あとアイテムを手に入れたらうれしいので、それを使って何かがしたい。戦闘というよりも、交換に近いですね。
(※4)五行思想……「万物は木・火・土・金・水の5属性の元素からなる」という、古代中国に端を発する自然哲学の思想。
井上:「アイテムバトル」と「風水バトル」の2つがあるんですけど、時代がそうさせたんだと思います。
安藤:制作期間はかなり長くなったとのことでしたが、具体的にどれくらいかかったんでしょうか?
木村:最初の計画の2.5倍くらいでしょうか。常識的に考えるとありえない延期ぶりですが、きっと当時の上長がいろいろと守ってくれていたんだろうなと(苦笑)。
安藤:制作期間がかかったのは、ゲーム開発が初めてだからでしょうか?
木村:それも大きいとは思いますが、それだけではない何かがありましたよ。武富くんが、溝に落ちた自転車のスポークをちゃんと描き込んでいる。ゲーム中では見えるわけがないのに。窓も5、6枚のテクスチャを重ねて汚してあるんです。「やっぱり、香港の窓はこうでなきゃ」ってこだわって。
安藤:ただの汚れにそこまでのこだわりがあったとは。
井上:クーロンズ・ゲートさんの言葉に従って作り続け、そろそろここでいいよと言われたから終わった感じです。お尻がなかったら、永遠に作り続けていたと思います。作り続けることができるだけのものだったんです。

蓜島:むしろ、まだまだできると思うけど。井上さんのデザインは、誰にも作れない。日本だけじゃなく、世界でも展開していたら方向性も変わっていたと思いますよ。
木村:じつは、海外でもリリースしようと思って英訳も試したんですよ。でも、あの言葉のニュアンスを英語にするのはものすごく難しかった。主語を吹っ飛ばした思わせぶりなセリフが多いので、うまく訳せないんですよね。例えば宗じいさんというキャラクターがいます。兄貴にすでに会っていて、そのじいさんの弟に会ったときに「俺だよ、弟の俺だよ」といったセリフを口にするんですが、それをそのまま英訳すると「Your Brother」になってしまう。
安藤:ニュアンスが全然違いますね。では、なんと訳せばいいかというと、それも難しい。
井上:木村さんは、アクの強いセリフが多いから翻訳は難しいと思いますよ(笑)。
安藤:ゲームテキストの翻訳も、まだ確立されていない時代。本作を英訳するとなると、世界観をかなり深く理解したうえで、言葉を噛み砕いて訳す必要があります。
木村:まぁ、無理ですよね(苦笑)。
安藤:製作期間のお話に戻しますが、蓜島さんにとってはいかがでしたか? なかなか作業が終わらないな……といった感覚もあったのでは。
蓜島:常に気を張って作業していたわけではなく、ずーっと長い間ちょこちょことやっていましたよ。3カ月に1曲とかのペースで。その間、もちろんほかの仕事も受けていましたが、なんの支障もなくこなすことができました。
井上:ダンジョンを作っては蓜島さんに頼みに行き……また作っては頼みに行き、としていました。
木村:じつは、海外でもリリースしようと思って英訳も試したんですよ。でも、あの言葉のニュアンスを英語にするのはものすごく難しかった。主語を吹っ飛ばした思わせぶりなセリフが多いので、うまく訳せないんですよね。例えば宗じいさんというキャラクターがいます。兄貴にすでに会っていて、そのじいさんの弟に会ったときに「俺だよ、弟の俺だよ」といったセリフを口にするんですが、それをそのまま英訳すると「Your Brother」になってしまう。
安藤:ニュアンスが全然違いますね。では、なんと訳せばいいかというと、それも難しい。
井上:木村さんは、アクの強いセリフが多いから翻訳は難しいと思いますよ(笑)。
安藤:ゲームテキストの翻訳も、まだ確立されていない時代。本作を英訳するとなると、世界観をかなり深く理解したうえで、言葉を噛み砕いて訳す必要があります。
木村:まぁ、無理ですよね(苦笑)。
安藤:製作期間のお話に戻しますが、蓜島さんにとってはいかがでしたか? なかなか作業が終わらないな……といった感覚もあったのでは。
蓜島:常に気を張って作業していたわけではなく、ずーっと長い間ちょこちょことやっていましたよ。3カ月に1曲とかのペースで。その間、もちろんほかの仕事も受けていましたが、なんの支障もなくこなすことができました。
井上:ダンジョンを作っては蓜島さんに頼みに行き……また作っては頼みに行き、としていました。

蓜島:スパンが長いから、いろいろと考えられた。ゲーム音楽とか世界観とか、研究ができたんです。後半は音作りがうまくなってきていて、ていねいに作れていることが今聴くとわかります。より深いところに行ける感じ。ただ、当時は録音機材がよくなくて、それでマスタリングもせずに渡していました。そこに対しての悔いはありますね。
安藤:失敗談などはありますか?
木村:仕事を外部にお願いすることもあって、どうお願いしていいか分からなかったことですかね。例えば授業中に面白いことがあったとして、それを昼休みに隣のクラスの友人に伝えようとしても、なかなかニュアンスが伝わらないことってあったじゃないですか。開発にも似たようなことがあって、あの独特の空気をどう伝えたらいいのかが難しい。文化や世界観の共有が、部内にしかなかったんですよね。
井上:人を選ぶプロジェクトではありましたよね。ビジョンが共有できる人としか一緒に作れない。
木村:その空気の源みたいなものの正体が何だったのか、今もってわからないんですよ。香港を訪れたことなのかな。
安藤:まるで結界の中で作業をしていたような感じですね。そこに出入りするには資格が必要で、それを所有している人はごくわずかという。
木村:確かに。あの場には不思議な何かがあった気がします。仕様書を作っても、汎用性がないからか、外部のメンバーに伝わらないことが多くて。
井上:木村さんの仕様書は、読み取るのが難しいから(笑)。「ここはこうしてほしい」ではなくて、「ここからはあなたが考えてくださいね」というものが多かったですよね。僕はそれを楽しんでいましたよ。
木村:鍵男じゃなく鍵穴男。鍵穴なので、自分でもよくわからない。ただ漠然と「穴があるんだろうな」くらいのイメージでシナリオを書いて、あとは井上さんにお任せ。
井上:こっちとしては「穴!? そうきたか!」って感覚でした。穴から連想して、お尻をこちらに向けさせたりしてね。チャレンジする時間とお金があったからこそできた遊び心ともいえるかも。
蓜島:発想は、もはや開発というより研究だもん。
井上:正直なところ、開発の途中までは天下を取れるなという自信があったんです。あれだけのクオリティのものはそうそうありませんでしたからね。ただ、そうこうしているうちに『ファイナルファンタジーVII』が出ちゃって。あれは、その後のゲームの方向性を決定づける、まさにエポックメイキングな作品でした。あそこで我々の運命も変わってしまったかもしれません(笑)。ちなみに、安藤さんの『鈴木爆発』は、いつ頃の発売でしたっけ?
安藤:2000年ですね。『クーロンズ・ゲート』の3年後になります。まだ初代PlayStationでしたね。
井上:あれもあのころのPlayStationじゃないと出せないゲームでしたよね。
安藤:わたしが当時所属していたエニックスは、自由な作風に寄り添っていた会社でした。先輩にいろいろなことを教えてもらって、自由に攻めたゲームがおもしろいと思ったんです。事実、先輩たちも『せがれいじり』や『アストロノーカ』といったぶっ飛んだゲームを作っていましたし。
安藤:失敗談などはありますか?
木村:仕事を外部にお願いすることもあって、どうお願いしていいか分からなかったことですかね。例えば授業中に面白いことがあったとして、それを昼休みに隣のクラスの友人に伝えようとしても、なかなかニュアンスが伝わらないことってあったじゃないですか。開発にも似たようなことがあって、あの独特の空気をどう伝えたらいいのかが難しい。文化や世界観の共有が、部内にしかなかったんですよね。
井上:人を選ぶプロジェクトではありましたよね。ビジョンが共有できる人としか一緒に作れない。
木村:その空気の源みたいなものの正体が何だったのか、今もってわからないんですよ。香港を訪れたことなのかな。
安藤:まるで結界の中で作業をしていたような感じですね。そこに出入りするには資格が必要で、それを所有している人はごくわずかという。
木村:確かに。あの場には不思議な何かがあった気がします。仕様書を作っても、汎用性がないからか、外部のメンバーに伝わらないことが多くて。
井上:木村さんの仕様書は、読み取るのが難しいから(笑)。「ここはこうしてほしい」ではなくて、「ここからはあなたが考えてくださいね」というものが多かったですよね。僕はそれを楽しんでいましたよ。
木村:鍵男じゃなく鍵穴男。鍵穴なので、自分でもよくわからない。ただ漠然と「穴があるんだろうな」くらいのイメージでシナリオを書いて、あとは井上さんにお任せ。
井上:こっちとしては「穴!? そうきたか!」って感覚でした。穴から連想して、お尻をこちらに向けさせたりしてね。チャレンジする時間とお金があったからこそできた遊び心ともいえるかも。
蓜島:発想は、もはや開発というより研究だもん。
井上:正直なところ、開発の途中までは天下を取れるなという自信があったんです。あれだけのクオリティのものはそうそうありませんでしたからね。ただ、そうこうしているうちに『ファイナルファンタジーVII』が出ちゃって。あれは、その後のゲームの方向性を決定づける、まさにエポックメイキングな作品でした。あそこで我々の運命も変わってしまったかもしれません(笑)。ちなみに、安藤さんの『鈴木爆発』は、いつ頃の発売でしたっけ?
安藤:2000年ですね。『クーロンズ・ゲート』の3年後になります。まだ初代PlayStationでしたね。
井上:あれもあのころのPlayStationじゃないと出せないゲームでしたよね。
安藤:わたしが当時所属していたエニックスは、自由な作風に寄り添っていた会社でした。先輩にいろいろなことを教えてもらって、自由に攻めたゲームがおもしろいと思ったんです。事実、先輩たちも『せがれいじり』や『アストロノーカ』といったぶっ飛んだゲームを作っていましたし。

井上:あの頃に活躍していたクリエイターたちと今でもたまに話しますが、たいがい「当時はよかったよね」って話になるんですよね。
安藤:「発想の自由さ」でしのぎを削る、いい時代でした。ゲームの文法が出来上がる前の自由さは、今後しばらく……それこそ、専用ゲーム機からスマホに構造が変わった時くらいの改革が起こらなければ望めないでしょうね。
後編に続く→毎年「ファイアの日」に何かが起こる? 『クーロンズ・ゲート』開発を手掛けた木村央志×井上幸喜×蓜島邦明ロングインタビュー【後編】
CHECK!
超レアもの!? お三方のサイン入り『クーロンズ・ゲート』スペシャルディスク(体験版)をプレゼント!
安藤:「発想の自由さ」でしのぎを削る、いい時代でした。ゲームの文法が出来上がる前の自由さは、今後しばらく……それこそ、専用ゲーム機からスマホに構造が変わった時くらいの改革が起こらなければ望めないでしょうね。
後編に続く→毎年「ファイアの日」に何かが起こる? 『クーロンズ・ゲート』開発を手掛けた木村央志×井上幸喜×蓜島邦明ロングインタビュー【後編】
CHECK!
超レアもの!? お三方のサイン入り『クーロンズ・ゲート』スペシャルディスク(体験版)をプレゼント!

今回の鼎談をお読みいただいた読者のなかから抽選で1名の方に、お三方のサインが入った『クーロンズ・ゲート』のスペシャルディスクをプレゼントします。プレゼントを希望される方は、
・郵便番号
・住所
・氏名
・お電話番号
・記事を読んだ感想
を明記いただき、下記のメールアドレスまでご応募ください。
プレゼント募集メールアドレス:otayori@sisilala.tv
締め切りは2018年1月14日(日)の23時59分。当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。 みなさんのご応募をお待ちしております。
●本プレゼントの応募を通じてお客様からご提供いただきました個人情報を、本プレゼントの運営に関すること以外の目的で使用することはありません。
●当社が本プレゼントを通じて得る個人情報は、お客様のご了承をいただかない限り、第三者に開示することは一切ありません。ただし、法令等により開示を求められた場合、人の生命および身体または財産などの重大な利益を保護するために緊急を要する場合には、お客様にお断りすることなく情報開示することがあります。
テキスト:長雨(Nagasame)レトロ作品から最新アプリまで、女性向けゲームをこよなく愛するキャラ萌えライター。
そこに燃え&萌えさえあれば、どんなジャンルでも楽しむことができる生き物です。
・郵便番号
・住所
・氏名
・お電話番号
・記事を読んだ感想
を明記いただき、下記のメールアドレスまでご応募ください。
プレゼント募集メールアドレス:otayori@sisilala.tv
締め切りは2018年1月14日(日)の23時59分。当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。 みなさんのご応募をお待ちしております。
●本プレゼントの応募を通じてお客様からご提供いただきました個人情報を、本プレゼントの運営に関すること以外の目的で使用することはありません。
●当社が本プレゼントを通じて得る個人情報は、お客様のご了承をいただかない限り、第三者に開示することは一切ありません。ただし、法令等により開示を求められた場合、人の生命および身体または財産などの重大な利益を保護するために緊急を要する場合には、お客様にお断りすることなく情報開示することがあります。
テキスト:長雨(Nagasame)レトロ作品から最新アプリまで、女性向けゲームをこよなく愛するキャラ萌えライター。
そこに燃え&萌えさえあれば、どんなジャンルでも楽しむことができる生き物です。
シシララTV オリジナル記事