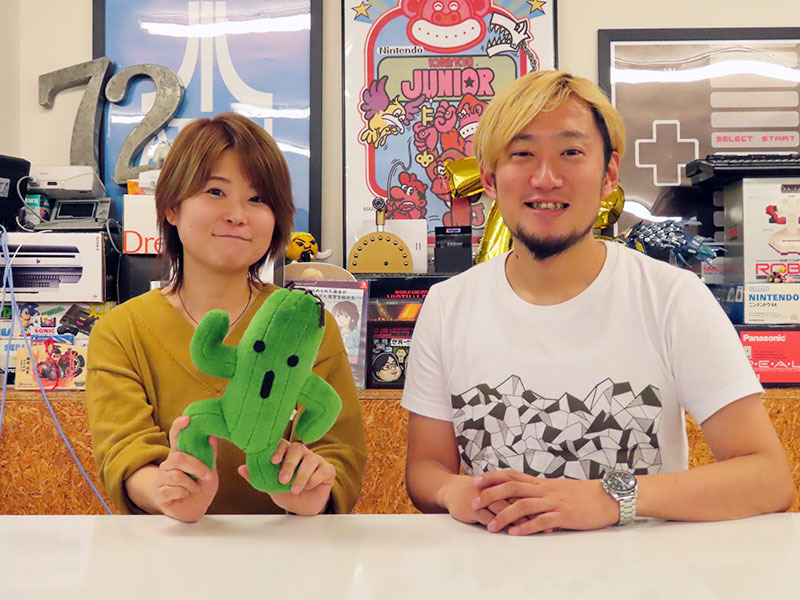「編集者とゲームプロデューサーは絶滅する。」三木一馬VS安藤武博 濃密対談(後編)
KADOKAWA/電撃文庫編集部の編集長を務め、今年の春に独立してクリエイターマネジメント企業「ストレートエッジ」を立ち上げたエンタメ業界の仕掛け人・三木一馬氏。エージェントとして『とある魔術の禁書目録』の鎌池和馬氏や『ソードアート・オンライン』の川原 礫氏などの作家陣をプロデュースする三木氏が、出版業界の最大手を辞してまで叶えたかったこととはなんなのか? 同じくゲーム業界最大手のスクウェア・エニックスを辞してシシララTVを立ち上げたゲームDJ・安藤武博がインタビューする。企画の後編である今回は、三木氏と安藤が図らずも意識を共有させた「編集者/ゲームプロデューサー絶滅論」が語られていく。
インタビュー前編はコチラ→「僕たちがKADOKAWAとスクエニを辞めた理由。」三木一馬VS安藤武博 濃密対談(前編)

▲左から安藤武博、三木一馬氏。
■三木一馬と安藤武博、それぞれの仕事の流儀
安藤:ここまでは三木さんが大手出版社を辞めた理由などについてお聞きしてきましたが、ここで三木さんのお仕事についての流儀もお聞きしたいと思います。作家さんとコミュニケーションをとる際に、心がけていることはありますか?
三木:作家さんが書いた作品を、「書いたその人よりも詳しくなってやろう」という意気込みで打ち合わせに臨むことですね。当然、実際に当人よりも詳しくなるなんてことはおこがましい話なのですが、かといって読み込みが浅く、上っ面で打ち合わせをしても、作家さんには見透かされてしまうんです。そんな編集者がいくら助言やアドバイスをしたところで、作家さんは首肯してはくれませんから。
安藤:作家さんの書いてきたものに対して、ダメ出しというか、書き直してもらったりはするんですね?
三木:ええ。僕はかなり口をはさむほうだと思います。もちろん、その人の作家性などを考慮しながらです。編集者たるもの「違う」と本当に感じてしまったのなら、どんなことをしてでも書き直してもらわなければならないと思っています。僕がとことん勉強したうえで打ち合わせに臨むのはそのためです。こちらの言い分に筋が通っていなければ、作家さんも書き直してはくれませんし、当然ながらいい作品にはなりませんから。
安藤:わたしも、毎週月曜日にさまざまなクリエイターさんをお呼びして、その方が手がけられたゲームを作り手と一緒に実況する「つくった人がゲーム実況」という番組を配信しているのですが、事前のリサーチは怠らないようにしています。これは自分が過去に遊んだことがないタイトルはもちろんのこと、すでに遊んで内容を把握している作品でもそうです。考え方は三木さんと同じで、予習、あるいは復習をしてそのゲームに対しての熱を高めておかないと、ゲストとして来てくれるクリエイターさんにも番組を見てくれているゲームファンに対しても失礼になると考えています。
三木:それは大切なことですね。
安藤:作り手として、ゲームを遊び続けなくてはいけないという意識もあります。三木さんも月に何冊もの小説をお読みになられているかと思いますが、わたしとしても、常にゲームを遊び続けていかなければ置いていかれてしまうという恐怖があります。退社・独立に不安はなかったのですが、唯一、ゲームに関する情報が入ってこなくなることは怖かった。スクエニという巨大企業に所属しているときは、入ってこない情報なんてありませんでしたから。そういう意味では、さまざまなクリエイターやゲーマーの人と交流できる実況生放送をものすごく重宝しています。生放送がHUBになって、スクエニにいたときとは違った角度で情報が入ってきますので、有意義かつ面白い。大きな会社に所属しているときは、とてもじゃないけどできなかったスタンスですね。

三木:常に最新のものを求められる、ゲームクリエイターならではのスタンスですね。その点、編集者はちょっと違っています。編集という仕事は比較的セクショナリズムというか、個人作業に依るところも多いので、横の情報ってほとんど入ってきません。名物編集者の編集必勝法は、門外不出でなかなかフリーユースとして世には出てこないんです。それはひとえに、テクノロジー勝負ではないから。電子書籍も増えているとはいえ、紙というアナログ媒体で勝負してきた産業なので、それが当たり前だったんですよね。とはいえ、これからもずっとそうであり続けることはよくないことだとも思っています。いろいろなメディアミックスを仕掛けていくとき、情報の欠落はウィークポイントになってしまうので、もう少し横の幅を広げてコミュニケーションしていければベストです。
編集者/ゲームプロデューサーは近い将来に絶滅する?
安藤:三木さんが独立してストレートエッジを立ち上げたきっかけを聞かせてもらっていいですか?
三木:これは色々なところでお話ししているんですけど、前の会社とこじれて独立したわけではありません。電撃文庫編集部って、たとえるならリードが長い鵜飼いに飼われた鵜とでもいいますか(笑)、なんなら陸の奥地から海にまで魚を取りに行ってもいいくらい、おもしろい作品を作る手段の自由度が高い編集部なんです。しかし、出版不況が叫ばれるなかで、今のままでいいのかという不安感がずっとありました。僕の中だけでの問題ではあるのですが、このまま出版に縛られていたら精神のレームダック状態……つまりトライする心が緩やかに死んでいくかもしれないと思ってしまったんです。出版社としては、これまでに培ってきたスキームは当然守らなければならない部分。作品単体に視点を向けてこれをより伸ばそうと考えたとき、媒体の戦略やイメージを重視して、出版社に寄り添う形で展開するのが今までの手法だとすれば、僕は作品そのものや作家さんそのものに寄り添うという新しい形で活動したかった。そうするためには、もう独立しかないかなと。
安藤:編集部からはかなり引き止められたのでは?
三木:そうですね……。僕としてもものすごくご恩があるので、無礼をはたらいてまで辞めていくつもりはありませんでした。普通、編集者が編集部を抜けるときって担当している作家さんも連れて行くかどうかがポイントになるんです。今回は自分がやりたいことを通すために辞めていくことになるので、作家陣もすべて置いていく形で考えていました。ただ、当時の上司にそうお話ししたら「そこまでの覚悟があるのであれば、お前が最後まで責任をとれ」と言われまして……。結果、フリー契約の編集者として一部の仕事は引き継ぎましたし、その上司にも社外取締役としてストレートエッジに参加していただいて、面倒を見てもらっています。
安藤:立場が変わって、お仕事の内容も大きく変化したのではないですか?
三木:そうですね。やるべきこと、やれることは広がりました。これまでと同様に編集者として作品に関わりつつ、同時にそのコンテンツをより一層広げていくためにはどうすべきなのか、今までと違ったアプローチでどんなことが出来るのかを常に考えて活動しています。これはありがたいことなのですが、正直、会社立ち上げから思っていた以上に仕事が忙しく、自分だけではとても回せないようになってきたので(汗)、スタッフの募集をかけたりもしています。
●作家/コンテンツに寄り添う“エージェント”としての仕事で業界改革を進める「ストレートエッジ」でお仕事をしてみたい方はコチラ
●作家/コンテンツに寄り添う“エージェント”としての仕事で業界改革を進める「ストレートエッジ」でお仕事をしてみたい方はコチラ

安藤:これまでとは違ったビジネスモデルを作り上げようとされているわけですね。苦労も多いと思いますが、発想が新しくて面白いです。昨今はゲームクリエイターにも、作家さんのように1人で作業をしてゲームを作ってしまう人が出てきました。今はまだインディーズレベルのものですが、近い将来、ゲームは集団で作るものというゲームのビジネスモデルも崩壊するかもしれません。そういった波に取り残されないようにするためにも、組織に守られて決まったルーティンをこなしていくだけではダメだと感じています。思考停止してはダメなんです。
三木:言われた仕事をこなしていくだけではもう限界ですよね。クリエイターに近しい仕事をしているとわかるのですが、「言われた仕事をこなすだけの人」は必要なくなってきています。IT化によって、いわゆる「中間職」はどんどん席を追われていくでしょう。僕としては近い将来、作家さんと編集者の関係性も変わると思っています。作家さんは自分の作りたいものを生み出し、それをうまく広げてくれそうなエージェントを自分で選べるようなシステムが構築されるかもしれません。もしくは、作家さん自身がそういったエージェントが経営する組織に所属することになるとか……そういった、クリエイターとエージェントのマッチングが重要になってくると思います。
安藤:お話を聞いていると、実際にその革命はいつ起こってもおかしくなさそうです。
三木:ただ、正直なところ、直近で今すぐに革命が起こるわけではないでしょうね。なぜなら、今はまだ雑誌やレーベルが持つブランド力が強いですから。
安藤:たとえば「電撃文庫の作品だから」という動機で購入してくれるお客さんが多い、ということですね。
三木:はい。しかしそのブランド力がなくなったとき、徐々に「この作品だから」、「このキャラだから」というところにシフトしていくでしょうし、そうなってくると雑誌やレーベルに依存していた編集者は仕事がなくなる可能性すらあります。正確には、編集者はエージェントに進化というか、変化する必要が出てくるってことですかね。

安藤:ゲームプロデューサーにも同じことがいえますね。誰もが自分で自分の作品をプロデュースできるようになったら、プロデューサーという職業はなくなるのかもしれない。事実、ディレクションもプロデュースも自分でやってしまうクリエイターは出てきていますから、あながち遠い未来というわけではないと思います。
■「原作を書いた人がゲーム実況」の構想も? 常に新しいことに挑戦し続けていく意義
安藤:先ほど、三木さんは新しい編集者の姿をエージェントという単語で表現されましたね。
三木:ええ。ただ、「エージェント」という表現が最適なのかは僕自身もわからないというか……。うさんくさく感じる人もいると思うので、何かいい名称を考えたいところではありますが(苦笑)。
安藤:それは考えたほうがよさそうですね。わたしは自ら「ゲームDJ」を名乗っていますよ。
三木:ゲームDJ! いいですよね! 安藤さんがゲームDJになったって人から聞いたときはビックリしたんですよ。「ゲームDJ? 何それ!?」って(笑)。
安藤:もはや概念のようなものなんですけど、自称というか、言った者勝ちですよね。クラブのDJというよりは、ディスクジョッキーのほうなんですけど。音楽には最近の流行から過去の名曲まで、いろいろなことを教えてくれるDJがいるじゃないですか。そろそろゲームにも、そんな存在が必要とされているのではと考え、だったら自分がその役割を担おうということでゲームDJを自称しました。
三木:素敵ですよ、その名前。すごく覚えやすいですし。
安藤:現在は、視聴者の方にも「DJ」って呼ばれたりしていて。番組でゲームを紹介することで「そんなゲームがあったなんて知らなかった」「番組きっかけで購入した」などと言われたりすると、ゲームDJ冥利に尽きますね。新しいことはもちろんなんですが、温故知新も大切にしながら色々なことを仕掛けていきたいと考えています。
三木:じつに安藤さんらしい仕事のスタンスだと思います。
安藤:DJっていうとどうしてもクラブの印象が先行して、ちょっとチャラいイメージもあるかもしれません。でも、楽しげな雰囲気は伝わるのかなと。何より響きがカッコ悪くてそこが覚えやすい。そしてそんな人間が三木さんのようなエンタメの最前線に立っている人と真面目に対談をし、情報を発信していくというギャップも面白い。既存のライターさんや編集者さんでは聞き出せないようなお話を聞き出していくというのも、ゲームDJとしての役割。わたしがスクエニを辞めると言い出したとき、こんな仕事をすることになると想像していた人は1人としていなかったと思うんですが、自分としては最初から明確にコンセプトを決めて取り組んでいるので、してやったり感はあります。
三木:じゃあ、僕もエージェントDJを名乗りますか。
安藤:いいですね! DJ、流行るといいなぁ(笑)。
三木:(笑)。実際のところ、僕が担当している作家さんたちにもゲーム好きな方はたくさんいますので、対談とか、それらの作品のゲームの実況とか、安藤さんに取り上げてもらいたいです。いかがですか、「原作を書いた人がゲーム実況」とか。
安藤:最高じゃないですか。近いうちにぜひお願いします! 三木さんには、「エンタメ業界採用セミナー」の生配信でもお世話になりましたし、一緒に組ませていただくと、色々な広がりがあって面白いです。
三木:僕自身、そういった手を取りあうことでより広がりが出てきそうな方々とは、積極的にお仕事をさせてもらいたいと思っていますので、こちらこそぜひよろしくお願いします。

安藤:三木さんも同じことを考えてくれているとうれしいのですが、面白いことをするために、未来を広げていくために、お互い大手企業を辞めて新しい事業を立ち上げた。我々にしかできない化学反応を生み出せる手ごたえを、対談させてもらって如実に感じて、とても刺激を受けています。ちなみに、会社名を「ストレートエッジ」とした理由も教えてもらえますか?
三木:公式サイトなどには「定規」としての意味を定義しています。作家さん、そしてコンテンツをしっかりとまっすぐに導いていく、直定規(ガイドライン)のような存在でありたいと考えています。
安藤:その口ぶりですと、何か裏テーマのようなものもありそうですね?
三木:ええ……じつは裏テーマがあります。1970年代のニューヨークで「マイナー・スレット」というハードコアバンドが活動していたんですけど、彼らが提唱していたのがまさに「ストレートエッジ」だったんですよ。これはその当時、ライブハウスにドラッグが蔓延していたり、アルコールやセックスに興じて音楽を全然楽しんでいないファンたちに打ち出した「ノードラッグ、ノードランク、ノーセックス」の精神なんです。
安藤:ドラッグや酒やセックスに興じていないで、まっすぐに音楽を楽しめということですね。
三木:はい。そして提唱した真意としてもう一つ、「同調圧力への反抗」という意味もあったんです。ただ、それはあまりに影響力が強くなりすぎて、ファンの暴走によってカルト化してしまいましたが……。ともあれ、ストレートエッジとは、貧困階級のカウンターカルチャーとでもいいますか、周囲を巻き込んで下から突き上げていくという精神なんですね。それにあやかって社名にさせてもらっています。「どこまでもストレートエッジに頑張ろう」と(笑)。ただ、凶暴な側面が前に出過ぎるのもどうかと思うので、あくまで裏のテーマにしています。

安藤:会社を立ち上げてみていかがですか。ベンチャーならではの身軽さや苦労話があると思うのですが、やはり楽しいのでは?
三木:そうですね。これまでは、たとえば「こんな施策をやりたい」と提案しても、各部署の役割分担などのいろんな“しがらみ”でやりたいことをMAXでやることは叶わなかったのですが、そういったことがなくなったので楽しいです。
安藤:わかります。それは「大企業病」とでもいうべきものなんですが、じつは会社が大きければ大きいほど避けられない部分なんですよね。小回りが利かない。大手企業の管理職ともなると、ムダだと思っているような会議にも毎週必ず出席しなくてはいけなかったりして、わたしにとっても大きなストレスでしたから、三木さんのお気持ちはよくわかります。
三木:一方で、自由になった反面、作家さんの成長戦略もより考えていかなければなりませんので、これまで以上に気を遣うべき部分も増えました。編集者とエージェントの一番大きな違いは、そうやって作家さんに寄り添う距離感の近さだと思っているので、作家さんお一人ごとにかける労力自体は電撃文庫編集部にいたときより増えています。
安藤:それをずっと1人で続けていくのは不可能ですよ。早く後進を育てていかないと。ちなみに、三木さんがそばに置きたい人材ってどんな人になるのでしょう?
三木:人として最低限のコミュニケーション能力は必要ですが、最終的には三木一馬という存在ですら超えていくぞっていう気概を持った人が第一ですね。セミナーでも口にしたことなんですけど「この人気作品に携わりたいから」という既存作品への憧れが動機になるのではなく、「あっと驚くような作品を手掛けてみたい」という、新しいものを作り続けることができる人を求めています。最初からスキルがなくてもいいんです。そこは教えることができます。ただ、最終的には作家さんと目標を同じくし、手を取り合って共闘できる人が必要なんです。安藤さん、どなたかご存知ないですかね?(笑)
安藤:三木さんからおいしいところを全部吸い出してやろうってくらいの気概を持った人ってことですよね……うーん、難しい。構造的には、そういう人はこないんじゃないかとも思います。なぜなら、もしそんな人がいたら、自分で別の会社を立ち上げているような気がしますので(笑)。
三木:それはおっしゃる通りかと。でも、ゲームクリエイターもそうだと思いますが、編集者やエージェントには何よりも行動力、そしてハングリー精神が必要ではないでしょうか。

安藤:今は週刊少年ジャンプがまだブランドとして強い。スクエニや電撃文庫も今はそうでしょう。ただ、それがずっと続いていくとは限らない。編集者、ゲームプロデューサーという職業自体がなくなるかもしれないという危機感。三木さんとわたしが、図らずも2人ともその可能性を感じているというのはものすごく興味深いことです。とはいえ、大きな企業の中で頑張り続けなければいけない人もいると思うんですよね。家族を守らなければならない人とか。
三木:もちろんです。そういう人たちは、大きな会社にいるからこそできることをやっていくこと、やり続けていくことが大切ですよね。
安藤:我々のような小さなベンチャー企業が小回りを利かせてこなせることもあれば、大企業でしかできないような横綱相撲だってある。そうやっていいもの、楽しいものを作り続けていくことが何よりも重要。
三木:そうですね。それだけは、いつの時代も変わらない根幹としてあり続けると思います。
安藤:これからのエンターテイメント業界を生き抜いていくための、生存戦略をお聞きできました。とても面白かったです。本日はありがとうございました!
●作家/コンテンツに寄り添う“エージェント”としての仕事で業界改革を進める「ストレートエッジ」でお仕事をしてみたい方はコチラ
シシララTV オリジナル記事