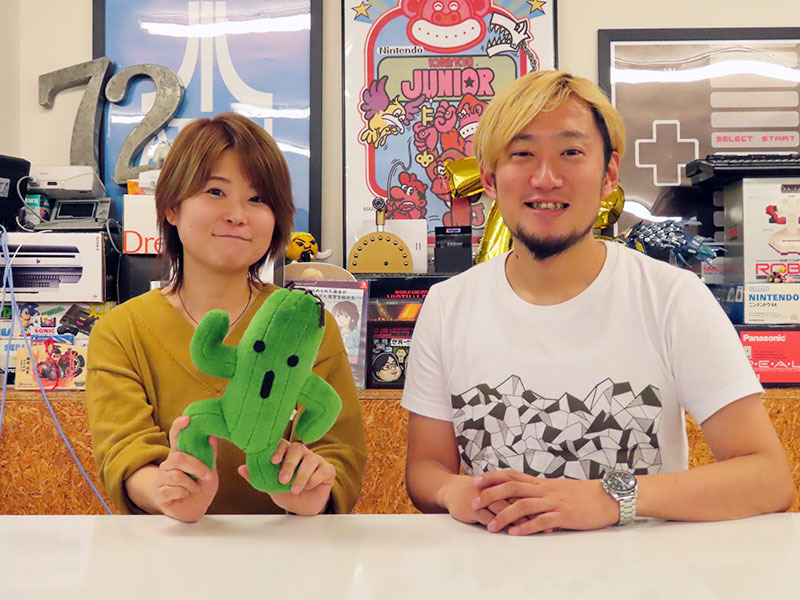売れるゲームと面白いゲーム…『激突!クラッシュファイト』終了から見るゲーム開発現場の最前線【〇〇サービス終了 – 後編】
始まりがあれば終わりもある。昨今、多くのゲームアプリが華やかにリリースされていくなか、その陰に隠れてサービス終了タイトルも日を追うごとに増加。ヒットの法則にはタイミングと運が付きものだが、クオリティの高さと期待度とは裏腹に、なかなかヒットに結びつかないことも数多い。
本企画「〇〇サービス終了 –開発現場から愛をこめて-」では、ゲームDJ・安藤武博がサービス終了に直面した開発・運営者たちに真っ向から話をうかがい、当時の状況や後世に活かすノウハウなど、ほかでは聞けない話題を展開していく。
第3回は、ポケラボの『激突!クラッシュファイト』。6人で大乱闘を繰り広げるリアルタイムアクションゲームの本作は、2016年6月にオープンβテスト(OBT)を開始し、意欲的な作品として注目されていた。しかし、そのOBTの結果を踏まえて「ユーザーに満足してもらうためのサービス提供が困難である」との結論に至り、正式サービスを迎える前に敢え無く終了となったのだ。
対談企画では、本作のプロジェクトマネージャー・信田郁氏が登場。現在の心境や終了する経緯など赤裸々に迫ってみた。
【前編プレイバック】
・サービス終了を決断したふたつの理由
・スマホゲームの作り直し期間について
前編の記事はこちら→正式サービスを迎える前に終了…ポケラボ『激突!クラッシュファイト』が下した決断【〇〇サービス終了 – 前編】
■『激突!クラッシュファイト』とは
第3回は、ポケラボの『激突!クラッシュファイト』。6人で大乱闘を繰り広げるリアルタイムアクションゲームの本作は、2016年6月にオープンβテスト(OBT)を開始し、意欲的な作品として注目されていた。しかし、そのOBTの結果を踏まえて「ユーザーに満足してもらうためのサービス提供が困難である」との結論に至り、正式サービスを迎える前に敢え無く終了となったのだ。
対談企画では、本作のプロジェクトマネージャー・信田郁氏が登場。現在の心境や終了する経緯など赤裸々に迫ってみた。
【前編プレイバック】
・サービス終了を決断したふたつの理由
・スマホゲームの作り直し期間について
前編の記事はこちら→正式サービスを迎える前に終了…ポケラボ『激突!クラッシュファイト』が下した決断【〇〇サービス終了 – 前編】
■『激突!クラッシュファイト』とは

リリース日:iOS版-、Android™版(オープンβテスト)2016年6月29日
サービス終了日:2016年9月30日
本作は、6人で大乱闘を繰り広げるリアルタイムアクションゲーム。バトルの時間は2分間と、隙間時間に気軽にプレイできるのが特徴。操作方法は非常に簡単で、3Dモデルのちびキャラをひっぱり操作で相手にぶつけて、場外にふっとばすだけ。与えたダメージと場外にふっとばした回数をもとに得点がつき、バトル終了時の得点で勝敗を競っていく。
バトルでは、爆弾や竜巻など行動を妨害するトラップや、巨大化、無敵になれるアイテムなどが出現。また、チームを組んで闘うバトルや、全参加者が敵となるバトルロイヤル、友達といつでも対戦できるプライベートバトルといった多彩な遊び方が用意されていた。
サービス終了日:2016年9月30日
本作は、6人で大乱闘を繰り広げるリアルタイムアクションゲーム。バトルの時間は2分間と、隙間時間に気軽にプレイできるのが特徴。操作方法は非常に簡単で、3Dモデルのちびキャラをひっぱり操作で相手にぶつけて、場外にふっとばすだけ。与えたダメージと場外にふっとばした回数をもとに得点がつき、バトル終了時の得点で勝敗を競っていく。
バトルでは、爆弾や竜巻など行動を妨害するトラップや、巨大化、無敵になれるアイテムなどが出現。また、チームを組んで闘うバトルや、全参加者が敵となるバトルロイヤル、友達といつでも対戦できるプライベートバトルといった多彩な遊び方が用意されていた。


■ユーザーから寄せられたネガティブな意見とは

ゲスト:信田 郁
ゲーム業界歴約13年。2004年より主にオンラインゲームの開発運用を経験し、ポケラボ入社後は、スマホアプリの開発に携わる。『激突!クラッシュファイト』では、プロジェクトマネージャーを担当。
ゲーム業界歴約13年。2004年より主にオンラインゲームの開発運用を経験し、ポケラボ入社後は、スマホアプリの開発に携わる。『激突!クラッシュファイト』では、プロジェクトマネージャーを担当。

聞き手:安藤 武博
過去スクウェア・エニックスにて、1998年からコンシューマーゲームやスマートフォンゲーム事業に携わる。スマホ事業ではF2P/売り切り型を問わず『拡散性ミリオンアーサー』や『ケイオスリングス』など、複数のヒット作を生み出す。2015年に株式会社シシララを設立。ゲームDJとしての活動をスタートさせる。最新作は『コスモスリングス』(AppleWatch)と『ブレイジング オデッセイ』(iOS/Android )。
過去スクウェア・エニックスにて、1998年からコンシューマーゲームやスマートフォンゲーム事業に携わる。スマホ事業ではF2P/売り切り型を問わず『拡散性ミリオンアーサー』や『ケイオスリングス』など、複数のヒット作を生み出す。2015年に株式会社シシララを設立。ゲームDJとしての活動をスタートさせる。最新作は『コスモスリングス』(AppleWatch)と『ブレイジング オデッセイ』(iOS/Android )。
安藤:我々の番組でコンセプトが実現できたとおっしゃっていましたが、OBTのアンケートでは想定とは異なる意見が寄せられたということでしょうか。
信田:どちらかというと、ポジティブな意見は7割ぐらいでした。内容も「スカッとする」「吹き飛ばしが気持ちいい」など、爽快感に関する内容が多かったです。ネガティブな意見は3割ぐらいでしたが、その内容はどれも一緒でした。
安藤:それは興味深かいですね。どういう部分がネガティブだったのでしょうか。
信田:操作性です。
安藤:そうなんですね。引っ張るだけの操作で、簡単なうえに奥深いゲームだと思ったのですが、そこが伝わらなかったと。
信田:ええ。出来る限りそうしたつもりでしたが、その面白さまで伝えることが出来なかったのです。
安藤:それは、何でなんでしょう。敵にぶつけて吹っ飛ばす本作の遊びは、めちゃくちゃ分かりやすいものです。『モンスト』もそれで大ヒットしているわけで、加えて対戦の部分は『スマブラ』(大乱闘スマッシュブラザーズ)的なアプローチで、至極分かりやすいと思うけどなぁ。
信田:恐らく引っ張って移動するというそれだけのことが、すでに難しいんだと思います。あとは「自分がやりたい感覚と違う」という意見も多かったですね。コントローラーでちょっと微調整して右に動きたいみたいなものが出来ないので。
安藤:まさに『スマブラ』のように操作したいと。でも、それとは違いますもんね。
信田:そうですね。その操作性とは違うところから始めてしまいましたが、「『スマブラ』と同じような感覚で遊べる引っ張り操作を生み出せよ」という世の中のオーダーもあったのかもしれません。
安藤:いま振り返ると、何か解決案はありますか。
信田:こればかりは分からないですね。
安藤:難しいですよね。シンプルな操作を求めている人もいれば、ガッツリした操作を求めている人もいる。『クラッシュファイト』はどちらに振っているのですか。
信田:どちらかというと、簡単よりにしたかったです。それに結構簡単に作ったほうなのですが、まだ操作性が難しいと思う人たちがいたのは、かなり予想外の出来事でした。
安藤:本当に引っ張ってぶつけるぐらいのことじゃダメなのかな。それを解決できるアイデアはどこかにあるんでしょうけど、今の段階ではまた次回作以降か…。とても難しい……この話はまさにゲームデザインの真髄だな。
信田:個人的には、あまりアクション要素を入れてもダメだと思っています。むしろ入れた時点で当初のコンセプトからズレてしまいます。
安藤:引っ張って、移動する、もうこの2アクションが難しいと思われてしまう。1アクションで全てが出来るように、“なんちゃって操作”でもいいから感じさせるように作らないとダメだったのかな。
信田:恐らくそういう要望だったのかもしれません。
安藤:たしかに。『パズドラ』だってスライドさせるだけだし、『モンスト』だって引っ張るだけ。そこだけ見るとメガヒットタイトルは、実は1アクションしかしていない説はある。ただ、その一方で『シャドウバース』など本格的なトレーディングカードゲームもヒットしています。それ以外にもかなり複雑な操作を要求するタイトルも受け入れられていますね。
先ほどおっしゃった通り『クラッシュファイト』は、ライト向けに手掛けられているからこそ、POPで万人ウケを狙ったタイトル、ロゴのデザイン、キャラクターデザインだと思います。逆に壮大な世界観でゴリゴリのコア向けに持っていくことは考えなかったのですか。
信田:ええ。あくまでも簡単な方向に振り切ろうとしていました。
安藤:なるほど。僕はどちらかというと、ライトなゲームを作った経験があまりない。前にいた会社の性質がそうだというのもありますが、いまだにライトなものでスクエニはヒットタイトルが少ないんですよね。
たとえば、『クラッシュファイト』の場合はゲームの体験自体がタイトルになっている。“激突”して、“クラッシュ”して、“ファイト”してとか。その一方で“オペラオムニア”や“ブレイブエクスヴィアス”、“シャドウバース”などゲームの世界観やかっこいい響きがタイトルになっているものもあります。
仮に僕がプロデュースするならば、ちょっと雰囲気のあるタイトルを付けて、キャラクターの等身を少し上げて、戦う理由を背負わせつつ、世界設定も7つの世界があって、ダンテの神曲みたいな感じで地獄巡りしていき、それぞれを司る魔人たちをぶつけて壊していく……。そういう感じで色づけてして売っていくのが、僕がプロデューサーとして得意とするところです。ただ、今回はそれをやめて老若男女でも遊べるようにしている。
僕から見ると「そんなところまで削ぎ落とすのか」というぐらいに、ライト向けにしていますが、実際に信田さん自身ライト向けに作ってみて、いかがでしたか。世界観に頼れない難しさなどもあると思います。

信田:じつは『クラッシュファイト』を企画していた当時、会社としての命題が、これまで手掛けてきた20VS20のゴリゴリの情報量が多いGvGを簡単にしよう、というものでした。
安藤:『運命のクランバトル』、『栄光のガーディアンバトル』、『戦乱のサムライキングダム』などポケラボのプレゼンスをグッと上げたタイトルたちですよね。
信田:はい。そこから簡単にできるようなGvGで新しい文脈を作っていきたいねというところまで戻ったのです。
安藤:売れたけど、「これ難しいよね」という話題がポケラボ社内であったわけですね。
信田:ええ。そのときに考えたのが、“ファミコンのゲームがなぜ楽しかったのか”という考えです。簡単だけど、難しくて、でも熱狂して。
安藤:思えば昔のゲームっぽいですよね。雰囲気とか破壊というキーワードもどこか『アイスクライマー』のようです。
信田:そうです、イメージしています。ただ実際には破壊部分は消えてしまいました。
安藤:吹っ飛ばす感じで『スマブラ』ライクになりましたけど、『アイスクライマー』の氷をガンガン割る感じのような破壊要素はあってもいいのかなと。一方で『アイスクライマー』の時代ってそもそもファミコンが爆発的な社会現象になっていたので、次にカセット差したら何が出てくるのかというワクワクがあったので、あまり世界観がなくても、ある程度は良かったですね。
でも、今はそうじゃない。ほかに可処分時間を潰す、かつ暇つぶしできるエンターテイメントがタダでいっぱいある時代のなかで、『アイスクライマー』の新作を出しても難しいわけです。
信田:『アイスクライマー』をはじめ、昔のゲームが与えてくれた体験というのは、友達同士で集まって遊ぶ、あの空間が何より楽しかったのです。どのゲームもコミュニケーションツールとして発揮しており、現実の我々に置き換えても、やはりそこがトリガーになるのかもしれません。
安藤:シンプルなものを提供して、そこから遊んだ後の体験があれば価値に繋がっていると。だから体験のデザインになっているのですね。ちなみに今でしたら世界観をどういうふうに変えたいなどはありますか。
信田:テレビみたいにしたいですね。テレビのチャンネルみたいに、何かの番組を見たいとき、適当に変えていったら違う世界にどんどん切り替わっていくという。
安藤:それは『スマブラ』とはまた違う感じですね。オールスター戦ではなくて、パラレルワールドのように戦国時代やハイファンタジーなど切り替わっていく形ですか。
信田:ええ。それこそゲーム内では、アントニオ猪木やガンダムなど様々な人物・キャラクターを出したかったです。ただ振り返ってみると、世界観の軸を決めないまま走り続けてデザインしていることになるので、結果的にものすごくブレるかもしれません。UIデザインにも影響するので、統一感がなくなるのはさすがに良くないと。
安藤:コラボも含めて色々な作品が参戦しやすい地場を作るのは、運営をする上で大事な要素です。仮に僕がプロデュースするのであれば、最初に「本作はこういう世界を構成している」という器を作ったと思います。それがいつの間にか、体験のデザインのほうが主軸になって……いやぁ面白いです。ゲーム作りの深いところです。
■PMとプロデューサー 双方で求められる役割
信田:じつは、今日はせっかくの機会なので、いくつか安藤さんに聞きたいことがあって質問事項にまとめてきました。おもに僕自身が悩んでいることです。
安藤:なるほど。どういう質問ですか。
信田:最初に企画を立てる時の話です。
ゲーム作りには、投資回収や開発工数などの実現性を加味した条件面と、純粋な面白さ、どちらの側面からも考えなければいけないと思います。
たとえば僕は、「これは絶対面白いんだ!でもどうやって採算とるか、実現できるかは全然わからない」と考える一方、「これは採算とれそうで実現もできそうだ、でもありきたり、ウリがない、二番煎じ感が強いなど面白そうに感じられない」といったケースでグルグルすることが多いと感じています。
今回の『クラッシュファイト』ではお金や制限になってしまいがちでした。そうなるとゲームが面白いかよりも、その工数で作りきれるかどうかの判断が優先軸にあるんですよ。それだとモノづくりとして良くないですし、でも工数も考えないとそもそもプロジェクトは破綻しますし……。
安藤:恐らく今回の信田さんの立場としては、プロデューサーであり、PM(プロジェクトマネージャー)なのだと思います。やはり理想の開発現場は、プロデューサー、ディレクター、PMがいることです。もっというと、プロデューサーがお祭りを起こすときに、事務作業も膨大にあるので、そこにアシスタントプロデューサーが付いているなど、その四枚岩がいいですね。
スクエニの場合は外部にディレクターを置く場合が多く、社内にはPMとプロデューサーとアシスタントプロデューサーが中心にプロジェクトを動かしていました。これだけ揃うといい感じに機能するのですが、通常はアシスタントやPMがいないことも多い。そうなるとプロデューサーがそれらを兼務しなければなりません。業務量が増えれば、それだけゲームを盛り上がる施策も減ってしまったり、苦しくなると会社に「リリースを伸ばしてほしい」と言い続けるプロデューサーになってしまったりします。
ですので、信田さんは、役職はPMかもしれませんが、立ち位置としてプロデューサーも兼務していたことになります。
信田:なるほど。でも今思えば私はPMの役割ばかりに集中してしまい、事実上プロデューサーの役割が不在だったのかもしれません。
安藤:そうですね。典型的なプロデューサー不在プロジェクトだと思います。僕は生粋のプロデューサーですが、今日これまで話してきた「足らない要素」「売れるための施策」などは、全部僕のようなプロデューサーの仕事ですから(笑)。
信田:なるほど(笑)。
安藤:明快に言ってしまえば、プロデューサーがいないからこそ、こういうことになったのですね。今回プロデューサーの重要性が出てきましたが、では、次回作以降はどういう感じに携わっていきたいですか。信田さん自身は、今後、PMなのか、プロデューサーなのか、それともディレクターなのか。

信田:僕はプロデューサーになりたいと考えています。得意不得意で分けたとき、得意はPMかもしれませんが、好きはプロデューサーです。ディレクターと一緒にゲームの根幹となる部分を話し合ったり、手掛けたものをより多くの人に届けたり、いろんな方とも出会ったりと考えを深めていきたいと思います。
安藤:今回のプロジェクトでは、ある意味、信田プロデューサー誕生のきっかけになったのかもしれませんね。プロデューサーがいなかったからこそ流行らなかった…というのが分かった点においては、とても有意義なプロジェクトだったのではないでしょうか。
モノの力だけで売れるのは黎明期ぐらいだと思います。例えばコンシューマーゲームは、ハードという仕組みが家庭に入ってくるそれ自体がすごく面白かった。ファミコンなんかは、ゲーセンなど外でお金払ってやっていたものが、1万円ちょっとで家でもできるようになった。カセットを入れ替えれば色々なゲームも遊べたし、その体験自体が面白いから、今となっては何でこれが100万本売れたのか分からないものも売れたりした時代でしたね。
信田:そうですね。
安藤:その後、ROMの容量が大きくなって、ゲームデータを翌日以降に持ち越せるようになりました。そこから物語性やキャラクターデザインなどが表現できるようになり、『ドラゴンクエスト』が社会現象になった。同じくして大ヒットを記録したのがスクウェアの初期のゲームたちです。厳密にいうと、当時のスクウェアもプロデューサー不在。ディレクターが中心に制作して、考えて、戦闘システムを編み出して、たとえプロデューサーがいなくてもモノがいいからミリオンセラーになる。
こうした移り変わりはコンシューマーゲームにもあったのですが、いよいよスマホゲームもその段階に入ってきている。とくにスマホゲームのほうは重症。何故なら、ゲームのバラエティの幅がとても狭いのです。マネタイズの影響もあると思うのですが、遊びの幅を大きく分けると5、6種類ぐらい。お客様からすれば、みんな似たようなゲームばかりですし、そこで差別化するためには仕掛けが絶対必要になってくる。
ソシャゲバブルのときは、同じものを作っても売れましたけど、ネイティブシフトになってからはもうそういう状態じゃないですし、やはりプロデューサーの存在感は増してきているのかなと思います。信田さんがプロデューサーになりたいのも分かります。
信田:プロデューサーでしたら、人の動かし方や自分のやりたいことを人に伝える力も重要なのかなと思うのです。
安藤:そうですね。これに関しては何か悩みがあったのですか。
信田:直近では、プレゼン中にあまり自信がないと思われていることです。たとえば、色々な人の意見を聞いたときに、僕の性格上、「たしかにそうですね」と企画の段階からなってしまい、よく上司からは「お前の軸はどこなんだよ」と言われることもあります。
安藤:打ち合わせや会議は、「ここは現場に踏ん張ってほしいところ」「ここは出席者みんなの意見を寄せ集めるところ」とふたつに分かれると思います。
たとえば、踏ん張るようなそぶりが見えないから、偉い人は「この人に多額の予算とスタッフを与えていいのだろうか」と不安に感じるのでしょう。ただ、信田さんのアプローチも正しくて、色々な人の意見を聞いて「お前面白くないよ」という場所を作るのも大事です。
ヒット作を手がけた後は、ときに“その人がつくるもの=すごいゲーム”みたいな感じになってしまうことがあるんですよね。言わば裸の王様になりがちなんですね。
“あの人は別枠”という扱いになってしまうと、自信を持って手掛けているものでも、ほかの人の意見を聞かずにアウトプットして結局ズレてしまうんですね。だからこそ、「ちょっとイケてなかったら気軽に言ってくれよ」という環境を作るのは大事。これは信田さんがメガヒットメーカーになっても、崩すべきではないところです。
信田:はい。
安藤:一方で、ゲームの投資を判断する会議では、お金を出す人たちは大金なので内心ドキドキしているわけですよ。売れるときは売れるし、売れないときは売れない。どんなヒットメーカーでも外すときは外す。
だからこそ、つくる前から色々想定して、偉い人の前で「僕の作品は売れます」と言い切るのは難しいと思います。ただ、Aさん、Bさん、ふたりのクリエイターがいたときに、Aさんが「絶対売れる。俺に任せろ」というのと、Bさんが「いやぁ、まあ当たるときは当たりますし…」となったとき、お金を出す人はどっちに出したいかということです。
Aの場合は、突っ張って会議通したけど課題満載だから一個ずつ潰していこうぜと現場に下ろしていく感じです。少なくても僕はこっちの人間でした。「売れるかどうかは分からない」なんて一言もいったことないですし、何なら「売れるに決まっているじゃないですか。俺が作るんですよ?」ぐらいの話をしていました。
当然、そこに至るまでは定量的なデータをもとに説明しますが、最終的には気合と自信の問題。ここはハッキリと「面白いゲームができる」と言わないと、ドキドキしてお金を出す偉い人たちも張れないと思います。
信田:なるほど。おっしゃるとおりだと思います。
安藤:正直なところ、やってみないと分からないところは多分にありますし、その本質は経営陣も分かっていると思います。それでも偉い人の前では、ガン攻めされて「そうですね。考え直します。」というふうになることが多い。そうならないためには、普段から徹底してそのプロジェクトのことを考えて、想定している問答を全部頭に叩き込んで、ネガティブな意見も含めて、最悪のケースを想定しながら臨むことが大事です。
信田:じつは現在、新作の企画について経営陣と4回ほど話し合いをしています。「もっとこうした方がいいんじゃない?」という提案に対して、自分の考えをうまく表現できなかったり、実現性の面からできないと切り出してしまうこともあり、自信をもって話せていないとみられる場面が多くありました。
安藤:考え抜くことも必要ですね。会議って面白くて、「こんなの売れない」「やめておけ」と言われるなかでも、「いや絶対売れる」という問答を繰り返していると、「もう分からん。お前が売れると言うんだったらやったらいい」と、ずっと止めていたにも関わらず、最終的に「やれ!」ってなることがあるんですね。新規で1位を取ることが目標であれば、初めてのことだから理詰めで来られても最終的に「初めてなので一回俺に賭けてください」というしかないのです。
それに会議で反対されたプロジェクトほど、成功するという法則はある。逆に偉い人全員が「これは鉄板だから売れるよね」というプロジェクト自体は、失敗するケースが多い。予定調和すぎるものはお客様を良い意味で裏切れない。むしろ誰かが異物感を抱くくらいがちょうど良いのです。ですから企画を突き返されたときは、「おぉ、反対意見が来た来た!」とチャンスだと思うほうがいいです。むしろ何も言われずスムーズに通るほうが心配になる。
そういう意味では、信田さんの次回作はヒットの流れがきているのかもしれません。だからこそ偉い人も気になるんでしょう。このタイトルに関しては“しつこく言ったほうがいいんじゃないか”という匂いがあるのだと思います。失敗した人のほうが、すごい果実が手に入るものです。
それを経て信田さんの次回作はどういうものになるのでしょうか。まだまだ話せないところもあると思いますが、構想だけでも聞かせてくれませんか。
信田:スマホゲームを作るのは変わらないです。日常や体験のほうがしっくりくるので、たとえIPタイトルを手掛けるうえでも、お客様が持っている思い出をきちんと掘り起こせるような体験を与えるのが大事だと考えています。内容は簡単かつ手軽にしていきます。
安藤:簡単、手軽、すごく大事だと思います。当然コントローラーで遊べるゲームには、なかなか勝てない部分もあると思います。携帯電話をゲーム機としてみる見方も当然あるのですが、じつはもっと手軽に楽しめるほうが、すごく広がるのではないのかなと。
スマホゲームはもっと簡単でもいいのかも。結局ソーシャルゲームの発明も、コンシューマで考えさせることを、考えさせずに省力してすっ飛ばしたというところが発明だった。これまでのゲームであれば、バトルシステムにはからなず駆け引きやすくみがあったなかで、ガシャーンとぶつかっただけでバトルが終了する。なんならぶつかる前から勝ち負けの演算が決まっているという衝撃的なゲームデザインでした。
近い将来、ゲームだけど、もはや見ているだけでも楽しいじゃんという時代になるのかもしれません。そのくらいの視点を持ちながらやらないと厳しいのかなと思います。
信田:恐らくスマホゲームでいうと、やはり簡単・手軽な部分はゲームコアになると思います。また、サイクルの部分で少し発明が必要になってくるのかもしれません。
安藤:というと?
信田:リアルと絡めるなどゲーム内外で継続してもらうための、“流れ”を作る必要があると思っています。リアルで1週間後に大会があるから頑張ろうみたいな、ゲーム内のみならずゲーム外で継続を促すような施策ですね。
安藤:いいですね。平日はゲーム内で練習、休日はリアルで大会。
信田:そうですね。どんどんゲーム外の継続率の伸ばし方は絶対あると思っています。ゲームは1プレイ数分以内に終わるのですが、サイクルのところでどんどん広がり、継続していくようなものを作っていくというイメージがありますね。
安藤:面白い。それは、最初に言っていたe-sports的な大会をしておけばよかったという話と、まさに繋がりますね。
信田:ええ、そうですね。
安藤:……さて、そろそろお時間も迫ってきましたので、最後の質問をさせていただきます。OBTとはいえ、『クラッシュファイト』をやり込んでいる方も多くいました。ぜひ、お客様に向けてメッセージをお願いします。
信田:まずは期間中遊んでいただいた方、本当にありがとうございました。正式サービスまでたどり着けなかったことは、大変申し訳なく思っていますが、正直なところあまり悲観的にはなっていません。
僕自身としては短い時間ではありましたが、お客様と一緒にプレイできたことが、ひとつひとつの体験として思い出みたいに残っています。遊んでいただいた方のなかに、ひとりでも「あのとき楽しかったね」と言ってもらればとても嬉しいと思います。僕もまたそんなゲーム作りをしていきます。
ポケラボでは一丸突破をスローガンに、各プロジェクトの振り返りを横展開し、よりよいゲーム作りができるよう取り組んでいます。今後も様々なタイトルの準備をしておりますので、ぜひご期待ください!
■ポケラボ
企業サイト
安藤:信田さんの新作は、いつぐらいですかね?
信田:1年~1年半以内には出したいですね。
安藤:楽しみにしています。本日はありがとうございました!
【〇〇サービス終了 バックナンバー】
・第1回『冒険クイズキングダム』
・第2回『ガーディアン・クルス』
・第3回『激突!クラッシュファイト』
テキスト:原孝則(Takanori Hara)
Pick UPs! 代表 / 編集者 / ライター / APPアナリスト 過去、ゲーム会社でマーケティング、広報、WEBプランナーなど多数のPR業務に従事。その後、Social Game Info 副編集長、Social VR Info 編集長を担当。現在は、ゲームとビジネスの観点で執筆・企画に尽力するほか、アプリデータ分析サービス「Sp!cemart」の編集長も兼務。
ツイッターアカウント→原 孝則@ha_tatsu
Pick UPs! 代表 / 編集者 / ライター / APPアナリスト 過去、ゲーム会社でマーケティング、広報、WEBプランナーなど多数のPR業務に従事。その後、Social Game Info 副編集長、Social VR Info 編集長を担当。現在は、ゲームとビジネスの観点で執筆・企画に尽力するほか、アプリデータ分析サービス「Sp!cemart」の編集長も兼務。
ツイッターアカウント→原 孝則@ha_tatsu
シシララTV オリジナル記事