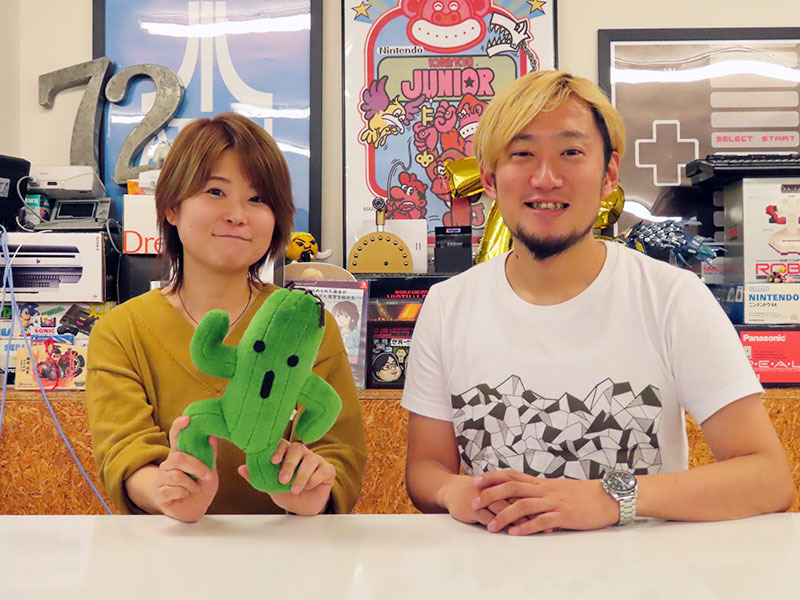スーパーアプリ若手クリエイターインタビュー(前編):クリエイターはゲームを作ることでしか救われない
名古屋に拠点を置き、『ライバルアリーナVS』などの人気ソーシャルゲームを多数世に送り出している気鋭の開発会社・スーパーアプリ。昨年の秋に東京オフィスも開設され、今後さらなる飛躍が期待されるこの気鋭の会社の主要スタッフに、ゲームDJ・安藤武博が鋭く切り込むインタビュー企画。第一弾は代表取締役である飯沼正樹氏に、第二弾ではその右腕でありブレーンである石橋広在氏に、今求められているクリエイター像などをうかがってきた。
そしてインタビュー企画の第三弾では、そんなスーパーアプリを引っ張る、若きゲームクリエイター10人にお集まりいただき、ゲーム作りへの情熱から自身がクリエイターを志すに至る原点となったゲームについて、お話をうかがった。

インタビュー時間90分超、文字数約25,000と、過去最多のボリュームとなったこの第三弾。前編では、おもに企画チーム、運営チーム、そしてプログラムチームの面々にうかがったお話をまとめていく。なお今回の記事では、若手クリエイターたちの名前を頭文字のアルファベットで表記している。
・スーパーアプリ vs 安藤武博 対談インタビュー企画
第一弾:気鋭のゲーム開発会社「スーパーアプリ」が求める未来とは? 社長の飯沼正樹氏に訊く
第二弾:「フリートゥプレイ」の先駆者が電撃移籍! スーパーアプリ・石橋氏が語る「変化と挑戦」
第一弾:気鋭のゲーム開発会社「スーパーアプリ」が求める未来とは? 社長の飯沼正樹氏に訊く
第二弾:「フリートゥプレイ」の先駆者が電撃移籍! スーパーアプリ・石橋氏が語る「変化と挑戦」
■自らの原点となった「大切なゲーム」から紐解くクリエイターの人物像
安藤武博(以下、安藤):今日はスーパーアプリを今まさに牽引し、そしてこれからを担っていくであろう若手スタッフ10名にお集まりいただき、さまざまなお話をお聞きしていきたいと思っています。では、まずはW.Nさんから順番に、自己紹介と自分が担当しているお仕事、そして人生においてすごく印象に残っているゲームについて教えてもらえますか。
W.Nさん:わかりました。印象に残っているゲームについてもお話しするんですね?
安藤:ええ。その人が好きなゲームを聞くことで、直感的にその人物の人となりがわかりますから。それは長い時間をかけてお話しをお聞きするのと同じくらい濃密な情報になると思うので、ぜひ教えてください。
W.N:承知しました。ではあらためまして、ゲームの開発部門に所属しておりますW.Nです。現在は新しいプロジェクトの立ち上げ……すごくモヤっとしているところをみんなで手探りで作っているところです。人生の1本は、『マジック:ザ・ギャザリング』になりますね。TVゲームじゃなくてごめんなさい。
安藤:いえいえ。W.Nさん、カードゲーマーだったんですね。かなりのやり手なんですか?
W.N:どうでしょう……一時期はプロを目指してやっていましたけどね。残念ながら、今は仕事が忙しくてほとんどプレイしていないんですけど、僕にとってのゲームの原点は『マジック:ザ・ギャザリング』だといえます。誰にも負けたくなかったからですね。『マジック:ザ・ギャザリング』に関しては。
安藤:プレイヤースキルがものすごく要求されるものですし、負けず嫌いなプレイヤーさんは多そうです。学生時代にプレイしていた感じででしょうか?
W.N:ええ。ただ、学生時代は金銭的にキツくなって一度プレイを諦めまして。スーパーアプリで働きはじめてから、あらためて再チャレンジしてみたんです。ただ、上位に辿り着くのはやっぱり難しかったわけですけど(苦笑)。
安藤:大会に出場されたりもしたのでしょうか? 差し支えなければ、どのような成績を収めていたのかも教えてもらえます?
W.N:地区大会で2番くらいでした。正直、全然強いほうではありませんでしたね。
安藤:地区大会とはいえ、2番というのはスゴいでしょう。かなり頑張ってるほうだと思います。もっと誇ってくださいね。では、続きまして……。
W.Nさん:わかりました。印象に残っているゲームについてもお話しするんですね?
安藤:ええ。その人が好きなゲームを聞くことで、直感的にその人物の人となりがわかりますから。それは長い時間をかけてお話しをお聞きするのと同じくらい濃密な情報になると思うので、ぜひ教えてください。
W.N:承知しました。ではあらためまして、ゲームの開発部門に所属しておりますW.Nです。現在は新しいプロジェクトの立ち上げ……すごくモヤっとしているところをみんなで手探りで作っているところです。人生の1本は、『マジック:ザ・ギャザリング』になりますね。TVゲームじゃなくてごめんなさい。
安藤:いえいえ。W.Nさん、カードゲーマーだったんですね。かなりのやり手なんですか?
W.N:どうでしょう……一時期はプロを目指してやっていましたけどね。残念ながら、今は仕事が忙しくてほとんどプレイしていないんですけど、僕にとってのゲームの原点は『マジック:ザ・ギャザリング』だといえます。誰にも負けたくなかったからですね。『マジック:ザ・ギャザリング』に関しては。
安藤:プレイヤースキルがものすごく要求されるものですし、負けず嫌いなプレイヤーさんは多そうです。学生時代にプレイしていた感じででしょうか?
W.N:ええ。ただ、学生時代は金銭的にキツくなって一度プレイを諦めまして。スーパーアプリで働きはじめてから、あらためて再チャレンジしてみたんです。ただ、上位に辿り着くのはやっぱり難しかったわけですけど(苦笑)。
安藤:大会に出場されたりもしたのでしょうか? 差し支えなければ、どのような成績を収めていたのかも教えてもらえます?
W.N:地区大会で2番くらいでした。正直、全然強いほうではありませんでしたね。
安藤:地区大会とはいえ、2番というのはスゴいでしょう。かなり頑張ってるほうだと思います。もっと誇ってくださいね。では、続きまして……。

K.Yさん:各種アプリの運営を担当しているK.Yです。印象に残っているゲームは、幼少期でいえば『ファイナルファンタジーVI』、大人になった今では、すごく直近のタイトルですけど『ペルソナ5』でしょうか。
安藤:なるほど、RPGがお好きなんですね。
W.N:あれ、K.Yさん『鉄拳』じゃないんですか?
K.Y:『鉄拳』はね……なんだろう。印象に残っているというか、生活の一部なので(笑)。
安藤:おお、ほかの人からタイトルが出るくらい『鉄拳』をやっているわけですね。たしかに、見た目からして格ゲーが上手そうですよね。プロゲーマー感があります。
K.Y:いえいえ、そこまで上手ではないですよ。
安藤:そうですか? よくうちの番組に来てくれている、プロゲーマーのふ~ど君なんかと同じ匂いを感じましたけど……。
K.Y:ありがとうございます。でも、匂いだけです(笑)。
安藤:わりとピリピリしたタイトルというか、ゲームセンターが好きそうな雰囲気もありますね。
K.Y:大好きですね、ピリピリ感。今もゲームセンターにはちょくちょく顔を出しています。
安藤:それに加えて『FFVI』に『ペルソナ5』となると、わりと世界設定やキャラクターがドライブしているRPGも好きということでしょうか。幼少期のタイトルに『FFVI』を挙げる時点で、なかなか若いなと思ってしまいました。
K.Y:『FFVI』を触ったのは、まだ小学生の時でしたね。その頃から、世界観に浸れるゲームが好きでした。それは今も変わっていませんね。
安藤:なるほど。では、次の方お願いします。
S.Tさん:運営チームに所属しております、S.Tです。人生のゲームは『バイオハザード』と『ファイナルファンタジーIV』、そして『風来のシレン』ですね。『バイオハザード』は『4』にめちゃくちゃハマって、いまだに実況動画なんかも見ちゃうくらい好きです。
安藤:『バイオ』も『FF』も4作目がお好きとのですが、これは偶然ですか?(笑)
S.T:『FF』は『III』も遊んでいましたけど、スーパーファミコンで『IV』を遊んだとき、ストーリーがあまりにもスキなく完成されていて、「あ、『FF』ってすごいなっ」て思ったんです。
安藤:『IV』のストーリーがお好きであると。時田さん(※1)が喜びますね。もしかして、『ライブ・ア・ライブ』や『クロノトリガー』もお好きですか?
(※1)時田さん:スクウェア・エニックスに所属している時田貴司さん。『半熟英雄』シリーズに『ファイナルファンタジーIV』、『ライブ・ア・ライブ』や『クロノ・トリガー』など、数々の名作RPGを手掛けてこられたレジェンドクリエイターの1人。
S.T:2本とも遊んでいました!
安藤:なるほど。作り込まれたストーリーものも好きだし、『バイオ4』みたいなやり込み部分が深いアクションゲームもお好きだということですね。
S.T:そうですね。
安藤:加えて『シレン』のような、底なし沼みたいなゲームもお好きだと……かなりゴリゴリのゲーマーじゃないですか!
S.T:いや、自分ではライトゲーマーの代表だと思っています(笑)。
安藤:S.Tさんの中で、ライトゲーマーというものの基準がどこにあるのかわかりませんけど、一般的に見たらかなりのゲーマーに属すると思いますよ(笑)。では、続いて……。
I.Jさん:I.Jです。『ライバルアリーナVS』のユーザーインターフェイスのデザインを担当しています。
安藤:UIデザイナーなんですね。では、人生の中で影響を受けたお気に入りのゲームについても教えてください。
I.J:僕、けっこう変わったゲームが好きでして、ドリームキャストで出た『ROOMMANIA(ルーマニア)#203』というゲームが大好きなんです。
安藤:まさかの『ルーマニア#203』! これはアツいタイトルが出てきましたね。じつは、わたしもかなり好きなゲームですけど、ここで「ネジ タイヘイ」とか言っても、誰も知らないのでは?(笑) ジャンル分けしようとすること自体がナンセンスというか、あの時代特有のバカゲーですよね。
安藤:なるほど、RPGがお好きなんですね。
W.N:あれ、K.Yさん『鉄拳』じゃないんですか?
K.Y:『鉄拳』はね……なんだろう。印象に残っているというか、生活の一部なので(笑)。
安藤:おお、ほかの人からタイトルが出るくらい『鉄拳』をやっているわけですね。たしかに、見た目からして格ゲーが上手そうですよね。プロゲーマー感があります。
K.Y:いえいえ、そこまで上手ではないですよ。
安藤:そうですか? よくうちの番組に来てくれている、プロゲーマーのふ~ど君なんかと同じ匂いを感じましたけど……。
K.Y:ありがとうございます。でも、匂いだけです(笑)。
安藤:わりとピリピリしたタイトルというか、ゲームセンターが好きそうな雰囲気もありますね。
K.Y:大好きですね、ピリピリ感。今もゲームセンターにはちょくちょく顔を出しています。
安藤:それに加えて『FFVI』に『ペルソナ5』となると、わりと世界設定やキャラクターがドライブしているRPGも好きということでしょうか。幼少期のタイトルに『FFVI』を挙げる時点で、なかなか若いなと思ってしまいました。
K.Y:『FFVI』を触ったのは、まだ小学生の時でしたね。その頃から、世界観に浸れるゲームが好きでした。それは今も変わっていませんね。
安藤:なるほど。では、次の方お願いします。
S.Tさん:運営チームに所属しております、S.Tです。人生のゲームは『バイオハザード』と『ファイナルファンタジーIV』、そして『風来のシレン』ですね。『バイオハザード』は『4』にめちゃくちゃハマって、いまだに実況動画なんかも見ちゃうくらい好きです。
安藤:『バイオ』も『FF』も4作目がお好きとのですが、これは偶然ですか?(笑)
S.T:『FF』は『III』も遊んでいましたけど、スーパーファミコンで『IV』を遊んだとき、ストーリーがあまりにもスキなく完成されていて、「あ、『FF』ってすごいなっ」て思ったんです。
安藤:『IV』のストーリーがお好きであると。時田さん(※1)が喜びますね。もしかして、『ライブ・ア・ライブ』や『クロノトリガー』もお好きですか?
(※1)時田さん:スクウェア・エニックスに所属している時田貴司さん。『半熟英雄』シリーズに『ファイナルファンタジーIV』、『ライブ・ア・ライブ』や『クロノ・トリガー』など、数々の名作RPGを手掛けてこられたレジェンドクリエイターの1人。
S.T:2本とも遊んでいました!
安藤:なるほど。作り込まれたストーリーものも好きだし、『バイオ4』みたいなやり込み部分が深いアクションゲームもお好きだということですね。
S.T:そうですね。
安藤:加えて『シレン』のような、底なし沼みたいなゲームもお好きだと……かなりゴリゴリのゲーマーじゃないですか!
S.T:いや、自分ではライトゲーマーの代表だと思っています(笑)。
安藤:S.Tさんの中で、ライトゲーマーというものの基準がどこにあるのかわかりませんけど、一般的に見たらかなりのゲーマーに属すると思いますよ(笑)。では、続いて……。
I.Jさん:I.Jです。『ライバルアリーナVS』のユーザーインターフェイスのデザインを担当しています。
安藤:UIデザイナーなんですね。では、人生の中で影響を受けたお気に入りのゲームについても教えてください。
I.J:僕、けっこう変わったゲームが好きでして、ドリームキャストで出た『ROOMMANIA(ルーマニア)#203』というゲームが大好きなんです。
安藤:まさかの『ルーマニア#203』! これはアツいタイトルが出てきましたね。じつは、わたしもかなり好きなゲームですけど、ここで「ネジ タイヘイ」とか言っても、誰も知らないのでは?(笑) ジャンル分けしようとすること自体がナンセンスというか、あの時代特有のバカゲーですよね。

I.J:ええ。なんのことはない、マンションの1室で暮らす住人・ネジ タイヘイを見守るだけのゲームなんですけど。気になるところをクリックしていくことで、ネジ タイヘイがそれに興味を持って、結果、物語が変化していくんですよね。
安藤:そうですね。密室劇というか……ええ、密室劇ですよね、それ以上に適切な言葉がなかなか見つからない(笑)。じつはあれ、予算制限に立ち向かったのがすごく透けて見えるというか、203号室でしかイベントが起こらないんですよね。たった1部屋で完結していて、でもなぜか引きつけられてしまう。
I.J:そうですね。とくになんの萌え要素もなく、1人のすごい平凡な大学生を追うというストーリーなんですけど、時々すごく不思議な物語が展開したりもして、とにかくハマってしまったんです。
安藤:言われてみると、I.Jさんは若干「ネジ タイヘイ感」があるかも。素朴で普通の青年に見えるというか……。でも、ゲームデザインとしてはとても参考になる作品でした。こんなに自由にゲームをデザインしてもいいんだ、ってあらためて納得したタイトルでしたね。すごくコアなファンが多いこともうなずけます。
I.J:そうですね。それが僕の人生の1本です。
安藤:ありがとうございます。では、次の方にいってみましょう。
M.Kさん:M.Kです。今のお仕事は開発と運営の両方で、サーバーのプログラムやインフラを見ていたりします。『カルドセプト』や『カオスシード』みたいに、変わったシステムのゲームが好きです。あとは、シシララTVさんでもやっていた『サイキックフォース』がものすごく好きで、大会にも出ていました。名古屋の大会で1回しか優勝できませんでしたけど。
安藤:1回しかって……1回でも優勝するというのは、かなりスゴいことですよ!
M.K:全国大会では、1回だけなんとか予選を突破できたぐらいなので、そこまでスゴいわけでは……(苦笑)。
安藤:シシララTVでは『カオスシード』もピックアップしたことがありますよ。ここにおられる中で、『カオスシード』を知っている方はいますか? ものすごくユニークなゲームなので、ぜひやってみてください。チュートリアルだけで3時間ぐらいかかりますけど(笑)。ちなみにMさんは、『カルドセプト』はどのバージョンが好きですか? 僕はドリームキャスト版がすごく好きなんです。
M.K:僕が一番遊んだのもドリームキャスト版ですね。
安藤:わたしは『カルドセプト』の対戦ですごく盛り上がっていたクチなんですけど、今考えてみると、あの独特の雰囲気は『ライバルアリーナVS』にも通じるものがある気がしますね。孤高というか、硬派なイメージといいますか、一言では表現しづらいのですが。
M.K:ええ、でもわかる気がします。自分が関わっているからどうかはわかりませんが、似た雰囲気はあるかもしれませんね。
安藤:『カルドセプト』はそのうちスマホにも出てきそうですよね。では、次の方お願いします。
安藤:そうですね。密室劇というか……ええ、密室劇ですよね、それ以上に適切な言葉がなかなか見つからない(笑)。じつはあれ、予算制限に立ち向かったのがすごく透けて見えるというか、203号室でしかイベントが起こらないんですよね。たった1部屋で完結していて、でもなぜか引きつけられてしまう。
I.J:そうですね。とくになんの萌え要素もなく、1人のすごい平凡な大学生を追うというストーリーなんですけど、時々すごく不思議な物語が展開したりもして、とにかくハマってしまったんです。
安藤:言われてみると、I.Jさんは若干「ネジ タイヘイ感」があるかも。素朴で普通の青年に見えるというか……。でも、ゲームデザインとしてはとても参考になる作品でした。こんなに自由にゲームをデザインしてもいいんだ、ってあらためて納得したタイトルでしたね。すごくコアなファンが多いこともうなずけます。
I.J:そうですね。それが僕の人生の1本です。
安藤:ありがとうございます。では、次の方にいってみましょう。
M.Kさん:M.Kです。今のお仕事は開発と運営の両方で、サーバーのプログラムやインフラを見ていたりします。『カルドセプト』や『カオスシード』みたいに、変わったシステムのゲームが好きです。あとは、シシララTVさんでもやっていた『サイキックフォース』がものすごく好きで、大会にも出ていました。名古屋の大会で1回しか優勝できませんでしたけど。
安藤:1回しかって……1回でも優勝するというのは、かなりスゴいことですよ!
M.K:全国大会では、1回だけなんとか予選を突破できたぐらいなので、そこまでスゴいわけでは……(苦笑)。
安藤:シシララTVでは『カオスシード』もピックアップしたことがありますよ。ここにおられる中で、『カオスシード』を知っている方はいますか? ものすごくユニークなゲームなので、ぜひやってみてください。チュートリアルだけで3時間ぐらいかかりますけど(笑)。ちなみにMさんは、『カルドセプト』はどのバージョンが好きですか? 僕はドリームキャスト版がすごく好きなんです。
M.K:僕が一番遊んだのもドリームキャスト版ですね。
安藤:わたしは『カルドセプト』の対戦ですごく盛り上がっていたクチなんですけど、今考えてみると、あの独特の雰囲気は『ライバルアリーナVS』にも通じるものがある気がしますね。孤高というか、硬派なイメージといいますか、一言では表現しづらいのですが。
M.K:ええ、でもわかる気がします。自分が関わっているからどうかはわかりませんが、似た雰囲気はあるかもしれませんね。
安藤:『カルドセプト』はそのうちスマホにも出てきそうですよね。では、次の方お願いします。

O.Mさん:O.Mと申します。『ライバルアリーナVS』のプログラムを担当しています。
安藤:O.Mさんが『ライバルアリーナVS』のあれこれをプログラムして動かしているんですね。
O.M:そうですね、概ね自分で動かしています。あとは社内のライブラリ関係とか、そういったフロント側のことをもやっています。人生に影響を受けたゲームは、セガの『バーチャロン』シリーズです。専門学生のときにみんなでワイワイとプレイしていたんですけど、そのとき一緒に遊んでいた人と結婚したくらいですから。
安藤:えーっ! ゲーマーにとって、そんなに幸せなことってあるんですね!
O.M:そうなんです。文字通り、あれは人生を変えてしまったゲームです(笑)。
安藤:ちなみにどちらから告白したんですか?
O.M:奥さんから告白されました。
安藤:それはすごい! ネットゲームをきっかけに結婚したという夫婦は見かけることも多いですけど、アクションゲーム……それも『バーチャロン』きっかけというのはなかなかないですよね。
O.M:そんなにコミュニケーションを取るようなゲームではありませんからね。もちろん、ゲームとしても大好きなタイトルなんですよ。「自分がロボットを操縦している」って感覚がスゴいじゃないですか。
安藤:安心しますよね、あの作り込まれたインターフェイス。
O.M:ハイスピードなゲーム性といい、ロボットのかっこよさとか外連味(けれんみ)みたいなものもぜんぶ入っていて、あそこまで完成度の高いゲームはなかなかないと思います。
安藤:スーパーアプリの若手クリエイターには『鉄拳』や『サイキックフォース』、そして『バーチャロン』といった対戦格闘ゲームが好きな人が多いんですね。だからこそ『ライバルアリーナVS』も、まるで格ゲーのようなプレイ感覚があるんだなと今自分のなかで納得できました。敗北したときの落ち込み具合とか、本当に格闘ゲームのそれですよね。
O.M:安藤さんのおっしゃるとおり、『ライバルアリーナVS』の、バトルが終わったあとの虚脱感というか、疲労度合いは格ゲーに近いものがあると思います。
安藤:似たようなゲーム性である『シャドウバース』には、不思議とそういうプレイ体験はないように思えるんですよね。それは、見た目はよく似ているかもしれないけれど、遊びとしては全然違うものになっているって証拠だと思います。その理由がなんなのかずっと考えていたんですが、やっぱり根本的なところに格ゲーのテイストがあるなんですね。作っている人の趣味趣向がにじみ出るものなんだな、って。
O.M:そうですね。集中して戦って、最後は一撃で仕留めるって部分は格闘技に通じるものがあると感じます。いかに相手のメンタルを折るかっていうのも大切ですからね。
安藤:わかります。シシララTVで番組をやったとき、プロゲーマーのふ~ど君を呼んだのは、まさにそこの手合いを見せて欲しかったからなんですよ。勝負には負けてしまったんですけど、やっぱり踏み込み方が鋭くて。相手の喉元へ一気にナイフの切っ先を突きつけるような感覚は、ちょっとアサシンみたいで怖かったくらいです。そういうのを実現できるゲーム性をなぜ作り上げることができたのか……その理由の一端を垣間見られました。格闘ゲーム『ザ・キング・オブ・ファイターズ』シリーズとのコラボも実現しましたが、すごく相性がいい組み合わせだったのではないでしょうか。
安藤:O.Mさんが『ライバルアリーナVS』のあれこれをプログラムして動かしているんですね。
O.M:そうですね、概ね自分で動かしています。あとは社内のライブラリ関係とか、そういったフロント側のことをもやっています。人生に影響を受けたゲームは、セガの『バーチャロン』シリーズです。専門学生のときにみんなでワイワイとプレイしていたんですけど、そのとき一緒に遊んでいた人と結婚したくらいですから。
安藤:えーっ! ゲーマーにとって、そんなに幸せなことってあるんですね!
O.M:そうなんです。文字通り、あれは人生を変えてしまったゲームです(笑)。
安藤:ちなみにどちらから告白したんですか?
O.M:奥さんから告白されました。
安藤:それはすごい! ネットゲームをきっかけに結婚したという夫婦は見かけることも多いですけど、アクションゲーム……それも『バーチャロン』きっかけというのはなかなかないですよね。
O.M:そんなにコミュニケーションを取るようなゲームではありませんからね。もちろん、ゲームとしても大好きなタイトルなんですよ。「自分がロボットを操縦している」って感覚がスゴいじゃないですか。
安藤:安心しますよね、あの作り込まれたインターフェイス。
O.M:ハイスピードなゲーム性といい、ロボットのかっこよさとか外連味(けれんみ)みたいなものもぜんぶ入っていて、あそこまで完成度の高いゲームはなかなかないと思います。
安藤:スーパーアプリの若手クリエイターには『鉄拳』や『サイキックフォース』、そして『バーチャロン』といった対戦格闘ゲームが好きな人が多いんですね。だからこそ『ライバルアリーナVS』も、まるで格ゲーのようなプレイ感覚があるんだなと今自分のなかで納得できました。敗北したときの落ち込み具合とか、本当に格闘ゲームのそれですよね。
O.M:安藤さんのおっしゃるとおり、『ライバルアリーナVS』の、バトルが終わったあとの虚脱感というか、疲労度合いは格ゲーに近いものがあると思います。
安藤:似たようなゲーム性である『シャドウバース』には、不思議とそういうプレイ体験はないように思えるんですよね。それは、見た目はよく似ているかもしれないけれど、遊びとしては全然違うものになっているって証拠だと思います。その理由がなんなのかずっと考えていたんですが、やっぱり根本的なところに格ゲーのテイストがあるなんですね。作っている人の趣味趣向がにじみ出るものなんだな、って。
O.M:そうですね。集中して戦って、最後は一撃で仕留めるって部分は格闘技に通じるものがあると感じます。いかに相手のメンタルを折るかっていうのも大切ですからね。
安藤:わかります。シシララTVで番組をやったとき、プロゲーマーのふ~ど君を呼んだのは、まさにそこの手合いを見せて欲しかったからなんですよ。勝負には負けてしまったんですけど、やっぱり踏み込み方が鋭くて。相手の喉元へ一気にナイフの切っ先を突きつけるような感覚は、ちょっとアサシンみたいで怖かったくらいです。そういうのを実現できるゲーム性をなぜ作り上げることができたのか……その理由の一端を垣間見られました。格闘ゲーム『ザ・キング・オブ・ファイターズ』シリーズとのコラボも実現しましたが、すごく相性がいい組み合わせだったのではないでしょうか。

▲『ライバルアリーナVS』は、先日『ザ・キング・オブ・ファイターズ』とのコラボも実現(※現在このコラボは終了しています)。
O.M:ちなみに、プログラマーとして一番ショックを受けたのは、セガの『ファンタシースター』でした。うちは兄弟の仲があまりよくなくて(苦笑)、兄が『ドラゴンクエスト』をやっているのを見て、「だったら僕はセガに行こう」と思い、メガドライブをお年玉で買ったんです。それで『ファンタシースター』を遊んだんですが、まず音がぜんぜん違うんですよね。ゲームサウンドがものすごくキレイで。戦闘もフルアニメーションでしたし、3Dのダンジョンもアニメーションしていて、とにかく新鮮でした。あと主人公が女の子っていうのもめずらしくて。「あ、こんなにスゴいものがあるんだ」ってショックを受けて、それからはずっとセガが大好きです。
安藤:セガが時代を先取りしまくっていた時代ですね。O.Mさんご自身には、そういったセガ魂みたいなものはありますか? 時代を先取りしてやろう……的な。
O.M:他人がやっていると興味を失うみたいな部分はありますね。人がやっていないことをやってやろうとか、そういうあまのじゃくな考えが自分の中にあります。
安藤:興味深いですね。たとえば『ライバルアリーナVS』でいえば、どういったところに「これは誰もやっていないだろう」とか「これはずっとやってみたかったことなんだよ」って要素を盛り込まれているのでしょうか?
O.M:『ライバルアリーナVS』に関しては、しっかりとシステムを構築しなければならないゲームなので、そういったあまのじゃくな部分は封印して真面目に作っていますね(笑)。そういう意味では、以前担当していた『神殺しの暗黒騎士』に関しては、開発スタッフみんなでいろいろなネタを出しあって、好き放題にやっていました。
安藤:O.Mさんのところまできて、いよいよトークがドライブしてきましたね。では、その『暗黒騎士』時代にやったこと、チャレンジしたことを教えてください。
O.M:スーパーアプリの作品ではじめて、バトルにアニメーションを取り入れたんですけど。勝手にエフェクト増やしてどんどん見た目を派手にしたり、デザイナーさんがくれた素材をプログラミングで勝手に動かしたりとか、まぁたくさんありますね……。
安藤:ああ、プログラマーが勝手に動かすパターンですね。超攻撃型というか、わりと受け身というよりは積極的に攻め込む形で作り込んでいく感じなのでは?
O.M:そうですね。「やっていいと言われたら、とことんやっちゃう」ところはあります。
安藤:そういう部分をチームとして共有できるというのは、スーパーアプリならではといえるのではないですか? 会社やチームによっては、仕様を決める前に勝手にやらないでもらえますか……みたいなところもあります。一方、スーパーアプリに関して言えば、「やる」ぶんには何も言われない……むしろやらないほうが怒られるというか「なんでやらないの?」みたいな空気があるように思えます。
W.N:おっしゃるとおり、スーパーアプリ全体にそういう雰囲気はありますね。そこら辺は、代表取締役である飯沼(※2)から影響を受けている部分も大きいですね。
(※2)スーパーアプリの代表取締役である飯沼さんと、ゲームDJ安藤武博の対談はこちらを参照のこと。
安藤:おお、まさに飯沼イズムなんですね。
W.N:社内の色々な場所に「全員で協力してやっていこうぜ!」ってポスターが貼ってあるんですけど。
安藤:それって社内の標語みたいな?
W.N:標語というか、目標というか。感動を創造していく循環モデルというものがあって、それは誰か1人がイニシアティブをとって「こうしなくてはならない!」と断ずるものではない、というのが根底にあるんです。全員が全員で、出来ることを最大限にやっていくというか。
安藤:セガが時代を先取りしまくっていた時代ですね。O.Mさんご自身には、そういったセガ魂みたいなものはありますか? 時代を先取りしてやろう……的な。
O.M:他人がやっていると興味を失うみたいな部分はありますね。人がやっていないことをやってやろうとか、そういうあまのじゃくな考えが自分の中にあります。
安藤:興味深いですね。たとえば『ライバルアリーナVS』でいえば、どういったところに「これは誰もやっていないだろう」とか「これはずっとやってみたかったことなんだよ」って要素を盛り込まれているのでしょうか?
O.M:『ライバルアリーナVS』に関しては、しっかりとシステムを構築しなければならないゲームなので、そういったあまのじゃくな部分は封印して真面目に作っていますね(笑)。そういう意味では、以前担当していた『神殺しの暗黒騎士』に関しては、開発スタッフみんなでいろいろなネタを出しあって、好き放題にやっていました。
安藤:O.Mさんのところまできて、いよいよトークがドライブしてきましたね。では、その『暗黒騎士』時代にやったこと、チャレンジしたことを教えてください。
O.M:スーパーアプリの作品ではじめて、バトルにアニメーションを取り入れたんですけど。勝手にエフェクト増やしてどんどん見た目を派手にしたり、デザイナーさんがくれた素材をプログラミングで勝手に動かしたりとか、まぁたくさんありますね……。
安藤:ああ、プログラマーが勝手に動かすパターンですね。超攻撃型というか、わりと受け身というよりは積極的に攻め込む形で作り込んでいく感じなのでは?
O.M:そうですね。「やっていいと言われたら、とことんやっちゃう」ところはあります。
安藤:そういう部分をチームとして共有できるというのは、スーパーアプリならではといえるのではないですか? 会社やチームによっては、仕様を決める前に勝手にやらないでもらえますか……みたいなところもあります。一方、スーパーアプリに関して言えば、「やる」ぶんには何も言われない……むしろやらないほうが怒られるというか「なんでやらないの?」みたいな空気があるように思えます。
W.N:おっしゃるとおり、スーパーアプリ全体にそういう雰囲気はありますね。そこら辺は、代表取締役である飯沼(※2)から影響を受けている部分も大きいですね。
(※2)スーパーアプリの代表取締役である飯沼さんと、ゲームDJ安藤武博の対談はこちらを参照のこと。
安藤:おお、まさに飯沼イズムなんですね。
W.N:社内の色々な場所に「全員で協力してやっていこうぜ!」ってポスターが貼ってあるんですけど。
安藤:それって社内の標語みたいな?
W.N:標語というか、目標というか。感動を創造していく循環モデルというものがあって、それは誰か1人がイニシアティブをとって「こうしなくてはならない!」と断ずるものではない、というのが根底にあるんです。全員が全員で、出来ることを最大限にやっていくというか。

安藤:なるほど。それはスタッフ全員に根付いているものなのでしょうか? たとえばI.Jさん、今すぐにその循環モデルについて説明してもらうことってできますか?
I.J:僕が一番感じるのは、固定観念にとらわれ過ぎず、みんなで意見し合うってところですかね。じつは、循環システムだと意識していなくても、そういうことが自然にできることがありまして。たとえば『ライバルアリーナVS』の企画を今井さんたちに投げたとき、「これはいいアイデアですね」と採用されたりします。その時、そこで終わりになるのではなく、「このアイデアを生かすんだったら、ここをこうすればもっと面白くなるよね」みたいな、「次はどうしたらいいのか」ってところまでを、またチームみんなで考えていける環境なんですよ。言葉にするとなかなか伝わりにくいかもしれませんが……。
安藤:いえいえ。ものすごく肌感覚で伝わってきましたよ。誰かが言ったことを飲み込んで、それを消化したうえで新たなアイデアを吐き出す……まさに感動を創造するための循環システムですね。
I.J:それぞれが好きなようにやらせてもらえているからこそ、って部分はあるかもしれませんね。僕の場合は、言われたものを作る際に、仕様のとおりに作ったものに加えて、自分のアイデアを盛り込んだ、仕様とは少し異なるパターンも作ることがあります。それを採用してもらえることもありますし、もちろん仕様の通りに進むことも多いんですけど、スーパーアプリの社風として、そういうモノづくりが出来る環境になっていると思います。
安藤:ライブ感あふれる制作環境なんですね。予定調和というよりは、こんなことをやってみたんだけどどう? って。それを受けて、「わかった。そっちがそう来るんだったら、俺はこういくよ」といった感じで、みんながアイデアを持ち出しつつ作り上げていくというのは、なかなか刺激的な現場だと思います。ゲーム作りってわりとカチッとしているというか、じつは設計図どおりに組み立てていく側面も強い。その点、スーパーアプリさんのモノ作りって、そもそもの構造図がしっかりしていると思うんですよ。地盤がしっかりと作られているからこそ、その上に作り上げる家屋に関しては、リアルタイムにアイデアを盛り込みながら作り上げていっても底から崩れることはない。そのように感じました。
W.N:はい。まさにそういう側面が、会社全体にあると思っています。
安藤:これはあくまでわたし個人の印象ですけど、スーパーアプリは、普通のゲーム会社とは性質がまったく逆のように思えるんです。スクウェア・エニックスでいえば、運営サイドはわりとポップな印象の人間が多くて、逆に開発サイドは骨太というか、男っぽいというか、なかなか距離感を詰めにくいタイプが多い印象でした。でも、それがスーパーアプリはまったく逆で、運営サイドの人間のほうがディレクター臭を感じるほど。わたしはこれまでに色々な開発チームにお会いしてきましたが、初対面でもどなたがディレクターでどなたがプロデューサーか、肌感覚でわかるんです。でも、スーパーアプリのみなさんにお会いしたときは、誰がディレクターなのかとっさに判断できませんでした。
飯沼正樹さん(以下、飯沼):今回のメンバー的に、ディレクションまである程度関われる人間が集まっているからこそ、って側面はあるかもしれませんね。
安藤:一般的には、開発と運営って完全にセクションが分かれていることが多いんですけど、スーパーアプリに関して言えば、運営が開発の領域に踏み込むこともあるんでしょうか?
飯沼:そうですね。明確な敷居はないですね。
安藤:それはかなり珍しいというか、独自の文化だと思います。極端な話、運営と開発はコミュニケーションこそ取るものの、お互いの作業については不可侵である……みたいなところもあります。それを、いわゆる「横断型」でやっているっていうのは、スーパーアプリならではの大きな特色ですね。
飯沼:それは狙ってそういう風にやっているのではなくて、そうしないと回らないからって部分もありますけどね(苦笑)。みんな必要にかられてやっている部分はあります。人員は限られているわけですし、名古屋っていう土地柄もあって、エンタメ系のキャリアが豊富な人はあまりいないんですよ。なので、それをフォローするためには、みんなで助け合っていかなきゃならないっていうのが大前提なんです。
I.J:僕が一番感じるのは、固定観念にとらわれ過ぎず、みんなで意見し合うってところですかね。じつは、循環システムだと意識していなくても、そういうことが自然にできることがありまして。たとえば『ライバルアリーナVS』の企画を今井さんたちに投げたとき、「これはいいアイデアですね」と採用されたりします。その時、そこで終わりになるのではなく、「このアイデアを生かすんだったら、ここをこうすればもっと面白くなるよね」みたいな、「次はどうしたらいいのか」ってところまでを、またチームみんなで考えていける環境なんですよ。言葉にするとなかなか伝わりにくいかもしれませんが……。
安藤:いえいえ。ものすごく肌感覚で伝わってきましたよ。誰かが言ったことを飲み込んで、それを消化したうえで新たなアイデアを吐き出す……まさに感動を創造するための循環システムですね。
I.J:それぞれが好きなようにやらせてもらえているからこそ、って部分はあるかもしれませんね。僕の場合は、言われたものを作る際に、仕様のとおりに作ったものに加えて、自分のアイデアを盛り込んだ、仕様とは少し異なるパターンも作ることがあります。それを採用してもらえることもありますし、もちろん仕様の通りに進むことも多いんですけど、スーパーアプリの社風として、そういうモノづくりが出来る環境になっていると思います。
安藤:ライブ感あふれる制作環境なんですね。予定調和というよりは、こんなことをやってみたんだけどどう? って。それを受けて、「わかった。そっちがそう来るんだったら、俺はこういくよ」といった感じで、みんながアイデアを持ち出しつつ作り上げていくというのは、なかなか刺激的な現場だと思います。ゲーム作りってわりとカチッとしているというか、じつは設計図どおりに組み立てていく側面も強い。その点、スーパーアプリさんのモノ作りって、そもそもの構造図がしっかりしていると思うんですよ。地盤がしっかりと作られているからこそ、その上に作り上げる家屋に関しては、リアルタイムにアイデアを盛り込みながら作り上げていっても底から崩れることはない。そのように感じました。
W.N:はい。まさにそういう側面が、会社全体にあると思っています。
安藤:これはあくまでわたし個人の印象ですけど、スーパーアプリは、普通のゲーム会社とは性質がまったく逆のように思えるんです。スクウェア・エニックスでいえば、運営サイドはわりとポップな印象の人間が多くて、逆に開発サイドは骨太というか、男っぽいというか、なかなか距離感を詰めにくいタイプが多い印象でした。でも、それがスーパーアプリはまったく逆で、運営サイドの人間のほうがディレクター臭を感じるほど。わたしはこれまでに色々な開発チームにお会いしてきましたが、初対面でもどなたがディレクターでどなたがプロデューサーか、肌感覚でわかるんです。でも、スーパーアプリのみなさんにお会いしたときは、誰がディレクターなのかとっさに判断できませんでした。
飯沼正樹さん(以下、飯沼):今回のメンバー的に、ディレクションまである程度関われる人間が集まっているからこそ、って側面はあるかもしれませんね。
安藤:一般的には、開発と運営って完全にセクションが分かれていることが多いんですけど、スーパーアプリに関して言えば、運営が開発の領域に踏み込むこともあるんでしょうか?
飯沼:そうですね。明確な敷居はないですね。
安藤:それはかなり珍しいというか、独自の文化だと思います。極端な話、運営と開発はコミュニケーションこそ取るものの、お互いの作業については不可侵である……みたいなところもあります。それを、いわゆる「横断型」でやっているっていうのは、スーパーアプリならではの大きな特色ですね。
飯沼:それは狙ってそういう風にやっているのではなくて、そうしないと回らないからって部分もありますけどね(苦笑)。みんな必要にかられてやっている部分はあります。人員は限られているわけですし、名古屋っていう土地柄もあって、エンタメ系のキャリアが豊富な人はあまりいないんですよ。なので、それをフォローするためには、みんなで助け合っていかなきゃならないっていうのが大前提なんです。

安藤:そうせざるを得なかった側面があったとして、それを実現できていることこそが素晴らしいんです。簡単に例えてみると、普通のレストランでは厨房と接客は完全に分かれていますよね。でも、スーパーアプリは厨房も接客もみんな対応できる。ある意味、ラーメン屋さんみたいな感じなんですよね。作るし「どうぞ」ってお客さんの顔を見ながら応対することもできる。
これは口で言うのは簡単な気もしますが、実現するのは大変。店員が少ないからやるしかないと言われても、「いや、俺はラーメンだけ作っていたいんだけど」って人がいてもおかしくないんですよ。でも、ちゃんとお客さんにもサービスしないと味の良さがわかってもらえないことを、全員が理解している。どんぶりに手を突っ込んで出しても気にならないというような、サービス精神がない人もいない。それはとても素晴らしいことだと思いますね。……と、お話がずいぶん膨らんでしまいましたが、ここで次の方にお話をお聞きしましょう。
M.Tさん:『ライバルアリーナVS』の企画、プランニングなど、企画職を担当しているM.Tです。
安藤:M.Tさんは普段、アップデートの内容をプランニングしたり、ゲームバランスを見たりされているんでしょうか?
M.T:そうですね。それに加えて、お客様への対応などもさせてもらっています。『ライバルアリーナVS』チームとして一番大切にしているのは、やっぱりユーザーさんの感情の部分なんですよ。たとえばお客さまからお問い合わせが来るだけでも、そのお客さまは今どんな気持ちになっているのだろうというところを考えながら、お話をお聞きしています。
安藤:どういったお問い合わせがくるんですか?
M.T:ゲーム内容に関するお問い合わせやご意見から、「勝負に負けて悔しい」「大会に優勝しました」ってご報告まで、さまざまです。
安藤:何かM.Tさんの印象に残っているお問い合わせなどありますか?
M.T:そうですね……グレシルっていう堕天使についてのお問い合わせは印象的でした。じつは、天使は人間と違って、おへそがないんですよ。だから、グレシルの画像にはおへそは描かれていないんですけど、見ようによってはおへそに見える影があるんです。それに気づいたユーザーさんから「グレシルのおへそってどこにあるんですか?」というお問い合わせが運営チームに届いたんです。
安藤:ユニークですね。それを受けて、どう返されたんでしょう?
M.T:一般的な返し方をするのなら、「グレシルにおへそはありません」と設定どおりに返事をしたり、「世界観の問題です」って淡白な言葉で返したりするんでしょうけど、そこは運営チームとお問い合わせ対応チームで話し合って、二人三脚で設定を考え出しました。
安藤:興味深い。その設定ってどんな内容なんですか?
M.T:一般的に天使にはおへそがないとされていますが、グレシルにはおへそがちゃんとあります。なぜなら『ライバルアリーナVS』の世界では、天使も創造主が作っているものなので、我々の世界でいうところの天使とはそもそも生まれ方からして異なっている……という設定をつけました。完全に後付け設定ですね。最終的には「ひもで隠れています」って返したんですけど(笑)。
これは口で言うのは簡単な気もしますが、実現するのは大変。店員が少ないからやるしかないと言われても、「いや、俺はラーメンだけ作っていたいんだけど」って人がいてもおかしくないんですよ。でも、ちゃんとお客さんにもサービスしないと味の良さがわかってもらえないことを、全員が理解している。どんぶりに手を突っ込んで出しても気にならないというような、サービス精神がない人もいない。それはとても素晴らしいことだと思いますね。……と、お話がずいぶん膨らんでしまいましたが、ここで次の方にお話をお聞きしましょう。
M.Tさん:『ライバルアリーナVS』の企画、プランニングなど、企画職を担当しているM.Tです。
安藤:M.Tさんは普段、アップデートの内容をプランニングしたり、ゲームバランスを見たりされているんでしょうか?
M.T:そうですね。それに加えて、お客様への対応などもさせてもらっています。『ライバルアリーナVS』チームとして一番大切にしているのは、やっぱりユーザーさんの感情の部分なんですよ。たとえばお客さまからお問い合わせが来るだけでも、そのお客さまは今どんな気持ちになっているのだろうというところを考えながら、お話をお聞きしています。
安藤:どういったお問い合わせがくるんですか?
M.T:ゲーム内容に関するお問い合わせやご意見から、「勝負に負けて悔しい」「大会に優勝しました」ってご報告まで、さまざまです。
安藤:何かM.Tさんの印象に残っているお問い合わせなどありますか?
M.T:そうですね……グレシルっていう堕天使についてのお問い合わせは印象的でした。じつは、天使は人間と違って、おへそがないんですよ。だから、グレシルの画像にはおへそは描かれていないんですけど、見ようによってはおへそに見える影があるんです。それに気づいたユーザーさんから「グレシルのおへそってどこにあるんですか?」というお問い合わせが運営チームに届いたんです。
安藤:ユニークですね。それを受けて、どう返されたんでしょう?
M.T:一般的な返し方をするのなら、「グレシルにおへそはありません」と設定どおりに返事をしたり、「世界観の問題です」って淡白な言葉で返したりするんでしょうけど、そこは運営チームとお問い合わせ対応チームで話し合って、二人三脚で設定を考え出しました。
安藤:興味深い。その設定ってどんな内容なんですか?
M.T:一般的に天使にはおへそがないとされていますが、グレシルにはおへそがちゃんとあります。なぜなら『ライバルアリーナVS』の世界では、天使も創造主が作っているものなので、我々の世界でいうところの天使とはそもそも生まれ方からして異なっている……という設定をつけました。完全に後付け設定ですね。最終的には「ひもで隠れています」って返したんですけど(笑)。

▲こちらが『ライバルアリーナVS』に登場するグレシル。たしかに、おへそがあるように見える。
安藤:でも、そう答えると質問した側としても「なるほど、天使の設定をわかっているな」と納得はできますもんね。
M.T:あと、先日開催された「Lobi感謝祭」で、グレシルのコスプレをしているコンパニオンのお姉さんがいて。もちろん、コスプレなのでおへそがあるんですよ。それでまたおへそ談義が盛り上がっちゃいまして(笑)。コスプレのお姉さんに「じつは先日、グレシルのおへそについてこういうやり取りがあったんです」ってその場でお話ししたら、ちゃんとひもでへそが隠れるようにうまくやってくれたんですよ。
安藤:それはコスプレのお姉さんもプロ意識がありますね。それだけ、ゲーム内のキャラクターが立っている証拠ともいえますよ。キャラが立っていないと、そもそもそういう議論にすらならないで、みんなの中でスルーされちゃいますからね。普通、キャラクターのへそに関して開発者とコスプレイヤーが話すなんてないですよ。とてもいいキャラクターを生み出している証拠ですね。では、そろそろM.Tさんの好きなゲームを教えていただけますか。
M.T:1本でと言われると、僕は『2Moons』というゲームを挙げます。日本では『DEKARON』という名前でリリースされていたMMO・RPGなんですけど、これはもともと『2Moons』というヨーロッパのゲームなんです。
安藤:『2Moons』ですか……月が2つある世界の物語なんですか?
M.T:そうです。世界観として、2つの月が重なるとき、世界が終わるという内容のものでした。じつは、このゲームを遊ぶまでの僕は人とコミュニケーションを取るのがめちゃくちゃ嫌いで、絶対に話さない、会話をしない人だったんです。学校のクラスメイトはおろか家族とも会話がなくて、本当に誰とも会話をしない生活をしていました。そんななかで、僕が初めてコミュニケーションを取ったのは、学校でも家族でもなくてこの『DEKARON』の世界だったんですよ。
安藤:頑なに人を寄せ付けなかったM.T少年は、ゲーム内の何がきっかけでコミュニケーションをとることになったんですか?
M.T:『DEKARON』って、いわゆるPK(Player Kill)ができるゲームなんですけど、僕はそのゲームを始めたばかりの頃、見ず知らずの人にPKされたんですよ。それにものすごく腹が立って「絶対こいつをPK仕返してやる」と心に近い、相手のキャラ名をメモに控えたんです。そのとき僕はレベル30くらいだったんですけど、PKを仕掛けてきた相手はレベル120とかで。そりゃもう、逆立ちしても絶対勝てないような相手だったわけです。当時、レベル120まで上げるのに3~4カ月かかるといわれていましたが、僕は1カ月でそこまで到達して、相手へのリベンジを果たすことができました。
安藤:おお、ちょっと怖いくらいに執着していたってことですね。でも、通常の3倍くらいの勢いでハマっていたってことでもあるわけか。
M.T:ええ。それで僕は、そのゲームで初めてNo.1を取ったんです。ゲーム内で1番強い人間になったんですよ。そこで「強いですね」「すごいですね」ってみんなに褒められて、それをきっかけにコミュニケーションをとることになりました。
安藤:みんなから認められた、という瞬間がゲームで初めて起こったんですね。そこまでは復讐の鬼だったけれど、1位になった瞬間に認められるという経験があって、コミュニケーションをとるようになった。
M.T:そこから、やっと学校で友だちとコミュニケーションを取るようになりました。今度はその友だちも誘ってゲーム内で最強のギルドを作り、さらにはゲーム内の最強メンバーをそろえて、チーム戦でもNo.1になりました。最終的には僕らしかそのサーバーにいなくなるぐらいまで遊んでいましたね。それぐらいの勢いでハマったゲームでした。最後までやりきったというか。
安藤:文字どおり、ゲームにいろいろ助けられたというか、M.Tさんがみんなと普通にしゃべれるようになったのは『DEKARON』のおかげだったんですね。
M.T:そうですね。色々な意味で、とても感謝している忘れられないゲームです。
安藤:わたしを含めた我々の世代は、ゲームクリエイターという仕事がなかったら、何をしていたかわからないような人の集まりなんです。今でこそ、大手のゲーム会社に務められると親御さんからは喜ばれると思いすが、わたしたちの時代は親戚を含めて、全員に反対されるようなことも多くて。ある意味、つぶしがきかない人が集まるような仕事だったとも言えるんですよね。だからこそ「何かおもしろいことを成し遂げよう」「我々はゲームを作ることでしか救われない。だった、すごいものを作ってみんなをワクワクさせたい」ってところがありまして。
でも、今ってちょっと違うというか、ゲームがビジネスになっている部分がある。それは業界として成熟してきた証でもあるんですが、新卒者の面接なんかを担当していたら、ゲームを作りたいからゲーム会社を志望しているわけではなく、大手企業だから安定しているだろう……といった人が意外と多くいることにビックリして。
つまるところ、今どきのゲームはそんな人たちが作っているのか、って愕然としたんですよ。ゲーム屋だと思っている自分からすれば、言葉を選ばずに言うと「そんな考え方だったらゲームなんて作らんといてほしいな」って感じるんですね。本来、ゲーム以外には何もないっていうぐらいの人がゲームを作るべきだとわたしは思っているんですけど……って、大分お話が逸れてしまってお恥ずかしいのですが。
飯沼:いえいえ、とても安藤さんらしいアツい言葉でしたよ。
安藤:何を言いたかったかというと、今のところスーパーアプリは、そういった「ゲームを作ることでしか救われない」っていうような人たちが集まって、モノ作りをしている会社だなと感じたってことです。みなさんと、とりわけM.Tさんとお話をしていて、強くそう感じました。ここでM.Tさんから「そんなことないですよ」「Webサービスもアリです」って言われたら、トークとしては最高のオチなんですけどね(笑)。
M.T:(笑)。でも、少なくとも僕なんかは、ゲームのこと以外はあまり得意ではないので。その一方、ゲーム……とくにMMO・RPGに特化していうと、僕よりMMO・RPGについて知っている人は世界に10人くらいしかいないとも自負しています。それくらいゲームをやりましたね、僕は。
安藤:M.Tさんはとりわけ突出しているのかもしれませんが、ここにいるメンバーは多かれ少なかれ、そういう側面を持った人たちばかりだと思います。あらためて、スーパーアプリという会社が際立っている部分が垣間見えた気がしますね。では、ここからはデザイナーチーム。女性メンバーにもお話をお聞きしていきましょう。(インタビュー後編に続く)
インタビュー後編:これからのゲームクリエイターに必要となるたった一つのモノ
●東京オフィスも本格始動した名古屋のゲームデベロッパー「スーパーアプリ」でお仕事をしてみたい方はコチラ
M.T:あと、先日開催された「Lobi感謝祭」で、グレシルのコスプレをしているコンパニオンのお姉さんがいて。もちろん、コスプレなのでおへそがあるんですよ。それでまたおへそ談義が盛り上がっちゃいまして(笑)。コスプレのお姉さんに「じつは先日、グレシルのおへそについてこういうやり取りがあったんです」ってその場でお話ししたら、ちゃんとひもでへそが隠れるようにうまくやってくれたんですよ。
安藤:それはコスプレのお姉さんもプロ意識がありますね。それだけ、ゲーム内のキャラクターが立っている証拠ともいえますよ。キャラが立っていないと、そもそもそういう議論にすらならないで、みんなの中でスルーされちゃいますからね。普通、キャラクターのへそに関して開発者とコスプレイヤーが話すなんてないですよ。とてもいいキャラクターを生み出している証拠ですね。では、そろそろM.Tさんの好きなゲームを教えていただけますか。
M.T:1本でと言われると、僕は『2Moons』というゲームを挙げます。日本では『DEKARON』という名前でリリースされていたMMO・RPGなんですけど、これはもともと『2Moons』というヨーロッパのゲームなんです。
安藤:『2Moons』ですか……月が2つある世界の物語なんですか?
M.T:そうです。世界観として、2つの月が重なるとき、世界が終わるという内容のものでした。じつは、このゲームを遊ぶまでの僕は人とコミュニケーションを取るのがめちゃくちゃ嫌いで、絶対に話さない、会話をしない人だったんです。学校のクラスメイトはおろか家族とも会話がなくて、本当に誰とも会話をしない生活をしていました。そんななかで、僕が初めてコミュニケーションを取ったのは、学校でも家族でもなくてこの『DEKARON』の世界だったんですよ。
安藤:頑なに人を寄せ付けなかったM.T少年は、ゲーム内の何がきっかけでコミュニケーションをとることになったんですか?
M.T:『DEKARON』って、いわゆるPK(Player Kill)ができるゲームなんですけど、僕はそのゲームを始めたばかりの頃、見ず知らずの人にPKされたんですよ。それにものすごく腹が立って「絶対こいつをPK仕返してやる」と心に近い、相手のキャラ名をメモに控えたんです。そのとき僕はレベル30くらいだったんですけど、PKを仕掛けてきた相手はレベル120とかで。そりゃもう、逆立ちしても絶対勝てないような相手だったわけです。当時、レベル120まで上げるのに3~4カ月かかるといわれていましたが、僕は1カ月でそこまで到達して、相手へのリベンジを果たすことができました。
安藤:おお、ちょっと怖いくらいに執着していたってことですね。でも、通常の3倍くらいの勢いでハマっていたってことでもあるわけか。
M.T:ええ。それで僕は、そのゲームで初めてNo.1を取ったんです。ゲーム内で1番強い人間になったんですよ。そこで「強いですね」「すごいですね」ってみんなに褒められて、それをきっかけにコミュニケーションをとることになりました。
安藤:みんなから認められた、という瞬間がゲームで初めて起こったんですね。そこまでは復讐の鬼だったけれど、1位になった瞬間に認められるという経験があって、コミュニケーションをとるようになった。
M.T:そこから、やっと学校で友だちとコミュニケーションを取るようになりました。今度はその友だちも誘ってゲーム内で最強のギルドを作り、さらにはゲーム内の最強メンバーをそろえて、チーム戦でもNo.1になりました。最終的には僕らしかそのサーバーにいなくなるぐらいまで遊んでいましたね。それぐらいの勢いでハマったゲームでした。最後までやりきったというか。
安藤:文字どおり、ゲームにいろいろ助けられたというか、M.Tさんがみんなと普通にしゃべれるようになったのは『DEKARON』のおかげだったんですね。
M.T:そうですね。色々な意味で、とても感謝している忘れられないゲームです。
安藤:わたしを含めた我々の世代は、ゲームクリエイターという仕事がなかったら、何をしていたかわからないような人の集まりなんです。今でこそ、大手のゲーム会社に務められると親御さんからは喜ばれると思いすが、わたしたちの時代は親戚を含めて、全員に反対されるようなことも多くて。ある意味、つぶしがきかない人が集まるような仕事だったとも言えるんですよね。だからこそ「何かおもしろいことを成し遂げよう」「我々はゲームを作ることでしか救われない。だった、すごいものを作ってみんなをワクワクさせたい」ってところがありまして。
でも、今ってちょっと違うというか、ゲームがビジネスになっている部分がある。それは業界として成熟してきた証でもあるんですが、新卒者の面接なんかを担当していたら、ゲームを作りたいからゲーム会社を志望しているわけではなく、大手企業だから安定しているだろう……といった人が意外と多くいることにビックリして。
つまるところ、今どきのゲームはそんな人たちが作っているのか、って愕然としたんですよ。ゲーム屋だと思っている自分からすれば、言葉を選ばずに言うと「そんな考え方だったらゲームなんて作らんといてほしいな」って感じるんですね。本来、ゲーム以外には何もないっていうぐらいの人がゲームを作るべきだとわたしは思っているんですけど……って、大分お話が逸れてしまってお恥ずかしいのですが。
飯沼:いえいえ、とても安藤さんらしいアツい言葉でしたよ。
安藤:何を言いたかったかというと、今のところスーパーアプリは、そういった「ゲームを作ることでしか救われない」っていうような人たちが集まって、モノ作りをしている会社だなと感じたってことです。みなさんと、とりわけM.Tさんとお話をしていて、強くそう感じました。ここでM.Tさんから「そんなことないですよ」「Webサービスもアリです」って言われたら、トークとしては最高のオチなんですけどね(笑)。
M.T:(笑)。でも、少なくとも僕なんかは、ゲームのこと以外はあまり得意ではないので。その一方、ゲーム……とくにMMO・RPGに特化していうと、僕よりMMO・RPGについて知っている人は世界に10人くらいしかいないとも自負しています。それくらいゲームをやりましたね、僕は。
安藤:M.Tさんはとりわけ突出しているのかもしれませんが、ここにいるメンバーは多かれ少なかれ、そういう側面を持った人たちばかりだと思います。あらためて、スーパーアプリという会社が際立っている部分が垣間見えた気がしますね。では、ここからはデザイナーチーム。女性メンバーにもお話をお聞きしていきましょう。(インタビュー後編に続く)
インタビュー後編:これからのゲームクリエイターに必要となるたった一つのモノ
●東京オフィスも本格始動した名古屋のゲームデベロッパー「スーパーアプリ」でお仕事をしてみたい方はコチラ
シシララTV オリジナル記事