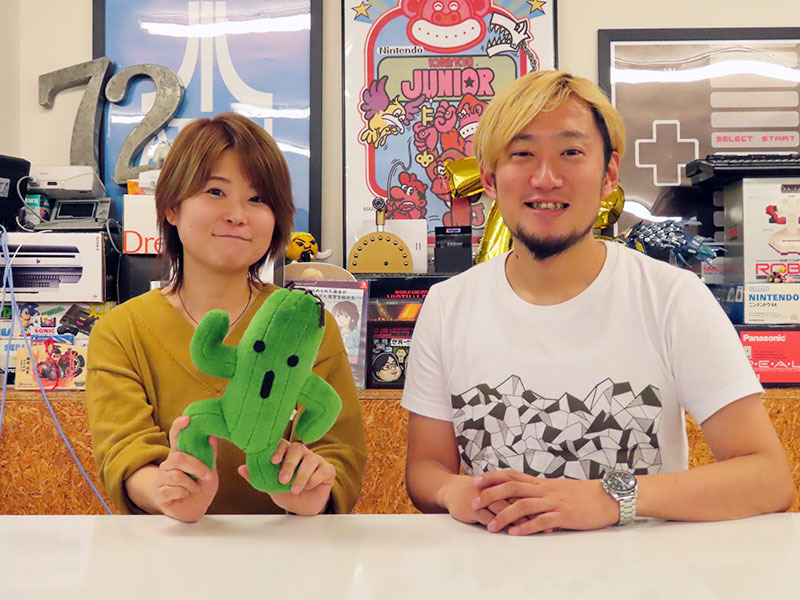スーパーアプリ若手クリエイターインタビュー(後編):これからのゲームクリエイターに必要となるたった一つのモノ
名古屋に拠点を置き、『ライバルアリーナVS』などの人気ソーシャルゲームを多数世に送り出している気鋭の開発会社・スーパーアプリ。昨年の秋に東京オフィスも開設され、今後さらなる飛躍が期待されるこの気鋭の会社の主要スタッフに、ゲームDJ・安藤武博が鋭く切り込むインタビュー企画。第一弾は代表取締役である飯沼正樹氏に、第二弾ではその右腕でありブレーンである石橋広在氏に、今求められているクリエイター像などをうかがってきた。
そしてインタビュー企画の第三弾では、そんなスーパーアプリを引っ張る、若きゲームクリエイター10人にお集まりいただき、ゲーム作りへの情熱から自身がクリエイターを志すに至る原点となったゲームについて、お話をうかがった。

インタビュー時間90分超、文字数約25,000と、過去最多のボリュームとなったこの第三弾。後編ではデザイナーチームの女性陣にスポットを当てつつ、話題はしだいに「今求められているゲームクリエイター像」へと及んでいく。
・スーパーアプリ vs 安藤武博 対談インタビュー企画
第三弾 前編:スーパーアプリ若手クリエイターインタビュー(前編):クリエイターはゲームを作ることでしか救われない
第一弾:気鋭のゲーム開発会社「スーパーアプリ」が求める未来とは? 社長の飯沼正樹氏に訊く
第二弾:「フリートゥプレイ」の先駆者が電撃移籍! スーパーアプリ・石橋氏が語る「変化と挑戦」
第三弾 前編:スーパーアプリ若手クリエイターインタビュー(前編):クリエイターはゲームを作ることでしか救われない
第一弾:気鋭のゲーム開発会社「スーパーアプリ」が求める未来とは? 社長の飯沼正樹氏に訊く
第二弾:「フリートゥプレイ」の先駆者が電撃移籍! スーパーアプリ・石橋氏が語る「変化と挑戦」
■これからのデザイナーやイラストレーターに求められる資質とは
安藤武博(以下、安藤):前編ではおもに男性陣にお話をお聞きしましたが、ここからはデザイナーチームの女性メンバーにお話をお聞きしていきたいと思います。では、まずはA.Tさんから。
A.Tさん:はい。デザイン部のA.Tと申します。先日まではグラフィックなど、開発のお仕事を手掛けていたんですけど、今は運営の方に回って演出などを担当しています。
安藤:そんなこともあるんですね。グラフィックを担当していた人が、運営側に回るというのはめずらしい気がします。では、そんなA.Tさんの人生の1本ってなんですか?
A.T:私の人生の1本は……みんな知っていると思うんですけど『ゼルダの伝説 時のオカリナ』です。
安藤:出た! 名作ですね。ニンテンドー64で遊んでいました?
A.T:ええ。それよりも前にもゲームを遊んだことも多分あったと思うんですけど、記憶に残っているなかで一番最初に遊んだのが『時のオカリナ』なんです。正直、最初はプレイをしていなくて、2人いるお兄ちゃんが一緒に遊んでいるのを横でずっと見ていただけなんですけど(笑)。私、ゲームを見るのが好きだったんですよ。当時は小学校1年生だったので、ゲームをやるのが怖いと思っていまして。
安藤:なるほど。モンスターとか、怖いデザインの敵なんかもいますもんね。それでも初めてやりたいなと思ったゲームが『時のオカリナ』だった、と。
A.T:はい。結局攻略本とかも買って、全部1人でプレイできるようになって。ものすごく時間をかけて遊んで、初めてクリアできたのはたぶん、小学3年生くらいになっていたと思います。それからもう20年くらい経つと思うんですけど、今住んでいる家にもニンテンドー64は実家から持ってきていて。毎年一回は絶対にクリアするまでプレイしています。
安藤:本当に好きなんですね。わたしにとっての「トップをねらえ」と一緒です。わたしはアニメの「トップをねらえ」がすごい好きで、一年に一回は見直しちゃうんですよ。
A.T:ゲームがすごく得意ってわけじゃないんですけど、『時のオカリナ』はなぜか毎年やりたくなるんです。
A.Tさん:はい。デザイン部のA.Tと申します。先日まではグラフィックなど、開発のお仕事を手掛けていたんですけど、今は運営の方に回って演出などを担当しています。
安藤:そんなこともあるんですね。グラフィックを担当していた人が、運営側に回るというのはめずらしい気がします。では、そんなA.Tさんの人生の1本ってなんですか?
A.T:私の人生の1本は……みんな知っていると思うんですけど『ゼルダの伝説 時のオカリナ』です。
安藤:出た! 名作ですね。ニンテンドー64で遊んでいました?
A.T:ええ。それよりも前にもゲームを遊んだことも多分あったと思うんですけど、記憶に残っているなかで一番最初に遊んだのが『時のオカリナ』なんです。正直、最初はプレイをしていなくて、2人いるお兄ちゃんが一緒に遊んでいるのを横でずっと見ていただけなんですけど(笑)。私、ゲームを見るのが好きだったんですよ。当時は小学校1年生だったので、ゲームをやるのが怖いと思っていまして。
安藤:なるほど。モンスターとか、怖いデザインの敵なんかもいますもんね。それでも初めてやりたいなと思ったゲームが『時のオカリナ』だった、と。
A.T:はい。結局攻略本とかも買って、全部1人でプレイできるようになって。ものすごく時間をかけて遊んで、初めてクリアできたのはたぶん、小学3年生くらいになっていたと思います。それからもう20年くらい経つと思うんですけど、今住んでいる家にもニンテンドー64は実家から持ってきていて。毎年一回は絶対にクリアするまでプレイしています。
安藤:本当に好きなんですね。わたしにとっての「トップをねらえ」と一緒です。わたしはアニメの「トップをねらえ」がすごい好きで、一年に一回は見直しちゃうんですよ。
A.T:ゲームがすごく得意ってわけじゃないんですけど、『時のオカリナ』はなぜか毎年やりたくなるんです。

安藤:しかし、小3でよく「水の神殿」をクリアできましたね。
A.T:「水の神殿」は本当に攻略本がないとできなくて。
安藤:僕はクリアするのに二週間ぐらいかかりましたよ。社会人1年生だったんですけど、僕にとっての『時のオカリナ』はとってもエポックなゲームで「水の神殿」のギミックを解いたときに、こんな複雑なデザインを立体的にできる人が日本にいるんだったら、僕はもうこんなゲーム作らなくていいなと思って、そういうゲームを作るのを諦めました。王道から逃げたというか、ちょっと場外乱闘チックに、ゲリラ戦みたいなゲームを作っていこうと決意させてられてしまったぐらい、すごいデザインでしたよね。
A.T:私はゲームのシステムとかよりも、最初は世界観が好きでハマっていましたね。
安藤:世界観ですか。『ゼルダ』の世界観って、言葉で説明するとどういうところが魅力的なんですかね。アートの人は基本的に、世界観とか世界設定とかをどれだけ考え抜いて表現できるかが大事だと思うので、意地悪な質問かもしれませんけど、あえて聞かせてもらいました。
A.T:言葉にするとすごく難しいんですけど。「いいな」と思ったのは『時のオカリナ』って火の担当、水の担当みたいに、それぞれの属性がぜんぜん違う人たちが集まって復活するお話しじゃないですか。そういった、本来であれば絶対に交わらないような部族が、世界のために力を合わせる……その集合体のような意識がすごく好きだったんです。リンクのデザインとかも好きだったんですけど、そういうもともとはぜんぜん敵でもいいような人たちが集まる、「アベンジャーズ」みたいなオールスター戦みたいなところが好きだったんですよね。
安藤:『時のオカリナ』って本格的に3Dになった最初の『ゼルダの伝説』だったので、これまで思っていた『ゼルダ』と、登場人物の造形の印象が大きく変わったんですよね。かわいいけど気持ち悪い、っていうか。それでも「さすがだな」と思ったのは、生きている人の生活感とか文化背景とかがすごくわかりやすかったこと。風車小屋で風車をまわしているおじさん1人とっても、「ああ、この人はこういう文化で生きているんだ」って感じさせてくれるんですよね。
住んでいる人の印象が変わることで、「おっ、違うエリアに来たんだな」って感じられるというのは、それだけ作り込んでいるからこそ。そこまでしてようやく、遊び手としてはすごい世界観を感じることができるわけですよね。そういう意味では、A.Tさんの今のお話は、ゲームをすごくやり込んでいるからこそ出てくる言葉だと思いました。
A.T:3DS版も出ているんですけど、やっぱり64のほうがいいんですよ。ポリゴンがガチガチなのがおもしろいんです。
安藤:じつはわたしは、64のコントローラーって『時のオカリナ』のために設計されたんじゃないかと思っているんですよ。あれは使用時に、オカリナを吹いているみたいになりますし、ボタンの配置も含めて、そうとしか思えない。たぶん、ハードを設計する時点で宮本茂さんが『時のオカリナ』のことを考えていて、こういう機能があるといいなっていうのを盛り込んだんじゃないかなって思っています。あくまで個人的な意見ですけど、わたしはニンテンドー64は、『時のオカリナ』を遊ぶためにあるゲームハードだよって言っても過言ではないかと。だからA.Tさんが、3DS版ではなく、いまだに64で遊んでいるというのも、ものすごくよくわかります。では、そろそろ次の方に……。
M.Nさん:はい。M.Nです。私も今、運営を手掛けながらイラストを担当させてもらっています。
安藤:A.Tさんと同様、運営でアートをやられているってことですね。
M.N:そうですね。私はたまに開発のお手伝いに入ることもありましたが、基本的にはずっと運営でやってきています。印象に残っているゲームは、私の場合は『スーパーマリオRPG』ですね。『時のオカリナ』もものすごく好きなんですけど。じつは私も、年に一度は必ず『スーパーマリオRPG』をクリアしています。
安藤:すごい! そういう人が集まっているのかな、スーパーアプリには(笑)。『スーパーマリオRPG』というと、開発をスクウェアが手がけたやつですね。
M.N:そうです。あとは、『MOTHER3』とかも印象深いですね。
安藤:わかります。でも、初代でも『2』でもなくて『3』なんですね。
M.N:初代も『2』もおもしろかったですが、私は『3』がすごく好きなんです。
安藤:シリーズのなかで『3』が一番好きって人に会ったのは初めてかもしれません。
M.N:そうですか? たしかに、『MOTHER』が好きな方って「シリーズは好きだけど『3』はちょっと……」って人が多いですよね。私は世界観がかなり好きなので『3』推しなんですけど。あとは『せがれいじり』と『がんばれ森川君2号』もかなり印象に残っています。
安藤:『せがれいじり』は私の師匠が作ったゲームです。シシララTVでも以前取り扱ったりしました。こう聞くと、かなりとがったゲームがお好きなようですね。とりわけ『スーパーマリオRPG』がお好きだということですが、具体的にはどんなところが印象に残っているんですか?
M.N:『マリオ』シリーズでいえば、クッパって悪役じゃないですか。でも『スーパーマリオRPG』では、クッパを自分のパーティに入れることができて、クッパと一緒に悪いヤツを倒すわけですよね。そのわけのわからなさに持っていかれたんですよ。だってあのゲーム、クッパが仲間として説明書に載ってるんですよ。なんでこいつがいるんだ!? っていう衝撃がすごすぎて(笑)。
A.T:「水の神殿」は本当に攻略本がないとできなくて。
安藤:僕はクリアするのに二週間ぐらいかかりましたよ。社会人1年生だったんですけど、僕にとっての『時のオカリナ』はとってもエポックなゲームで「水の神殿」のギミックを解いたときに、こんな複雑なデザインを立体的にできる人が日本にいるんだったら、僕はもうこんなゲーム作らなくていいなと思って、そういうゲームを作るのを諦めました。王道から逃げたというか、ちょっと場外乱闘チックに、ゲリラ戦みたいなゲームを作っていこうと決意させてられてしまったぐらい、すごいデザインでしたよね。
A.T:私はゲームのシステムとかよりも、最初は世界観が好きでハマっていましたね。
安藤:世界観ですか。『ゼルダ』の世界観って、言葉で説明するとどういうところが魅力的なんですかね。アートの人は基本的に、世界観とか世界設定とかをどれだけ考え抜いて表現できるかが大事だと思うので、意地悪な質問かもしれませんけど、あえて聞かせてもらいました。
A.T:言葉にするとすごく難しいんですけど。「いいな」と思ったのは『時のオカリナ』って火の担当、水の担当みたいに、それぞれの属性がぜんぜん違う人たちが集まって復活するお話しじゃないですか。そういった、本来であれば絶対に交わらないような部族が、世界のために力を合わせる……その集合体のような意識がすごく好きだったんです。リンクのデザインとかも好きだったんですけど、そういうもともとはぜんぜん敵でもいいような人たちが集まる、「アベンジャーズ」みたいなオールスター戦みたいなところが好きだったんですよね。
安藤:『時のオカリナ』って本格的に3Dになった最初の『ゼルダの伝説』だったので、これまで思っていた『ゼルダ』と、登場人物の造形の印象が大きく変わったんですよね。かわいいけど気持ち悪い、っていうか。それでも「さすがだな」と思ったのは、生きている人の生活感とか文化背景とかがすごくわかりやすかったこと。風車小屋で風車をまわしているおじさん1人とっても、「ああ、この人はこういう文化で生きているんだ」って感じさせてくれるんですよね。
住んでいる人の印象が変わることで、「おっ、違うエリアに来たんだな」って感じられるというのは、それだけ作り込んでいるからこそ。そこまでしてようやく、遊び手としてはすごい世界観を感じることができるわけですよね。そういう意味では、A.Tさんの今のお話は、ゲームをすごくやり込んでいるからこそ出てくる言葉だと思いました。
A.T:3DS版も出ているんですけど、やっぱり64のほうがいいんですよ。ポリゴンがガチガチなのがおもしろいんです。
安藤:じつはわたしは、64のコントローラーって『時のオカリナ』のために設計されたんじゃないかと思っているんですよ。あれは使用時に、オカリナを吹いているみたいになりますし、ボタンの配置も含めて、そうとしか思えない。たぶん、ハードを設計する時点で宮本茂さんが『時のオカリナ』のことを考えていて、こういう機能があるといいなっていうのを盛り込んだんじゃないかなって思っています。あくまで個人的な意見ですけど、わたしはニンテンドー64は、『時のオカリナ』を遊ぶためにあるゲームハードだよって言っても過言ではないかと。だからA.Tさんが、3DS版ではなく、いまだに64で遊んでいるというのも、ものすごくよくわかります。では、そろそろ次の方に……。
M.Nさん:はい。M.Nです。私も今、運営を手掛けながらイラストを担当させてもらっています。
安藤:A.Tさんと同様、運営でアートをやられているってことですね。
M.N:そうですね。私はたまに開発のお手伝いに入ることもありましたが、基本的にはずっと運営でやってきています。印象に残っているゲームは、私の場合は『スーパーマリオRPG』ですね。『時のオカリナ』もものすごく好きなんですけど。じつは私も、年に一度は必ず『スーパーマリオRPG』をクリアしています。
安藤:すごい! そういう人が集まっているのかな、スーパーアプリには(笑)。『スーパーマリオRPG』というと、開発をスクウェアが手がけたやつですね。
M.N:そうです。あとは、『MOTHER3』とかも印象深いですね。
安藤:わかります。でも、初代でも『2』でもなくて『3』なんですね。
M.N:初代も『2』もおもしろかったですが、私は『3』がすごく好きなんです。
安藤:シリーズのなかで『3』が一番好きって人に会ったのは初めてかもしれません。
M.N:そうですか? たしかに、『MOTHER』が好きな方って「シリーズは好きだけど『3』はちょっと……」って人が多いですよね。私は世界観がかなり好きなので『3』推しなんですけど。あとは『せがれいじり』と『がんばれ森川君2号』もかなり印象に残っています。
安藤:『せがれいじり』は私の師匠が作ったゲームです。シシララTVでも以前取り扱ったりしました。こう聞くと、かなりとがったゲームがお好きなようですね。とりわけ『スーパーマリオRPG』がお好きだということですが、具体的にはどんなところが印象に残っているんですか?
M.N:『マリオ』シリーズでいえば、クッパって悪役じゃないですか。でも『スーパーマリオRPG』では、クッパを自分のパーティに入れることができて、クッパと一緒に悪いヤツを倒すわけですよね。そのわけのわからなさに持っていかれたんですよ。だってあのゲーム、クッパが仲間として説明書に載ってるんですよ。なんでこいつがいるんだ!? っていう衝撃がすごすぎて(笑)。

安藤:それってやっぱり、パーティに入れることができるからっていう狙いがあったんでしょうね。しかし、なんでクッパを仲間に入れようって思ったんでしょう。主要キャラクターだからっていうのもあったのかもしれないけど。
M.N:パッケージで横並びになっているじゃないですか。あそこにクッパがいるのがまず「ん?」って感じだったんですけど、実際に遊んでみて、キャラクターがかなりコミカルに描かれていて、クッパがギャグっぽいことを言ったりとか「城はなくなるけどマリオは倒せる、どうしよう、う~ん」みたいなことを言いだしたりして。すごく人間味あふれるクッパっていうか、はじめてキャラクター性みたいなものを感じられて、すごく好きになったんです。
安藤:たしかに、クッパがプレイヤーキャラクターになるということはものすごくエポックメイキングなことでしたよね。いつもは悪者なんですけど、仲間にすると頼れる存在っていうのは印象深かった。『マリオカート』でも、だいたい早い人はドンキーコングかクッパを使いこなしてましたし。
M.N:そうですね。
安藤:加速は遅いけど、一度トップスピードに乗れば圧倒的に速くてロマンがあった。クッパを使いこなすために、ロケットスタートを必死に練習しました。ファミコン時代は倒すべき相手だったんですけど、スーパーファミコンでは自分で操れるっていうところにシフトしていたので、そういう遊びみたいなものを『スーパーマリオRPG』でも入れたかったんでしょうね。しかし、それをパッケージや説明書から見出すというのは面白い。アート関係の人ならではの感性かもしれませんね。
では、そんなM.Nさんがこれからスーパーアプリでやってみたいことも教えてください。こういうプロジェクトがあったら参加してみたいとか、やってみたいこととかあったりするんじゃないですか?
M.N:ゲームとして作りたいと思うのは、やはりとんがったゲームでしょうか。いわゆる「バカゲー」とかを、スマートフォンで出してみたいです。
安藤:バカゲーは作るの難しいですよ(笑)。でも、おもしろいと思います。ゲームはプレイヤーを泣かせる方が簡単なんですよ。逆にいえば、笑わせるのはすごく難しくて、泣かせようとしたときの10倍、いや100倍くらい真剣に作らないと笑ってもらえないんですよね。真剣にやらないとただ単にふざけているように思われたり、寒くてすべったみたいな感じになったりするので、相当真面目に作らないといけないんです。
わたしがプロデュースした『鈴木爆発』という作品はバカゲーだと言われていますけど、作っているときはものすごく真剣でした。真剣にバカな話を、わりと命がけでしていたりしました。でも、M.Nさんがそれを望むのであれば、ぜひスーパーアプリで成し遂げてほしいなと思います。M.Nさんとしては、現在、そういうことができる環境にいると思っていますか?
M.N:ええ。きっとやれるんじゃないかなと思います。
安藤:会社によっては「そんなの無理だ。うちはもうキャラクタービジネスに徹していこう」みたいな戦略の会社もありますよね。そういう意味ではスーパーアプリって、ある日突然『ガドラン★マスター!』でいわゆるギルドバトルを発明したり、『ライバルアリーナVS』みたいな格ゲーを彷彿とさせるゲームを生み出したりと、すごくユニークな会社だと思います。その辺の環境で新しいことにチャレンジしていくイメージみたいな、なんていうか雰囲気みたいなのって感じることとかあります? これは感覚的なものかもしれませんが。
M.N:そうですね。自由な発想、個人の個性みたいなものすごく大事にするなぁ、というのはやっぱり感じます。「そこをもっとぶつけてこいよ!」みたいな雰囲気が会社全体にあるんですよね。
M.T:NGがないんですよね、基本的に。とりあえず言ってみたら、そこからどんどん転がっていくんです。ただ、言い出したやつは最後まで責任を持ってやろう、みたいな空気もあります。言うのは自由で、やるのも自由。でも、その代わりそれを成し遂げるだけの行動はちゃんと最後までやるべき、っていうスタンスです。
安藤:そこもある意味、飯沼イズムなのかもしれませんね。では、最後に……。
M.N:パッケージで横並びになっているじゃないですか。あそこにクッパがいるのがまず「ん?」って感じだったんですけど、実際に遊んでみて、キャラクターがかなりコミカルに描かれていて、クッパがギャグっぽいことを言ったりとか「城はなくなるけどマリオは倒せる、どうしよう、う~ん」みたいなことを言いだしたりして。すごく人間味あふれるクッパっていうか、はじめてキャラクター性みたいなものを感じられて、すごく好きになったんです。
安藤:たしかに、クッパがプレイヤーキャラクターになるということはものすごくエポックメイキングなことでしたよね。いつもは悪者なんですけど、仲間にすると頼れる存在っていうのは印象深かった。『マリオカート』でも、だいたい早い人はドンキーコングかクッパを使いこなしてましたし。
M.N:そうですね。
安藤:加速は遅いけど、一度トップスピードに乗れば圧倒的に速くてロマンがあった。クッパを使いこなすために、ロケットスタートを必死に練習しました。ファミコン時代は倒すべき相手だったんですけど、スーパーファミコンでは自分で操れるっていうところにシフトしていたので、そういう遊びみたいなものを『スーパーマリオRPG』でも入れたかったんでしょうね。しかし、それをパッケージや説明書から見出すというのは面白い。アート関係の人ならではの感性かもしれませんね。
では、そんなM.Nさんがこれからスーパーアプリでやってみたいことも教えてください。こういうプロジェクトがあったら参加してみたいとか、やってみたいこととかあったりするんじゃないですか?
M.N:ゲームとして作りたいと思うのは、やはりとんがったゲームでしょうか。いわゆる「バカゲー」とかを、スマートフォンで出してみたいです。
安藤:バカゲーは作るの難しいですよ(笑)。でも、おもしろいと思います。ゲームはプレイヤーを泣かせる方が簡単なんですよ。逆にいえば、笑わせるのはすごく難しくて、泣かせようとしたときの10倍、いや100倍くらい真剣に作らないと笑ってもらえないんですよね。真剣にやらないとただ単にふざけているように思われたり、寒くてすべったみたいな感じになったりするので、相当真面目に作らないといけないんです。
わたしがプロデュースした『鈴木爆発』という作品はバカゲーだと言われていますけど、作っているときはものすごく真剣でした。真剣にバカな話を、わりと命がけでしていたりしました。でも、M.Nさんがそれを望むのであれば、ぜひスーパーアプリで成し遂げてほしいなと思います。M.Nさんとしては、現在、そういうことができる環境にいると思っていますか?
M.N:ええ。きっとやれるんじゃないかなと思います。
安藤:会社によっては「そんなの無理だ。うちはもうキャラクタービジネスに徹していこう」みたいな戦略の会社もありますよね。そういう意味ではスーパーアプリって、ある日突然『ガドラン★マスター!』でいわゆるギルドバトルを発明したり、『ライバルアリーナVS』みたいな格ゲーを彷彿とさせるゲームを生み出したりと、すごくユニークな会社だと思います。その辺の環境で新しいことにチャレンジしていくイメージみたいな、なんていうか雰囲気みたいなのって感じることとかあります? これは感覚的なものかもしれませんが。
M.N:そうですね。自由な発想、個人の個性みたいなものすごく大事にするなぁ、というのはやっぱり感じます。「そこをもっとぶつけてこいよ!」みたいな雰囲気が会社全体にあるんですよね。
M.T:NGがないんですよね、基本的に。とりあえず言ってみたら、そこからどんどん転がっていくんです。ただ、言い出したやつは最後まで責任を持ってやろう、みたいな空気もあります。言うのは自由で、やるのも自由。でも、その代わりそれを成し遂げるだけの行動はちゃんと最後までやるべき、っていうスタンスです。
安藤:そこもある意味、飯沼イズムなのかもしれませんね。では、最後に……。

O.Yさん:O.Yと申します。『ライバルアリーナVS』の企画やゲームデザインを手掛けています。僕はめちゃめちゃベタなんですけど、『ポケットモンスター』で育ってきました。『赤』や『緑』の頃から遊んでいます。最近は『ストリートファイター』シリーズを遊んでいて、会社でも結構プレイしています。
安藤:会社にあるんですか? 格ゲーができる環境が。
O.Y:あります。
安藤:よくありますよね、ゲーム会社には。盛り上がっているんですか?
O.Y:いや、小人数でちょこちょこやっています。僕は対戦ゲームが好きなんですよ。
安藤:では、『ポケモン』も対戦で盛り上がったクチですかね?
O.Y:そうですね。
安藤:『ライバルアリーナVS』の格ゲーに似た手ごたえって、やっぱりそこらへんの影響が大きそうですね。
O.Y:『ライバルアリーナVS』って、最初は将棋みたいな本当におカタい感じで、企画書をマネージャーの今井から見せてもらって「手伝ってよ」って言われたときは、あまり理解できていなかったんですね。正直、「なんだこのゲームは」って思いながら動き始めたんですけど、作っていくうちにだんだんわかりやすくなっていくというか、誰にでも理解できるようになっていったんですよ。そして気がついたら、読み合いや駆け引きといった格ゲーっぽい手ごたえも出てきました。最初は「突撃」というシステムももっとわかりづらかったんですよ。
安藤:具体的には?
O.Y:最初は「相手がどこに動くかを予想する」というか、「移動先を読んで正解したら威力が倍になる」みたいなシステムでした。それも含めて、本当に難しいゲームだと思っていたわけですが、メンバーが少しずつ増えていったことで色々なアイデアが盛り込まれ、どんどん洗練されていったんです。こう言ってしまうとなんですが、僕が今まで作ってきたゲームの中で一番手ごたえがあるというか、自信を持って世に出せるゲームだと思っています。
安藤:そう言い切れるのは素晴らしいことですね。やるべきことはやりきったと。運営は続いていくんだけども、今の時点ではやりたいものを出しきれているということですよね。
O.Y:そうですね。自信を持っておもしろいと言える完成度になったかな、と。
安藤:ちなみに、O.Yさんがプロジェクトを全面的に任されたのって今回が初めてなんですか?
O.Y:いえ、ほかにもありますよ。メインゲーム部分を任されたのは。
安藤:それはスーパーアプリに入って何年目で、何歳のときでした?
O.Y:23歳のときですかね。入って2年でした。
安藤:おおっ、それはいい会社ですね。エニックスもそういう会社で、僕が『鈴木爆発』をプロデュースしたのは22歳のときです。そのくらいの年齢のときからいきなりプロジェクトを任せられると伸びるんですよね。会社によっては「お前はまだ若いから今は準備をしていなさい」って、アシスタント的に手伝わされることもあると思うんですけど。
O.Y:やりたいって言えば、やらせてくれる会社ですね。僕も、20歳くらいまではプログラムなんて書いたことすらない人間で、まったく別の仕事をしていたんですけど、たまたま勉強会でプログラムを学ぶ機会があって、せっかくプログラムを組めるようになったんだから、自分が好きなゲームを作ろうと思い立ち、この会社に入ったんですけど。その時は『ライバルアリーナVS』みたいなアプリゲームを作れるようになるなんて、想像もしていなかったです。
安藤:2作品目でバンバン前衛を任されているっていうのはすごいことですね。それだけチャンスを与えてもらえる会社ってことで、このインタビュー記事を読んだ人の中にはうらやましいと感じる人もいるかもしれません。ここだったら若くてもいけるというか、作りたいもの、野心がある人が来たらいきなり活躍できるって感じなんでしょうか?
O.Y:それはあると思いますよ。『ライバルアリーナVS』チームはけっこう若いメンバーが多いんです。僕は5年目ですけど、M.Tなんかは2年目ですし、今日ここに来ていないメンバーの中にも、2年目でライブラリの根っこを触っているプログラマーとかいますし、全体的にかなり若いですね。
■変わっていかなくてはいけないモノ、そして変わってはいけないコト
安藤:ではここからはまとめとして、みなさんが一緒に働きたいと思えるような人、スーパーアプリに加わってほしいと思えるような人材はどんな方かというところを聞いていきたいと思います。ではまず、M.Tさんはどんな人に来てもらいたいと思っています?
安藤:会社にあるんですか? 格ゲーができる環境が。
O.Y:あります。
安藤:よくありますよね、ゲーム会社には。盛り上がっているんですか?
O.Y:いや、小人数でちょこちょこやっています。僕は対戦ゲームが好きなんですよ。
安藤:では、『ポケモン』も対戦で盛り上がったクチですかね?
O.Y:そうですね。
安藤:『ライバルアリーナVS』の格ゲーに似た手ごたえって、やっぱりそこらへんの影響が大きそうですね。
O.Y:『ライバルアリーナVS』って、最初は将棋みたいな本当におカタい感じで、企画書をマネージャーの今井から見せてもらって「手伝ってよ」って言われたときは、あまり理解できていなかったんですね。正直、「なんだこのゲームは」って思いながら動き始めたんですけど、作っていくうちにだんだんわかりやすくなっていくというか、誰にでも理解できるようになっていったんですよ。そして気がついたら、読み合いや駆け引きといった格ゲーっぽい手ごたえも出てきました。最初は「突撃」というシステムももっとわかりづらかったんですよ。
安藤:具体的には?
O.Y:最初は「相手がどこに動くかを予想する」というか、「移動先を読んで正解したら威力が倍になる」みたいなシステムでした。それも含めて、本当に難しいゲームだと思っていたわけですが、メンバーが少しずつ増えていったことで色々なアイデアが盛り込まれ、どんどん洗練されていったんです。こう言ってしまうとなんですが、僕が今まで作ってきたゲームの中で一番手ごたえがあるというか、自信を持って世に出せるゲームだと思っています。
安藤:そう言い切れるのは素晴らしいことですね。やるべきことはやりきったと。運営は続いていくんだけども、今の時点ではやりたいものを出しきれているということですよね。
O.Y:そうですね。自信を持っておもしろいと言える完成度になったかな、と。
安藤:ちなみに、O.Yさんがプロジェクトを全面的に任されたのって今回が初めてなんですか?
O.Y:いえ、ほかにもありますよ。メインゲーム部分を任されたのは。
安藤:それはスーパーアプリに入って何年目で、何歳のときでした?
O.Y:23歳のときですかね。入って2年でした。
安藤:おおっ、それはいい会社ですね。エニックスもそういう会社で、僕が『鈴木爆発』をプロデュースしたのは22歳のときです。そのくらいの年齢のときからいきなりプロジェクトを任せられると伸びるんですよね。会社によっては「お前はまだ若いから今は準備をしていなさい」って、アシスタント的に手伝わされることもあると思うんですけど。
O.Y:やりたいって言えば、やらせてくれる会社ですね。僕も、20歳くらいまではプログラムなんて書いたことすらない人間で、まったく別の仕事をしていたんですけど、たまたま勉強会でプログラムを学ぶ機会があって、せっかくプログラムを組めるようになったんだから、自分が好きなゲームを作ろうと思い立ち、この会社に入ったんですけど。その時は『ライバルアリーナVS』みたいなアプリゲームを作れるようになるなんて、想像もしていなかったです。
安藤:2作品目でバンバン前衛を任されているっていうのはすごいことですね。それだけチャンスを与えてもらえる会社ってことで、このインタビュー記事を読んだ人の中にはうらやましいと感じる人もいるかもしれません。ここだったら若くてもいけるというか、作りたいもの、野心がある人が来たらいきなり活躍できるって感じなんでしょうか?
O.Y:それはあると思いますよ。『ライバルアリーナVS』チームはけっこう若いメンバーが多いんです。僕は5年目ですけど、M.Tなんかは2年目ですし、今日ここに来ていないメンバーの中にも、2年目でライブラリの根っこを触っているプログラマーとかいますし、全体的にかなり若いですね。
■変わっていかなくてはいけないモノ、そして変わってはいけないコト
安藤:ではここからはまとめとして、みなさんが一緒に働きたいと思えるような人、スーパーアプリに加わってほしいと思えるような人材はどんな方かというところを聞いていきたいと思います。ではまず、M.Tさんはどんな人に来てもらいたいと思っています?

M.T:スーパーアプリとしてって話であれば、やっぱり自発的にプランを提示できる人、それがどんなプランであれ自分から動ける人がといいと思います。会社によっては、プランはすでに会社側にあって、そのプランを確実にこなす人が欲しいという企業もあると思いますが、スーパーアプリは自分から提案していくことを主体としている会社ですので。会社の「こうだぞ」っていうところに縛られることなく、自分なりの、自分だけのプランをどんどん出していける人に来ていただいて、一緒に働いていきたいなと思います。
O.M:やっぱりやりたいことがある人がいいですよね。自分でやりたいことがあって、それに向かってどんどんやっちゃえる人。やりたいことがある人なら、それに向かって勉強したり、努力したり、なんらかの形で発信したりできると思うので。とにかく「てっぺんとったろ」みたいな感覚を持っている人なら大歓迎です。
安藤:いいですね。「てっぺんとったろ」って人に来てほしいというのは、なかなか言えることじゃないですよ。では、W.Nさんからもぜひ。
W.N:たぶんうちの会社の特徴なんですけど、エンジニアやデザイナー、プランナーが全部同じフロアにいて、すごく近いところにいるんですよ。僕のようなプランナーの目線で言うと、全部の人と真剣に話をできる人がいいんです。それぞれにこだわりや思いであったり、やりたいことがあったりするので、ちゃんとそれを噛み砕いてしっかり作っていける人ですね。そんなのいきなりできるって人がそうそういないと思いますが、ちゃんと人の話を聞けないと取りこぼしたりもしますので、「みんなと膝を付き合わせていく」って気持ちをしっかり持っている人と働きたいと思います。
安藤:運営チームのお2人はいかがですか?
K.Y:芯がしっかりしている人がいいですね。志や人としての根っこの部分がしっかりしている人が理想です。
安藤:経験は不問ですか? 運営としてのお仕事に関して。
K.Y:そうですね。私もまったくノーキャリアで来て、いろいろ任せてもらったりとかしているので、経験は会社に入ってから積めばいいと思います。あとは、芯の強い人。何があっても折れないっていう芯の強さがあれば、なんでもできますからね。
O.M:やっぱりやりたいことがある人がいいですよね。自分でやりたいことがあって、それに向かってどんどんやっちゃえる人。やりたいことがある人なら、それに向かって勉強したり、努力したり、なんらかの形で発信したりできると思うので。とにかく「てっぺんとったろ」みたいな感覚を持っている人なら大歓迎です。
安藤:いいですね。「てっぺんとったろ」って人に来てほしいというのは、なかなか言えることじゃないですよ。では、W.Nさんからもぜひ。
W.N:たぶんうちの会社の特徴なんですけど、エンジニアやデザイナー、プランナーが全部同じフロアにいて、すごく近いところにいるんですよ。僕のようなプランナーの目線で言うと、全部の人と真剣に話をできる人がいいんです。それぞれにこだわりや思いであったり、やりたいことがあったりするので、ちゃんとそれを噛み砕いてしっかり作っていける人ですね。そんなのいきなりできるって人がそうそういないと思いますが、ちゃんと人の話を聞けないと取りこぼしたりもしますので、「みんなと膝を付き合わせていく」って気持ちをしっかり持っている人と働きたいと思います。
安藤:運営チームのお2人はいかがですか?
K.Y:芯がしっかりしている人がいいですね。志や人としての根っこの部分がしっかりしている人が理想です。
安藤:経験は不問ですか? 運営としてのお仕事に関して。
K.Y:そうですね。私もまったくノーキャリアで来て、いろいろ任せてもらったりとかしているので、経験は会社に入ってから積めばいいと思います。あとは、芯の強い人。何があっても折れないっていう芯の強さがあれば、なんでもできますからね。

安藤:ありがとうございます。じゃあ続けてS.Tさんは?
S.T:ちょっと被ってしまうんですけども、やっぱり目的がはっきりしている方がいいですね、「ゲームを作りたい」っていう思いは大前提として、「こういうものを作りたい」っていうものがあれば、自然と技術も身についていくと思うので。まずはそこからだと思います。
安藤:はっきり「これがやりたい」って決まっている人がいいってことですね。では、続けてI.Jさんは?
I.J:僕もほぼほぼ同じことなんですけど、やりたいっていう気持ちを持っている人かなと思います。やっぱり自分がやりたいって気持ちを持って作るのと、別にいいやって思いながら作るのとでは、できた制作物に差が出てくると思うので。
安藤:M.Kさんはいかがです?
M.K:サーバー側もいろいろな試みを裏でやっていますので、ネットワーク関連でいろいろやってみたいって人にとっては面白い職場だと思います。ベンチャーならではの制約もあるんですけど、 インフラから本当に触ってプログラムでまとめてみようと思えばできるので、やりがいはありますよ。
安藤:スーパーアプリに入れば、プログラマーとしてこんなことができますよって話ですね。けっこういろいろ任せられて、いろいろ動かして組み立てていけるってことですぁ。
M.K:そうですね。若い人に自分もどんどん任せられるものは任せちゃうので。チャンスはあると思います。
M.T:勉強会とかもありますしね。
安藤:勉強会?
M.T:ええ。プログラマーさんたちは週一で自主的に集まって勉強会をやっているんですよ。
安藤:技術的には自分の腕を磨くことができる環境だということですね。素晴らしい取り組みだと思います。自主的に集まっているってところがいいですよ。では、女性チームいきましょうか。
A.T:私はデザイナー目線になるんですけど、トレンドが追える人、そして勤勉な人と一緒に働きたいですね。ソシャゲって前はデザインもゴリゴリで、金のフチやすごいエフェクトがバリバリについていればいいって風潮があったように思うのですが、今はそんなに単純ではありませんから。やはり、デザインというものはトレンドがころころ変わっていくものなので、それを学んでいける視野の広さは必要だと思います。自分の中で芯というか、変えたくないものはあると思いますが、それを持ったうえでトレンドを追える人が「デザイナー」なのではないかと。
安藤:どういう人が「トレンドを追える人」なんでしょう。ゲーム外にもやっぱり興味がある人ですか?
A.T:だと思います。ファッションだったりとか、女の子だったらメイクとか。デザイナーに必要なのは、いろいろなところに行って、いろいろな情報をインプットすること。それは別にゲームじゃなくても、広告だったり看板だったりとか、自分が見てカッコいいって思ったものを取り入れられる力がある人が強いと思います。
安藤:スーパーアプリの女性スタッフを見ていると、みなさんファッションとかメイクとかに興味があって、女子力が高いなと感じます。そういったアンテナの高さは必要ですよね。
S.T:ちょっと被ってしまうんですけども、やっぱり目的がはっきりしている方がいいですね、「ゲームを作りたい」っていう思いは大前提として、「こういうものを作りたい」っていうものがあれば、自然と技術も身についていくと思うので。まずはそこからだと思います。
安藤:はっきり「これがやりたい」って決まっている人がいいってことですね。では、続けてI.Jさんは?
I.J:僕もほぼほぼ同じことなんですけど、やりたいっていう気持ちを持っている人かなと思います。やっぱり自分がやりたいって気持ちを持って作るのと、別にいいやって思いながら作るのとでは、できた制作物に差が出てくると思うので。
安藤:M.Kさんはいかがです?
M.K:サーバー側もいろいろな試みを裏でやっていますので、ネットワーク関連でいろいろやってみたいって人にとっては面白い職場だと思います。ベンチャーならではの制約もあるんですけど、 インフラから本当に触ってプログラムでまとめてみようと思えばできるので、やりがいはありますよ。
安藤:スーパーアプリに入れば、プログラマーとしてこんなことができますよって話ですね。けっこういろいろ任せられて、いろいろ動かして組み立てていけるってことですぁ。
M.K:そうですね。若い人に自分もどんどん任せられるものは任せちゃうので。チャンスはあると思います。
M.T:勉強会とかもありますしね。
安藤:勉強会?
M.T:ええ。プログラマーさんたちは週一で自主的に集まって勉強会をやっているんですよ。
安藤:技術的には自分の腕を磨くことができる環境だということですね。素晴らしい取り組みだと思います。自主的に集まっているってところがいいですよ。では、女性チームいきましょうか。
A.T:私はデザイナー目線になるんですけど、トレンドが追える人、そして勤勉な人と一緒に働きたいですね。ソシャゲって前はデザインもゴリゴリで、金のフチやすごいエフェクトがバリバリについていればいいって風潮があったように思うのですが、今はそんなに単純ではありませんから。やはり、デザインというものはトレンドがころころ変わっていくものなので、それを学んでいける視野の広さは必要だと思います。自分の中で芯というか、変えたくないものはあると思いますが、それを持ったうえでトレンドを追える人が「デザイナー」なのではないかと。
安藤:どういう人が「トレンドを追える人」なんでしょう。ゲーム外にもやっぱり興味がある人ですか?
A.T:だと思います。ファッションだったりとか、女の子だったらメイクとか。デザイナーに必要なのは、いろいろなところに行って、いろいろな情報をインプットすること。それは別にゲームじゃなくても、広告だったり看板だったりとか、自分が見てカッコいいって思ったものを取り入れられる力がある人が強いと思います。
安藤:スーパーアプリの女性スタッフを見ていると、みなさんファッションとかメイクとかに興味があって、女子力が高いなと感じます。そういったアンテナの高さは必要ですよね。

M.N:では、私はイラストレーターの立場から意見すると、とりあえず描くのが好きな人が一番ですね。もう血を吐きながら描いて、描いて、ひたすら描き続けたあとに「あぁ、それでもやっぱり描いていたい」ってなったことがある人がいいです。
安藤:息をするかのように描き続ける人?
M.N:そうですね。描くのが大好きだということが、何より大切だと思います。
安藤:納得です。僕がずっと付き合ってきた優れた絵描きの人はずっと絵を描いています。お酒を飲みに行ったりしても、ずっと絵を描いているような人も少なくない。ナプキンの裏とかで、いきなり似顔絵合戦を始めたり(笑)。では最後に、社長である飯沼さんがスーパーアプリの若い人たちにどのように接していて、どんな感じで勤めてもらいたいと思っているのかを教えてください。
飯沼:先ほど「芯がある人がいい」という話がありましたが、そういった部分は絶対に必要ながら、不易流行というか、変わっていいものと変わってはいけないものがあったりするんですよね。そういった変わってはいけないもの、逆に変わらなくてはいけないものをしっかりと切り分けて考えていける人がいいです。世の中はいろいろ変わって行くんですけど、結局人間という存在自体はそんなに大きく変わっていくものではない。だからこそ、そういったところに基づいて物事を組み立てていく必要があります。
たとえばゲームデザインに関しても、何がおもしろいのか、何がおもしろくないのかは常に考えつつ、プレイをする人たちの立場になったときにどう感じるのかまでちゃんと作品に落とし込める人が強い。そうは言っても、世の中に流行り廃りはあるので、その中で今、世の人々が何を欲しているのかをちゃんと肌で感じ取れるような、感受性豊かに生活できている人と一緒に仕事をしていきたいと思います。
安藤:不易流行。示唆に富んだ言葉ですね。哲学的なんですけど「変わらないように変わっていく」というのも、じつは大事なことだと思いまし。たとえばずっと長く続いているブランドは、ただひたすらその立場を守っているように思われがちですけど、それは変わらないのではなく、変わってはいけないからこそそうしている側面があるんです。「変わらないところは変わらないで欲しい」って思われているからこそ、積極的に変わらないようにしていく。それを貫くというのは、この流動的な時代においてなかなか難しいことだと思います。
飯沼:何から何まで新しければそれでいいっていうことはないんですよね。中には、変わらないことを望まれているものはたしかにあります。
安藤:「これは絶対に意思を持って変えないんだ」ってことを明確に押し出していくということは、ある意味で「そのように変化していっている」と言えるのではないでしょうか。「これはこれでいいや」って感じでダラダラ続いているのとは違います。これは絶対に変えちゃダメなことでしょ、と議論しながら進んでいくことは、それだけである種の変化かなと思います。そして、その両方ができるかどうかはゲーム作りの一番難しいところだし、おもしろいところなのかなと感じました。
新しくないと飽きられちゃうし、新しいものも取り入れつつ、守るべきところは守る。とても難しいことだと思いますけど、ゲーム作りはそれだけ人生を賭けるに値するような仕事だと、あらためて感じました。スーパーアプリには、そういう志を持った人が集まっていると思える90分間でしたね。本日はどうもありがとうございました!
●東京オフィスも本格始動した名古屋のゲームデベロッパー「スーパーアプリ」でお仕事をしてみたい方はコチラ
安藤:息をするかのように描き続ける人?
M.N:そうですね。描くのが大好きだということが、何より大切だと思います。
安藤:納得です。僕がずっと付き合ってきた優れた絵描きの人はずっと絵を描いています。お酒を飲みに行ったりしても、ずっと絵を描いているような人も少なくない。ナプキンの裏とかで、いきなり似顔絵合戦を始めたり(笑)。では最後に、社長である飯沼さんがスーパーアプリの若い人たちにどのように接していて、どんな感じで勤めてもらいたいと思っているのかを教えてください。
飯沼:先ほど「芯がある人がいい」という話がありましたが、そういった部分は絶対に必要ながら、不易流行というか、変わっていいものと変わってはいけないものがあったりするんですよね。そういった変わってはいけないもの、逆に変わらなくてはいけないものをしっかりと切り分けて考えていける人がいいです。世の中はいろいろ変わって行くんですけど、結局人間という存在自体はそんなに大きく変わっていくものではない。だからこそ、そういったところに基づいて物事を組み立てていく必要があります。
たとえばゲームデザインに関しても、何がおもしろいのか、何がおもしろくないのかは常に考えつつ、プレイをする人たちの立場になったときにどう感じるのかまでちゃんと作品に落とし込める人が強い。そうは言っても、世の中に流行り廃りはあるので、その中で今、世の人々が何を欲しているのかをちゃんと肌で感じ取れるような、感受性豊かに生活できている人と一緒に仕事をしていきたいと思います。
安藤:不易流行。示唆に富んだ言葉ですね。哲学的なんですけど「変わらないように変わっていく」というのも、じつは大事なことだと思いまし。たとえばずっと長く続いているブランドは、ただひたすらその立場を守っているように思われがちですけど、それは変わらないのではなく、変わってはいけないからこそそうしている側面があるんです。「変わらないところは変わらないで欲しい」って思われているからこそ、積極的に変わらないようにしていく。それを貫くというのは、この流動的な時代においてなかなか難しいことだと思います。
飯沼:何から何まで新しければそれでいいっていうことはないんですよね。中には、変わらないことを望まれているものはたしかにあります。
安藤:「これは絶対に意思を持って変えないんだ」ってことを明確に押し出していくということは、ある意味で「そのように変化していっている」と言えるのではないでしょうか。「これはこれでいいや」って感じでダラダラ続いているのとは違います。これは絶対に変えちゃダメなことでしょ、と議論しながら進んでいくことは、それだけである種の変化かなと思います。そして、その両方ができるかどうかはゲーム作りの一番難しいところだし、おもしろいところなのかなと感じました。
新しくないと飽きられちゃうし、新しいものも取り入れつつ、守るべきところは守る。とても難しいことだと思いますけど、ゲーム作りはそれだけ人生を賭けるに値するような仕事だと、あらためて感じました。スーパーアプリには、そういう志を持った人が集まっていると思える90分間でしたね。本日はどうもありがとうございました!
●東京オフィスも本格始動した名古屋のゲームデベロッパー「スーパーアプリ」でお仕事をしてみたい方はコチラ
シシララTV オリジナル記事